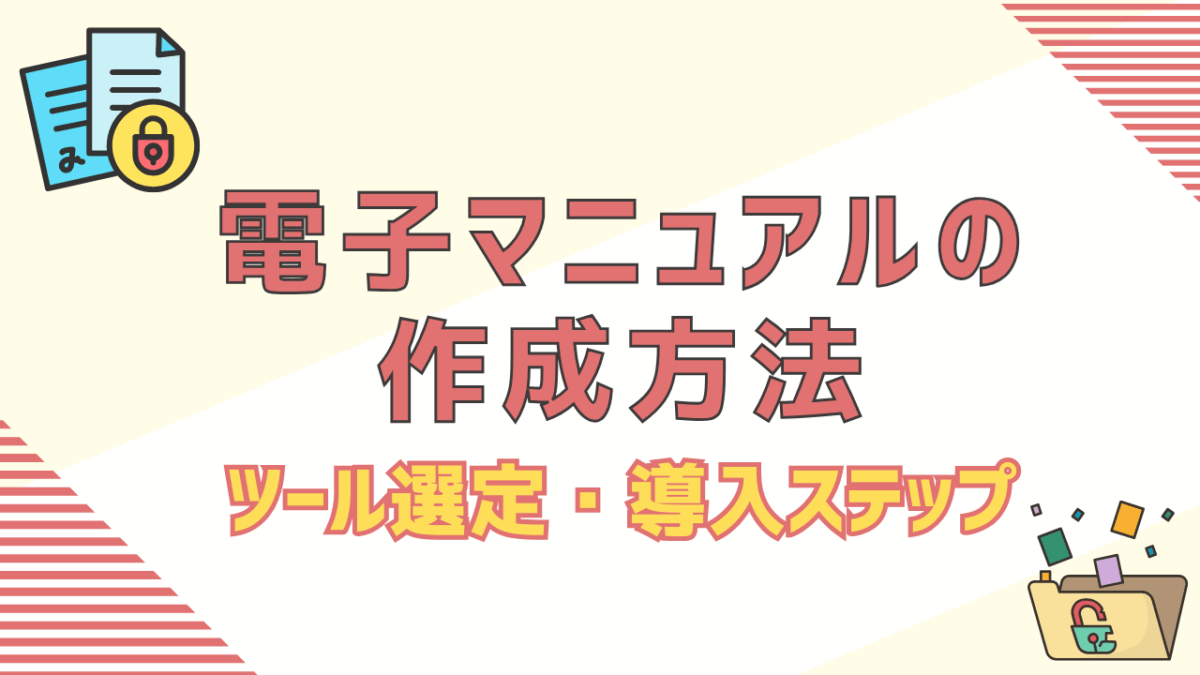業務マニュアルの整備は、どの企業にとっても重要な課題です。しかし、従来の紙マニュアルには「更新に手間がかかる」「検索しづらい」「担当者依存になりやすい」といった多くの課題がありました。せっかく作ったマニュアルが現場で活用されず、属人化や業務の非効率を招いているケースも少なくありません。こうした背景のなか、「電子マニュアルの作成」が急速に注目を集めています。特に、働き方改革やリモートワークの普及によって、いつでも・どこでもアクセスできるマニュアルの必要性が高まり、紙からデジタルへの移行が進んでいます。
さらに近年では、無料で使える優秀なツールが数多く登場したことで、電子マニュアルの導入ハードルが大きく下がりました。小規模なチームや個人事業主でも、コストをかけずにわかりやすいマニュアルを作成・共有できるようになっています。
本記事では、電子マニュアルの特徴やメリット、無料で使えるツールの紹介、作成手順や注意点、社内教育や業務効率化への活用方法をわかりやすく解説します。これから電子マニュアルの導入や見直しを考えている方にとって、実用的なヒントが得られる内容です。まずは無料ツールを活用して、無理なく導入を始めてみましょう。
電子マニュアルの導入を検討している企業や現場担当者向けの記事です。紙ベースの課題から、電子化による更新性・共有性・コスト削減のメリットを整理。さらに導入時のポイントや運用方法まで実務視点で解説しています。
電子マニュアルとは?紙との違いと導入メリット
電子マニュアルの定義と主な形式
電子マニュアルとは、業務手順や製品説明などの情報を、紙ではなくデジタル形式で提供するマニュアルのことです。Webブラウザ、PC、タブレット、スマートフォンなど、さまざまなデバイスから閲覧できる点が特徴です。
主な形式としては、以下のようなものがあります。
- HTML形式:Web上で閲覧・検索しやすく、更新も容易
- PDF形式:レイアウトが固定されており、印刷や共有に便利
- 動画形式:操作手順や実演の説明に最適で、視覚的に理解しやすい
情報の性質や利用者のニーズに応じて、形式を使い分けることで、より効果的なマニュアルを作成できます。
紙マニュアルとの違い:即時更新・検索性・多言語対応
紙のマニュアルは長年使われてきた実績がありますが、以下のような課題を抱えています。
- 更新の手間とコスト:改訂時に印刷し直す必要があり、手間もコストも発生
- 検索性の低さ:必要な情報にたどり着くのに時間がかかる
- 多言語対応の難しさ:言語ごとに冊子を用意する必要があり、管理が煩雑
一方、電子マニュアルではこれらの課題を解消できます。
- 最新情報への即時更新が可能
- キーワード検索やリンク機能によって情報アクセスが迅速
- 多言語対応も翻訳データの切り替えで柔軟に対応可能
特に、変化の激しい業務や製品に関する情報は、電子化によって常に最新の状態を保つことができます。
電子化することで得られる業務効率・教育効果の向上
電子マニュアルを導入することで、以下のような業務上のメリットが得られます。
- 新人教育の効率化:いつでも・どこでも閲覧でき、OJTの補助ツールとして活用可能
- 業務の標準化:属人化を防ぎ、誰が見ても同じ手順で作業ができる
- 情報の一元管理:複数部署や拠点間での共有がスムーズになり、管理コストが削減
特に、業務の属人化が課題となっている企業においては、電子マニュアルによって業務ナレッジの見える化が進み、組織全体の生産性向上につながります。
電子マニュアルを無料で作成できるおすすめツール5選
【目的別】電子マニュアル作成ツール選定のポイント
電子マニュアルの作成には多くのツールがありますが、重要なのは「どのような形式で、誰に向けて、どう活用するか」を明確にしたうえで、自社に合ったツールを選ぶことです。以下のような視点で検討すると、目的に合ったツールを選定しやすくなります。
動画で説明したい場合
操作手順や作業フローを視覚的に伝えるため、動画編集や共有機能の有無がポイントになります。
テキスト+画像で構成したい場合
情報を正確に伝えるには、テキスト装飾・画像挿入・レイアウトの自由度が重要です。見出しや段組み、図表の扱いやすさなども判断材料となります。
チームで共有・更新したい場合
社内で共同作業するには、リアルタイム編集や権限設定、更新履歴管理など、コラボレーション機能が求められます。
このような観点で選定することで、目的に適した形でマニュアルを効率的に構築・運用することが可能になります。
以下にご紹介する5つの無料ツールは、どれも導入しやすく、それぞれ異なる特徴と強みを持っています。用途に合わせて柔軟に活用してみてください。
1. Google ドキュメント|クラウド共有に強い

- 特徴:Googleアカウントがあればすぐに使える、シンプルな文書作成ツール。Google Driveとの連携でオンライン共有もスムーズです。
- おすすめ用途:テキスト主体のマニュアル、社内レビューが頻繁な業務フロー
- 強み:
- コメント・提案モードでのフィードバック
- アクセス権限の細かな設定(閲覧・編集・コメント)
- バージョン履歴による編集管理
- PDF・Word形式での出力にも対応
社内手順書や業務フローのドラフトを複数人で編集・検証する場面に最適です。
Googleドキュメントについては、Googleドキュメントでマニュアルを作成・共有する方法!効率化のコツとおすすめツールを徹底解説でも詳しくご紹介しています。
2. Notion|テンプレート豊富&柔軟な構成

- 特徴:ブロック構造により、テキスト、画像、表、チェックリストなどを自由に組み合わせて文書を作成可能。柔軟なナレッジベース構築に向いています。
- おすすめ用途:社内Wiki、部門ごとの業務マニュアル、プロジェクト管理ドキュメントなど
- 強み:
- 初心者にも使いやすいUIとテンプレート
- 階層化・タグ付けによる情報整理
- Webページとしての公開機能(社外共有も可能)
新入社員用のオンボーディングガイドや業務ナレッジ集を社内に蓄積・共有する際に適しています。
Notioneについては、Notionでマニュアルを作成する方法!テンプレート活用・データベース連携完全ガイドでも詳しくご紹介しています。
3. Canva|ビジュアル重視のマニュアル作成に最適

- 特徴:直感的に使えるデザインツールで、視覚的に訴求力のある資料を簡単に作成可能。テンプレートも豊富です。
- おすすめ用途:画像や図解を多用した操作マニュアル、外部向けのビジュアル資料
- 強み:
- プレゼン資料のような分かりやすいレイアウト
- フローチャート、イラスト、アイコンの活用
- 作成物のPDFダウンロードや印刷にも対応
作業手順や業務フローを、図やアイコンを使って視覚的に説明したいときに有効です。
4. YouTube|無料の動画マニュアル公開手段

- 特徴:動画形式で操作や作業の流れをわかりやすく伝えることができ、限定公開や非公開設定も可能です。
- おすすめ用途:製品の使い方、機械の操作、社内研修コンテンツなど
- 強み:
- 手順や作業をリアルに見せることで理解を促進
- コメントや再生回数による反応確認
- 動画URLをマニュアル内に埋め込むことで併用も可能
コールセンターや製造現場など、実演を見せる方が効果的な業務の教育・共有に最適です。
5. WordPress|ナレッジベース化に最適
- 特徴:自社専用のマニュアルサイトやナレッジベースを構築できる無料CMS(コンテンツ管理システム)。柔軟な情報設計が可能です。
- おすすめ用途:社内ポータルやカスタマーサポート向けのオンラインマニュアル
- 強み:
- カテゴリやタグで情報を整理しやすい
- プラグインで機能を自由に拡張可能
- 社内だけでなく外部ユーザー向けにも公開できる
製品サポートのFAQサイトや、部門横断的なナレッジ共有ページの構築などに適しています。
無料プランの制限には注意が必要
上記のツールはすべて無料で始められるという点で魅力的ですが、それぞれに下記のような制限があります。
- 保存容量に上限がある(例:Canvaのクラウド容量など)
- 履歴保存やアクセス制御機能が制限されている場合がある(例:Notion無料版)
- 外部公開や共有時のセキュリティ設定に制限があるツールも
そのため、運用開始前に必要な機能が無料プラン内で対応できるかどうかを確認し、必要であれば有料プランの導入も検討しておくと安心です。
電子マニュアルを作成する手順
電子マニュアルを効果的に活用するには、「わかりやすく、使いやすい構成」であることが重要です。ここでは、はじめて電子マニュアルを作成する方にも実践しやすい、5つの基本ステップをご紹介します。
電子マニュアル作成手順①:対象業務・読者を明確にする
まずは、「誰が・何の目的で・どんな業務に使うのか」を明確にしましょう。
- 利用者:新入社員、現場スタッフ、サポート部門など
- 目的:業務手順の標準化、教育研修、問い合わせ削減など
- 対象業務:日次業務、ツール操作、商品管理、対応フローなど
この段階で読者のITリテラシーや業務理解度も把握しておくと、適切な表現レベルや情報量を設計しやすくなります。
電子マニュアル作成手順②:マニュアルの構成を設計する(業務分解図の活用がおすすめ)
次に、全体の構成設計を行います。ここでは、業務内容を細かく整理して「どの作業を、どの順番で説明するか」を明確にすることが重要です。
その際に役立つのが、業務分解図(タスク分解)です。業務を一つひとつの工程に分解することで、漏れや重複を防ぎ、構造的なマニュアルが作れます。
参考:「業務分解図」作成ツールはこちら
電子マニュアル作成手順③:コンテンツを作成する(テキスト・画像・動画)
構成が固まったら、具体的なコンテンツ作成に進みます。形式は業務内容や利用者の理解度に応じて、以下のように使い分けましょう。
- テキスト:手順やルールの明文化に有効(例:手順書、チェックリスト)
- 画像(スクリーンショットや図):操作手順や画面案内に適している
- 動画:ソフトの操作説明や現場作業の実演に最適。理解度向上に効果的
要点を押さえた短く、明確な説明を心がけ、読み手の視点で情報整理することが大切です。
電子マニュアル作成手順④:フォーマット選定とデザイン
次に、どのツールで、どんな形式で公開するかを選定します。
例えば
- Google ドキュメント/Notion:チームでの共同編集に強み
- Canva/PowerPoint:視覚的にわかりやすい資料向け
- YouTube:操作手順や現場業務の動画説明に適している
読みやすいデザインや適切なレイアウト(見出し・余白・アイコンなど)も、マニュアルの理解度に大きく影響します。
電子マニュアル作成手順⑤:公開・共有・フィードバック設計
最後に、完成したマニュアルを誰に・どのように届けるかを計画します。ここでは以下の点が重要です。
- 共有方法:社内ポータル、クラウドストレージ、メール、QRコードなど
- 権限管理:編集制限や閲覧のみ設定で情報の改ざん防止
- フィードバックの仕組み:利用者の意見や改善要望を収集するしくみを設ける
また、公開後も定期的に内容を見直し、常に最新状態を保つ運用体制を構築することが、継続的な効果につながります。
失敗しないための注意点とよくある課題
電子マニュアルは便利な反面、運用方法を誤ると「作っただけで活用されない」「すぐに古くなる」など、かえって混乱を招く原因にもなりかねません。ここでは、電子マニュアル作成・運用時によくある課題と、それを回避するための対策を解説します。
書き手と読み手の視点のズレ
専門知識のある担当者がマニュアルを作成すると、「前提の説明が抜けている」「用語が難しい」といった問題が生じがちです。読み手にとって不親切な内容になると、マニュアルが活用されなくなります。
対策:
- 対象読者のスキルレベル・前提知識を事前に確認する
- 初心者目線での説明を意識する
- 作成後に別のメンバーに読んでもらい、フィードバックを得る
更新が滞ることで陳腐化
「最初に作ってから更新されていない」「記載内容が現場の実態とズレている」といった状態になると、マニュアルの信頼性が損なわれます。
対策:
- 更新担当者とスケジュール(例:四半期ごとの見直し)をあらかじめ決める
- ツールの「更新日」「最終編集者」を表示しておく
- 利用者からのフィードバックを集めやすくし、更新のきっかけをつくる
使われないマニュアルになる理由とその対策
せっかく作ったのに「存在を知られていない」「探しづらい」「使いづらい」といった理由で使われないケースも多くあります。
対策:
- 社内ポータルやチャットツールでの定期的な周知
- 目次や検索機能を備えた構造化されたマニュアルにする
- フローチャートや図解を活用し、視覚的にもわかりやすくする
無料ツール利用時の制限と対処法
無料ツールには機能や容量の制限があります。たとえば、Google ドキュメントは共有範囲の管理が難しい場合があり、Notionは無料プランでは履歴の保存に制限があります。
対策:
- 利用目的と必要な機能をあらかじめ整理しておく
- 制限を補うためにツールを組み合わせて使う(例:Notion+YouTube)
- 将来的な有料プランの移行も視野に入れた検討をしておく
電子マニュアルは「作ること」自体が目的ではなく、「実際に使われ、業務を支えること」が本来の目的です。そのためには、作成後の運用体制や更新フローを含めた設計が不可欠です。
電子マニュアルの効果的な活用方法
電子マニュアルは「作って終わり」ではなく、業務の現場で実際に活用し続けてこそ意味があります。ここでは、電子マニュアルを業務の中で活かす具体的な活用方法を4つのシーンに分けてご紹介します。
1. 教育研修での活用(OJTの補助)
新入社員や異動者の研修では、電子マニュアルをOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)の補助教材として活用できます。
- 事前学習ツールとして:基本的な業務知識や操作を動画やテキストで事前に習得
- 現場での参照ツールとして:スマホやタブレットでその場で手順を確認できる
- 繰り返し学習が可能:学び直しや復習に最適。新人教育の属人化も防げる
マニュアルと研修を連動させることで、教育の標準化と効率化が図れます。
2. 業務引き継ぎ・社内ナレッジの標準化
業務の引き継ぎや担当交代時、電子マニュアルは知識の可視化・継承ツールとして効果的です。
- 担当者が不在でも、誰でも同じ手順で業務を進められる
- 経験やノウハウを形式知化し、属人化を防止
- 新しいメンバーが業務理解する時間を短縮し、立ち上がりを早くする
特に定型業務や繰り返しの作業ほど、マニュアルによる標準化の効果が高まります。
3. FAQやカスタマーサポートとの連携
社外対応が必要な業務では、電子マニュアルをFAQや顧客対応マニュアルとして活用することも可能です。
- よくある質問をWeb上にまとめ、問い合わせ対応の効率化
- カスタマーサポートの回答品質を一定に保ち、対応のばらつきを防止
- チャットボットや問い合わせフォームと連携し、即時対応が可能に
顧客満足度の向上と同時に、サポート業務の生産性も改善されます。
4. アクセス解析による改善サイクル
電子マニュアルを「改善し続ける情報資産」として運用することも重要です。特にWebベースや動画形式の場合、以下のようなアクセス解析データを活用できます。
- どのページがよく読まれているか
- どのコンテンツで離脱しているか
- 検索されているキーワード
こうしたデータをもとに、マニュアルの構成や表現を見直し、利用者目線での継続的な改善につなげることができます。
まずは無料ツールで電子マニュアル作成を始めよう
電子マニュアルは、業務効率化・教育の仕組み化・ナレッジの共有といったさまざまな面で企業活動を支える重要な資産になります。
最初から完璧を目指す必要はありません。まずは無料ツールで小さく始めることで、手軽に取り組むことができます。そして、運用を続けながら内容を磨き上げ、組織に合ったかたちで育てていくことが成功の鍵です。
業務の整理・構成に不安がある場合は、「業務分解図」を活用するのも効果的です。情報の整理と構造化を支援し、誰が見ても使いやすいマニュアル作りを実現できます。
ーーー
How to Create Electronic Manuals for Free: A Complete Guide to Benefits, Tool Selection, and Implementation Steps
業務分解図で業務を“見える化”しよう
業務改善・マニュアル整備・新人教育・DX推進。
すべての出発点は、業務を分解して理解することです。
📥 業務分解図テンプレートでまずは1つの業務から整理してみませんか?
▼こちらの記事もおすすめ▼
Googleドキュメントでマニュアルを作成・共有する方法!効率化のコツとおすすめツールを徹底解説
【完全ガイド】Wordでマニュアル作成する方法!デザイン・レイアウトの工夫もご紹介
カルチャーブックとは?理念ブック・クレドブックとの違いや作り方・活用事例を徹底