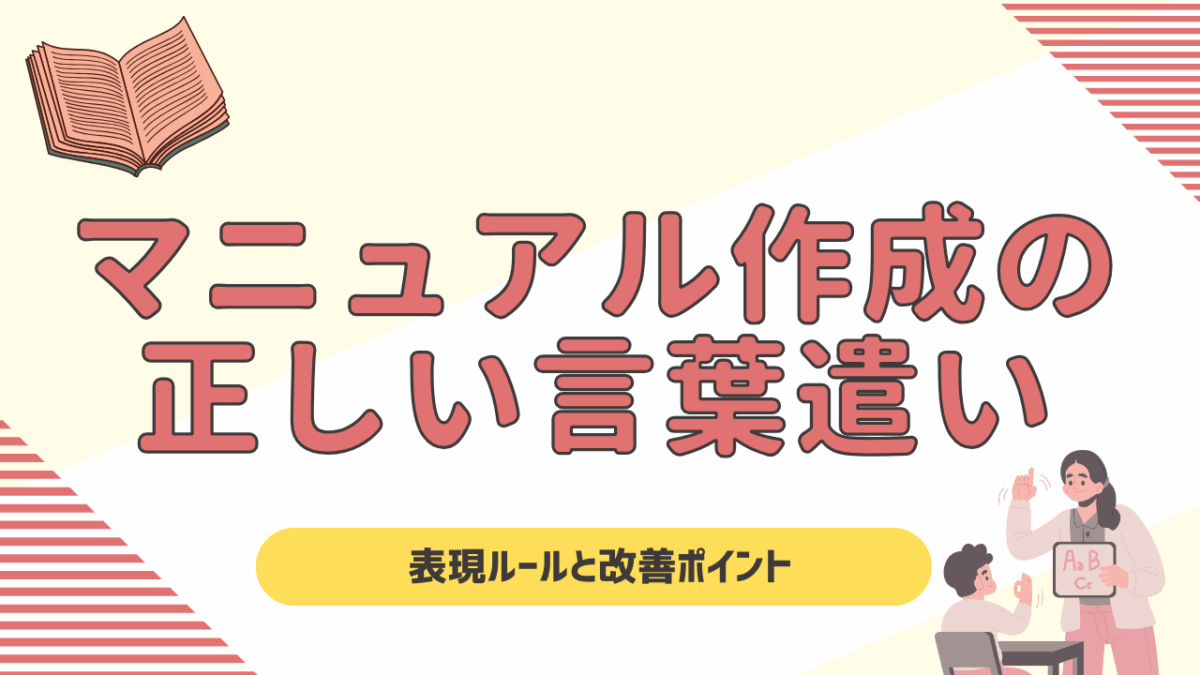業務マニュアルを作成するうえで、手順やルールを正確に記載することはもちろん重要ですが、それと同じくらい大切なのが「言葉遣い」です。
「適宜対応してください」「通常通り進めてください」といった曖昧な表現が、現場での解釈のズレやミスを引き起こすケースは少なくありません。また、敬語と命令形が混在することで、マニュアルの統一感が損なわれ、読み手にとって混乱のもとになることもあります。
そこで本記事では、「マニュアル作成における言葉遣い」をテーマに、なぜ言葉選びが重要なのか、どのような表現がNGなのか、そして“伝わるマニュアル”を実現するための表現ルールや改善テクニックを詳しく解説します。品質を高め、現場で「本当に使われる」マニュアルを目指すために、ぜひ参考にしてください。
マニュアル作成では手順の正確さに加え、「言葉遣い」が品質を大きく左右します。曖昧な表現や敬語・命令形の混在は、読み手による解釈のズレや業務ミスを招く原因に。この記事では、避けるべきNG例、主語の明確化・文体統一・数値指定などの基本ルール、箇条書きや補足説明など“伝わる表現テクニック”を紹介します。
なぜマニュアル作成に言葉遣いが重要なのか
マニュアルは、単に情報を記載するだけでは不十分です。読み手が正確に理解し、迷いなく行動できることが何よりも重要であり、その成否を大きく左右するのが「言葉遣い」です。
曖昧な表現や主観的な言い回しは、業務ミスや属人化の原因となり、マニュアル全体の信頼性を損なうリスクがあります。
だからこそ、誰が読んでも同じ解釈で、同じ行動に移せる“伝わる言葉遣い”を意識することが欠かせません。ここでは、マニュアル作成における「言葉遣い」の重要性を、起こり得るリスクや改善効果とともに解説します。
読み手によって意味が変わるリスク
マニュアルは、誰が読んでも同じ行動が取れることが理想です。しかし、言葉遣いが曖昧だと、読み手によって解釈が変わってしまう恐れがあります。例えば、「できるだけ早く対応してください」という表現は、ある人には「今すぐ」、別の人には「今日中」と解釈されるかもしれません。このように、言葉遣いひとつで業務の質にばらつきが生じてしまうのです。
結果として、対応の遅延や認識のずれが、クレームやトラブルを招く可能性もあります。
曖昧な言葉遣いが業務ミスを生む可能性
「なるべく多く」「通常どおりに」「一通り確認」など、明確でない言葉遣いは、具体的な行動に落とし込むのが難しく、ミスや確認漏れの原因になります。特に、業務に関わるメンバーの人数が多い場合や、経験に差がある現場では、言葉遣いの不明確さがリスクを倍増させる可能性が高くなります。
業務標準化や属人化の防止という観点でも、表現の精度と一貫性は極めて重要です。
言葉遣い次第でマニュアルの「伝わる力」が変わる
同じ内容でも、言葉遣いによって「わかりやすさ」や「再現性」は大きく変わります。例えば、「次へ進んでください」よりも「右下の『次へ』ボタンをクリックしてください」と書いた方が、読み手の行動をより的確に導けます。
つまり、マニュアルにおける言葉遣いは、業務の手順を伝えるだけでなく、実行精度を高める“コミュニケーションツール”でもあるのです。
伝えたいことが正確に伝わるかどうかは、どんな言葉で、どのように書かれているかにかかっています。
マニュアル作成で避けるべきNGな言葉遣い例
マニュアルが活用されない理由の多くは、「書き方」の曖昧さにあります。意図が伝わらない、解釈に幅がある表現は、誤解や業務ミスにつながる危険性があります。以下では、特に避けるべきNG表現を具体的に紹介します。
「適宜」「なるべく」「〜と思います」など曖昧な表現
- NG例:「必要に応じて対応してください」「なるべく早く提出してください」「○○だと思います」
- 問題点:人によって「必要」や「なるべく」「思います」といった表現は読み手の解釈が異なるため、対応のばらつきが発生します。
- 改善案:「〇〇のタイミングで対応してください」「〇日以内に提出してください」など、明確な条件や期限を指定しましょう。
「して下さい」「お願い致します」など敬語・命令口調の混在
- NG例:「確認して下さい」「ご確認をお願い致します」
- 問題点:口調が統一されていないと、読み手に違和感を与えたり、指示の強弱が曖昧になります。
- 改善案:「確認します」「確認してください」など、文体(常体/敬体)を統一し、指示は平易な命令形で書くのが原則です。
「前回と同様に」「通常通り」など前提が不明確な言い回し
- NG例:「前回と同様に処理してください」「通常通りに作業してください」
- 問題点:「前回」や「通常」が何を指すのかが不明確で、読み手によって判断が異なります。特に新入社員や引き継ぎ時には混乱の原因になります。
- 改善案:「〇〇手順書の3ページを参照」「マニュアル〇〇に記載の通り」と、具体的な参照先や手順を明記しましょう。
これらのNG表現を避けるだけで、マニュアルの「伝わる力」は大きく変わります。次は、どのような表現が適しているか、マニュアルにふさわしい言葉遣いのルールを見ていきましょう。
マニュアル作成に適した言葉遣いの基本ルール

マニュアルは、「誰が読んでも同じように再現できる」ことが求められる業務文書です。曖昧さを排除し、読み手が迷わず動けるような表現に整えることが、マニュアルの品質を大きく左右します。以下の4つの基本ルールを押さえておきましょう。
主語・目的語を明確にし、誰が何をするかをはっきりさせる
マニュアルでは「誰が」「何をするか」があいまいだと、現場での判断にゆらぎが生まれます。
例えば、
- NG例:「申請書を提出してください」
→ 誰が提出するのかが不明 - 改善例:「営業担当者が、申請書を上長に提出します」
このように、主語を明記することで責任範囲が明確になり、作業の抜け漏れや誤解を防ぐことができます。
常に丁寧語ではなく「です・ます」調もしくは「である調」で統一する
敬語や命令形が混ざった文章は、読み手にとって混乱を招く原因になります。マニュアルでは、丁寧すぎる表現(例:「お願いいたします」)や命令形(例:「提出せよ」)は避け、「です・ます調」あるいは「である調」のいずれかに統一するのが基本です。文体にはそれぞれ異なる特性があるため、目的や場面に応じて使い分けることが大切です。
統一例(です・ます調):
- 「フォームに情報を入力します」
- 「ボタンをクリックします」
統一例(である調):
- 「送信ボタンを押す」
- 「〇〇の確認を行う」
特に操作手順や作業フローの説明では、「~する」「~を押す」などの「である調(常体)」が用いられることが多く、簡潔で命令的になりすぎない表現として適しています。
一方で、「マインドセット」「業務の意義」「心得」などの解説では、やさしく読みやすいトーンで伝える必要があるため、「です・ます調(丁寧語)」を使うケースもあります。マニュアル全体の中での言葉遣いは“統一”が原則でありつつも、章ごとの目的に応じて使い分けることも有効です。
- 心構えや解説部分:です・ます調で丁寧に
- 手順や操作方法:である調で簡潔に
このように意図的に使い分ける場合は、「どのパートでどの文体を使うか」を事前にルール化しておくと、全体の整合性が保たれます。
「です・ます調」と「である調」の特徴
| 文体 | 特徴 | 向いている場面 |
| です・ます調 | ・やわらかく丁寧な印象を与える ・読み手に親しみやすく、抵抗感を与えにくい ・対話的なニュアンスがある | ・社内向けマニュアルの導入部やマインドセットの説明 ・初心者向けマニュアルや教育資料 |
| である調 | ・事実や命令、ルールを明確に伝えられる ・論理的で簡潔な印象を与える ・統一感のある構成にしやすい | ・操作手順やフローチャートの説明 ・技術マニュアルや業務フロー解説 |
「〇秒以内」「〇回繰り返す」など数値で指示を明確にする
「すぐに」「適切なタイミングで」などの曖昧な時間や回数の指示では、人によって判断が異なり、ミスにつながる恐れがあります。可能な限り、具体的な数値で条件を示しましょう。
- NG例:「すぐにログインしてください」
- 改善例:「エラー表示から30秒以内にログインボタンを再度押します」
このように数値を用いることで、判断基準を統一し、業務の再現性を高めることができます。
伝わるマニュアルを実現する言葉遣いテクニック
正確な言葉選びだけでなく、「いかに伝わりやすくするか」という工夫もマニュアル作成では欠かせません。特に業務マニュアルのように複数人が利用する文書では、視認性や直感的な理解がカギになります。ここでは、実際に使われるマニュアルで効果的な3つの表現テクニックをご紹介します。
読点(、)や箇条書きを活用して読みやすくする
1文が長くなったり、情報が詰め込まれすぎたりすると、読み手は内容を正しく理解できません。読点(、)を適切に使って区切ることでリズムよく読み進めることができます。また、条件や手順が複数ある場合は、箇条書きにすることで視覚的に整理され、理解度が高まります。
- NG例:このボタンを押して設定画面を開き入力欄に必要事項を記入し保存ボタンをクリックしてください。
- 改善例:
- 「設定」ボタンを押します
- 入力欄に必要事項を記入します
- 「保存」ボタンをクリックします
言い換えや補足を加えて誤解を防ぐ
専門用語や社内用語が多く含まれるマニュアルは、読み手によって理解に差が出てしまいます。初学者や新入社員でも迷わず読めるように、必要に応じて簡単な言い換えや補足説明を入れると効果的です。
- 例:「リード」とは見込み顧客のことを指します
- 例:「マスタデータ(基幹となる基準情報)」を更新します
補足は「()」や脚注、別途図解などで加えるとスマートに伝えられます。
スクリーンショットや図解と合わせて言葉の意味を可視化する
文章だけでは操作イメージがつかみにくい場面では、スクリーンショットや図解を併用することで、理解のスピードが大きく向上します。特にITツールの操作マニュアルや申請書類の記入例など、視覚的な補助があると読者は迷いにくくなります。
- ボタンや画面の位置を矢印付きで指し示す
- 完成イメージを表示してゴールを明示する
- フローチャートを使って処理手順を図式化する
こうした視覚要素は、言葉の不足を補うだけでなく、読み手の記憶にも残りやすくなります。
マニュアル作成における言葉遣いをチェック・改善する仕組み
どんなに丁寧に作ったマニュアルでも、1人の主観では誤解や表現ミスを見逃してしまうことがあります。そのため、マニュアルの「言葉遣いの品質」を担保するには、チェック・改善の体制づくりが不可欠です。ここでは、継続的に言葉の精度を高めていくための実践ポイントを紹介します。
レビュー担当を明確にし、ダブルチェックを実施
マニュアル作成では、少なくとも「作成者」「レビュー担当者」を分けるのが基本です。読み手目線での確認が入ることで、曖昧な表現や誤字脱字、読みづらい構成が発見されやすくなります。
- 「内容レビュー」と「言葉のレビュー」を別担当に分けるのもおすすめ
- 評価項目に「主語が明確か」「曖昧な表現はないか」などのチェックリストを導入すると効果的です
表現ガイドライン(用語集・言い回しルール)を整備
社内で使用するマニュアルが複数ある場合や、複数人で作成・更新を行う場合は、表現ルールを統一するためのガイドラインを用意しておくと便利です。
- よく使う用語の定義(例:「申請」「承認」「登録」など)
- 文体ルール(「です・ます」調の統一、敬語の使用有無など)
- NGワード一覧(「なるべく」「基本的に」などの曖昧語)
このような共通基準があることで、誰が作っても“同じ品質”のマニュアルが保てます。
現場からのフィードバックを定期的に反映する仕組みづくり
マニュアルは一度作って終わりではなく、「実際に使ってみてどうだったか?」という現場の声を反映し続けることで、精度が高まっていきます。
- 利用者が簡単にコメントできるフィードバックフォームを設置
- 月1回・四半期ごとなど、定期的な見直しスケジュールを設定
- 「改善ログ」を残して、誰がどの表現をどう変えたか履歴を管理
このように、改善を前提とした運用体制を組み込むことで、使われ続けるマニュアルに育てていくことができます。
正しい言葉遣いがマニュアルの品質を左右する
マニュアルは単なる手順書ではなく、「業務を正しく再現するための仕組み」です。その再現性を高めるうえで、言葉遣いの質は非常に重要な要素です。
言葉は「業務の再現性」を高めるための最重要要素
「適宜」「なるべく」など曖昧な言葉や、敬語と命令口調の混在は、現場での解釈のズレやミスにつながります。一方で、主語・目的語を明確にし、具体的かつ定量的な表現で統一されたマニュアルは、誰が見ても同じ行動を再現できる、強力な業務インフラになります。
「伝わるマニュアル」は、言葉遣いの見直しから始まる
良いマニュアルをつくるには、まず「伝えるための言葉選び」を意識する必要があります。表現ルールを定め、レビュー体制を整え、現場からの声を反映していく仕組みを整えることで、マニュアルの質は格段に向上します。
マニュアルの目的は、読む人が迷わず、業務をスムーズに実行できること。その鍵を握るのが“言葉”であることを、今一度見直してみてはいかがでしょうか。
参考:マニュアル作成のための表現ガイドライン(サンプル)
1. 文体・語尾のルール
| 項目 | ルール内容 | 例 |
| 文体の統一 | 「です・ます調」で統一(原則) | ○:ボタンをクリックします。×:ボタンをクリックしろ。 |
| 命令形の使用 | 原則禁止。「〜してください」ではなく、「〜します」で記述 | ○:データを保存します。×:データを保存してください。 |
| 語尾のブレ | 1文書内で語尾の調子(〜する/〜です)を混ぜない | 例:常に「〜します」で統一する |
2. 用語・表記の統一
| 用語 | 説明・定義 | 使用例 |
| 登録 | システムやツールへのデータ入力 | 顧客情報を登録します。 |
| 申請 | 承認を得るための操作 | 経費精算を申請します。 |
| 承認 | 上長などが申請内容を確認し許可する | 上司が承認を行います。 |
| 削除/消去 | 「削除」で統一(表現を統一) | 顧客データを削除します。 |
3. 禁止表現(NGワード)一覧
| NG表現 | 理由 | 推奨表現例 |
| なるべく | 解釈が人により異なり、行動がばらつく | 「〇日以内に」「すぐに」など具体化 |
| 適宜 | 判断基準が曖昧でミスにつながる | 「〜のタイミングで実施」など |
| 基本的に | 例外があることを示唆し不安を与える | 原則は記載し、例外は別途記述 |
| 前回と同様に | 前回の内容が明確でないと混乱を招く | 「〇〇手順と同様の操作を行います」など |
| 思います | 主観的で責任の所在が曖昧 | 「〜です」「〜します」など断定表現 |
4. 数値・単位の扱い方
- 数値は「半角」表記とし、単位は必ずつける(例:5分、10件)
- あいまいな表現(例:「少し待つ」「時間を空ける」)は避ける
5. 図・スクリーンショットの使用ルール
- 画像には必ずキャプション(例:「図1:ログイン画面」)をつける
- 操作対象となるボタン・項目は赤枠などで強調する
図内にテキストが含まれる場合、文字が潰れないサイズを維持する
マニュアルの言葉遣い、プロに相談してみませんか?
「曖昧な表現が多くて不安」「属人化をなくす表現ルールを整えたい」そんなお悩みは、業務改善のプロ mayclassにご相談ください。
マニュアル改善や表現ガイドラインの整備、運用定着まで幅広くサポートいたします。

ーーー
Proper Wording in Manuals: How to Write Clear and Effective Instructions
▼こちらの記事もおすすめ▼
【完全ガイド】Wordでマニュアル作成する方法!デザイン・レイアウトの工夫もご紹介