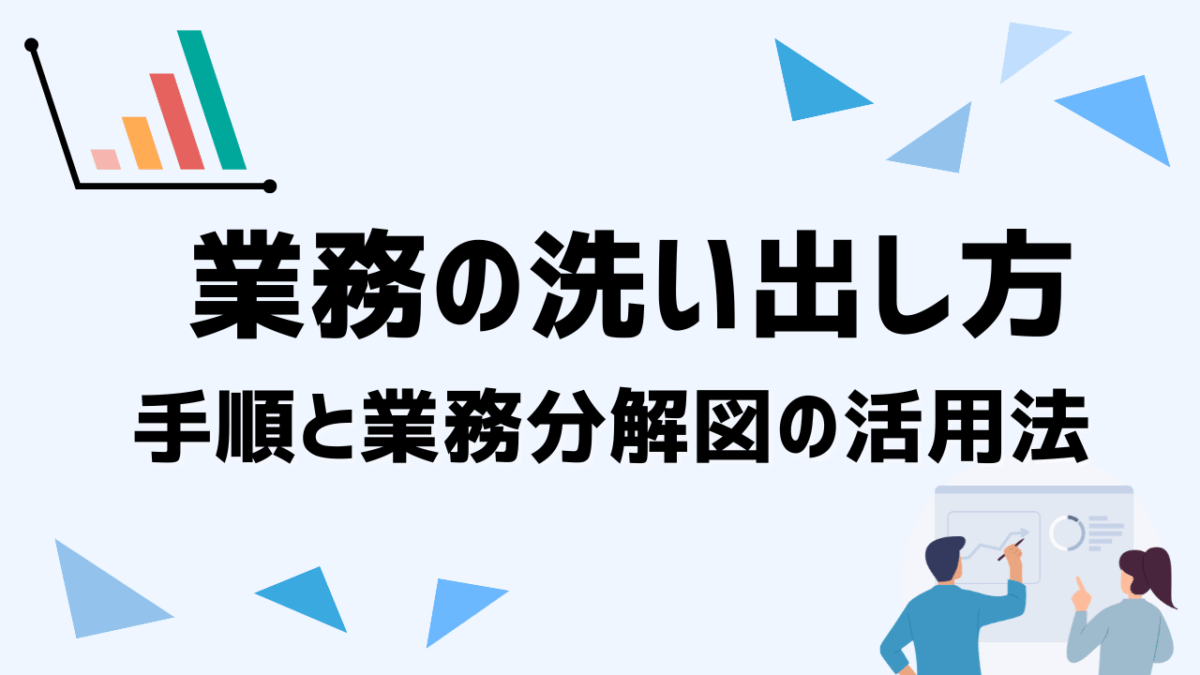業務の洗い出しは、ムダを見つけて効率化を進めたり、マニュアルを整備したりするうえで重要です。
しかし実際には、「日々の業務が多すぎて、何から整理すればよいか分からない」「いざ洗い出しても、どう分析・活用すればいいのか分からない」 といった声も多く聞かれます。
属人化やマニュアルの不備により、引継ぎや新人教育がスムーズに進まないケースもあります。
この記事では、実務で使える具体的な洗い出し手順や業務分解図の活用法を分かりやすく解説します。
「業務の洗い出し」を出発点に、属人化防止・効率化・マニュアル整備を進めるための実務的なやり方をまとめたガイドです。
ステップに沿って棚卸しを行い、チームで協力しながらツールや業務分解図を使って「見える化」をしてみましょう!
なぜ業務の洗い出しが必要なのか
近年、働き方改革や業務効率化への関心が高まるなか、業務を洗い出すことの重要性も増しています。なぜ今この取り組みが求められているのか、主な理由を3つ紹介します。
属人化を防ぎ、業務効率化を実現する
「その作業は◯◯さんしか分からない」といった属人化は、企業にとって大きなリスクです。担当者が不在の時に業務が止まってしまったり、トラブルが発生しても対応できなかったりする可能性があります。
業務を洗い出すことで、誰がどの業務を担っているのかが明確になり、業務の全体像を可視化できます。その結果、重複している作業を省いたり、業務を適切に振り分けたりすることができ、チーム全体の生産性向上にもつながります。
マニュアル作成・引継ぎを確実にする
業務の洗い出しは、マニュアル化の基盤になります。
作業の目的・手順・注意点が整理されていれば、誰が担当しても同じ品質で業務を遂行でき、引継ぎの際も混乱を防げます。
特に人事異動や退職が多い組織の場合、言葉での引継ぎだけでは情報が抜けがちです。あらかじめ業務を洗い出し、文書として残しておくことで新人教育にも活用でき、育成コストの削減にもつながります。
コスト削減・リスク管理につながる
ムダな作業、重複している作業、非効率な作業を洗い出すことで、コスト削減につながります。また、業務全体を見える化すると潜在的なリスクに気づきやすくなり、対策の優先順位も立てやすくなるのが業務の洗い出しのメリットです。
たとえば、毎月手作業で行っていたデータ入力業務を自動化したことで、年間数十時間の工数を削減できた例があります。
こうした問題も業務を丁寧に洗い出し、情報を一元管理する体制を整えることで、未然に防ぐことが可能です。
業務の洗い出し方の基本手順
業務の洗い出しは、闇雲に進めても効果は期待できません。抜けや重複を防ぎ、改善につなげるためには正しい順序で進めることが重要です。
ここでは、実務に活かせる5つのステップを紹介します。
業務の洗い出し方①:業務の目的を明確にする
最初に確認すべきは、「その業務はなぜ必要なのか」という点です。
目的が曖昧なままだとムダな作業まで洗い出してしまい、見直しの効果が薄れてしまいます。
業務を洗い出す時は、次のような視点を持ちましょう。
- その業務は、組織のどんな目標に貢献しているか?
- そもそも必要な業務か、やらなくてもよい業務か?
ゴールを設定することで洗い出すべき範囲が明確になり、後の業務改善にもつなげやすくなります。
業務の洗い出し方②:担当者や関係者を整理する
次に、各業務に関わっている人物を洗い出します。
業務が属人化している場合、担当者の退職や異動が業務の停滞につながるリスクがあるため、誰が何を担っているかを明確にすることは重要です。
以下のような分類で整理すると、見落としを防げます。
- 主担当者・副担当者
- 承認者・決裁者
- 関係部署の連携担当者
- 外部業者や協力会社
誰がどの業務に関わっているかを把握しておけば、無理のない分担やスムーズな引き継ぎにつなげることができます。
業務の洗い出し方③:業務の流れをリスト化する
担当者が明確になったら、次は業務の具体的な流れを時系列に沿って洗い出しましょう。
業務の前後関係や、関連作業のつながりを意識しながら整理することがポイントです。
以下のように整理すると漏れを防ぐことができます。
- 定期業務:日次・週次・月次など
- 不定期業務:年1回の棚卸、決算対応など
- 突発業務:クレーム対応、緊急の依頼
- 季節業務:年末調整、イベント準備
チェックリスト形式やフローチャートを併用すると、視覚的にも整理しやすくなります。
業務の洗い出し方④:頻度・工数・重要度を記録する
各業務について、以下の情報をあわせて記録することで、改善の優先順位がつけやすくなります。
- 実施頻度(例:週1回、月2回など)
- 1回あたりの工数(例:30分、2時間など)
- 業務の重要度(高・中・低などで評価)
こうした情報を記録しておけば、「時間をかけているが成果に直結していない業務」や、「手間は少ないが重要な業務」が明確になります。
業務の洗い出し方⑤:問題点や改善余地を見つける
業務を洗い出した後は、それぞれの業務に対して改善余地がないかをチェックしましょう。
以下のような視点で確認すると、見落としを防ぎやすくなります。
- ムダな作業になっていないか?
- 自動化できる部分はないか?
- 手順を簡略化できる余地はないか?
- 他部署と内容が重複していないか?
業務を一つひとつ見直すことで、改善のヒントが見えてきます。
効率的に業務を洗い出すポイント
業務の洗い出しは、ただ作業を並べるだけでは不十分です。
実際の現場では、「どこまで洗えばいいか分からない」「他人の業務が見えない」といった悩みに直面することも多いものです。
業務を洗い出す時は、4つのポイントを押さえてより効果的に進めましょう。
チームの協力を得る
一人で業務を洗い出そうとすると、どうしても視野が狭くなりがちです。
特に例外対応やいつものやり方など、無意識に行っている業務は見落としやすい傾向があります。
そこで、同じ業務に関わるメンバー同士で定期的にミーティングを開き、互いの業務内容を共有し合うことが効果的です。
- 新人視点:細かい作業や気づきを拾いやすい
- ベテラン視点:全体最適や改善余地に気づきやすい
こうした多様な視点を取り入れることで、より立体的で実態に即した業務リストが作成できます。
社内外のツール活用法
手書きメモや口頭確認だけでは、業務の洗い出しや整理には限界があります。デジタルツールを使い情報の蓄積・共有・更新をスムーズに行いましょう。
次のようなツールが便利です。
- 業務フロー作成ツール:draw.io、Lucidchart など
- タスク管理ツール:Backlog、Trello、Notion、Asana など
- 表計算ソフト:Excel、Googleスプレッドシート(フィルタ・色分けなどが便利)
とくにクラウド型のツールを使えば、リモート環境でも複数人が同時編集・コメントできるため、チームでの業務可視化に有効です。
業務分解図を活用する
洗い出した業務をただ羅列するだけでは、関連性や構造が見えにくく、改善の優先度もつけづらくなります。そこで役立つのが「業務分解図(WBS)」の活用です。
業務分解図とは、大きな業務を中項目・小項目へと階層的に細分化して整理する手法です。
このように構造化することで、以下のメリットが得られます。
- 抜け漏れや重複が防げる
- 属人化のリスクが可視化される
- マニュアル整備や自動化の対象も見えやすくなる
単なる作業一覧では見えなかった課題や非効率も、業務分解図を使えば整理しやすくなります。

業務分解図を使った洗い出しの具体例
業務を正確に、かつ効率的に洗い出すには、「業務分解図(WBS)」の活用が有効です。業務のつながりや構造を視覚的に整理できるため、見落としや属人化を防ぐだけでなく、改善やマニュアル化にもつなげやすくなります。
業務分解図とは何か(階層的に業務を整理する図)

業務分解図(WBS: Work Breakdown Structure)とは、プロジェクトや業務全体をより小さく、管理しやすい単位に分割した図のことです。大きな業務を徐々に細分化していくことで、具体的なタスクレベルまで可視化できます。
たとえば、「営業活動」という大きな業務を「見込み客の発掘」「提案資料作成」「商談」などに分解し、さらにそれぞれの詳細な作業に分けていきます。
営業活動
└─ 見込み客の発掘
└─ 顧客リストの作成
└─ メール送付・テレアポ
└─ 商談準備
└─ ヒアリング
└─ 提案資料作成
└─ 契約処理
└─ 見積もり作成
└─ 契約書締結
└─ アフターフォロー
└─ 定期連絡
└─ 満足度調査
このように細分化することで、業務の構造と担当範囲がひと目で分かります。
業務分解図を活用する4つのメリット
業務分解図を活用すると、次の4つのメリットが得られます。
抜け漏れなく業務を整理できる
業務を階層的に整理することで、必要な作業を見落とさずに把握できます。
たとえば、「月次報告」という業務を分解すると「データ収集」「分析」「資料作成」「承認」「提出」といった一連の流れが明確になり、必要な作業を漏れなく把握できます。
属人化の防止に役立つ
業務の内容と担当者を明確にすることで、特定の担当者に業務が集中する属人化を防ぐことが可能です。
誰がどの作業を担っているかが見えるようになるため、業務の分担がしやすくなり、引き継ぎが必要な業務も把握しやすくなります。
業務改善やマニュアル作成に直結する
細分化された業務は、そのままマニュアルの目次や手順書として活用しましょう。
作業ごとの所要時間や頻度も整理しやすいため、「どの作業にムダがあるか」「自動化できるか」といった改善のヒントも自然と見えてきます。
実際の業務分解図の例(部門ごとの業務を細分化)
たとえば営業部門の場合、業務分解図は以下のように整理できます。
- 営業部門
- 顧客開拓
- ターゲット顧客リスト作成
- テレアポ
- メールマーケティング
- 展示会出展
- 商談
- ヒアリング
- 提案書作成
- 見積もり作成
- プレゼンテーション
- 契約
- 契約書作成
- 契約書締結
- 請求書発行
- 顧客フォロー
- 定期訪問
- 問い合わせ対応
- アフターフォロー
- 顧客満足度調査
- 顧客開拓
業務を階層的に分解することで、部門内の業務内容を体系的に把握できるようになります。
さらに業務同士のつながりや流れも明確になるため、どこに課題があるかを見つけやすく、具体的な改善策を検討しやすくなるのもメリットです。
業務の洗い出し後に取り組むべきこと
業務の洗い出しはあくまでスタート地点です。洗い出した情報を基に、具体的な改善策を実行していく必要があります。
ここでは、洗い出し後に取り組むべき3つのアクションを解説します。
改善すべき業務を選定する
すべての業務を一度に改善することは現実的ではありません。洗い出した業務の中から、以下の基準で改善優先度を決めていきます。
- 重要度が高い業務:組織全体の目標達成に大きく貢献する業務
- 緊急度が高い業務:放置すると問題が発生する可能性が高い業務
- 改善効果が高い業務:改善することで大きな成果が期待できる業務
こうした要素を考慮し、改善すべき業務を選定しましょう。
業務効率化ツールやシステムを導入する
改善対象が明確になったら、次は「仕組み化」です。選定した改善対象の業務に対して、適切なツールやシステムの導入を検討します。
- RPA→ Excelの転記、データ集計など、定型作業を自動化
- SFA→ 顧客情報や案件進捗の一元管理・見える化
- CRM→ 顧客対応履歴の蓄積、再提案タイミングの管理
ツールの力を借りることで人手に頼っていた作業が減り、より重要な業務に時間を使えるようになります。
マニュアル整備・標準化を進める
改善とツール導入が進んだあとは、組織の共通ルールとして定着させるためにマニュアル整備が必要です。
マニュアルを整備する際は以下の点に注意しましょう。
- 手順は「誰が読んでも再現できる」レベルで記載する
- 注意点・よくあるミス・効率的に進めるコツも添える
- 更新タイミング(例:四半期ごと、業務変更時)をルール化する
マニュアルが整っていれば属人化のリスクが減り、新人教育や業務の引き継ぎもスムーズになります。
業務を洗い出して効率化しよう
業務の洗い出しは、「やって終わり」の作業ではありません。組織の状況やメンバーの体制、ツールの導入状況などによって、業務の中身は日々変化しています。そのため、定期的に見直しを行い、常に最適な状態にアップデートしていくことが重要です。
まずは自分が担当している業務や、身近なチームの業務から小さく始めてみましょう。小さな改善の積み重ねが、全体の効率化と業務品質の向上につながります。
業務の洗い出しには業務分解図を活用しよう!
業務の洗い出しなら、まずは業務分解図の無料テンプレートを活用してみてください。
現場に合わせて簡単にカスタマイズできるので、業務の「見える化」と「共有」がすぐに実践できます。

※業務分解図メール受け取りご希望の際は、お問合せ内容に「業務分解図希望」と記載してください。
ーーー
How to Identify Business Tasks: Step-by-Step Workflow Analysis Using Business Process Maps
▼下記記事もおすすめ▼
【図解でわかる】生産性向上と業務効率化の違いとは?意味・目的・施策を徹底比較!