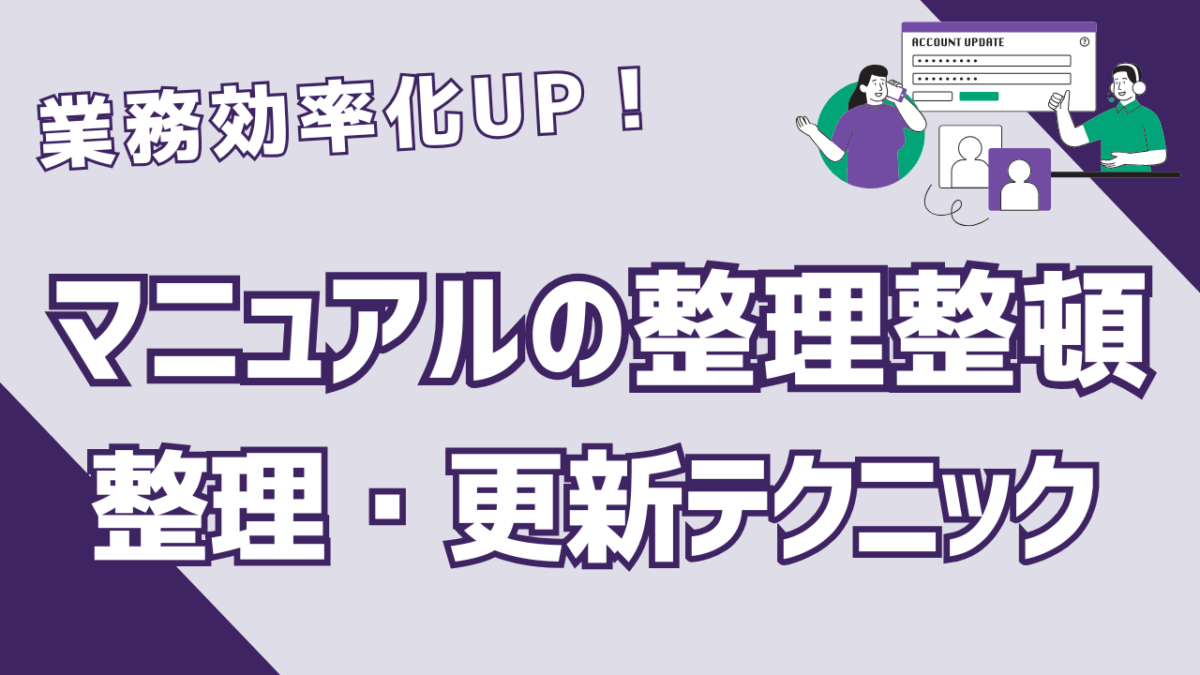作成したマニュアルは、その後きちんと活用されていますか?情報が古くなったり、量が増えて煩雑になっていたりすると、いつの間にか現場では使われなくなり、放置されがちです。また内容が重複していたり、どこに何があるのか分かりにくかったりすると、かえって業務効率を落とす原因にもなります。
この記事では、マニュアルを整理・体系化し、現場で本当に使える形にアップデートするための具体的な手順を解説します。誰でもすぐに実践できるノウハウとして、ツールの活用法、分類方法、更新頻度の目安、運用体制の整備まで網羅。マニュアルの見直しを通して、業務効率を改善していきましょう。
放置されがちなマニュアルを、現場で使われる形にアップデートするための整理・体系化ガイドです。
陳腐化・重複・検索性の低さなどの課題と、現状分析→ルール設計→情報整理→体系化→更新→運用体制整備までの具体的ステップ、種類別の整理方法、継続改善のポイントを網羅した実践記事です。
マニュアル整理の必要性とメリット
なぜマニュアルは煩雑化するのか?
マニュアルは「一度作ったら完成!」ではなく、業務の変化とともに更新・管理していかなければならないものです。しかし実際には、多くの企業が「とりあえず作ったものの、その後の更新は手つかず」の状態に陥っています。すると結果として、現場では使われない、形式だけのマニュアルが量産されてしまうのです。
マニュアルが煩雑化するのは、次のような理由が挙げられます。
- 情報の陳腐化:製品の仕様変更や業務プロセスの改善が反映されていない。
- 情報が多すぎる:余分な情報が多かったり、関連情報が一箇所にまとまっていなかったりで、探すのに時間がかかる。
- 情報が重複している:同じ内容が複数のページ・ドキュメントに分散して記載されており、どれが最新なのかわからない。
- 内容が不十分:説明不足で、読んでも結局誰かに問い合わせする手間が発生してしまう。
- 検索性が悪い:目次が整備されておらず、キーワード検索でも情報がヒットしない。
こうした要因が積み重なると、マニュアルの利用頻度が下がり、現場では徐々に自己流で対応するようになります。すると業務ミスや教育の非効率、属人化といった問題が起こってくるのです。
マニュアル整理がもたらす主なメリット
では、マニュアルを整理、更新することには、具体的にどんなメリットがあるのでしょうか?
マニュアル整理がもたらすメリット①:業務効率の向上
情報が見やすく整理されていると、必要な情報にすぐアクセスできます。例えば、業務中に操作手順を確認する際に探す時間や手間を省ければ、作業時間を大幅に短縮できます。
マニュアル整理がもたらすメリット②:ミスの削減
古い情報や間違った内容を参照することがなくなり、判断や作業の正確性が上がります。とくにクレームやトラブル対応など、正確性が求められる場面ではとても重要です。
マニュアル整理がもたらすメリット③:教育・研修の効率化
新入社員や異動者への引き継ぎする際に、質の高いマニュアルがあれば、現場の負担を減らし早期戦力化が実現できます。また、指導する側による「教え方のバラツキ」も抑制できます。
マニュアル整理がもたらすメリット④:属人化の解消
ベテラン社員の知識やノウハウが、整理されたマニュアルに落とし込まれていれば、その後に誰が対応しても一定の業務レベルを保つことができます。退職や異動に伴うノウハウの喪失といったリスクも防止にもつながります。
マニュアル整理がもたらすメリット⑤:顧客満足度の向上
正確かつスピーディな対応が可能になるため、問い合わせやトラブル対応の質が上がり、顧客満足度も向上します。
マニュアル整理がもたらすメリット⑥:監査・法令対応に有利
近年、組織におけるコンプライアンスや内部統制は重視されています。業務の根拠がきちんとマニュアルとして明文化されていれば、監査対応の手間やリスクを減らすこともできます。
これらの理由から、マニュアルを整理することは単なる一過性の作業、優先度の低い事項ではなく、企業全体のパフォーマンスと信頼性を底上げする重要な取り組みであるといえるでしょう。
マニュアル整理の基本手順と進め方

マニュアルを整理する際は、感覚的に見た目を整えるだけではなく、明確なステップに基づいて進めることが重要です。以下は、実践的かつ再現性の高い整理プロセスです。
1. 現状分析
まず、‟現状あるマニュアルがどのような問題を抱えているか”を洗い出します。全体の構成、更新状況、記載内容の正確性、見やすさ、情報の重複や漏れなど、さまざまな角度から確認します。現場へのヒアリングやアンケート、アクセスログの分析なども有効です。「使われていないマニュアル」には、必ず理由があります。現場の声をデータとして集めることで、改善すべきポイントが見えてきます。
2. 整理の目的を明確にする
次に、‟何のためにマニュアルを整理するのか”を明確にします。この目的によって整理のアプローチは変わるため、ゴールの設定は欠かせません。例えば、
- 新入社員がひとりで業務を理解できるようにしたい
- トラブル時の初動対応を迅速にしたい
- 問い合わせ対応件数を減らしたい
また、この段階で関係部署と目的を共有し、合意を得ておくこともポイントです。
3. 整理方針を決定する
目的が明確になったら、‟どのようなルールで整理するか”を決めていきます。情報の分類軸(業務別、フロー別、職種別など)や、文書構成、書式ルール、命名規則などを統一しましょう。マニュアルが複数ある場合は、管理番号やフォルダ構成、タグ付けなども必要です。情報の探しやすさを重視し、利用者目線で設計しましょう。
4. 情報を取捨選択する
‟現状のマニュアルを精査し、必要な情報だけを残す作業”です。すでに古くなっている情報、重複している内容、曖昧な内容が記載されている部分などは削除、統合していきます。
加えて、不足している情報も追加します。業務の運用フローに照らしあわせて、必要な前提情報や例外的な対応、注意点なども網羅されているかをチェックしましょう。
5. 分類して体系化する
情報がそろったら、構造化して見やすい形に再構築します。目次の作成、章立ての整理、リンク機能の活用、ハイパーリンクやアンカーなどを駆使し、ナビゲーション性を高めます。情報が体系的にまとまっていれば、迷わず目的のページにたどり着くことができます。また、図解やフローチャート、表などのビジュアル要素も効果的です。
6. 更新、修正する
再構築したマニュアルの内容を、最新の情報にアップデートします。業務手順や画面キャプチャの差し替え、制度変更の反映など、事実ベースで記載内容の正確性を高めていきます。修正した内容は関係者に確認してもらい、ダブルチェック体制を整えておくと安心です。
7. ツールを活用する
整理・更新作業を効率化するために、以下のツールを活用すると良いでしょう:
- Excel / Word:小規模なマニュアルの初期整理に有効
- マニュアル作成専用ツール:マニュアル専用のレイアウトやテンプレート、検索機能があり便利(例:Teachme Biz、Kibelaなど)
- クラウドドキュメント:Google DocsやNotionなど、共同編集・履歴管理が可能
- タスク管理ツール:TrelloやBacklogなどで整理作業の進捗を管理
種類別:マニュアルの整理方法
マニュアルには、用途や対象が異なるさまざまな種類があります。それぞれの特徴に合わせた整理の仕方を知ることで、より効果的に活用されるマニュアルにすることできます。
業務マニュアル
業務フローに沿って整理されたマニュアルです。業務の流れを可視化し、実際の現場で誰もが迷わず作業できることを目的としています。
- 業務フローの再設計:無駄な手順や重複項目、ボトルネックとなっている部分を排除する
- タスクごとの分解:業務を細かく分けて、誰が・何を・いつ行うのかを明示する
- 業務に必要な書類・ツールのリンク付け:関連する資料やシステム画面、外部資料などへのリンクを併記する
参考:業務マニュアルの更新方法!効率化と最新情報維持のポイントとは?
操作マニュアル
機械やシステム、アプリケーション等の使い方を解説するものです。そのマニュアルを見て順を追って進めていけば操作できるよう、視覚的な要素とステップごとの明確な説明が必要です。
- 最新の画面キャプチャの活用:古いUIでは混乱を招くため、定期的に画像を更新する
- ステップごとの解説:一手順ずつ番号付きで説明し、分岐条件や補足も記載する
- トラブル対応も掲載:想定されるエラーやFAQもあわせて記載しておく
参考:操作マニュアル作成ガイド!はじめてでも安心、実践で使えるマニュアルの作り方
教育マニュアル
新人教育や研修に使用されるテキスト的なマニュアルです。業務だけでなく、理念や社内文化、組織ならではのルールまで広くカバーする必要があります。
- 目的ごとの構成:業務習得用、社内ルール理解用、キャリア支援用など目的で分ける
- 動画やスライドの活用:理解促進のため、視覚的、聴覚的に訴えるような教材も取り入れる
- テストや確認問題の添付:学んだあとに知識の定着を確認する仕組みを導入する
その他マニュアル(規程集・FAQなど)
- 規程集:ルールや制度に関する文書。改訂履歴や発効日を明記し、誤解を防止する
- FAQ:問い合わせを元に作成し、随時更新する。カテゴリ分けとキーワード検索を徹底しておく
- トラブル対応マニュアル:過去、実際にあった事案をベースに、再発防止策を明記する
種類ごとに適した形式や運用体制を整えることで、マニュアルの有用性は格段に向上します。
マニュアル整理を継続するためのポイント
マニュアルは一度整理したら終わり…ではありません。継続的に改善していく運用体制を作らなければ、すぐに再び形骸化してしまいます。
1. 運用体制の明確化
この先、誰がマニュアルを更新&管理するのかを明確にし、その担当者には権限と責任を持たせます。組織によっては、マニュアル管理チームを設けてもよいでしょう。
担当者の設定例:
- 更新担当者の役割分担
- 部署ごとの更新責任の所在
- 承認フローの明文化
2. 更新頻度の設定
更新のタイミングをあらかじめ決め、ルール化します。定期更新(四半期ごと、半期ごと)に加えて、業務変更や制度変更があった際にはその都度すぐに見直しを実施します。
スケジュール例:
- 毎月第1週:操作マニュアルの確認
- 四半期ごと:業務マニュアルの更新会議
3. 社内への周知・共有
マニュアルを更新したら、関係者にはすぐに共有しましょう。社内ポータル、チャット、メール、掲示板など複数のチャネルを活用すると情報が伝わりやすくなります。また、更新内容を要約した「更新サマリー」、「変更点一覧表」などを添付するとより理解が早まります。
4. フィードバックの仕組み化
更新後も利用者からの意見や要望を集めることで、マニュアルの継続的改善につながります。Googleフォーム、社内チャット、意見箱などを使って、誰でも簡単に投稿できる仕組みを作りましょう。フィードバックを定期的に確認し、改善案として検討・反映するサイクルを設定します。
5. 管理ツールの導入
バージョン管理、アクセス制限、更新履歴の記録などができるツールを活用すると、運用の手間が激減します。
- バージョン管理:いつ・誰が・何を更新したかを明示できる
- アクセス制御:編集権限を限定し、誤操作を防止できる
- 履歴機能:過去のマニュアルとの差分を簡単に把握できる
これらを取り入れることで、属人的な運用を避け、組織として持続可能なマニュアル管理体制を築くことができます。
マニュアルを整理すれば業務が変わる
マニュアルは、単なる文書ではありません。業務の品質を保証し、効率を高め、組織全体の知識を共有するための「資産」です。その資産が活用されていないというのは、組織として大きな機会損失につながるということです。
マニュアルは整理、更新することで「現場で本当に使われる情報源」へと生まれ変わります。定期的に見直し、更新する仕組みを作ることで、ミスの削減、教育コストの低下、顧客満足度の向上、業務の標準化という形で、確実に組織の成果として返ってきます。
「使われるマニュアル」への第一歩は、今あるマニュアルを見直すことから。まずは一つ、目の前のマニュアルの現状把握からスタートしてみてください。
マニュアルの整理はmayclass
マニュアルの整理や作成に取り組む中で、「どこから手を付ければいいかわからない」「業務全体の流れを可視化したい」と感じたら、mayclassの「業務分解図」サービスをぜひご活用ください。
・ 現場の業務を一つひとつ丁寧に分解し、
・ 誰でも理解できる業務構造を“見える化”
・ マニュアル化や引き継ぎにもそのまま活用可能
業務分解図があれば、マニュアル整理が驚くほどスムーズに進みます!
まずは無料相談から、貴社の業務改善をサポートいたします。

※業務分解図メール受け取りご希望の際は、お問合せ内容に「業務分解図希望」と記載してください。
ーーー
Organize and Update Manuals: Techniques to Keep Them Current and Efficient
▼こちらの記事もおすすめ▼
【完全ガイド】Wordでマニュアル作成する方法!デザイン・レイアウトの工夫もご紹介