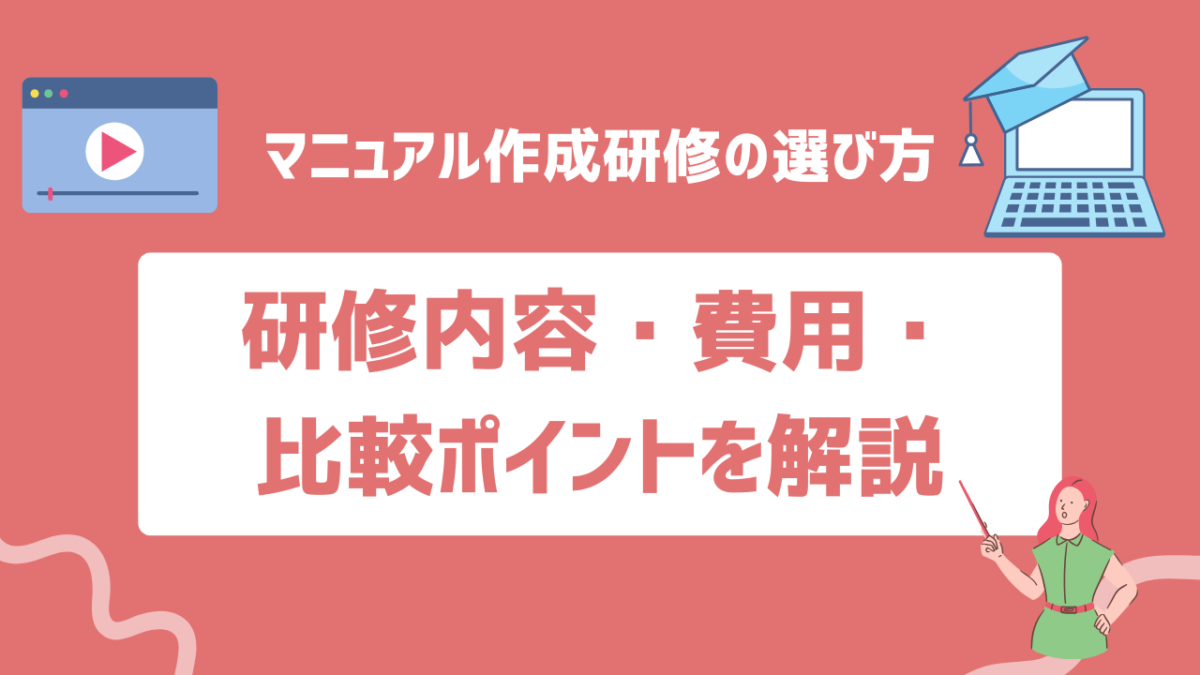「マニュアル作成研修を導入したいけれど、どれを選べばよいのかわからない…」そんなお悩みはありませんか?
高品質なマニュアルは、業務の標準化や新人教育、顧客対応の品質向上など、さまざまな場面で大きな効果を発揮します。しかし、誰でも簡単に作れるものではなく、実は一定のスキルとノウハウが必要です。
そこで注目されているのが、マニュアル作成の基礎から実践まで学べる「マニュアル作成研修」。本記事では、研修を選ぶ際のポイントや効果的なカリキュラム内容、費用の目安などをわかりやすく解説します。社員のスキルアップと業務効率化を同時に実現するための第一歩として、ぜひご活用ください。
「どのマニュアル作成研修を選べばいいか分からない…」という企業担当者向けの記事です。
新人教育や業務標準化に欠かせない“伝わるマニュアル”を作るために、研修の選び方・内容・費用相場・効果測定のポイントをわかりやすく解説。集合・オンライン・社内研修などの違いも比較しながら、社員のスキルアップと業務効率化を両立する方法を紹介しています。
マニュアル作成研修のポイント
マニュアル作成研修の導入を検討しているものの、「どの研修を選べばよいのかわからない」「内容に差がありすぎて比較しにくい」と悩んでいませんか?
効果的なマニュアル作成研修を選ぶには、目的や対象者に合ったプログラムを選ぶことが大切です。ここでは、研修選びで失敗しないためのポイントをわかりやすく解説します。
マニュアル研修の目的を明確にする
まずは、「どのようなスキルを習得させたいのか」を明確にしましょう。目的をはっきりさせることで、適切な研修内容を選びやすくなります。
例えば、「新人教育のためにマニュアル作成の基本スキルを身につけたい」「顧客対応マニュアルの品質を高めたい」など、具体的な目標を設定することが成功の第一歩です。
対象者のレベルに合わせて選ぶ
研修の効果を高めるには、対象者のスキルレベルに合った研修を選ぶことが重要です。
初心者向け研修では、マニュアル作成の基本や構成の考え方などを丁寧に学べる内容が適しています。中級者以上の場合は、より実践的な事例や改善手法を含む研修がおすすめです。
実践的な研修内容かを確認する
研修内容も重要な選定ポイントです。座学だけでなく、ワークショップや演習など、実際にマニュアル作成を体験できるプログラムであるかどうかを確認しましょう。
「学んだ知識をすぐに業務に活かせるかどうか」が、研修の質を左右します。
講師の実績・専門性をチェックする
研修の効果は、講師のスキルにも大きく左右されます。講師がどのような実績・経験を持っているか、専門分野は何かを事前に確認しましょう。
実務経験が豊富で、現場に即したノウハウを提供できる講師であれば、より実践的な学びが得られます。
費用と時間のバランスを見極める
最後に、研修の費用と所要時間も重要な判断ポイントです。自社の予算やスケジュールに合わせて、無理なく導入できる研修を選びましょう。
費用対効果の高いプログラムを選ぶことで、限られたリソースでも高い成果を得ることが可能です。
マニュアル作成研修で学ぶべき内容
マニュアル作成研修では、現場ですぐに役立つ「伝わるマニュアル」を作成するための知識と技術を、体系的に学ぶことができます。ただ単に手順をまとめるだけでなく、誰が読んでも理解しやすく、実際の業務で活用されるマニュアルに仕上げるためには、いくつかの重要なスキルが必要です。ここでは、代表的な研修内容を紹介します。
マニュアル作成の基本:目的・読者・構成
マニュアル作成において最も大切なのは、「誰に」「何を」「どう伝えるか」を明確にすることです。
このパートでは、まずマニュアルの作成目的(例:業務の標準化、新人教育、顧客対応など)を明確にし、次に読者(読み手)のレベルや立場に合わせた情報の伝え方を学びます。また、読みやすく理解しやすい構成(章立て・見出し・目次の設計)についても習得します。
わかりやすい文章の書き方
どれほど情報が正しくても、文章が難解であれば伝わりません。研修では、誰が読んでも理解しやすい文章の書き方を学びます。
具体的には、1文を短く簡潔にまとめる技術、曖昧な表現を避けるコツ、そして専門用語を使用する際には必ず補足説明を加えることなどがポイントです。読み手に負担をかけず、スムーズに理解してもらえる表現力を身につけます。
図表や画像の効果的な活用
文章だけでは伝わりにくい情報も、図や画像を活用することで直感的に理解できるようになります。
このパートでは、業務フローを可視化するフローチャートの作成方法、手順を示すスクリーンショットの使い方、複雑な情報を整理する表の作成など、視覚的要素の活用法を学びます。適切に図表を使うことで、読者の理解度が飛躍的に高まります。
ツールの活用スキル
マニュアルはツールによって仕上がりや作業効率が大きく変わります。研修では、WordやPowerPointなどの一般的なソフトに加え、マニュアル作成専用ツールの活用方法についても学びます。
それぞれのツールの特徴や便利な機能(スタイル設定、目次の自動生成、図表の挿入など)を知ることで、より見やすく、編集しやすいマニュアルを効率よく作成できるようになります。
レビューとフィードバックの習慣化
マニュアルは作って終わりではなく、継続的な改善が求められます。研修では、作成したマニュアルを第三者の視点でチェックし、フィードバックを受けるプロセスの重要性について学びます。
例えば、読み手の理解度を確認したり、誤解を招きやすい表現を改善したりすることで、より実用的で高品質なマニュアルに仕上がります。また、社内でのレビュー体制の整え方や改善サイクルの定着方法についても習得します。
おすすめのマニュアル作成研修形態と提供機関

マニュアル作成研修には、受講スタイルや実施方法によってさまざまな種類があります。自社の目的や受講者の状況、研修にかけられる時間やコストに応じて、最適な形態を選ぶことが大切です。ここでは、代表的な3つの研修形態の特徴と、それぞれのメリット・デメリット、提供機関の例についてご紹介します。
集合研修(対面研修)
集合研修は、講師と参加者が一堂に会して実施される、いわゆる「対面型」の研修です。
【メリット】
・講師から直接指導を受けられるため、疑問点をその場で解消しやすい
・グループワークやディスカッションを通じて、他の参加者との意見交換や気づきが得られる
・集中しやすく、研修に没頭できる環境が整いやすい
【デメリット】
・会場までの移動が必要で、時間や交通費などのコストがかかる
・スケジュール調整が難しく、他業務との兼ね合いが必要
【提供機関の例】
・企業向けの研修会社
・専門教育機関
・業務改善を支援するコンサルティング会社
オンライン研修
オンライン研修は、ZoomやTeams、専用プラットフォームを活用して自宅や職場から参加できる研修スタイルです。
【メリット】
・インターネット環境があればどこからでも受講可能で、全国どこでもアクセスできる
・録画視聴が可能な場合は、復習や欠席時のフォローにも便利
・移動時間が不要なため、業務と両立しやすい
【デメリット】
・対面に比べてコミュニケーションがやや取りづらい場合がある
・演習やグループワークなどの実践型研修では、臨場感や効果が弱まるケースもある
【提供機関の例】
・eラーニングプラットフォーム(例:Udemy、Schooなど)
・企業研修を専門とするオンラインサービスプロバイダー
社内研修(インハウス研修)
社内研修は、自社の業務や課題に合わせてカスタマイズされた内容で実施される研修です。自社で講師を用意したり、外部講師を招いて社内で開催する形式です。
【メリット】
・自社の業務に即した実践的な内容で研修が行える
・業務フローや実際のマニュアルを題材にすることで、より実務に直結したスキルが身につく
・自社独自の教材やガイドラインを使った研修が可能
【デメリット】
・内容の企画・設計や講師の手配など、準備に時間と労力がかかる
・外部講師を依頼する場合は、コストが高くなる場合もある
【実施方法の例】
・社内にスキルを持つ担当者が講師となる内部研修
・マニュアル作成の専門家を招へいして行う外部講師研修
マニュアル作成研修費用相場
研修を選ぶ際には、費用も重要な判断材料になります。一般的な相場感を把握しておくと、適正なコストで導入しやすくなります。
【集合研修】
1人あたり約1万円〜5万円程度です。
会場費や講師料などが含まれるケースが多いです。
【オンライン研修】
1人あたり約5,000円〜3万円程度です。
コストを抑えつつ柔軟に参加できるため人気が高まっています。
【社内研修(講師派遣型)】
1回あたり約10万円〜30万円前後が目安です。
講師の専門性や研修時間、教材費などにより変動します。
マニュアル作成研修後の効果測定とフォローアップ
マニュアル作成研修は、単に受講して終わりでは意味がありません。学んだ知識やスキルを実務でしっかり活かせるようにするためには、研修後の効果測定やフォローアップの仕組みが非常に重要です。研修の成果を定着させるための具体的な取り組みを以下に紹介します。
マニュアル研修効果の測定方法
研修がどれだけ効果的だったかを把握するためには、定量的・定性的な評価が必要です。代表的な方法は次のとおりです。
【アンケート調査】
研修終了後に実施するアンケートでは、参加者の理解度や満足度を把握できます。内容のわかりやすさ、講師の説明力、実務への役立ち度など、多角的に評価することで、今後の研修改善にもつながります。
【スキルチェック】
研修で習得した内容が、実際にどの程度身についているかを確認するためのテストや演習です。事前・事後でスキルレベルの変化を可視化することで、学習効果を客観的に把握できます。
マニュアル研修後の実践とフィードバック
研修で学んだ内容を実際の業務で活用し、実践を通してさらにスキルを深めることが重要です。
【OJT(On-the-Job Training/職場内実習)】
実際のマニュアル作成業務を通じて、学んだ知識を実践に落とし込むことでスキルが定着しやすくなります。上司や先輩のサポートを受けながら作業することで、より実践的な知識が身につきます。
【上司からのフィードバック】
作成したマニュアルを上司が確認し、改善点や良かった点をフィードバックすることで、受講者は自分の課題を明確にし、次回以降に活かすことができます。
スキル定着のための施策
研修直後は理解が深まっていても、時間が経つと忘れてしまうこともあります。継続的に学ぶ機会を設けることで、スキルの定着を図ることが大切です。
【継続学習の実施】
定期的なeラーニング受講や社内勉強会などを通して、知識の復習・アップデートを行いましょう。短時間でも継続的に学習する仕組みが効果的です。
【社内共有会の開催】
研修で得た学びや、実際のマニュアル作成で得た工夫・改善点などを社内で共有する機会を設けましょう。チーム全体のスキル向上や情報共有に役立ちます。
マニュアル作成ガイドラインの作成
研修で学んだ内容をそのままにせず、社内の標準ルールとして明文化することも重要です。マニュアル作成に関する「社内ガイドライン」を整備することで、誰がマニュアルを作っても一定の品質が担保され、属人化の防止にもつながります。
例:文章表現のルール、図表の挿入基準、レビュー手順など
定期的な研修の見直し
マニュアル作成の手法やツールは、時代とともに変化しています。また、業務内容や対象者も変わることがあるため、研修も定期的に見直すことが必要です。
【最新トレンドや業務変化への対応】
新しい作成ツールの導入、DX推進による業務変化、多様な働き方への対応など、最新のニーズを反映した研修内容にアップデートしましょう。定期的に研修を刷新することで、常に実践的で価値のある学習環境を提供できます。
マニュアル作成研修を導入しよう
マニュアル作成研修は、社員のスキルアップだけでなく、業務の効率化や社内のナレッジ共有にも大きく貢献します。効果的な研修を選び、学んだ内容を実務にしっかりと活かすことで、組織全体の生産性向上にもつながります。
ぜひ本記事を参考に、自社に最適な研修形態や内容を検討し、伝わるマニュアル作成のスキルを社内に定着させていきましょう。
ーーー
How to Choose Effective Manual Creation Training: Programs, Costs, and Comparison Points
マニュアル作成研修ならmayclass
mayclassでは、マニュアル作成に関する研修の企画・実施も承っております。
「社員にマニュアル作成スキルを身につけさせたい」「現場に即した実践的な研修を探している」といったご相談にも柔軟に対応可能です。
貴社の業務内容やレベルに合わせたオリジナル研修プランのご提案も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

▼こちらの記事もおすすめ▼
【業務マニュアル作成のコツ】完璧な目次の作り方ガイド!項目例もご紹介