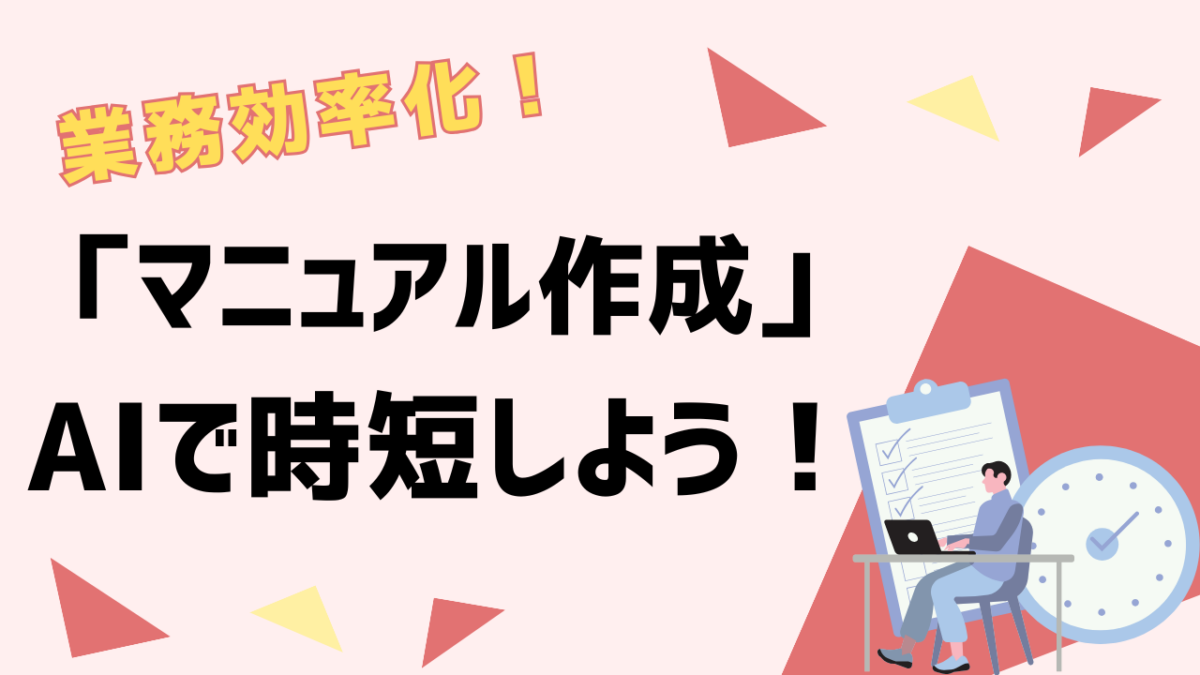業務の効率化を図りたい…それは多くの職場で共通する願いです。
とはいえ、「どこから改善すればいいのかわからない」「導入したツールがうまく機能しない」「効果が実感できない」といった悩みを抱える現場も少なくありません。実は、効率化の第一歩は、業務情報の「共有」と「標準化」。そして、その基盤となるのが“マニュアル”です。今では、ChatGPTなどの無料で使える生成AIツールを活用すれば、面倒に感じがちなマニュアル作成も驚くほどスムーズに始められます。本記事では、AIを使ったマニュアル作成の方法を紹介します。加えて、業務効率化につながるプロンプト作成のコツや、実際に活用する際のポイントについてもわかりやすく解説しますので、ぜひ、最後までご覧ください。
業務効率化を“AI×マニュアル”で実現したい人向けの記事です。
「どこから改善すればいいかわからない」と悩む担当者に向けて、AIを使ったマニュアル作成による業務改善の始め方をわかりやすく解説。主要AIツールの特徴・価格・使いどころ・注意点を比較し、効果的なプロンプトの書き方や導入ステップも紹介。
マニュアルをAIで効率化し、現場の共有・標準化・教育を加速させたい方におすすめの内容です。
なぜ業務効率化にマニュアルが必要なのか?
「属人化が進んでいる」「人によってやり方が違う」「新人教育に時間がかかる」
こうした現場の混乱や非効率は、業務のやり方が体系化されていないことに起因しています。
マニュアルが整備されていれば、業務は標準化され、誰がやっても同じ品質で作業を進められます。結果としてミスが減り、引き継ぎもスムーズになり、教育コストの削減にもつながります。つまり、マニュアルは「業務効率化」のための“基盤”です。「分かりやすく伝える仕組み」があるだけで、組織の動きは格段にスムーズになります。
AIツールなら、効率的にマニュアル作成ができる
業務効率化のために、マニュアルが重要であることは理解していても、実際に整備されている企業はまだ少なく、「つくりたいけれど、手が回らない」「時間がかかるから後回しにしてしまう」という声が絶えません。そこで登場するのが、ChatGPTに代表される生成AIツールです。
たとえば、ある業務の大まかな手順を箇条書きで入力するだけで、自然な文章に整えてくれたり、「この内容をわかりやすい日本語にして」「業務マニュアルっぽくフォーマルに整えて」などの指示にも柔軟に対応してくれます。
AIを使ったマニュアル作成に向いている業務とは?
次のような反復性が高く、手順が明確な業務はAIとの相性が抜群です。
- 社内のルーティン業務(経費申請、勤怠入力、システム操作など)
- オンラインサービスやアプリの利用ガイド
- ヘルプデスク向けFAQ
- 業務フローの手順書(新人研修マニュアルなど)
逆に、「現場での判断が多い業務」「頻繁に仕様が変わる業務」などは、構造化が難しく、マニュアル化そのものに工夫が必要です。そうした場合は、まず部分的にAIを活用し、人が補完することで精度と実用性のバランスをとることが重要になります。
おすすめのAIマニュアル作成ツール
マニュアル作成のプロであるmayclassのライターが活用しているマニュアル作成に便利なAIツールを紹介します。どのツールも無料で始められますが、機能制限がある場合もあるため、導入前に確認が必要です。
| ツール名 | 用途 | メリット | デメリット | 公式サイト | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | 文章作成、構成案、企画、校正、情報収集 | 素早く構成作成でき、多様な表現が可能。有料版は画像生成やコード実行にも対応 | 表現に違和感が出ることがあり、確認や工夫が必要 | https://openai.com/chatgpt | 無料(GPT-3.5)/有料(GPT-4:$20/月) |
| AIチャットくん | 文章作成、相談、質問対応 | LINEで手軽に使え、操作が簡単 | 回答は簡易的で、専門性には弱い | https://www.ai-chat.jp/ | 無料(一部機能制限あり)/有料プランあり(月¥600〜) |
| Gemini | 文章作成、メール文面、情報調査 | Googleサービスと連携し、作業がスムーズ | 日本語は、一部機能や出力品質において、ChatGPTに劣ることも | https://gemini.google.com/ | 無料/Google One加入で有料版利用可(¥2,900/月) |
| Felo | 文章作成、情報整理 | プレゼン作成、思考整理、画像生成を自動で支援 | 学術性・信頼性が求められる用途には不向き | https://felo.ai/ja/search | 無料/有料 |
| Canva | 資料・画像作成 | デザインが統一される/テンプレ豊富 | 細かい調整が難しい | https://www.canva.com/ja_jp/ | 無料/有料(¥1,500/月〜) |
| Napkin | 図表作成、メモ整理 | テキスト入力でビジュアルを自動生成 | シンプル設計のため、複雑な操作には不向き | https://napkin.one/ | 無料(一部有料) |
| Notta | 音声の文字起こし | 精度が高い | 有料でないと文字数などの機能制限あり | https://www.notta.ai/ja | 無料プランあり/有料(月¥1,200〜) |
ChatGPT(OpenAI)
用途: 文章作成、アイデア整理、構成案、校正、リサーチ
メリット: 文章の下書きや構成が素早く作成でき、多彩な表現も可能。有料版では画像生成やコード実行、記憶機能も使えます。
デメリット: 回答に違和感が出る場合があり、出力内容の確認や質問の工夫が求められます。
公式サイト: https://openai.com/chatgpt
価格: 無料(GPT-3.5)/有料(GPT-4:$20/月)
参考:【完全版】ChatGPTで業務効率化!すぐ使えるスゴ技10選|マニュアル作成・可視化まで徹底ガイド
AIチャットくん
用途: 文章作成、相談、アイデア出し、カジュアルな質問対応
メリット: LINE上で手軽に利用でき、アプリのインストール不要。日常的な会話やライトな相談に向いており、親しみやすさが特長。
デメリット: 回答内容はシンプルで、専門性の高い内容や複雑な依頼には不向き。情報の正確性も要確認。
公式サイト: https://www.ai-chat.jp/
価格: 無料(一部機能制限あり)/有料プランあり(月¥600〜)
Gemini(Google)
用途: ライティング、メール作成、情報検索
メリット: GmailやGoogleドキュメントと統合されており、日常業務との連携がスムーズ。
デメリット: 日本語での精度や一部の出力内容が、ChatGPTと比較してやや劣ることがあります。
公式サイト: https://gemini.google.com/
価格: 無料/Google One加入で有料版(月¥2,900)
Geminiについては、Geminiとは?無料版でできること、特徴と便利な使い方、他のAIとの違いをわかりやすく解説の記事でも詳しくご紹介しています。併せてご覧ください。
Felo
用途: 情報整理、思考の可視化、プレゼン支援
メリット: キーワードからの画像生成やマインドマップ、資料自動作成など多機能。思考整理に役立ちます。
デメリット: 学術的な文献調査や正確性が重要な情報には不向き。
公式サイト: https://felo.ai/ja/search
価格: 無料/有料プランあり
Canva
用途: プレゼン資料・SNS画像・チラシなどのデザイン作成
メリット: 統一感のあるデザインが簡単にでき、テンプレートも豊富。非デザイナーでも使いやすい。
デメリット: 細部のカスタマイズや自由度はやや制限される場合があります。
公式サイト: https://www.canva.com/ja_jp/
価格: 無料/有料プラン(月¥1,500〜)
参考:Canvaでマニュアル作成する方法!デザイン初心者でもわかりやすく作れるコツ
Napkin
用途: アイデア整理、図解作成、メモの可視化
メリット: 入力したテキストをもとに、直感的なビジュアルをAIが生成。メモを視覚的に整理できます。
デメリット: シンプル構造ゆえに、詳細な分類や複雑な設定には不向き。
公式サイト: https://napkin.one/
価格: 無料(一部有料機能あり)
Notta
用途: 会議やインタビューなどの音声文字起こし
メリット: 高精度な認識技術で、手間なく文字に起こせます。多言語対応もあり。
デメリット: 無料版では文字数や機能に制限があるため、長時間利用には有料プランが必要。
公式サイト: https://www.notta.ai/ja
価格: 無料プランあり/有料(月¥1,200〜)
AIツールの使い方

AIツールを活用することで、マニュアル作成や文章の整備がスムーズに行えます。ここでは、基本的な機能と活用のポイントを紹介します。
AIツール:プロンプト作成のコツ
AIに期待通りの成果を出してもらうためには、プロンプト(指示文)の設計が最も重要です。以下の工夫をすることで、より精度の高いアウトプットが得られます。
目的をはっきり伝える
例えば、以下のように目的をはっきりと伝えると良いでしょう。
- 「業務マニュアルとして簡潔にまとめてください」
- 「新人にもわかるようにやさしい言葉に言い換えてください」
何をしたいのか、どのようなトーンで仕上げたいのかを明示すると、AIはその意図を正確に汲み取ります。
出力形式を具体的に指示する
- 「箇条書きで整理してください」
- 「表形式で比較してください」
フォーマットを指定することで、読み手にとって見やすい形で出力されます。
追加指示で修正を繰り返す
- 「この部分をもっと具体的に」
- 「専門用語の説明を追加してください」
一度の出力で完璧なものを求めず、追加の指示を繰り返すことで質を高めるのがポイントです。
AIツール:活用例と応用のヒント
AIツールは、以下のような業務に役立てることができます。
■ 業務マニュアルのたたき台を作る
マニュアルの構成や文章をAIに作ってもらい、あとから内容を調整することで作業時間を大幅に短縮できます。
■ 社内共有文書の文章チェックやわかりやすさ向上
社内向けのお知らせやルール説明文を、わかりやすく書き直したり、敬語や表現の統一をしたりするのに便利です。
■ スピーチやプレゼン資料のトーン調整
カジュアル・ビジネス向けなど、場面に合った雰囲気に文章を整えてもらうことができます。
■ よくある質問(FAQ)や定型文の作成・整理
問い合わせ対応用の定型文や、質問に対する答えを整理しておくFAQの作成にも活用できます。
AIマニュアル作成ツール導入のステップ
ニーズの整理(目的と課題の明確化)
まずは、ツールを導入する理由を明確にします。
「どんな業務を効率化したいのか」「どのような課題を解決したいのか」を具体的に洗い出します。
- 属人化している業務マニュアルを可視化したい
- 作業手順のミスを減らしたい
- 問い合わせ対応を自動化したい
この段階で関係部署へのヒアリングを行い、導入目的を社内で共有しておくことが重要です。
ツールの比較・選定(機能・コスト・使いやすさなど)
複数のAIツールを比較し、次の観点から自社に合ったものを選定します。
- 機能性:自動生成・編集・更新のしやすさ
- 操作性:現場スタッフが使いやすいUI/UXか
- コスト:初期費用・月額費用・ユーザー数課金の有無
- サポート体制:導入後のフォローやFAQ機能の充実度
- 拡張性:他システムとの連携が可能か(例:チャットボットや社内ポータル)
可能であればデモを依頼し、実際の画面を見ながら検討しましょう。
情報の整理とデータ準備
AIが学習・生成する元となる情報を整備します。
- 現在使用しているマニュアル・FAQ・手順書を集約
- 情報の重複や内容の古さを確認し、必要に応じて修正
- ファイル形式(PDF/Word/テキストなど)を統一し、AIが読み取りやすい形に変換
情報が不足している場合は、現場からヒアリングして補完することも大切です。
トライアル運用(試験導入での検証)
一定の部署または限定的な業務範囲でツールを試験導入します。
- 実際の業務に近い形でマニュアルを作成・活用
- 出力される内容の正確さや表現のわかりやすさを確認
- 現場からのフィードバックを収集し、調整・改善ポイントを洗い出す
この段階で、「どの程度作業負担が減るか」などの効果測定を行うと、社内説明にも役立ちます。
本格導入と定着支援
トライアルの結果をもとに導入の意思決定を行い、組織全体へ展開します。
- 利用マニュアルやガイドラインを整備
- 社内説明会や研修を実施して、操作方法を共有
- 活用を促進するため、運用ルール(更新頻度、担当者、フィードバック窓口など)を明確にする
定期的に利用状況や改善点を見直すことで、ツールの効果を最大限に活かせます。
AIツール活用のはじめ方と注意点
AIに不慣れな方でも、以下のステップで導入・活用がスムーズに進められます。
STEP 1|業務の洗い出しと整理
まずは、AIで対応したい業務を選びます。
「どの作業をマニュアル化したいか」「どんな手順があるか」を、紙やメモなどでざっくり書き出して全体像を整理しましょう。
- 新人向けの作業手順書を作りたい
- 問い合わせ対応のテンプレートを作りたい
STEP 2|AIに依頼する内容をまとめる
AIに伝えるポイントを明確にします。
以下のような項目を簡潔にまとめると、より的確な出力が得られます。
- どんな業務か(例:備品発注の流れ)
- 誰向けか(例:新入社員、パートスタッフ)
- どんな雰囲気で書いてほしいか(例:やさしく丁寧に)
- 出力形式(例:箇条書き、手順形式、Q&A形式)
STEP 3|AIに依頼してマニュアルを作成する
ChatGPTなどのAIに、上記内容をもとに指示を出します。
「◯◯業務について、新人向けにわかりやすく手順をまとめてください」と依頼するイメージです。
STEP 4|内容を確認・修正する
AIが出力した内容はそのまま使わず、必ず自分の目でチェックを。
実際の業務と合っているか、不足点や言い回しの修正が必要かを確認し、必要に応じて編集します。
STEP 5|整えて、社内で共有する
完成したマニュアルは、見やすく整理して保存します。
CanvaやGoogleドキュメント、社内Wikiなどでフォーマットを整え、必要な人がアクセスしやすい場所で共有しましょう。
活用時の注意点
AIは非常に便利なツールですが、活用する際には情報の取り扱いに十分な注意が必要です。特に、個人情報や企業の機密情報は、安易にAIに入力しないよう徹底する必要があります。また、利用しているAIツールのプライバシーポリシーや利用規約を事前に確認し、どのような情報が保存・学習に使われる可能性があるのかを理解しておくことも大切です。
さらに、社内全体で安全にAIを活用するためには、AI利用に関するガイドラインを整備することが有効です。たとえば「入力してはいけない情報の例」「使用可能なAIツールのリスト」「生成された内容のチェック体制」などを明文化しておくことで、安心してAIを活用できる環境を整えることができます。
AIでマニュアル作成を検討されている方は併せてマニュアル作成に無料AIを活用!コストを抑えて効率化する方法とおすすめツールの記事もご覧ください!
プロに頼むという「最も確実な時短」
AIは、マニュアル作成に便利なツールですが、上手に活用するには、プロンプトの習得など“使う技術”が必要であり、情報収集といった学習コストも必要です。場合によっては、マニュアル作成の専門家であるプロに依頼するのが結局時短になり、効率的な業務もあります。
プロのライターは、単に文章が書けるだけでなく、以下のようなスキルを持っています。
- 業務の流れをヒアリングし、論理的に整理・言語化する力
- 読み手のスキルレベルや使用環境に応じた適切な構成・文体の設計力
- 更新・運用しやすいドキュメント構造の提案力
加えて、最近ではAIツールを適切に併用するライターも増えており、AIの強み(スピードや生成力)と人の強み(判断力や構成力)を組み合わせた、高品質かつ効率的なマニュアル制作が実現できます。
業務効率化の鍵は、「誰でも迷わず動ける仕組み」をつくること。その第一歩として、マニュアルの整備をAIの力とともに始めてみてはいかがでしょうか。
ーーー
Speed Up Manual Creation with AI: Save Time and Improve Workflow
マニュアル作成ならmayclassへ
mayclassでは、マニュアル作成の専門家が貴社のニーズに合わせたマニュアルを提供します。
- プロによるヒアリング
業務内容を丁寧にヒアリングし、特性を的確に捉えたマニュアルを作成。 - 優先度に基づくマニュアル化
重要な業務から優先的に対応し、早期の業務改善を実現。 - わかりやすいデザイン
読みやすく、視覚的にも整理されたフォーマットを提案。

▼こちらの記事もおすすめ▼
AIマニュアル作成ツールで時間とコストを削減!選び方と活用法