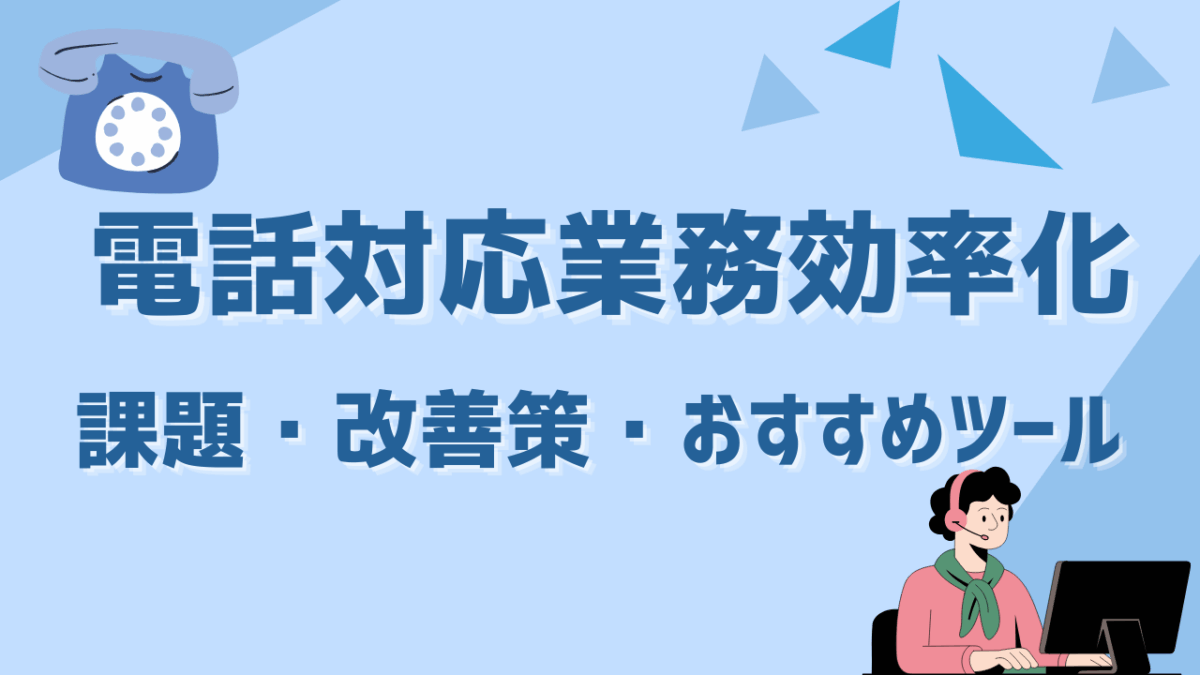電話対応は、顧客との信頼関係を築くうえで欠かせない業務です。
一方で、一件ごとの対応に時間を取られやすく、担当者の負担が大きいのも実情です。
「メモの取り忘れ」「伝達ミス」「誰が対応したか分からない」といったトラブルは、現場で頻発しやすい課題の一つです。
近年では、リモートワークやハイブリッド勤務の普及により、電話対応の分散化・属人化が進んでいます。結果として、情報共有や引き継ぎがスムーズに行えず、コア業務への集中が難しくなっている企業も少なくありません。
本記事では、こうした電話対応業務の課題を整理したうえで、
・現場ですぐに実践できる効率化の具体策
・業務改善と相性の良いツールの選び方
・AIやマニュアル整備を活用した再現性ある改善ステップ
を分かりやすく解説します。
単なる「ツール導入」ではなく、仕組みとして効率化を定着させる方法を知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
企業の電話対応業務に課題を感じている経営者・管理者・現場担当者向けに、属人化や情報共有不足、リモート環境での対応負担などの問題を整理し、効率化するための実践的な方法をわかりやすく解説しています。対応ルールの整備、代行サービス、通話記録・共有、チャット誘導、AI応答システムなどの改善策を紹介し、Google VoiceやZoom Phoneなどおすすめのツールもまとめています。電話対応の負担を軽減し、生産性を高めたい方に役立つ総合ガイドです。
電話対応業務における主な課題
電話対応は日々の業務の中で発生頻度が高く、一見シンプルに見えて属人化しやすい業務です。対応内容が個人に依存してしまうと、品質のばらつきや引き継ぎミスにつながりやすく、顧客満足度にも影響を及ぼします。ここでは、現場で特に多く見られる課題を整理します。
1. 一人に業務が集中しやすく、属人化が進む
電話対応は「担当者の経験や感覚」に依存しやすい業務の代表例です。
たとえば、「この取引先はAさんが詳しい」「この案件はBさんでないと対応できない」といった状況が自然と生まれ、同じ問い合わせでも担当者によって対応方針が異なることがあります。
結果として、特定の人に電話が集中し、その人が不在になると対応が止まる──いわゆる業務の属人化が進行します。
属人化が進むと、引き継ぎや新人教育にも時間がかかり、業務効率が低下。さらに、情報が個人の頭の中に留まることで、チーム全体のパフォーマンスにムラが生じます。
こうした状態を放置すると、「電話対応=特定の人の仕事」になり、誰もが対応できる仕組みづくりが難しくなってしまいます。
2. メモ・伝達ミスによるトラブル発生
電話対応では、話しながらメモを取る必要があるため、聞き間違いや書き漏れが起きやすいものです。
口頭でのやり取りは記録が残らないため、「確かに伝えた」「聞いていない」という認識のズレがトラブルに発展することもあります。
特に紙のメモや付箋などで管理している場合、紛失・誤読・転記漏れといったリスクが高まり、担当者が変わるたびに情報が断絶してしまいます。
たとえば、納期変更の連絡をメモしたつもりがチームに共有されず、結果的に顧客との信頼を損なうミスにつながるケースも珍しくありません。記録が残らないということは、「振り返りができない」ということでもあり、ミスの再発防止や業務改善にも支障をきたします。
3. 応対履歴の共有不足(誰が何を対応したか不明)
電話対応後に「誰がどんな内容で対応したのか」が共有されていないと、同じ問い合わせに対して複数人が重複対応してしまうことがあります。
たとえば、営業担当とサポート担当の両方が同じ顧客に別々に折り返しをしてしまい、顧客から「同じ説明を何度も受けている」と不満を持たれるケースです。
また、担当者が退職・異動した際に履歴が残っていないと、過去のやり取りをたどることができず、対応の再現性が失われます。
共有不足の背景には、「口頭伝達で済ませてしまう文化」や「システム上での記録手段が整っていない」といった構造的な問題があります。この状態が続くと、顧客対応の一貫性が失われ、社内の信頼関係やチームワークにも悪影響を及ぼします。
4. 電話本数が多く、コア業務に集中できない
電話が頻繁に鳴る職場では、業務のリズムが何度も中断され、生産性が大幅に低下します。
1本の電話が短時間でも、対応・記録・共有の時間を含めると1件あたり5〜10分を要することもあり、1日に数十本となれば大きな負担です。
特に少人数体制の企業では、「電話が鳴るたびに作業が止まる」状況が慢性化し、重要な資料作成や顧客対応の準備が後回しになります。
このような中断が続くと、集中力の低下やミスの増加にもつながり、結果的に残業時間の増加やモチベーション低下を招きます。コア業務に時間を割けない状態が続けば、「電話に追われる職場」から抜け出せなくなるリスクがあります。
5. リモートワーク環境で電話対応が難しい
テレワークの普及により、オフィスの代表電話をどのように受けるかが新たな課題となっています。自宅勤務中の社員が会社の電話に直接出ることはできず、オフィス勤務者に負担が集中するケースが増えています。
代替として個人の携帯電話を利用する場合もありますが、個人情報の流出リスクやプライバシーの問題が懸念されます。
また、リモート環境では、誰がどの電話を受けたのかが共有されにくく、折り返し対応の遅れや二重対応が発生しやすくなります。
こうした状況では、「電話を取る」こと自体がストレス要因となり、チーム全体の連携にも影響を及ぼします。リモートワークを前提とした業務設計を行わない限り、電話対応が組織の分断を生む要因となってしまうのです。
電話対応業務を効率化する5つの方法
電話対応の非効率を解消するには、単に「電話を減らす」ことではなく、ルール整備・仕組み化・ツール活用の3つを組み合わせることが重要です。ここでは、業務の属人化を防ぎ、誰でも一定水準で対応できるようにする5つの方法を紹介します。
1. 対応ルール・マニュアルを整備する
まず取り組むべきは、「誰が、どんな場合に、どう対応するか」を明確にすることです。
応答の流れや一次対応・転送基準をマニュアル化することで、担当者ごとの判断差をなくし、教育コストを削減できます。
また、FAQや応答スクリプトを整備すれば、新人や派遣スタッフでも一定品質で対応可能になります。
「初めて電話を取る人でも迷わない仕組み」を整えることが、効率化の第一歩です。
【ポイント】
- 一次対応・転送・折り返しの判断をフローチャート化
- 「言い回し集」や「よくある質問」を社内共有フォルダで一元管理
2. コールセンター・代行サービスを活用する
社内リソースが限られている場合は、電話代行やカスタマーサポートサービスの活用も有効です。
専門スタッフが一次受電を担当することで、社内は本来のコア業務に集中できます。
たとえば、営業電話のフィルタリングや、営業時間外の一次受付を外部に委託するだけでも、担当者の負担は大幅に軽減されます。最近では、秘書代行・問い合わせ代行など、業種や目的に応じた柔軟なサービスも増えています。
【ポイント】
- 一次対応を委託し、折り返し対応のみ社内で実施
- 対応ログを共有できるサービスを選定
3. 電話内容を記録・共有できる仕組みを導入する
電話内容を記録し、履歴として残すことで「誰が・いつ・何を対応したか」を可視化できます。CRM(顧客管理システム)やSFA(営業支援システム)と連携させることで、対応履歴を自動で蓄積・共有する仕組みが整います。
また、録音や自動文字起こし機能を活用すれば、報告書や日報の作成もスムーズになります。聞き漏らしや伝達ミスを防ぐだけでなく、対応品質の改善にもつながります。
【ポイント】
- 録音データ+文字起こしで「見える電話記録」を残す
- CRM連携で履歴をチーム全体で共有
4. チャットや問い合わせフォームへ誘導する
すべての問い合わせを電話で受ける必要はありません。
チャットやWebフォームを設けて、電話以外の窓口に誘導することで対応件数を分散できます。
特に、よくある質問や確認事項はチャットボットに置き換えると、24時間対応が可能になります。
顧客側にとっても「待たずに解決できる」利便性が向上します。
【ポイント】
- ホームページに「よくある質問」「問い合わせフォーム」を設置
- チャットボットで営業時間外対応を自動化
5. AIツール・自動応答システムの導入
近年では、AI音声応答(IVR)やAIオペレーターの導入が進んでいます。
要件を自動で振り分けたり、AIが一次応答を行ったりすることで、担当者が対応すべき件数を大幅に減らせます。
さらに、通話内容の自動文字起こしや要約機能を活用すれば、会話記録の整理や報告資料作成の時間も短縮可能です。
AIを活用した“電話業務の自動化”は、今後の効率化の中心的な手段となるでしょう。
【ポイント】
- AIが一次対応を行い、要件に応じて担当部署へ転送
- 通話内容を自動でテキスト化・要約して蓄積
電話対応業務を効率化できるおすすめツール
電話対応の効率化を進めるうえで、ツールの選定は欠かせません。
ここでは、目的別に活用しやすい代表的なツールを紹介します。
「どの課題にどう効くのか」という観点から、自社に合った組み合わせを検討してみましょう。
Google Voice
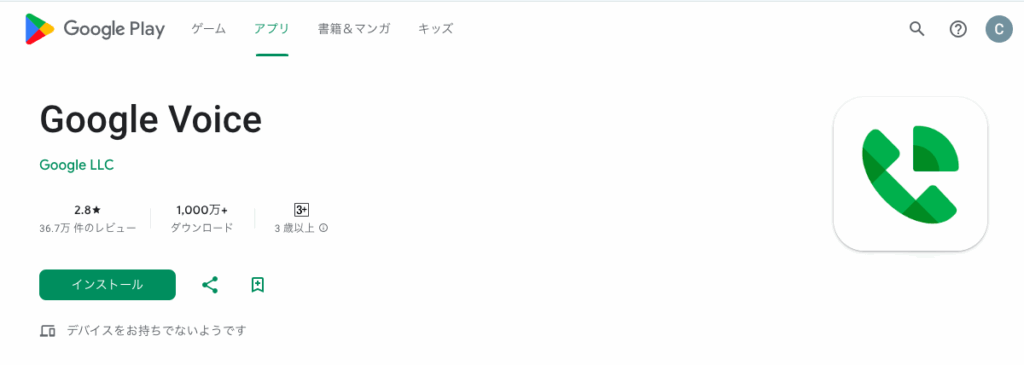
特徴
Googleが提供するクラウド電話サービス。Gmail・Googleカレンダー・Google Workspaceとの連携がスムーズで、インターネット環境があればどこからでも発着信が可能です。
代表番号を使ってリモート勤務中でも受電・発信ができ、個人の携帯電話番号を使わずに業務対応できます。
活用シーン
- 在宅勤務や外出先で代表電話を受けたいとき
- Google Workspaceを社内で利用している企業
導入メリット
- クラウド上で通話ログを自動保存し、対応履歴を確認可能
- Googleアカウントで統合管理できるため、導入・運用が簡単
活用ポイント
- リモート勤務でも代表番号で発着信可能
- 通話ログをクラウドで管理し、対応漏れを防止
Zoom Phone

特徴
Web会議ツール「Zoom」に電話機能を統合したクラウド電話システム。会議・商談・電話を同一アプリで管理でき、操作性が統一されています。通話履歴や録音データも自動保存され、社内共有が容易です。
活用シーン
- 社内外とのやり取りをすべてZoomで完結させたい場合
- 海外拠点やリモートチームとの連携が多い企業
導入メリット
- 会議・通話履歴を一元管理できる
- オンライン商談と電話対応を切り替えながら実施可能
活用ポイント
アプリひとつで会議と通話を管理
自動保存された通話履歴をチームで共有
LINE WORKS Call

特徴
LINE WORKSに搭載されたビジネス向け通話機能。顧客との通話履歴がチャットルームに自動送信されるため、対応の見える化が可能です。LINEとの親和性が高く、社内外コミュニケーションを統合できます。
活用シーン
- 顧客対応後に内容をすぐ共有したい場合
- 社内チャットと電話を一体で運用したい場合
導入メリット
- 通話直後に対応履歴をチーム共有
- 社内外とのやり取りを同一プラットフォームで完結
活用ポイント
対応内容をチャットで即共有し、情報漏れを防ぐ
顧客対応履歴をリアルタイムで可視化

特徴
ビジネスチャットツール「Chatwork」と電話機能を連携させ、通話履歴をチーム内で共有できる仕組み。誰が・いつ・何を話したかを記録し、複数人でのフォロー体制を整えられます。
活用シーン
- 複数人で同じ顧客を対応している部署
- 通話後の報告・共有を自動化したい場合
導入メリット
- 電話対応後の共有漏れを防止
- 対応の引き継ぎがスムーズになり、属人化を防ぐ
活用ポイント
通話履歴を自動共有し、対応状況を即時把握
チーム全体でフォロー体制を構築
AI GIJIROKU

特徴
AIが会話内容をリアルタイムで文字起こし・要約する議事録作成ツール。ZoomやGoogle Meet、電話音声などに対応し、話者ごとの発言も自動識別します。
活用シーン
- 通話内容の議事録化や報告書作成を効率化したい場合
- 社内会議や営業報告を自動記録したい場合
導入メリット
- 会話内容を自動で記録・要約
- 文字起こし結果をそのまま議事録・報告書に転用可能
活用ポイント
通話内容を自動でテキスト化
AIによる要約で報告作業を時短化
Notta

特徴
多言語対応のAI文字起こしツール。録音・録画・オンライン会議の内容をリアルタイムで文字化し、クラウド上で共有できます。キーワード検索や翻訳機能も搭載。
活用シーン
- 海外顧客との商談記録
- 通話内容を他部署と共有する際の要約作成
導入メリット
- 会話の重要ポイントを自動抽出
- チーム共有がスムーズで、情報伝達ミスを防止
活用ポイント
会話ログをリアルタイムで可視化
多言語対応で海外チームとも連携可能

特徴
日本語の音声認識に強みを持つAI文字起こしツール。医療・金融・製造など専門用語の多い業界で高精度に対応でき、既存システムとの連携にも柔軟です。
活用シーン
- 医療・士業・金融など専門業種の通話文字起こし
- 専門用語が多い顧客対応の議事録化
導入メリット
- 専門用語にも対応する高い認識精度
- 国内企業のニーズに合わせたUI・セキュリティ設計
活用ポイント
専門業種でも高精度の文字起こし
国内サポートが充実し、安心して導入可能
カイクラ(KAIKURA)

特徴
特徴
着信情報を自動表示し、顧客対応履歴を一元管理できるクラウド電話システム。中小企業でも導入しやすい手軽さが特徴で、SMS送信やメモ登録など顧客対応の即時記録が可能です。
活用シーン
- 顧客対応履歴をチームで共有したい企業
- コール数の多い営業部門・カスタマーサポート部門
導入メリット
- 対応履歴の一元化でミスや重複対応を防止
- 顧客情報の可視化で迅速な応対を実現
活用ポイント
電話+CRM+SMSを統合して対応スピードUP
社内全員が顧客状況をリアルタイムで把握
IVRy(アイブリー)

特徴
ノーコードでIVR(自動音声応答)システムを構築できるクラウドツール。営業時間外や繁忙時でも自動で電話応答が可能で、要件に応じて転送やメッセージ取得を自動化します。
活用シーン
- 小規模事業者や店舗での一次対応
- 営業時間外の問い合わせ受付
導入メリット
- 専門知識不要で自動応答を構築
- 人手不足の時間帯でも対応を継続可能
活用ポイント
営業時間外の一次対応を自動化
着信内容の仕分けで担当者の負担を軽減
電話対応業務効率化を定着させるためのポイント
電話対応の効率化は、ツールを導入しただけでは長続きしません。
一時的に業務が楽になっても、運用ルールが曖昧なままでは、数ヶ月後には元に戻ってしまうケースもあります。
ここでは、改善を“定着”させるための3つのポイントを紹介します。
1. 定期的なマニュアル更新と改善サイクル(PDCA)
対応ルールやスクリプトは、時間の経過とともに古くなります。
新しい問い合わせ内容や顧客層の変化に合わせて、定期的にマニュアルを見直すことが重要です。
「現場で発生した課題 → 対応改善 → 反映 → 教育」というサイクルを回すことで、効率化の仕組みが継続します。
【実践のヒント】
- 月1回の見直しミーティングを設定し、改善提案を共有
- FAQ更新・テンプレート改訂を担当者がローテーションで実施
2. 対応品質の見える化・フィードバック共有
効率化と同時に重要なのが、対応品質の維持・向上です。
録音データや文字起こし内容を活用して、応対スキルを客観的に振り返る仕組みを整えましょう。
定期的なフィードバック共有を通じて、チーム全体のレベルアップを図ることができます。
【実践のヒント】
- 通話内容のサンプルを共有し、良い対応事例を学ぶ
- 評価基準を可視化し、改善をポジティブに捉えられる文化をつくる
3. “個人のスキル”ではなく“仕組み”で支える文化づくり
電話対応の属人化を防ぐには、「経験豊富な人に頼る体制」から「誰でも一定品質で対応できる体制」へと変える必要があります。
そのためには、マニュアル・FAQ・ツールの整備を通じて“仕組みで支える文化”を浸透させることが大切です。
【実践のヒント】
- 対応手順・判断基準を共有ドキュメント化
- 教育や引き継ぎを“感覚”ではなく“仕組み”で行う
効率化のゴールは、電話を減らすことではなく、「誰が対応しても同じ品質を保ちながら顧客満足度を高める」ことです。
仕組み化とツール活用を両輪に、持続可能な改善体制を構築しましょう。
電話対応の効率化は「仕組み」と「ツール」で実現できる
電話対応の非効率さは、多くの企業が抱える共通課題です。
「誰が」「どのように」対応しているのかが不透明なままでは、ミスや属人化が避けられません。
まずは、現状の業務を可視化し、課題を明確にすることが改善の第一歩です。
そのうえで、マニュアル整備・ルール設計・AIツール導入といった手段を組み合わせることで、属人化や情報の分断を防ぎ、誰でも均一な品質で対応できる体制を築けます。
重要なのは、ツールを導入して終わりではなく、定期的な見直しと仕組みの改善サイクルを回し続けることです。
電話対応の効率化は、単なる“時短”ではなく、
顧客満足度を高め、チーム全体の生産性を底上げする仕組みづくりにほかなりません。
日々の小さな工夫を積み重ねながら、誰もが安心して対応できる環境を整えていきましょう。
業務改善・業務効率化ならmayclass
「電話対応の可視化」「マニュアル化」「AI活用による改善サイクル構築」を検討されている場合は、当社の業務可視化・改善サービス「業務分解図テンプレート」や「flowzoo」を活用してみてください。
現場ヒアリングから仕組み設計まで、再現性ある業務改善の仕組みづくりをサポートします。

ーーー
How to Streamline Telephone Support Operations: Challenges, Solutions, and Top Tools
▼下記記事もおすすめ▼
【最新AI徹底解剖】Geminiアプリは何がすごい?できること5選と活用術