誰かが休むたびに業務が滞る、急に欠員が出て引き継ぎに準備がかかる。そんなよくある現場の課題を解決するには、「業務マニュアルの標準化」が欠かせません。標準化されたマニュアルがあれば、誰が作業を引き継いでもスムーズに対応できるだけでなく、業務の仕組み化が進み、全体の業務効率化にもつながります。また業務マニュアルの標準化は、一人ひとりの業務、提供する製品やサービスなどの質を均一に保つために最も効果的な方法でもあります。
本記事では、業務マニュアルを作ることのメリットや効果、生産性を高めるためのマニュアル作りの具体的なポイントとコツを解説します。
この記事は、業務マニュアルの標準化を進めたい方におすすめです。
「標準化とは何か」「マニュアル化との違い」から始まり、業務マニュアルの標準化による4つの効果(属人化防止・品質向上・生産性向上・教育コスト削減)を解説。さらに、「目的の明確化」「フォーマットや用語の統一」「レビュー体制の整備」など8つのポイントと、「現状把握→手順定義→作成→教育・改善」の4ステップ実践法を紹介しています。
誰が担当してもスムーズに業務を進められる“使えるマニュアル”づくりのヒントが詰まった内容です。
そもそも、業務の標準化とは?
業務の標準化とは、“業務プロセスや作業手順を、誰が見ても同じようにできるように統一すること”です。それによって「誰かがいないと業務が進まない」、「進め方ややり方がわからない」といった属人化を防ぐことができます。特に、業務マニュアルを標準化することは、組織全体の生産性を向上させる上でとても重要です。
標準化とマニュアル化の違いとは?
標準化とマニュアル化について、ここで改めて定義しておきます。標準化は、業務プロセスや手順を統一することが目的です。一方、マニュアル化は、標準化したものを書類やデータなどで具体化することです。つまり、業務の標準化はあらゆる仕事における土台であり、マニュアル化はそれを形にする作業というわけです。
たとえば、飲食店での接客マニュアルで考えてみるとわかりやすいでしょう。「お客様を迎える際の言葉」「注文を取る順序」「会計時の対応」などが明確に定義されて“標準化”されており、その手順が書面などで“マニュアル化”されていれば、新人スタッフでも迷うことなく業務に取りかかることができます。このように、標準化とマニュアル化はどちらも密接に関連しており、組織の仕組み化には欠かせない要素なのです。
なぜ業務マニュアルの標準化が必要なのか?
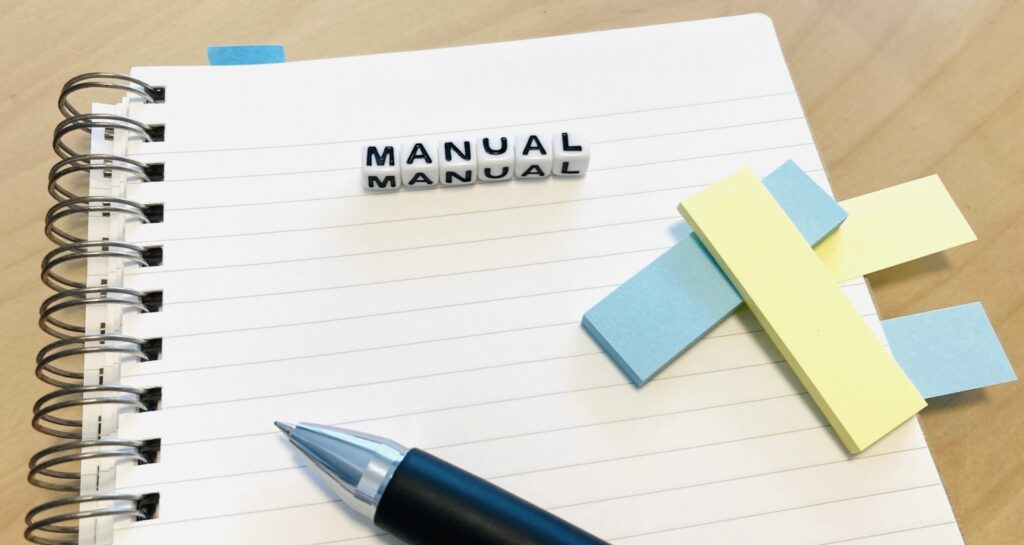
業務マニュアルの標準化とは、“統一された業務プロセスや手順を、誰でも理解しやすくわかりやすい形式で記録・共有すること”です。単に手順が書かれている業務マニュアルを作っただけでは機能せず、標準化されていなければ意味のないものになってしまいます。
業務マニュアルの標準化が必要な理由
理由1:業務の属人化を防ぐため
業務が特定の人に依存しており、担当者によって業務の進め方が異なると、その人が急に休んだり退職したりした際に大きな支障が出ます。また、個人に責任や負担が増えることで必要以上にストレスがかかり、モチベーションの低下を引き起こすなど、結果的に離職につながる可能性も懸念されます。
理由2:ミスを減らし、品質を安定的に提供するため
業務マニュアルの標準化は、作業ミスを防ぎ、安定した品質を確保するために不可欠です。特に製造業においては、一つの工程でミスが起きたり、人によって業務の質にばらつきが生じたりすると、業務全体に影響します。
理由3:生産性、作業効率を高めるため
業務プロセスが可視化されずにブラックボックス化してしまうと、改善点を見つけにくく生産性が向上しないという課題が発生します。また違う人が同じ作業をしてしまう二重作業も発生することがあります。
理由4:教育コストを削減するため
新しいスタッフを育成する際に標準化されたマニュアルがないと、その都度教えなければならない、人によって指導内容が違うといった指導のムラが発生してしまいます。
属人化によるリスクとデメリット
属人化とは、特定の人が業務のノウハウを独占してしまい、他の人が代替できない状態のことです。そうした状況は、次のようなリスクやデメリットを引き起こします。決して短期的な一面だけでなく、長期的に組織に悪影響を及ぼす可能性があります。
・業務の停滞や停止のリスクがある
特定の人しかその業務の内容ややり方を知らないと、最悪の場合、業務が完全に止まってしまう可能性があります。特にトラブル対応や緊急対応が必要なケースでは、解決までに時間がかかり顧客満足度が低下するなど、組織全体に悪影響を与えかねません。
・情報共有不足、情報漏洩のリスクが高まる
業務の知識やノウハウ、必要な情報が他のメンバーに共有されないことで生産性の低下を生み出し、さらには情報漏洩や機密情報の隠ぺいがあっても気づかないなどセキュリティ面でのリスクもあります。
・組織やメンバーの成長を妨げる
いつまでも後輩が育たず、組織的な成長が妨げられることがあります。
・組織全体の生産性が落ちる
属人化は業務の非効率化の大きな要因です。特定の作業において周囲のメンバーがその人の指示を待たなければならず、結果として時間のロス、生産性の低下にも繋がります。
標準化によるメリット(生産性向上、品質向上、教育コスト削減など)
業務マニュアルを標準化することで、属人化による非効率な作業やミスを減らし、生産性や品質を向上させることができます。また、教育コストの削減、業務の平準化といった効果も期待できます。具体的には、以下のようなメリットがあります。
1. 生産性向上
標準化されたマニュアルにそって作業を行うことで、作業手順のばらつきやムダが減り、効率的に進むようになります。また、マニュアルを参照することで、作業の質が均一化され、手戻りや修正作業が減少する効果も期待できます。特に新人や経験の浅い担当者にとっては、標準化されたマニュアルは業務をスムーズに進めるための大きな手助けになります。
2. 品質向上
標準化されたマニュアルには、その作業におけるもっとも効率的で基本となる手順が反映されています。そのため、一定水準以上の品質を担保することができます。また、マニュアルに基づいた作業を行うことで、ミスや漏れを防ぎ質の良い製品やサービスに仕上がります。品質の向上は、企業そのものの信頼にも重要な要素です。
3. 教育コスト削減
標準化されたマニュアルは、新入社員教育やOJTの効率化に役立ちます。マニュアルを参照することで誰でも必要な知識やスキルをスムーズに習得でき、教育担当者の負担も軽減されます。また、ベテランスタッフのノウハウをマニュアルに体系的にまとめることで、暗黙知を形式知化し、組織全体の知識資産として活用することもできます。結果的に、教育にかかる時間とコストを大きく減らすことができます。
4. 業務の平準化
特定の担当者に業務が集中していたり、担当者によって業務の進め方が大きく異なったりすると、休暇や異動時に業務が滞ることがあります。標準化されたマニュアルがあれば、誰でも同じ手順で業務を進めることができるため、業務が標準化できます。
5. 顧客対応の均質化
顧客対応業務において、対応手順やFAQをマニュアル化することで、どの担当者が対応しても一定水準のサービスを提供することができ、顧客満足の向上に繋がります。また、クレーム発生時の対応手順も明確化しておくことで、迅速で適切な対応が可能になります。
業務マニュアルの標準化のポイントとは?
業務マニュアルを標準化することは、組織の効率性を高め、品質を安定させるために欠かせません。そんな標準化されたマニュアルの特徴には次のようなものがあります。
標準化されたマニュアルの特徴
第一に、シンプルで分かりやすいことが大切です。複雑すぎるマニュアルでは、誰も実行できない、理解できない、使われない可能性が高くなってしまいます。ここでは、業務マニュアルを標準化させるために重要な8つのポイントを解説します。
1.目的の明確化
業務マニュアルを作成する際、まず「誰のために、何のために作成するのか」を明確にしましょう。例えば、新人教育を効率化するため、あるいは業務のばらつきを抑えるためなど、具体的な目的を設定することが重要です。目的が明確であれば、内容に一貫性が生まれ、必要な情報を適切に盛り込むことができます。
2.対象範囲の明確化
次に、どの業務を標準化の対象にするのかを定めることが必要です。組織内の全ての業務を一度に標準化しようとすると、労力が膨大になります。まずは影響の大きい業務や、現場で混乱が生じやすい業務に絞って標準化を進めるのが効果的です。
3.作成手順の標準化
マニュアルを誰がどのように作成するのかも明確にしておく必要があります。作成担当者を明確にし、チェック体制や作成プロセスを標準化することで、質の高いマニュアルを安定的に作成できます。この段階では、現場の意見を取り入れる仕組みを整えることも重要です。
4.フォーマットの統一
マニュアルは見やすさと使いやすさが求められます。そのため、フォーマットの統一が欠かせません。たとえば、項目ごとの見出しや段落構成を統一し、図表や写真を効果的に活用することで、視覚的にも理解しやすいマニュアルを作成できます。
5.用語の統一
業務マニュアルでは、同じ用語が異なる意味で使われることを避けるために、用語を統一する必要があります。特に専門用語や略語については、必ず統一した定義を設け、読者が混乱しないようにしましょう。用語の統一は、組織全体の一貫性を高める効果もあります。
6.表現方法の統一
文章表現も簡潔でわかりやすいことが求められます。同じ意味を持つ内容が異なる表現で記載されると、読む人に混乱を与えかねません。「主語+動詞+目的語」のような簡潔な文構造を徹底することで、読みやすさを向上させましょう。
7.レビュー体制の構築
マニュアルの正確性と最新性を維持するためには、レビュー体制の構築が欠かせません。作成後には、内容の確認を行う担当者を決め、複数人の目でチェックする仕組みを整えましょう。この過程で、内容の齟齬や不備を修正し、完成度を高めることができます。
8.更新頻度の設定
業務は常に進化、更新されていきます。そのため、マニュアルは作ったら終わりではなく、定期的に見直して最新の情報に更新することが重要です。そこで更新頻度をあらかじめ設定しておくのがおすすめです。例えば、半年に一度や年度末にレビューを行うスケジュールを組むと良いでしょう。
標準化した業務マニュアル作りの具体的な進め方

上記を踏まえて、標準化された業務マニュアルを作るための具体的な進め方を解説します。
ステップ1:現状の業務プロセスを洗い出す
まずは現状の業務をすべてリストアップし、それぞれの業務フローや手順を明らかにします。このステップでは、次のポイントを押さえましょう。
・業務内容の棚卸し
日常的に行われている作業を細かく記録します。特に、複数の担当者が異なるやり方で進めている業務は注意して洗い出すようにします。
・属人化の特定
誰がどの業務を担当しているのかを把握し、属人化している作業を明らかにします。属人化している業務は標準化の優先順位が高いものです。
ステップ2:基本手順の定義する
業務を標準化する際は、最も効率的で品質の高い作業手順を「基本手順」として定義することが重要です。
・現場からのヒアリング
実際に業務を行っている担当者から、基本手順、効率的な進め方、注意点を聞き出します。現場の意見を取り入れることで実用的なマニュアルを作ることができます。
・テスト実施
基本手順を実際に試し、問題点がないかを確認します。必要に応じて修正を加え、現実に即した手順に整えていきます。
ステップ3:マニュアルの作成と公開
標準化された手順をマニュアルとして文書にします。その際、次のポイントが大切です。
・わかりやすさを重視
専門用語や複雑な表現を避け、誰が読んでも理解できる内容にします。具体例や図解を取り入れるいいでしょう。
・フォーマットの統一
どの業務マニュアルも同じ形式で記載することで、利用者が迷わず使えるようになります。
・アクセスしやすい環境に置く
作成したマニュアルはいつでもだれでも見やすい場所に置いておきます。紙だけでなく、デジタルデータとしても共有するなど、いつでもどこでも閲覧可能な状態にします。
ステップ4:運用のための教育とフィードバック
業務マニュアルを完成させたら、使いこなすための教育の機会が欠かせません。さらに利用者からのフィードバックをもらい、継続的な改善を繰り返さなければなりません。
・社員教育の実施
新しいマニュアルを導入する際は、社員全員に使い方をレクチャーします。トレーニングを行うことで、現場でのスムーズな活用が期待できます。
・定期的な見直し
時代や業務内容の変化に対応するため、定期的にマニュアルを見直し、アップデートします。標準化されたマニュアルが現場でどのように使われているのかをヒアリングし、適切に活用されているかを確認しましょう。
業務マニュアルの標準化は、それ自体がゴールではなく、運用し続ける中で効果を発揮します。利用状況の確認、効果測定、見直しと改善のサイクルを継続的に回すことで、マニュアルの品質を維持し、組織の成長を支える重要な資産とすることができるのです。
業務マニュアル標準化で生産性UP!
業務マニュアルの標準化は、単なる文書作成ではなく、組織全体の生産性向上、企業の成長に繋がる重要な取り組みです。目的を明確にし、フォーマットや用語、表現方法の統一、そしてレビュー体制の構築といった具体的な手順を踏むことで、質の高いマニュアルを作成できます。特に、一度作成して終わりではなく、現場の声を反映させること、定期的に見直しを行うことは、マニュアルの有効性を高める上で欠かせない要素です。また、組織の変化や事業の進展に合わせて、常にアップデートしていかなければならず、決して片手間でできるラクな業務ではありません。作り方の手順やポイントが理解できても、実際には「本業が忙しい」、「何から手を付けていいのかわからない」といった方も多いのが現状です。
そんな時はぜひ一度、マニュアル作成のプロ集団である株式会社mayclassにご相談ください。自社に最適な、標準化された業務マニュアル作成のヒントをアドバイスし、課題解決に向けたマニュアル作りを一緒に取り組んでまいります。
ーーー
[Work Efficiency] How to Standardize Operation Manuals to Boost Productivity

▼下記記事もおすすめ▼


