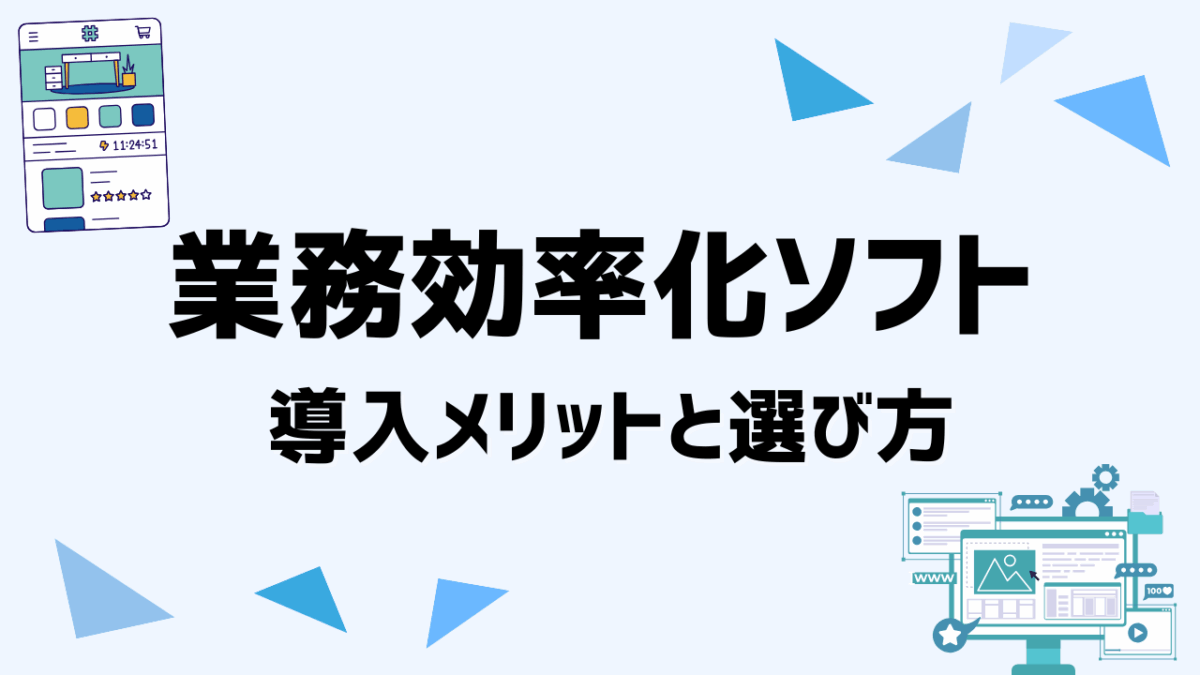近年は働き方改革やDXの広がりとともに、企業は「限られた人員と時間で成果を出す」ことの必然性、重要性がより強く求められるようになっています。人手不足や残業規制が進む中、今までのように長時間労働で補うといった働き方は難しくなりました。一方で、顧客の期待や市場競争は高まり続けているため、一人ひとりの生産性を上げることが欠かせません。
そこで注目されているのが「業務効率化ソフト」です。タスク管理や情報共有、経費精算、RPAによる自動化など、部門ごとの課題に直接アプローチできる点が大きな魅力です。
本記事では、代表的なソフトを紹介しつつ、導入メリットや選び方をわかりやすく解説します。
働き方改革・DX推進で業務効率化が急務となる企業担当者向けの記事です。
タスク管理・情報共有・経費精算・RPAなど、多様な業務効率化ソフトの特徴やメリットをわかりやすく整理し、自社に合うツール選定のポイントを解説します。単なるツール紹介ではなく、「ソフト導入が業務フロー改善の入口になる」という視点も提供し、現場で成果を出すための実践的なガイドとなっています。
なぜ業務効率化ソフトが今求められているのか
働き方や企業を取り巻く環境が大きく変わる中で、業務効率化ソフトは単なる便利ツールではなく、現場を支える“必需品”となりつつあります。なぜこれほど注目されているのでしょうか。
人手不足・残業規制・DX推進という時代背景
日本の労働市場は、深刻な人手不足に直面しています。少子高齢化によって労働人口が減少し続ける一方で、企業に求められる業務の範囲はむしろ広がっていると言えます。営業活動や顧客対応に加え、法規制対応や新規サービス開発など、従業員にかかる負担は増えるばかりです。
さらに、働き方改革関連法によって残業時間の上限が厳格に定められ、長時間労働に頼る働き方は法的にも許されなくなりました。そのため「少ない人数でどう効率的に業務を回すか」という課題は、どの業種・どの規模の企業でも避けて通れないテーマとなっています。
さらに、近年は著しいDX化に向けた取り組みが推進されています。国も企業も「デジタル技術の活用による生産性向上」を掲げ、システムやツールを積極的に導入する動きが広がっています。つまり、業務効率化ソフトは「流行」ではなく、現代の企業にとって不可欠な基盤なのです。
業務効率化ソフトの導入で得られる3つの効果
業務効率化ソフトを導入するとさまざまなメリットがありますが、主に3つの効果が挙げられます。
まず、最大の効果が「時間の節約」です。例えば、経費精算ソフトを使えば領収書の処理にかかる時間を大幅に削減できます。RPAを使えば、毎日繰り返しているデータ入力作業を自動化でき、担当者はより戦略的な仕事に注力できるようになります。
次に「ミスの削減」です。人が繰り返し作業をすると、どうしても入力漏れや計算間違いが起こります。ソフトに任せることでヒューマンエラーを減らし、データの信頼性を高められます。特に会計や経理の分野では顕著です。
最後は「情報共有の迅速化」です。これまでは社内メールや紙資料でやり取りしていた情報を、クラウドソフトに集約すれば、いつでもどこからでも同じ情報を複数人で確認できます。これにより、部門をまたいだ意思決定もスピードアップし、全体の生産性が向上します。
既存の業務フローを改善する入り口としてのソフト活用
ただ、業務効率化ソフトは単に導入するだけで効果が出るわけではありません。むしろ「なぜこの業務が必要なのか」「この手順に無駄はないか」といった根本的な課題を生み出してくれます。ソフト導入のプロセス自体が、既存業務を見直すチャンスになるのです。
例えば、承認フローを自動化しようとしたとき「承認者が多すぎて時間がかかっているのでは?」と気づくことがあります。ここで承認ステップを減らせば、ソフトに頼らなくても業務は効率化されることになります。つまり、ソフトはあくまできっかけで、本質は業務フローそのものを改善することにあるのです。
業務効率化については、業務効率化の全てがわかる!具体的な手順・ツールも完全解説の記事や、【図解でわかる】生産性向上と業務効率化の違いとは?意味・目的・施策を徹底比較! の記事でも詳しくご紹介しています。併せてご覧ください。
業務効率化に貢献するソフトの主な種類
ひと言で‟業務効率化ソフト”と言っても、その種類や機能は多岐にわたります。ここでは代表的なジャンルごとにそのソフトの特徴やおすすめの企業タイプ、導入効果を整理して紹介します。
タスク・プロジェクト管理ソフト(例:flowzoo、Backlog、Asana)
タスクやプロジェクトの進行を把握しやすくするソフトは、チームでの仕事を効率的に進めるうえで欠かせません。情報を可視化し、遅延やミスを防ぐ効果があります。
①flowzoo
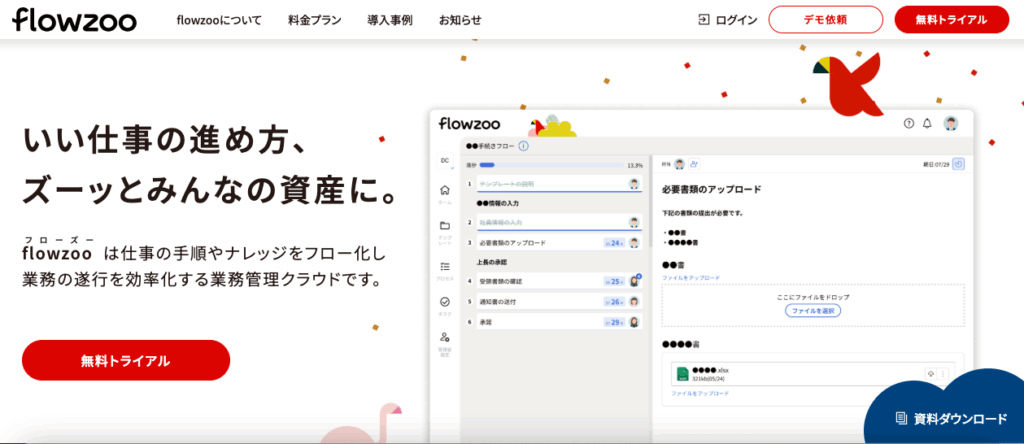
【特徴】
- 業務の成功パターンをテンプレート化し、誰もが活用できる形で共有可能
- 属人化を防ぎ、企業のナレッジ資産を蓄積できる
- ベストな進め方をテンプレートとして保存・共有でき、組織全体での均質な業務遂行を実現できる
- 個々のタスクを時系列で一覧表示し、「誰が」「何をいつまでに」すべきかがひと目で分かる
- 生産性・マネジメント効率を向上
【おすすめの企業タイプ】
- 担当者だけが知っている業務が多く、新人や異動者が馴染みにくい企業
- 新人研修や業務引き継ぎに時間がかかっている企業
- 複数タスクが同時進行しがちな現場や、進捗や未対応が見えづらいチーム
<導入後に期待できる効果>
- 各人の業務ノウハウがテンプレート化され、属人化を排除して組織の標準業務として活用可能
- タスク進捗が可視化されることで、業務の抜け漏れや重複を防ぎ、円滑な進行と管理を実現
- 新人や異動者が標準テンプレート通りに業務を進められるため、早期戦力化が可能に
- 業務フローと手順が明確なテンプレートとして残ることで、ヒューマンエラーのリスクが低減
flowzooについては、flowzooとは?特徴・機能・導入メリットをわかりやすく解説!でも詳しくご紹介しています。併せてご覧ください。
②Backlog
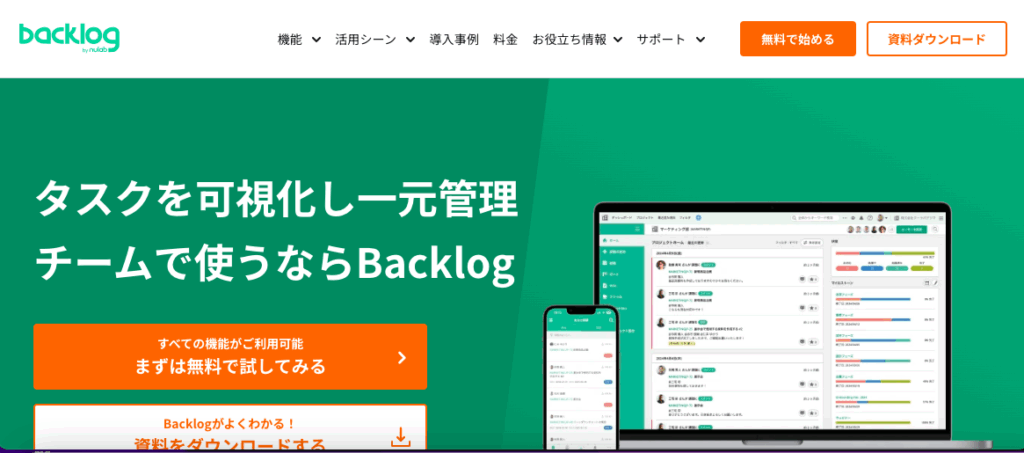
【特徴】
- 日本企業の利用実績が多く、国産ならではの使いやすさがある
- ガントチャートやバーンダウンチャートで進捗を直感的に把握できる
- 課題ごとに担当者・期限を設定でき、チーム全体で状況を共有しやすい
- Git(ファイルのバージョン管理ができるシステム開発ツール)との連携機能があり、エンジニアチームにも最適
【おすすめの企業タイプ】
- 社内プロジェクトを複数走らせている、進捗管理に課題を感じている企業
- Excelやメールでのタスク管理が限界に達している企業
- 開発部門と他部門が一緒に動くことが多い企業
<導入後に期待できる効果>
- 会議時間の大幅な削減
- プロジェクトの遅延の減少、納期遵守率の向上
- タスクの抜け漏れ減少、品質トラブルの発生率低下
③Asana
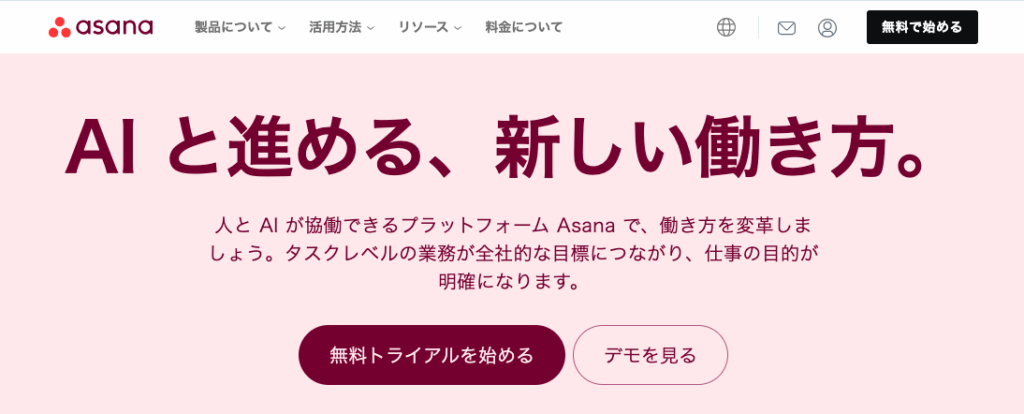
【特徴】
- 海外でも広く利用されており、グローバルなプロジェクト管理に強い
- タスクを「リスト」「ボード」「タイムライン」など多様な形式で表示可能
- 外部サービス(Google Drive、Slackなど)との連携が豊富
- 直感的なUIで、ITスキルが高くない人でも操作しやすい
【おすすめの企業タイプ】
- 海外拠点や外部パートナーとのコラボレーションが多い企業
- 柔軟にタスク管理のスタイルを切り替えたい企業
- スタートアップやベンチャーなどスピード重視で動く企業
<導入後に期待できる具体的な効果>
- 複数拠点間での進捗共有が円滑化される
- 報告にかかる手間の削減
- 部署横断での連携強化
- タスクの優先順位付けがスムーズに
- メール依存が減り、外部パートナーとのやり取りが一本化される
ドキュメント共有・ナレッジ管理ソフト(例:Notion、Confluence)
情報を一元管理し、社内の知識を蓄積・共有するためのソフトは、探す手間を減らし意思決定を加速させることができます。
①Notion

【特徴】
- メモ、タスク管理、Wiki、データベースを一つに統合できるオールインワン型
- ページのレイアウト自由度が高く、社内マニュアルから議事録まで幅広く活用可能
- 個人利用からチーム利用までスケーラブルに対応できる柔軟性
- シンプルながら拡張性があり、ノーコードでデータベース的な使い方も可能
【おすすめの企業タイプ】
- まだ情報共有のしくみが整っておらず、柔軟に始めたい企業
- 部署ごとに情報管理方法がバラバラで、標準化を進めたい企業
- 少人数のチームでも成長スピードが速く、組織拡大に備えたい企業
<導入後に期待できる効果>
- 探し物に費やす時間が減り、業務効率の向上
- 会議の議事録やマニュアルが統一され、情報の重複や齟齬が解消される
- 新人教育に必要な時間が短縮され、早期に戦力化できる
②Confluence
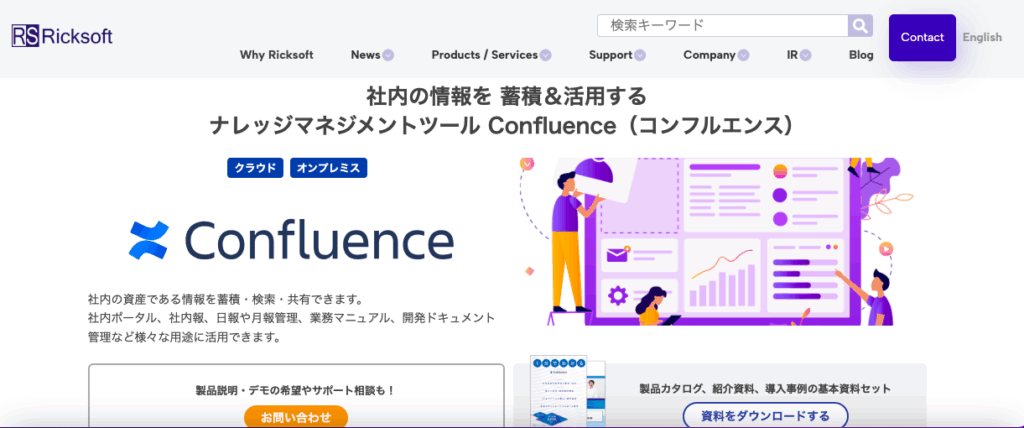
【特徴】
- 大規模組織でのナレッジ管理に最適化されている
- 「Jira」などのプロジェクト管理ツールと強く連携しやすい
- ページの階層管理や権限設定が細かくでき、大規模プロジェクトで情報が整理しやすい
- ドキュメントを共同編集でき、リアルタイムで複数人が作業可能
【おすすめの企業タイプ】
- 部署や拠点が多く、情報が分散しやすい大企業
- IT部門や開発部門が中心となってプロジェクトを回している企業
- ナレッジの属人化を解消したい企業
<導入後に期待できる具体的な効果>
- 大規模プロジェクトでの情報共有がスムーズになる
- 社内のナレッジが体系化される
- 同じ質問への対応が減る
- 文書の改訂履歴が明確になり、コンプライアンスリスクの低下につながる
③esa

【特徴】
- 文書・アイデア・ノートをチームでまとめて管理できるリポジトリ機能を提供し、知識の透明化と共有を促進
- フォルダやタグで文書を分類し、Markdown対応で編集・閲覧が容易
- バージョン管理も備え、変更履歴の追跡も可能
- コメントやスレッド機能、Slackやメールへの通知連携機能を備え、ドキュメントに対するフィードバックや反応がリアルタイムに共有できる
- ミニマルかつ見やすいデザインで、技術チーム・非技術チーム問わず使いやすさを重視した設計
【おすすめの企業タイプ】
- 仕様書・会議メモ・ノウハウなどを一元管理したい開発・企画チーム
- 階層型・タグ型の整理やバージョン管理ができるため、情報量や更新頻度が高い企業
- フィードバックのやり取りや通知機能を重宝するプロジェクトやチーム
<導入後に期待できる具体的な効果>
- ドキュメントが体系的に保存され、誰でも必要な情報にすぐアクセスできるようになる
- コメント・通知連携があることで、ドキュメントの改善やアップデートが活発になり、情報の鮮度が保たれる
- 個人に依存しないドキュメント管理が可能
- 通知機能により、ドキュメントの更新やコメントがリアルタイムで伝わる
RPA・業務自動化ソフト(例:Power Automate、WinActor)
人が行う定型的な操作をロボットに任せるRPAは、手作業の削減とヒューマンエラー防止に大きな効果を発揮します。
①Power Automate
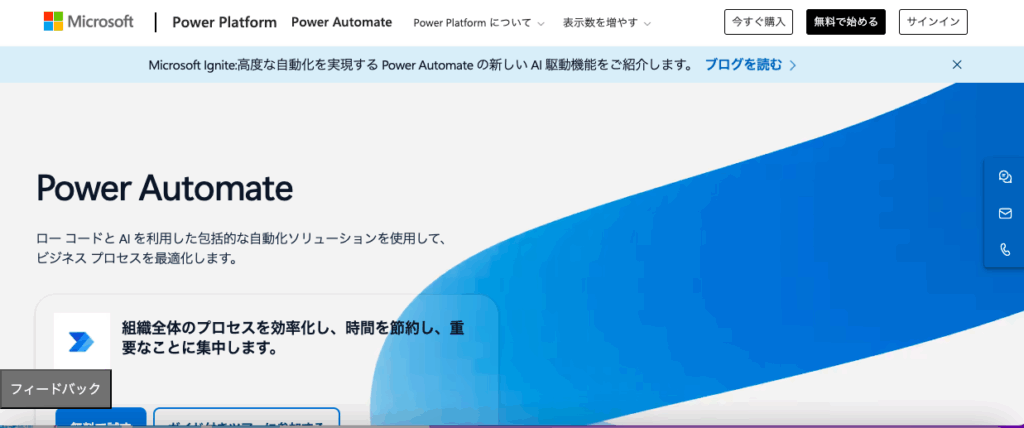
【特徴】
- Microsoft製品との親和性が高く、ExcelやOutlookとの自動連携が得意
- クラウド型であり、TeamsやSharePointとの連携にも強い
- 低コード・ノーコードでの開発が可能で、プログラミング知識がなくても利用可能
- AI Builderなどを利用し、画像認識や自然言語処理を組み合わせた高度な自動化も可能
【おすすめの企業タイプ】
- Office製品を中心に業務を回している企業
- クラウドサービスを活用している企業
- ITリテラシーの高い従業員が多く、自動化の範囲を広げたい企業
<導入後に期待できる具体的な効果>
- Excel集計作業が自動化され、月末処理にかかる時間が大幅に削減される
- メールの定型返信が自動化され、担当者の対応時間が大幅削減される
- 人的ミスが減少し、品質トラブル防止につながる
②WinActor

【特徴】
- 日本企業の業務に合わせた設計で、国内導入実績が豊富
- 専門知識がなくても操作しやすいインターフェイス設計
- Windowsアプリケーションや独自システムとの親和性が高く、業種を問わず利用可能
- 国内ベンダーによるサポートが手厚く、導入時の教育体制も充実
【おすすめの企業タイプ】
- 日本独自の業務フローや基幹システムを利用している企業
- 社内に専門エンジニアが少なく、簡単に導入したい企業
- サポートや研修体制を重視する企業
<導入後に期待できる具体的な効果>
- 手作業で行っていた入力業務が自動化され、担当者の残業が削減できる
- 紙ベースの業務が効率化され、業務スピードが向上
- 短期間での導入が可能で、ROI(投資対効果)が早期に得られる
会計・経費精算ソフト(例:freee、マネーフォワード)
経理部門の手間を大幅に軽減するソフトは、正確性とスピードを両立させます。
①freee

【特徴】
- UIがシンプルで初心者でも迷わず操作できる
- 銀行口座やクレジットカードと連携し、自動で仕訳を作成
- 給与計算や請求書発行機能も備え、バックオフィス業務を一元化可能
- スマホアプリが使いやすく、領収書を撮影して経費登録できる
【おすすめの企業タイプ】
- 経理担当者が少人数で、作業を効率化したい中小企業
- 会計知識が浅いスタッフでも扱いやすいソフトを探している企業
- クラウドで場所を問わず経理処理を進めたい企業
<導入後に期待できる具体的な効果>
- 経費精算がスマホで完結するため、社員の申請負担が軽減される
- 会計処理のスピードが上がり、月次決算の早期化が実現
- 経理担当者の入力作業が減り、チェック業務に集中できる
②マネーフォワード

【特徴】
- レポート機能や分析機能が豊富で、経営判断に役立つ情報を提供してくれる
- 銀行やカード会社との連携数が多く、幅広い金融データを自動取得できる
- 中小企業から大企業まで幅広く利用されており、拡張性が高い
- 部門別の予算管理やキャッシュフロー分析に強い
【おすすめの企業タイプ】
- 財務データを経営戦略に活かしたい企業
- 多拠点や複数部門の経理処理を効率化したい中堅〜大企業
- データを活用して経営判断を迅速にしたい経営層主導の企業
<導入後に期待できる具体的な効果>
- 財務データの可視化が進み、経営層の意思決定がスピードアップする
- 部門ごとのコストを正確に把握でき、予算管理の精度が向上
- キャッシュフローの把握が容易になり、資金繰りリスクを回避できる
チャット・社内コミュニケーションソフト(例:Slack、Chatwork)
コミュニケーションのスピードを高めるソフトは、情報共有の質を大きく改善します。
①Slack

【特徴】
- 外部サービスとの連携数が非常に多く、ワークフローの自動化にも活用可能
- プロジェクト単位で「チャンネル」を作成し、会話を整理しやすい
- グローバル企業や開発チームでの利用実績が多く、国際的な協働にも強い
- 音声・ビデオ通話機能も搭載し、オンライン会議ツールとしても利用可能
【おすすめの企業タイプ】
- IT部門や開発チームを持つ企業
- 海外拠点や外部パートナーとのやり取りが多い企業
- 業務効率化のために外部サービスとの連携を積極的に活用したい企業
<導入後に期待できる具体的な効果>
- 社内メールが激減し、レスポンススピードが向上する
- 外部ツールとの連携でき、業務フローがシームレスになる
- チャンネルごとの議論整理で情報の見返しやすさが高まる
②Chatwork

【特徴】
- 日本企業向けに開発されているため、操作が直感的でシンプル
- 国内ユーザーが多く、中小企業や地方企業でも導入しやすい
- タスク管理機能が標準搭載され、業務進行とチャットが一体化
- 国内サポートが充実しており、日本語でのマニュアルやサポート体制が安心
【おすすめの企業タイプ】
- 初めてチャットツールを導入する企業
- 国内取引が中心で、日本語サポートを重視する企業
- コストを抑えつつコミュニケーションを改善したい中小企業
<導入後に期待できる具体的な効果>
- 電話やFAX中心の企業でもコミュニケーションスピードが向上
- チャットとタスクが一体化し、進行状況の見える化がアップ
- サポートを活用しながら短期間で定着させられる
部門別に見る業務効率化ソフトの導入メリット
業務効率化ソフトは、部門ごとに異なる課題に応じて役立つ機能を発揮します。営業・人事・経理・製造など、それぞれの現場でどのような効果が得られるのかを具体的に確認していきましょう。
営業部門:顧客管理やレポート作成を自動化
営業活動は、顧客とのコミュニケーションだけでなく、データ入力や報告作業など裏方的な事務作業も想像以上に多く発生します。顧客情報管理のCRM機能を持つソフトを導入すれば、商談履歴や顧客情報を一元管理でき、レポートも自動生成されます。その結果、営業担当者は本来の「売る」活動に集中でき、成果につながりやすくなります。
人事・総務部門:労務・勤怠・書類管理の省力化
人事や総務は、社員の勤怠管理、社会保険手続き、入退社に伴う書類作成など幅広い業務を担当しています。労務管理ソフトを導入すれば、勤怠データが自動集計され、給与計算との連動も容易になります。従業員自身が申請や確認を行える仕組みを導入すれば、管理部門の負担は大きく軽減されます。
経理部門:手入力の排除と計算ミスの削減
経理業務は、特に手作業が多く、数字の正確性が求められます。会計ソフトや経費精算ソフトを導入すれば、領収書の自動読取や仕訳の自動化が可能になり、入力作業を大幅に削減できます。その分、経理担当者はチェックや分析など、より高度な業務に時間を使えるようになります。
現場・製造部門:マニュアルや手順書のデジタル化
製造や現場作業では、紙のマニュアルを参照するといったアナログな業務習慣がまだまだ残っています。これらをデジタル化すれば、タブレットやスマートフォンからすぐに最新情報を確認でき、作業効率が向上します。また、現場からのフィードバックをその場で入力・共有できるため、改善サイクルも早まります。
業務効率化ソフトの選び方と導入時の注意点
ソフトを選ぶときは、自社の課題に合っているかどうかを軸に判断することが大切です。ここでは導入時に押さえておきたい視点や注意点を紹介します。
自社の業務課題に合ったソフトを選ぶ
業務効率化ソフトを導入する前に、自社が抱える課題を明確にしましょう。例えば「情報共有に時間がかかっている」「入力作業の負担が大きい」など、解決したいポイントを特定することが重要です。課題に合わないソフトを導入すると、現場で使われなくなり、投資が無駄になってしまいます。
操作性・サポート・料金体系の確認ポイント
ソフトは使いやすさが命です。どんなに機能が豊富であっても、操作が難しければ現場には浸透しません。また、トラブルが起きた際に迅速なサポートが受けられるかどうかも重要です。料金体系についても、ユーザー数課金なのか定額制なのかを把握し、将来の利用規模を見据えて選びましょう。
無料トライアルやスモールスタートのすすめ
いきなり全社導入するのではなく、まずは無料トライアルや小規模な部署でのテスト導入から始めるのがおすすめです。実際の業務で使ってみることで、操作性や効果を具体的に確認できます。スモールスタートで成功事例を作れば、他部署への展開もスムーズに進みます。
業務効率化を成功させるには、単にソフトを導入するだけでなく「どのような考え方で改善を進めるのか」を理解しておくことも重要です。
そのための代表的な考え方については「【保存版】業務効率化フレームワーク15選!生産性向上のポイントとは?」で詳しく解説しています。
業務効率化ソフトを正しく選んで現場改善を加速
業務効率化ソフトは導入することがゴールではありません。実際に現場で使われ、働き方を変えることができて初めて効果を発揮します。導入後の活用を成功に導くためのポイントは以下です。
ソフトは「使う人」が主役。現場に合った選定を
どんなに高機能なソフトでも、使う人が使いづらければ意味がありません。業務効率化ソフトは、導入する企業ではなく「使う現場」が主役です。現場の意見を取り入れながら選定することで、実際に利用され、効果を発揮するソフトになります。
導入後の定着サポートとルール整備も忘れずに
導入後にありがちなのが「最初だけ使って、その後は定着しない」というケースです。これを防ぐには、従業員向けの研修やマニュアル整備、利用ルールの明確化が欠かせません。さらに、定期的に運用状況を振り返り、改善を続けることで、ソフトの効果は長期的に発揮されます。
業務効率化ソフトを活用しよう
業務効率化ソフトは、ただ便利なツールではなく、企業が直面する人手不足や働き方改革の課題を解決するための強力な武器です。タスク管理から会計、RPA、情報共有まで幅広い分野に応用でき、部門ごとの課題解決に直結します。導入の際には、自社の課題に合ったソフトを選び、現場での定着を意識しましょう。
ソフトをうまく活用すれば、従業員一人ひとりの負担が軽減され、組織全体の生産性が向上します。これからの時代において、業務効率化ソフトは「選択肢」ではなく「必須のインフラ」となるはずです。

ーーー
12 Best Software Tools for Work Efficiency: Benefits and Selection Tips by Department
▼こちらの記事もおすすめ▼
業務効率化ツールの比較ガイド!おすすめツールと導入ポイントの完全ガイド