業務効率化を本当に成果につなげるためには、「やみくもな改善」ではなく、明確な目標設定が欠かせません。目標があいまいなままでは、どこまで改善できたのかが判断できず、現場のモチベーションも続きにくくなります。反対に、数値や期限を明確に定めた目標があれば、改善活動の方向性がそろい、組織全体の行動が一貫性を持ちます。
本記事は『業務改善・業務効率化の原則と目標を徹底解説!4原則・3要素・8原則を一挙紹介』の詳細解説編として、目標設定の実務的な方法にフォーカスしています。業務効率化の目標設定に役立つ「SMART法」や「KPI/KGI」の考え方をわかりやすく解説し、実務で使える具体的な指標例も紹介します。さらに、目標設定を定着させ、成果を持続させるためのポイントも整理しました。
このガイドを読むことで、単なる理論ではなく、実務に直結する目標設定のステップが明確になります。明日からの業務改善にすぐ活かせる内容になっていますので、ぜひ参考にしてください。
本記事は、業務効率化の成果を“きちんと出したい”企業の管理職・現場リーダー・業務改善担当者向けの目標設定ガイドです。なぜ目標設定が必要なのかを整理しつつ、KGI/KPI・SMART法・OKRの基本と使い分け、時間・コスト・品質など具体的な指標例までわかりやすく解説。改善の方向性をそろえ、成果を数値で見える化するための実務的なヒントが得られる内容です。
なぜ業務効率化に目標設定が必要か
業務効率化を成功に導くためには、最初に「何を達成するのか」という明確なゴールを定めることが不可欠です。
目標がなければ、改善活動の方向性があいまいになり、現場ごとにバラバラな施策が進んでしまう恐れがあります。その結果、時間やコストをかけても、組織全体としての成果が見えにくくなります。
一方で、明確な目標設定があれば、取り組むべき優先事項がはっきりし、現場メンバー全員が同じ方向を向いて動くことができます。例えば「残業時間を20%削減する」という具体的な目標を設定すれば、その達成に向けた施策や改善点を効果的に選び、実行できます。
また、目標は成果を数値化して評価するための基準にもなります。改善活動の進捗を定期的にチェックし、必要に応じて修正することで、効率化の取り組みを継続的にブラッシュアップできます。さらに、達成度が可視化されることで、現場のモチベーションも維持・向上しやすくなります。
要するに、業務効率化の目標設定は「方向性を示す羅針盤」であり、「成果を測る物差し」です。この2つを兼ね備えることで、改善活動は一過性のものではなく、組織文化として根付いていきます。
成果測定のための基準
業務効率化の目標は、単なるスローガンではなく、最終的な成果を正しく評価するための「物差し」として機能させる必要があります。
例えば「作業時間を30%削減する」という目標があれば、進捗状況を数値で確認でき、改善施策が適切に機能しているかを判断できます。
成果測定の基準を設けることで、
- 進捗が可視化される:現状がどの程度改善されているかを明確に把握できる
- 改善点が早期に発見できる:数値の変化から課題を見つけ、迅速に修正できる
- 達成感とモチベーションが生まれる:改善の成果を数字で実感でき、現場のやる気につながる
測定基準は、可能な限り定量的であることが理想です。時間、コスト、品質、顧客満足度など、改善対象に合わせて指標を選びます。また、測定頻度をあらかじめ決め、定期的に記録・共有することで、組織全体での振り返りと改善がスムーズに進みます。
このように、明確な成果測定の基準を設定することは、業務効率化を継続的に成功させるための重要なステップです。
改善活動の方向性の明確化
明確な目標が設定されていると、業務効率化の施策に優先順位をつけやすくなります。
目標が曖昧なままでは、「どの改善から着手すべきか」が判断できず、リソースの分散や効果の薄い施策に時間を費やしてしまうリスクがあります。
方向性を明確にすることで、
- 優先順位が定まる:効果と実行可能性が高い施策から着手できる
- リソース配分が最適化される:人員・時間・予算を効果的に活用できる
- 組織全体の一体感が高まる:共通の目標に向かって行動がそろう
また、方向性を決める段階では、現場の意見や課題感を吸い上げることが重要です。現場視点の改善案は実現性が高く、導入後の定着率も向上します。
さらに、業務効率化の方向性は固定的なものではなく、定期的な見直しが必要です。環境の変化や新しい課題に応じて柔軟に修正し、常に最適な改善活動を維持することが、長期的な成果につながります。
業務効率化の目標設定方法
業務効率化を効果的に進めるには、「何を目指し」「どのように進捗を測るか」という目標設定の仕組みを整えることが不可欠です。目標があいまいなまま改善活動を始めてしまうと、途中で方向性がぶれたり、成果が正しく評価できなくなってしまいます。
そこで活用できるのが、KGI(重要目標達成指標)やKPI(重要業績評価指標)、さらにSMART法やOKRといったフレームワークです。KGIとKPIは最終ゴールとその進捗を測るための数値基準、SMART法は目標を実行可能な形に落とし込むための設計指針、OKRは変化の早い環境で柔軟に見直せる目標管理の枠組みとして機能します。
これらを組み合わせることで、日々の現場改善から中長期の経営目標まで、一貫性のある業務効率化の計画を立てられます。それぞれの特徴や使い方を具体的に見ていきましょう。
KPIとKGIの違い
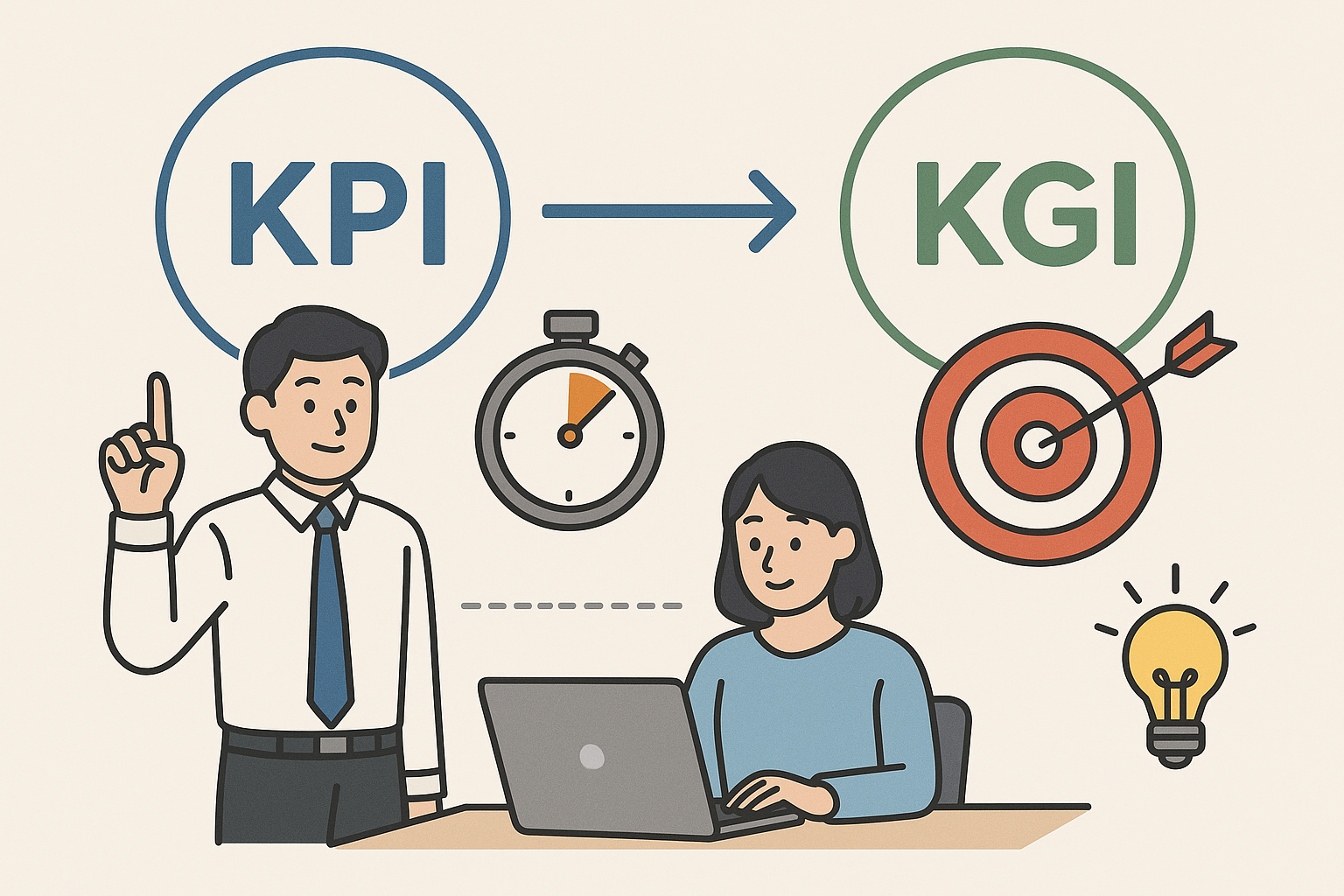
業務効率化では、KGI(重要目標達成指標)とKPI(重要業績評価指標)を組み合わせて設定することが重要です。
- KGI:最終的に到達したいゴール
- KPI:そのゴールへの進捗を測る中間指標
例として、KGIが「顧客対応時間を30%削減」であれば、KPIは「問い合わせから初期対応までの時間を2時間以内に短縮」といった形になります。
KGIは全体の方向性を示し、KPIは現場が日々の進捗を確認するための指標として機能します。
効果的な目標設定を行うためには、業務効率化8原則完全ガイド!無駄をなくし生産性を高める具体的手法が役立ちます。
SMART法の概要
SMART法は、実効性の高い目標設定を行うためのフレームワークです。
- Specific(具体的):誰が見ても同じ意味に解釈できるようにする
- Measurable(測定可能):進捗や成果が数値で把握できる形にする
- Achievable(達成可能):現実的かつ実現可能な範囲で設定する
- Relevant(関連性がある):業務効率化の目的や課題と直結している
- Time-bound(期限が明確):達成期限を設定し、進捗管理をしやすくする
SMART法を活用すれば、抽象的な目標ではなく、実行可能かつ測定可能な形に落とし込むことができます。
OKRの活用
変化の速い環境では、OKR(Objectives and Key Results)の導入も効果的です。
OKRは「目標(Objectives)」と、その達成を示す「主要な成果指標(Key Results)」をセットで設定します。短期間での見直しが可能なため、状況に応じた柔軟な改善活動が行えます。
業務効率化の指標例
業務効率化の成果を正しく評価するには、明確で測定可能な数値指標を設定することが欠かせません。指標は、改善活動の方向性や成果を数値化して把握するための「物差し」となる存在です。
もし指標がなければ、「改善できているのか」「どのプロセスに課題が残っているのか」を客観的に判断できず、せっかくの取り組みが形骸化してしまう可能性があります。また、組織全体で成果を共有しにくくなり、モチベーションの低下や改善スピードの鈍化にもつながります。
ここでは、時間短縮・コスト削減・品質向上という3つの主要な視点から、実際に活用できる評価指標の例をご紹介します。これらの指標は、改善の進捗や効果を数値で可視化できるため、経営層への説明や現場へのフィードバックが容易になります。業種や業務内容によって最適なものは異なるため、自社の業務フローや改善目的に合ったものを選定し、定期的なモニタリングや改善サイクル(PDCA)の運用に役立てましょう。
時間短縮に関する指標
業務効率化の効果を測定する際、最もわかりやすく成果が見えやすいのが「時間短縮」に関する数値指標です。作業時間の短縮は、生産性向上やコスト削減にも直結し、現場の負担軽減にもつながります。
- 作業1件あたりの平均処理時間(分や秒で計測)
例:伝票処理、顧客データ入力、出荷作業などの1件ごとの平均時間を数値化し、改善施策前後で比較。 - 顧客対応の初期レスポンス時間(時間単位)
例:問い合わせメールやチャットへの初回返信時間を短縮することで顧客満足度を向上。 - 会議の平均所要時間(分単位)
例:会議時間を数値で管理し短縮することで、作業時間を確保し全体効率を改善。
時間短縮の成果は数値として明確に表れるため、現場メンバーが達成感を得やすく、改善活動の継続につながります。
コスト削減に関する指標
業務効率化は時間だけでなく、コストの削減にも効果をもたらします。コスト面の改善は数値による証拠が残りやすく、経営層からも評価されやすい分野です。
- 材料や備品の使用量削減率(%表示)
例:紙やインク、梱包材などの消耗品使用量を削減。削減前後の数値比較が有効。 - 外注費の削減額(円単位)
例:外部委託していた業務を社内で効率的に処理し、削減額を明確に算出。 - エネルギー使用量の削減率(%表示)
例:電気・ガス・水道などの使用量を数値化し、節約分を可視化。
コスト削減の進捗は財務データと直接リンクするため、数値報告として経営会議や取締役会資料にそのまま活用できます。
品質向上に関する指標
業務効率化は「速さ」や「安さ」だけを追求すると、品質が犠牲になるリスクがあります。そのため、品質向上の数値指標をあわせて設定することで、バランスの取れた改善が可能になります。
- クレーム件数の減少率(%表示)
例:苦情や返品対応件数を数値で追跡し、減少率を算出。 - 納期遵守率(%表示)
例:予定納期どおりに納品できた割合を数値化し、顧客信頼性を測定。 - 作業ミス発生率の低下(%表示)
例:入力ミスや検品漏れ件数を定期的に集計し、改善度を数値で評価。
品質指標を組み込むことで、効率化による品質低下を防ぎ、数値で証明できる改善成果を維持できます。
参考:業務効率化は“数値化”から始まる!成果を見える化する方法と実践ステップ
KPI / KGI評価シート例(業務効率化用)
| 分類 | KGI(重要目標達成指標) | KPI(重要業績評価指標) | 数値目標 | 現状値 | 測定方法 | 測定頻度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間短縮 | 顧客対応時間を30%削減 | 初期レスポンス時間を2時間以内に短縮 | 2時間以内 | 3時間 | 顧客対応履歴から抽出 | 月次 | 改善施策後の推移を比較 |
| 時間短縮 | 会議時間を20%削減 | 会議の平均所要時間を40分以内に短縮 | 40分以内 | 50分 | 会議記録システム | 月次 | 議題の事前共有を徹底 |
| 時間短縮 | 処理スピード15%向上 | 作業1件あたりの平均処理時間を5分短縮 | 20分以内 | 25分 | 作業記録シート | 週次 | マクロ・RPA導入予定 |
| コスト削減 | 材料費10%削減 | 備品使用量の削減率 | 10%以上 | 5% | 購買履歴の集計 | 月次 | デジタル化で紙使用削減 |
| コスト削減 | 外注費15%削減 | 外注費削減額 | 年間300万円削減 | 年間100万円削減 | 経理データ | 四半期 | 内製化できる業務を洗い出し |
| コスト削減 | エネルギーコスト5%削減 | 電気使用量削減率 | 5%以上 | 2% | 電気料金明細 | 月次 | LED照明導入済み |
| 品質向上 | クレーム件数20%減 | クレーム件数の減少率 | 20%以上 | 10% | 顧客サポート記録 | 月次 | クレーム分析を実施 |
| 品質向上 | 納期遵守率98%達成 | 納期遵守率 | 98%以上 | 95% | 生産管理システム | 月次 | 工程管理の見直し中 |
| 品質向上 | 作業ミス率15%低下 | 作業ミス発生率 | 5%以内 | 8% | 検品記録 | 月次 | ダブルチェック体制導入 |
活用方法
- KGIを先に設定し、最終ゴールを明確化する(例:顧客対応時間を30%削減)。
- そのKGI達成のためのKPIを複数設定し、進捗を数値でモニタリング。
- 「現状値」と「数値目標」の差を確認し、改善施策の優先順位を決定。
- 測定方法・測定頻度を決めて、データ取得のブレを防ぐ。
- 月次・週次の定例会で進捗を共有し、施策の効果を検証。
目標達成と数値管理を確実にするためのポイント
業務効率化の取り組みを成功させるには、単に目標を立てるだけでは不十分です。計画段階で理想的なゴールを設定していても、実行の途中で進捗や数値の変化が見えなくなり、改善活動が形骸化してしまうことは少なくありません。そこで重要になるのが、進捗を数値で把握する仕組み、情報を共有する体制、そして改善を継続的に回すサイクルを確立することです。
ここからは、目標を確実に達成し、数値として成果を証明するための実践的なポイントを順を追って解説します。
目標進捗を数値でモニタリングする仕組み
どれだけ優れた業務効率化の目標を立てても、計画通りに進まなければ十分な成果は得られません。達成までの道のりを管理するためには、日々の進捗を数値で可視化し、課題が出ればすぐに軌道修正できる体制を整えることが不可欠です。
進捗確認は単なる報告ではなく、改善点を早期に発見し、次のアクションにつなげるための重要な工程です。作業時間、コスト削減率、品質指標など、複数の観点から評価できる数値指標を設定し、週次や月次で記録・分析すると効果的です。
このとき、現場担当者が簡単に数値を入力できるフォーマットを用意することや、集計を自動化できるツールを導入することが、負担を軽減し継続を可能にします。進捗モニタリングを効果的に行うことで、目標達成への道筋を常に確認でき、成果を数字として積み上げられます。
進捗をモニタリングする仕組みづくりには、業務改善4原則とは?現場で活かせる実践ステップを徹底解説 を参考にしてください。
チーム全員で目標と数値を共有する方法
進捗や目標の達成度合いは、関係者全員が同じ数値を共有できる状態を保つことが重要です。情報共有が不十分だと、チーム間で認識のズレが生まれ、施策の方向性もぶれやすくなります。
社内掲示板や共有ドキュメント、タスク管理ツール、定例ミーティングなど、組織に合った方法を活用し、定期的に目標の達成状況を発信しましょう。
特に、進捗や成果を数値で見える化することは効果的です。達成率や改善率をグラフやチャートで示すと、状況が直感的に理解でき、参加意欲が高まります。また、高い数値を達成した事例や短期間で改善が進んだケースを共有することで、他チームのモチベーション向上にもつながります。この透明性のある情報共有は、組織全体の改善スピードと成果の質を引き上げます。
継続的に目標と数値を見直す改善サイクル
業務効率化は一度の取り組みで完結せず、継続的な見直しと更新が欠かせません。市場環境や顧客ニーズ、社内体制は常に変化しており、最初に立てた目標や数値基準が長期間有効であるとは限りません。
定期的に目標の妥当性を評価し、新しい課題や環境の変化に合わせて施策を修正することで、効率化の成果を長期的に維持できます。
この継続サイクルを組織に根付かせるには、PDCA(計画・実行・評価・改善)の流れを定着させることが効果的です。目標を小さな単位に分け、それぞれに明確な数値目標を設定して短期間で評価できる形にすると、改善活動のテンポが保てます。さらに、評価結果をチーム全体で共有し、次のアクションに素早く反映させることで、改善のスピードと精度が向上します。
こうしたサイクルが定着すれば、業務効率化は単なる一時的な施策ではなく、組織の競争力を高めるための持続的な仕組みとして機能し続けます。
業務効率化のための目標を設定しよう
業務効率化を成功させるためには、明確な目標設定と適切な指標の活用が欠かせません。
KPIやKGI、SMART法、OKRといったフレームワークを組み合わせることで、抽象的な理想ではなく、現場で実行可能な具体策へと落とし込むことができます。
また、進捗のモニタリングやチーム内での共有、改善の継続サイクルを意識すれば、短期的な成果だけでなく長期的な改善文化の定着にもつながります。
効率化の取り組みは一度で完結するものではなく、継続して磨き続ける姿勢が成果を最大化する鍵となります。
業務効率化の目標設定から実行、そして定着までを一貫して進めるには、適切な分析と計画立案が不可欠です。「業務分解図 」では、現状の業務を細かく可視化し、SMARTな目標設定を支援する仕組みをご提供しています。
自社に合った効率化の進め方を見つけたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

ーーー
How to Set Effective Work Efficiency Goals: SMART, KPI/KGI, and Real-World Examples
▼こちらの記事もおすすめ▼
業務効率化は“数値化”から始まる!成果を見える化する方法と実践ステップ
【図解でわかる】生産性向上と業務効率化の違いとは?意味・目的・施策を徹底比較!
【保存版】営業資料の作り方を徹底解説!成果につながる構成・デザイン・伝え方のコツとは?



