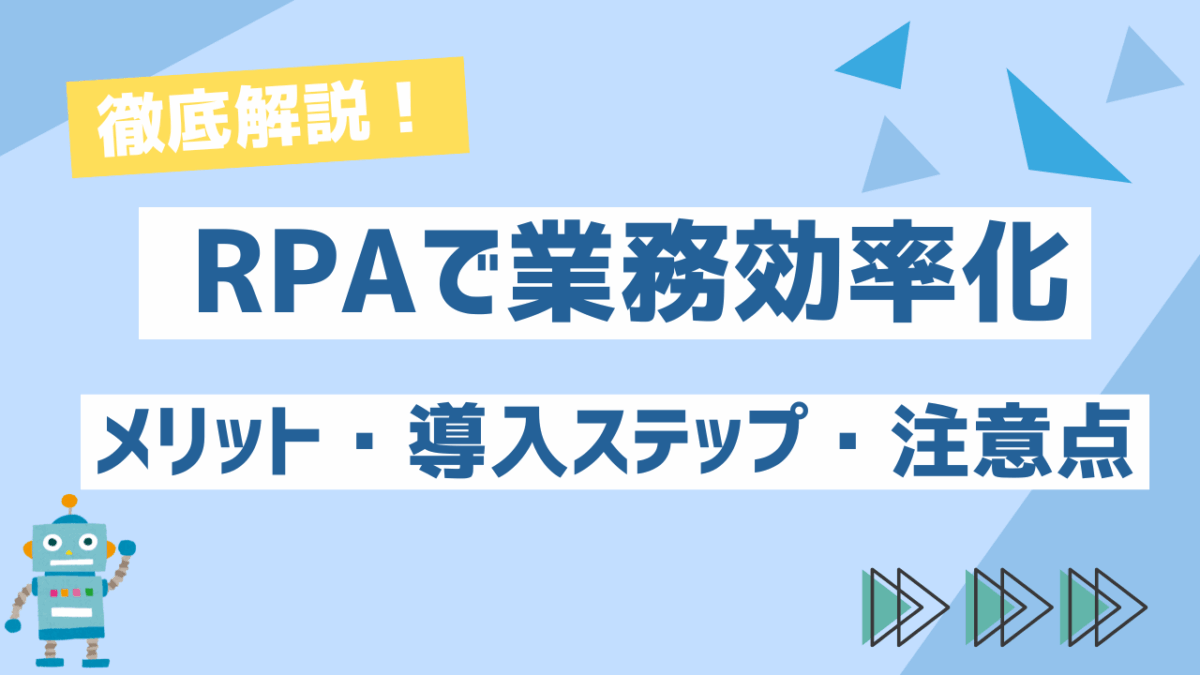「業務のムダをなくしたい」「人手不足をテクノロジーで解決したい」と考えている方も多いのではないでしょうか。そんな課題の解決策として、今注目されているのがRPA(Robotic Process Automation)です。RPAは、定型的な事務作業を自動化することで、作業時間を大幅に削減し、業務効率を大きく高めることができます。
この記事では、RPAを使って業務を効率化するための基本的な知識や導入手順、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。RPA導入を検討している方や、自社に合った活用方法を探している方は、ぜひ最後までご覧ください。
RPAは、人が繰り返し行う事務作業を自動化し、業務効率を大きく高める注目の技術です。人手不足や働き方改革の中で、時間削減・ミス防止・属人化解消・生産性向上を同時に実現できる手段として幅広い企業で導入が進んでいます。
この記事では、RPAの基礎、向いている業務、導入メリット、注意点、導入ステップ、主要ツールの比較までをわかりやすく整理。自社でどの作業を自動化すべきか、導入前に知っておきたいポイントが短時間で理解できる内容です。
なぜ今「RPA × 業務効率化」なのか
いま、企業は人手不足や働き方の見直しといった大きな変化に直面しています。少子高齢化により労働力が減り続ける中で、限られた人材でどうやって効率よく仕事を進めるかが大きな課題となっています。どんな業種・規模の企業であっても、「業務を効率化すること」は避けて通れないテーマです。
その解決策として期待されているのが、RPA(Robotic Process Automation)です。RPAは、人がパソコンで繰り返し行っている作業を、ソフトウェアのロボットに任せることで、自動化できる技術です。RPAを導入することで、作業時間の短縮はもちろん、業務のやり方を標準化したり、作業ミスを減らしたりといった効果も期待できます。また、社員がより価値の高い仕事に集中できるようになり、働き方そのものの改善にもつながります。
RPAとは?業務効率化との関係をわかりやすく解説
RPAとは、ホワイトカラー業務の中でも、定型的で繰り返し発生する作業をソフトウェアの「ロボット」に代行させる技術です。人間がPC上で行っていたルーチンワークを自動で実行することで、業務を効率化し、作業時間を大幅に短縮することが可能になります。
RPAが担うのは、以下のような業務です。
- データ入力や集計
- 顧客情報の更新
- 各種帳票の作成・送信
- システム間のデータ連携
これらは多くの企業で毎日行われている作業ですが、手作業で行うと時間がかかり、ヒューマンエラーも起こりやすくなります。RPAを導入することで、こうした課題を一気に解決できるのが大きな特徴です。
さらに、RPAは「人の手を介さずに処理を行う」だけでなく、「業務そのものを標準化し、見える化する」という副次的効果もあります。属人化していた業務をRPAが担うことで、誰でも同じ品質で作業を遂行できる体制が整い、組織全体の生産性向上にもつながります。
つまりRPAは、単なる作業自動化ツールではなく、業務効率化を根本から支える仕組みといえるでしょう。
RPAは、定型業務の自動化によって業務効率化を強力に推進しますが、さらに非定型業務や創造的な作業の効率化を図るには、AIの活用も有効です。特にChatGPTは、文章作成・マニュアル化・情報整理・アイデア出しなど、これまで人間が時間をかけて行っていた業務をサポートし、作業負担を大幅に軽減します。
RPAと組み合わせることで、日々の業務を「自動化+高度化」できるのが大きな魅力です。
詳しくは、【完全版】ChatGPTで業務効率化!すぐ使えるスゴ技10選|マニュアル作成・可視化まで徹底ガイドをご覧ください。
RPA導入による業務効率化の主なメリット
RPAを導入することで、単に作業を自動化するだけでなく、業務の質や働き方そのものにも良い影響を与えることが期待されます。ここでは、RPAがもたらす代表的なメリットを4つの観点から整理します。
RPA導入メリット①:作業時間の削減
RPAは人間のように疲れることがなく、24時間体制で稼働できます。これにより、時間のかかっていた定型業務を短時間で処理できるようになり、社員が本来注力すべき業務に時間を使えるようになります。特に膨大なデータ入力や帳票作成などの作業では、劇的な時間短縮が期待できます。
RPA導入メリット②:エラーの防止と作業品質の向上
人が行う作業には、どうしてもミスがつきものです。数字の打ち間違いや転記ミスなど、些細なエラーでも後工程に影響を及ぼす可能性があります。RPAを活用すれば、決められたルール通りに正確に作業を行うため、ヒューマンエラーのリスクを大幅に減らすことができます。
RPA導入メリット③:業務の標準化と属人化の解消
手作業に依存している業務は、人によってやり方やスピードが異なり、属人化しやすいという課題があります。RPAを導入することで、業務手順を明確にし、ツールに作業を任せることができるため、特定の担当者に頼らず、誰でも一定の水準で業務を遂行できる仕組みが整います。
RPA導入メリット④:社員の負担軽減と働き方改革の推進
単調で負荷の高い作業をRPAに任せることで、社員のストレスや残業時間を減らすことができます。その結果、より創造的で価値の高い業務に集中できる環境が整い、企業全体としての生産性や働きやすさの向上にもつながります。
RPAが向いている業務とは?

RPAはすべての業務に適しているわけではなく、特に自動化に向いている業務とそうでない業務があります。ここでは、RPAの適用対象として効果が出やすい業務の特徴と、部門ごとの具体例を紹介します。
RPAに適している業務の特徴
RPAが効果を発揮するのは、次のような条件を満たす業務です。
- 作業手順がルール化されている
- 同じ処理を繰り返し行う
- 人手で処理すると時間がかかる
- 複数のシステムをまたいで作業している
- 人的ミスが発生しやすい
こうした業務は、ロボットに置き換えることで効率化と品質向上の両立が期待できます。
部門別の適用例
RPAの導入は、さまざまな部門で実現可能です。以下は、代表的な部門別の適用イメージです。
- 経理部門:請求書の発行、経費精算、取引データの入力
- 総務部門:勤怠情報のチェック、入退社処理、備品管理
- 人事部門:人事データの更新、応募者情報の登録、給与明細の送信
- 営業部門:顧客情報の入力、日報の集計、レポート作成
- 情報システム部門:アカウント管理、定期的なログ確認、データ移行作業
これらの業務に共通するのは、手順が明確で、繰り返しの作業が多いことです。逆に、判断が複雑だったり、対人対応が必要な業務にはRPAはあまり向いていません。
自社業務に向いているかどうかの見極め方
RPAの導入効果を最大限に引き出すには、業務の棚卸と可視化が不可欠です。現在の業務を一つひとつ洗い出し、「ルール通りに処理できるか」「作業量が多いか」といった観点で整理してみましょう。自動化に向いている業務を見つけ出すことで、効率化の第一歩が踏み出せます。
RPA導入における注意点と落とし穴
RPAは非常に便利なツールですが、導入すれば必ず成功するわけではありません。効果を最大化するためには、事前の準備や導入後の運用体制が欠かせません。ここでは、導入時によく見られる注意点と陥りやすい落とし穴を整理します。
目的が不明確なまま導入してしまう
「RPAが流行っているから」「他社が導入しているから」といった理由だけで導入を進めると、思ったような効果が出ないことがあります。自社が抱えている業務課題を明確にし、何のためにRPAを導入するのかを最初に定義しておくことが重要です。
対象業務の選定が甘い
すべての業務がRPAに適しているわけではありません。適さない業務に無理にRPAを適用しようとすると、かえって非効率になることもあります。前章で紹介した「ルール化・反復性・大量処理」といった観点で、適切な業務を選定する必要があります。
社内理解や協力体制が不足している
RPAは業務のやり方そのものを変えるため、現場の理解と協力が欠かせません。担当者がRPAを「自分の仕事を奪うもの」と誤解してしまうと、導入後の運用がうまくいかなくなります。導入前から関係者に丁寧に説明し、納得感を持ってもらうことが大切です。
導入後の保守・運用体制が不十分
RPAは一度導入すれば終わりではなく、業務の変更に応じて設定を修正したり、稼働状況をモニタリングしたりする必要があります。ツールの操作や修正を担う担当者を確保し、定期的なメンテナンス体制を整えておくことが継続的な活用につながります。
RPA導入ステップ|業務効率化までの流れ
RPAを導入する際は、いきなり本格的な開発や運用を始めるのではなく、段階を踏んで進めることが成功の鍵です。ここでは、業務効率化を実現するための代表的なステップを5段階に分けて解説します。
RPA導入ステップ①:現状業務の可視化と整理
まずは、自社の業務内容を洗い出し、どの業務がどのように行われているのかを明らかにすることから始めます。フロー図や一覧表などを活用して、作業手順・担当者・使用ツールなどを整理し、現状を客観的に把握することが重要です。
RPA導入ステップ②:自動化対象業務の選定
可視化した業務の中から、RPAに向いている業務を選びます。ルールに基づいて処理されており、作業量が多く、繰り返し発生するものが候補となります。初めて導入する場合は、影響範囲が狭く、効果が見えやすい業務を選ぶとスムーズです。
RPA導入ステップ③:ツールの選定とPoC(概念実証)の実施
RPAツールには多くの種類があり、自社のIT環境や人材スキルに応じた選定が必要です。いきなり本番導入するのではなく、小規模な業務で試験運用(PoC)を行うことで、実際の操作性や効果を確認しながら、課題を洗い出せます。
RPA導入ステップ④:本格導入と運用体制の整備
PoCで効果が確認できたら、本格的に導入を進めます。この段階では、運用管理者や開発担当者を明確にし、障害時の対応フローやマニュアルの整備など、安定稼働に向けた体制づくりが求められます。
RPA導入ステップ⑤:効果測定と改善のループ構築
導入後は、期待通りの効果が出ているかを定期的に確認し、必要に応じて設定や運用を見直します。業務環境の変化や社員のフィードバックをもとに改善を繰り返すことで、RPAを継続的に活用できる仕組みが整います。
業務効率化を実現するRPAツール5種
| ツール名 | 特徴 | 主な機能 |
| UiPath | 操作が直感的で、グローバルでの導入実績が多く、学習教材が充実 | デスクトップ/クラウド自動化、ドラッグ&ドロップ開発、AI連携、OCR対応 |
| WinActor | 国産ツールで日本企業の業務に適合。公共機関での採用実績も多数 | 日本語GUI、自動記録機能、外部システム連携、Office操作自動化 |
| BizRobo! | 業務の可視化からロボ作成・運用まで対応。柔軟な導入形態が特徴 | クラウド/オンプレ対応、業務フロー分析、複数ロボ管理、スケジューリング |
| Automation Anywhere | AI連携やクラウド対応に優れ、大規模・複雑な業務に適した設計 | クラウドネイティブ、Botストア、API連携、分析ダッシュボード |
| Power Automate | Microsoft製品との連携に優れ、既存のOffice環境を活かしやすい | Teams/Outlook連携、テンプレート豊富、クラウドフロー、条件分岐自動化 |
UiPath(ユーアイパス)
UiPathは、世界中で高いシェアを誇るグローバルRPAツールです。操作は直感的でノーコード開発にも対応しており、非エンジニアでも扱いやすいのが特長です。デスクトップ型とクラウド型の両方を選択でき、AI連携やOCR(文字認識)にも対応しています。多くの教材やコミュニティが整備されているため、導入や学習のしやすさにも定評があります。
WinActor(ウィンアクター)
WinActorは、NTTグループが開発した日本製のRPAツールで、国内の中小企業や自治体を中心に広く導入されています。Excelやメール、基幹システムなど日本の業務環境に合わせた操作性が強みです。日本語のユーザーインターフェースやサポートが充実しており、ITに不慣れな現場でも比較的導入しやすい点が評価されています。
BizRobo!(ビズロボ)
BizRobo!は、業務プロセスの可視化からロボット開発、運用管理までをトータルで支援する国産RPAツールです。クラウド・オンプレミスの両対応が可能で、柔軟な運用ができる点が特長です。複数のロボットを一元管理できるため、中堅企業や部門をまたぐ自動化に適しています。シナリオ作成機能も充実しており、複雑な業務にも対応可能です。
Automation Anywhere(オートメーション・エニウェア)
Automation Anywhereは、AIや機械学習との連携に強みを持つ、クラウドネイティブなRPAツールです。高度な自動化ニーズを持つ企業向けに設計されており、業務プロセスを分析・改善するための分析機能も備えています。Botの共有マーケットプレイス「Bot Store」や、拡張性の高いAPI連携機能も用意されており、大規模・複雑な業務に適しています。
Power Automate(パワーオートメート)
Power Automateは、Microsoftが提供するクラウドベースのRPAサービスで、OutlookやTeams、ExcelなどMicrosoft 365製品との親和性が高い点が魅力です。テンプレートが豊富で、簡単な業務であれば短時間で自動化を始めることができます。IT部門だけでなく一般部門の社員が自ら業務を自動化できる、手軽さと拡張性を兼ね備えたツールです。
RPAツール選定のポイントと比較検討のコツ
RPAを導入する際には、どのツールを選ぶかが成果を左右する重要な要素となります。市場には多種多様なRPAツールがあり、自社に適したものを見極めるにはいくつかの比較ポイントを押さえる必要があります。ここでは、RPAツールを選ぶうえでの代表的な判断軸をご紹介します。
RPAツール選定のポイント①:操作性と学習コスト
RPAを現場で活用するには、担当者が日常的に使える操作性が求められます。ノーコードまたはローコードで直感的に操作できるツールであれば、専門的なプログラミングスキルがなくても運用できます。誰が運用するかを踏まえて、ツールの操作難易度を確認しましょう。
RPAツール選定のポイント②:サポート体制と導入支援の有無
導入時やトラブル発生時に、どれだけサポートを受けられるかも重要です。日本語での対応やFAQ、電話・チャットサポートの有無などを確認し、自社の体制に合ったベンダーを選ぶことが大切です。また、導入支援サービスがあるかどうかもチェックポイントです。
RPAツール選定のポイント③:導入・維持にかかるコスト
RPAには無料から高機能な有料ツールまでさまざまな価格帯があります。初期導入費用、月額使用料、ライセンス数、保守費用などを比較し、自社の予算とスケールに応じた選定が必要です。将来的に利用範囲を拡大する可能性がある場合は、拡張性も視野に入れて検討しましょう。
RPAツール選定のポイント④:自社業務との親和性と拡張性
既存の業務システムやIT環境とスムーズに連携できるかどうかもポイントです。特定のソフトやクラウドサービスとの相性、API連携の可否など、自社の運用実態に照らして確認しましょう。また、将来的にAIやOCRとの連携を見据える場合は、拡張性も重要な判断材料となります。
RPAを活用して、業務効率化の第一歩を踏み出そう
業務効率化は多くの企業にとって喫緊の課題であり、その有効な手段としてRPAが注目されています。定型的な作業を自動化することで、単なる時間短縮にとどまらず、業務品質の向上や社員の負担軽減、働き方改革の推進など、さまざまなメリットが得られます。
ただし、RPAは導入すれば自動的に成果が出るものではありません。目的や対象業務を明確にしたうえで、段階を踏んで着実に進めることが成功のカギとなります。また、導入後の運用や改善も含めた長期的な視点で取り組むことが重要です。
まずは自社の業務を整理し、RPAの導入に適した業務があるかどうかを検討してみましょう。小さな業務からスモールスタートすることで、リスクを抑えつつ効果を体感できます。自社に合ったツールや運用体制を見極めながら、業務効率化の第一歩を踏み出すことが、持続可能な業務改善への近道となるはずです。
ーーー
How to Achieve Work Efficiency with RPA: Benefits, Steps, and Best Practices
業務効率化なら専門家にお任せ!
仕事のムダやムラを減らし、スピーディーで質の高い業務を実現しませんか?Mayclassは、業務マニュアルを通じて、効率的な働き方をサポートします。業務の流れを明確にし、属人化を防ぐことで、誰もがスムーズに作業を進められる仕組みを構築。さらに、ノウハウの共有が進み、業務品質の向上にもつながります。職場のパフォーマンスを最大化するなら、mayclassにお任せください!

▼下記記事もおすすめ▼