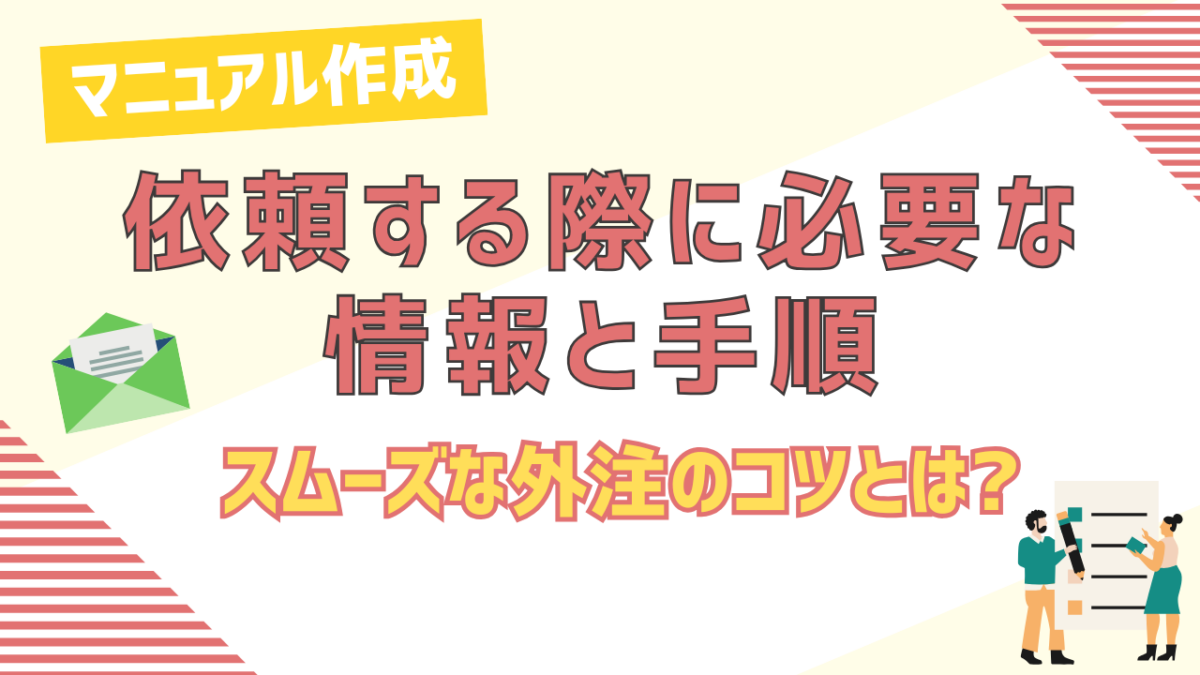業務の標準化や新人教育の効率化を図るうえで、マニュアルの整備は欠かせません。しかし、「社内で作成する時間がない」「クオリティの高いマニュアルを作りたい」といった理由から、外部の専門業者に依頼する企業も増えています。
しかし、マニュアル作成を外注する際には、「何を伝えればよいのか」「どのような手順で進めるのか」を把握しておかないと、思うような成果が得られないこともありますよね。
本記事では、マニュアル作成を依頼する際に必要な情報や手順、注意点をわかりやすく解説します。スムーズに外注し、業務効率化を実現するためのポイントを押さえておきましょう。
「マニュアルを作りたいけど、時間がない」「プロに任せて質の高いものを作りたい」そんな方におすすめの記事です。
この記事では、マニュアル作成を外部に依頼する際の流れやポイントをわかりやすく解説。依頼前に整理すべき内容(目的・対象・形式・予算など)や、業者選びで失敗しないコツ、注意点までしっかり紹介しています。
初めて外注を検討している方や、効率よく高品質なマニュアルを作りたい方にぴったりの内容です。
マニュアル作成依頼の必要性
まずは、マニュアル作成を依頼する必要性について一緒に見ていきましょう。
マニュアル作成を依頼する企業が増えている理由
近年、多くの企業がマニュアル作成を外部に依頼するケースが増えています。特に、業務の属人化を防ぎ、標準化を進めることが求められる中で、専門的なノウハウを持つ外部企業への依頼が注目されています。
社内でマニュアルを作成しようとすると、以下のような課題が発生しがちです。
- 担当者の負担が大きい(本来の業務に支障が出る)
- ノウハウが属人化している(経験者しか作成できない)
- 作成スキルにばらつきがある(分かりやすいマニュアルが作れない)
こうした課題を解決するために、プロのマニュアル作成代行会社に依頼する企業が増えています。
マニュアル作成を依頼すべきケースとは?
マニュアルを自社で作成するよりも、マニュアル作成を外部に依頼することで業務の効率化や品質向上が期待できます。特に、以下のような場合は、外部の専門家に任せた方が効率よくマニュアル作成が進む可能性があります。
業務の属人化が進んでいる
業務が特定の担当者に依存している場合、マニュアルを整備しないままでは、退職や異動の際に知識が失われ、業務の継続性が損なわれるリスクがあります。社内でマニュアルを作成しようとすると、業務内容を把握している担当者が作業を行う必要がありますが、通常業務との両立が難しく、作成が後回しになることが少なくありません。また、文章化のスキルには個人差があり、作成者ごとに表現や構成が異なることで、統一性のないマニュアルができてしまうケースもあります。
一方で、マニュアル作成の外注を活用すれば、業務を体系的に整理し、誰が読んでも理解しやすい形でマニュアルを作成できます。さらに、プロのライティング技術を活かし、統一感のあるフォーマットで仕上げることで、情報の分かりやすさが格段に向上します。担当者の負担を軽減しながら、標準化された業務プロセスを確立できる点も、外注を選択する大きなメリットです。
新入社員の教育に時間がかかっている
新入社員の研修において、毎回同じ説明を繰り返さなければならない状況は、教育担当者にとって大きな負担となります。また、担当者ごとに指導の仕方が異なることで、教えられる内容にバラつきが生じ、一貫性のない研修になりがちです。さらに、口頭説明が中心となると、情報の抜け漏れが発生するリスクもあります。
こうした課題を解決するには、分かりやすいマニュアルを整備し、研修の標準化を図ることが重要です。外部の専門業者に依頼すれば、誰が読んでも理解しやすい研修用のマニュアルを作成できるだけでなく、必要に応じて図解や動画を取り入れることも可能になります。分かりやすいマニュアルにより、新入社員が自主的に学習できる環境を整えることができ、研修の負担を軽減しながら教育の質を向上させることができます。
マニュアルの内容が古く、最新の業務フローに対応していない
業務の進め方は時代とともに変化し、ツールやプロセスの見直しが行われることも少なくありません。しかし、マニュアルの更新作業が後回しになってしまうと、実際の業務とマニュアルの内容が食い違い、業務ミスや生産性の低下を招く恐れがあります。また、マニュアルをどのように更新すればよいのか判断が難しく、担当者が手をつけにくいという問題も発生しがちです。
外注を活用することで、業務フローを客観的に整理し、最新の業務内容に即したマニュアルへとアップデートできます。専門家の視点から、必要な情報を適切に取捨選択し、見やすく編集することで、実務に役立つマニュアルへと仕上げることができます。また、紙のマニュアルからデジタルフォーマットへの移行や、検索性の向上など、業務の利便性を高める提案を受けることも可能です。
マニュアル作成のための時間やリソースが不足している
マニュアルの作成には時間と労力がかかるため、通常業務をこなしながら作成を進めるのは簡単なことではありません。業務と並行してマニュアルを作成しようとすると、十分な時間を確保できず、作成作業が後回しになりがちです。また、文書作成に慣れていない場合は、構成や表現に迷い、完成までに多くの時間を要することもあります。最悪の場合、作成途中で頓挫し、未完成のまま放置されることも珍しくありません。
外注を利用すれば、専門のライターや編集者が作成を担当するため、短期間で質の高いマニュアルを完成させることができます。また、社内のリソースを消費することなく、業務に集中できる環境を維持できる点もメリットの一つです。さらに、スケジュール管理が明確になり、納期内に確実にマニュアルを完成させることができるため、計画的な業務運営が可能になります。
マニュアルを自社で作成しようとすると、業務の負担が増えたり、クオリティのばらつきが発生したりと、さまざまな課題に直面します。一方で、外部のマニュアル作成専門業者に依頼すれば、短期間で統一感のある高品質なマニュアルを作成でき、業務の標準化や教育の効率化をスムーズに進めることが可能です。
マニュアル作成依頼で必要な情報は?

マニュアル作成をスムーズに進めるためには、依頼時に必要な情報を整理し、的確に伝えることが重要です。以下のポイントを明確にすることで、作成するマニュアルの方向性が定まり、期待に沿った仕上がりになります。
依頼内容の詳細
まず、どの業務についてのマニュアルを作成するのかを具体的に伝える必要があります。例えば、「新入社員向けの業務手順書」「製品の取り扱いマニュアル」「カスタマーサポート業務の対応フロー」など、対象となる業務の範囲を明確にしましょう。また、対象者(新入社員、管理職、社外顧客など)も伝えておくと、より適切な内容に仕上がります。
目指すマニュアルの品質
マニュアルの品質を決める際には、どのような目的で、どの程度の詳細さで作成するのかを明確にすることが重要です。業務の内容や対象者によって、求められる情報のレベルや表現方法が変わるため、以下の視点を考慮しながら決定していきます。
まず、マニュアルの目的を明確にします。例えば、新入社員が業務をスムーズに習得するためのものなのか、熟練者が高度な業務を実施する際の指針となるものなのか、または社外向けの製品マニュアルなのかによって、求められる情報の粒度が異なります。新入社員向けであれば、業務の基礎や手順を丁寧に説明する必要があり、熟練者向けであれば、より高度な業務のポイントや注意点を中心にまとめる必要があります。
次に、業務の背景や応用方法、トラブル対応の手順をどの程度盛り込むのかを決定します。例えば、飲食店の調理マニュアルを作成する場合、基本的な調理手順だけではなく、食材の管理方法や衛生管理のルール、盛り付けのポイントなども記載することで、業務の標準化と品質向上が図れます。また、製造業やIT業界などでは、トラブル発生時の対応フローを明記することで、業務の安定性を高めることができます。
さらに、情報の表現方法も重要な要素です。テキストのみで構成するのか、写真やイラストを活用するのか、動画を組み合わせるのかによって、伝わりやすさが大きく変わります。特に、機械の操作や製品の組み立てなど視覚的な要素が多い業務の場合、文章だけでなく、図解や写真を多用することで理解しやすいマニュアルになります。
これらの要素を総合的に検討し、どのような品質のマニュアルを目指すのかを明確にすることで、外注先に具体的な要望を伝えやすくなり、より実用的で効果的なマニュアルを作成することができます。
マニュアルの形式
作成するマニュアルの形式も、事前に決めておくべきポイントです。紙ベースの冊子として作成するのか、デジタル形式で提供するのかを選択し、それに応じたフォーマットを指定します。
例えば、紙のマニュアルは印刷しやすいWordやPDFが適しており、更新しやすいマニュアルを作成するならPowerPointやGoogleスライドが便利です。また、社内のナレッジ共有ツールやクラウドストレージに掲載する場合は、編集・検索しやすいデジタル形式が望ましいでしょう。用途や運用方法に応じて、最適な形式を選ぶことが重要です。
希望の納期
マニュアルの完成時期を明確にすることで、スケジュールに沿った進行が可能になります。例えば、新入社員向けのマニュアルなら「入社の3カ月前までに完成させる」、退職予定者の引き継ぎ用マニュアルなら「最終出社日の2カ月前までに仕上げる」など、業務スケジュールを考慮して納期を設定するとスムーズです。また、急ぎの場合は短期間で対応できるかどうかも確認し、納期の調整が必要になることもあります。依頼する際は、希望納期とあわせて、スケジュールに柔軟性があるかどうかを伝えておくとよいでしょう。
希望の予算
マニュアル作成には、内容のボリュームや作成形式、修正の回数などに応じて費用が変動します。事前に予算の目安を決めておくことで、見積もりの際に適切なプランを提案してもらいやすくなります。例えば、シンプルな手順書であれば比較的低コストで作成可能ですが、図解や動画を含めた詳細なマニュアルになると、制作コストが高くなる傾向があります。また、納期が短い場合や追加の編集・修正が多くなる場合も、費用が増加する可能性があるため、事前にどの程度の予算を考えているのかを明確にしておくことが重要です。
マニュアル作成依頼の手順
マニュアルを外部の専門業者に依頼する際は、適切なプロセスを踏むことで、スムーズかつ高品質な成果物を得ることができます。以下の手順に沿って進めることで、ニーズに合ったマニュアル作成を実現できます。
マニュアル作成依頼手順1:マニュアル作成代行会社の選定
まず、マニュアル作成を依頼する業者を選定します。代行会社によって得意とする分野や対応範囲、提供できるサービス内容が異なるため、複数の業者を比較することが重要です。選定の際には、以下のポイントを確認するとよいでしょう。
- コストパフォーマンス:料金とサービス内容のバランスが適切か
- 信頼性:過去の実績や口コミ、取引実績が豊富か
- 対応範囲:業務内容に適したマニュアルを作成できるか(紙媒体・デジタル・動画など)
また、自社の業務内容を十分に理解してもらえるかどうかも、業者選定の重要なポイントとなります。実績のある業者であれば、業務の流れや専門知識を反映した質の高いマニュアルを提供してくれる可能性が高くなります。
マニュアル作成依頼手順2:依頼できる業務範囲の確認
マニュアル作成代行会社にも、それぞれ得意とする分野や対応できる業務範囲に違いがあります。
例えば、製造業向けの業務マニュアルに特化している業者、ITシステムの操作マニュアル作成を得意とする業者、動画マニュアルやEラーニング用コンテンツを作成できる業者など、専門性が異なるため、自社の業務に適したサービスを提供しているかを確認することが重要です。
また、マニュアル作成の際に必要な素材(写真・イラスト・動画)の準備が可能か、社内でのヒアリングや取材を実施してくれるかなど、作成プロセスのサポート内容も確認しておくと安心です。
マニュアル作成依頼手順3:依頼内容の具体化
業者の選定が完了したら、マニュアルの内容を具体的に決めていきます。この段階では、以下のポイントを整理し、業者に的確に伝えることが求められます。
- マニュアルの対象業務(どの業務についてのマニュアルか)
- 対象者(新入社員向け・経験者向け・社外向けなど)
- マニュアルの形式(紙・デジタル・動画など)
- 記載する情報の詳細レベル(基本手順のみか、トラブル対応や応用例も含めるか)
- 納期の目安
依頼内容を具体的にすることで、業者との認識のズレを防ぎ、スムーズに作業を進めることができます。
マニュアル作成依頼手順4:見積もり依頼
依頼内容が決まったら、見積もりを依頼します。業者によって料金体系が異なるため、単に総額を比較するだけでなく、費用の内訳を確認することが重要です。具体的には、以下の項目をチェックします。
- 基本料金(マニュアルの作成費用)
- 追加料金の有無(修正回数に制限があるか、取材費がかかるか)
- 納期のスケジュール(短納期の場合の追加費用など)
複数の業者から見積もりを取ることで、適正な価格で依頼できるかどうかを判断しやすくなります。
マニュアル作成依頼手順5:契約と開始
見積もりの内容に納得できたら、契約を締結し、マニュアルの作成を開始します。契約時には、納品物の形式や修正対応の範囲、納期の厳守など、事前に合意した内容が契約書に明記されているかを確認しましょう。
また、作成途中で業務フローの変更や追加の要望が発生する可能性もあるため、必要に応じて業者と連携しながら調整を行います。定期的に進捗を確認し、必要があればこちらの要望を伝えてマニュアル内に取り入れてもらうことで、より完成度の高いマニュアルを作成することができます。
マニュアル作成代行会社に依頼する際の注意点
マニュアル作成を外部に依頼することで、高品質な成果物を得られる一方で、業者の選定や契約内容を適切に確認しないと、期待した内容と異なる結果になることもあります。スムーズに進めるためには、事前に押さえておくべき注意点があります。ここでは、特に重要な3つのポイントについて解説します。
業者の実績や得意分野を確認
マニュアル作成代行会社には、それぞれ得意とする分野があります。例えば、製造業向けの業務マニュアルに強みを持つ会社、ITシステムの操作マニュアル作成を専門とする会社、研修用の動画マニュアルを得意とする会社など、対応可能な領域が異なります。そのため、自社の業務に適したマニュアルを作成できる業者かどうかを事前に確認することが重要です。
業者の実績をチェックする際には、過去の事例やクライアントの業種、サンプルの提供が可能かどうかを確認するとよいでしょう。また、同じ業界での実績がある業者であれば、業務内容をスムーズに理解してもらえるため、より実用的なマニュアルが完成しやすくなります。
継続的な更新・改善が可能か確認
マニュアルは、一度作成すれば終わりではなく、業務の変化に合わせて定期的な更新が必要になります。作成したマニュアルが陳腐化しないよう、継続的な改善やアップデートが可能かどうかを確認しておくことが重要です。
例えば、新しい業務フローが追加された際に、迅速にマニュアルを更新できる体制があるか、マニュアルの修正・追加作業に対応しているかを事前に確認しましょう。業者によっては、一定期間内の修正が無料で行える場合もありますし、都度追加費用が発生する場合もあります。自社の業務運用に適したサポート体制があるかどうかを見極めることが重要です。
追加費用の発生条件を明確にしておく
マニュアル作成を依頼する際には、見積もりの段階で費用の内訳を確認し、追加費用が発生する条件を明確にしておくことが大切です。業者によっては、契約時に提示された金額以外に、以下のようなケースで追加費用が発生する場合があります。
- 修正回数の制限:一定回数以上の修正には追加料金がかかることがある
- 取材・ヒアリング費用:業務内容の詳細なヒアリングが別途費用になることがある
- デザインやレイアウトの変更:フォーマットや構成の大幅な変更に追加料金が発生することがある
こうした費用がどのような条件で発生するのかを事前に確認し、予算オーバーにならないよう注意が必要です。契約前に業者としっかり話し合い、不明点をなくしておくことが、スムーズなマニュアル作成につながります。
プロに依頼してスムーズにマニュアルを作成しよう
マニュアル作成を外部に依頼することで、業務の標準化や教育の効率化を実現し、社内の負担を大幅に軽減できます。しかし、スムーズに進めるためには、依頼内容を具体的に整理し、適切な代行会社を選定することが重要です。
依頼する際には、業務の内容や目的、マニュアルの品質、形式、納期、予算などを明確にし、見積もりや契約内容をしっかり確認しましょう。また、業者の実績や得意分野をチェックし、継続的な更新・改善が可能かどうかを見極めることも大切です。
社内でマニュアル作成を行うのが難しい場合や、高品質なマニュアルを短期間で作成したい場合は、プロのマニュアル作成代行を活用するのが最適な選択肢です。専門業者のノウハウを活かし、分かりやすく実用的なマニュアルを作成することで、業務の効率化や教育の質の向上を実現しましょう。
ーーー
How to Request Manual Creation Outsourcing: Required Info, Steps, and Smooth Workflow Tips
見やすくわかりやすいマニュアルを作成ならmayclass
mayclassでは、マニュアル作成のプロが、貴社のニーズに合わせたマニュアルを提供します。
1.プロによるヒアリング
マニュアル作成のプロが、貴社の業務内容を丁寧にヒアリングします。これにより、業務の特性やニーズを正確に把握し、適切な内容を盛り込むことができます。
2.優先度に基づくマニュアル化
業務の優先度を見極め、重要な業務から順次マニュアル化を進めます。これにより、最も必要な情報を早急に整備し、業務の効率化を図ります。
3.わかりやすいデザイン
マニュアルのデザインにおいて、視覚的にわかりやすいレイアウトやフォーマットを提案します。これにより、情報が整理され、読者が理解しやすくなります。
mayclassと共に、業務の効率化を図り、組織の成長を加速させましょう。

▼こちらの記事もおすすめ▼
【業務マニュアル作成のコツ】完璧な目次の作り方ガイド!項目例もご紹介