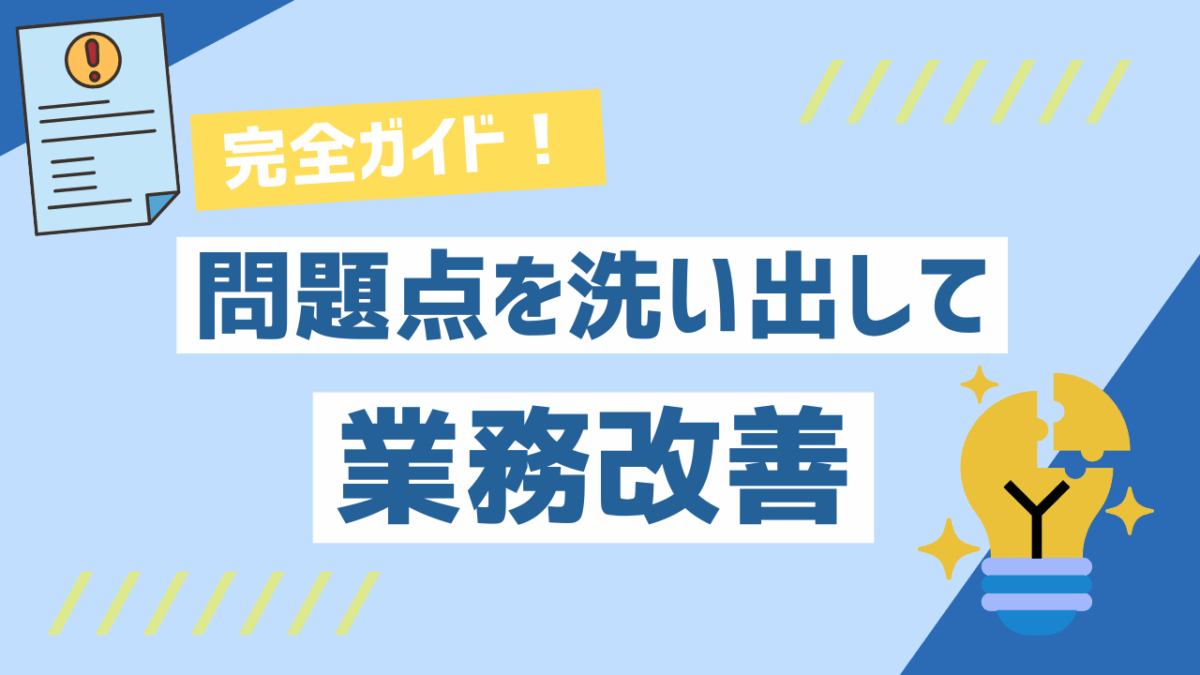業務改善を進めたいと考えていても、 「どこに問題があるのか分からない」「改善ポイントが見えてこない」 と、最初の一歩が踏み出せずにいませんか?現場で本当に効果的な業務改善を進めるには、業務の問題点を洗い出して可視化することが欠かせません。
本記事では、問題点の見つけ方や具体的な改善ステップ、役立つツールまで、現場で使える視点でわかりやすく解説します。
「どこから業務改善に手をつければいいか分からない」と感じている方向けの実務ガイドです。業務の問題点を洗い出す考え方から、属人化・ミス多発・負荷過多など典型的な課題の見つけ方、業務分解図やアンケート・データ分析などの具体的なツール活用法、5ステップでの整理手順までを分かりやすく解説。改善アイデアの出し方や優先度のつけ方など、「現場で実際に動かすところ」までイメージできる内容になっています。
業務改善における「問題点の洗い出し」とは?
業務改善を進めるには、やみくもに対策を講じるのではなく、まず「どこに問題があるのか」を明らかにすることが何より大切です。
ここでは、業務改善のスタート地点となる「問題点の洗い出し」がなぜ重要なのかと、よく混同されがちな「業務改革」との違いについても確認しておきましょう。
問題点の洗い出しが業務改善の起点になる理由
業務改善をうまく進めるには、まず「どこをどう変えるべきか」を正しく把握することが大事です。
とはいえ、日々の業務の中で当たり前になっている作業やルールには、気づかないまま非効率やムダが入り込んでいることも少なくありません。
例えば、紙の申請書を使ったフローが毎回の確認に時間を取っていたり、複数人で確認が必要な処理が誰の担当か曖昧だったりといったケースは、どの職場にも見られるものです。問題点を事前に明確にしておけば、上司や他部署との共有がしやすくなり、改善案にも納得を得やすくなります。
さらに、優先順位をつけやすくなるため「手が付けやすい部分」から取りかかることで、早い段階で成果を出しやすくなるのも大きなメリットです。
「業務改善」と「業務改革」の違いも理解しよう
「業務改善」と「業務改革」は似た言葉ですが、それぞれの目的やアプローチには明確な違いがあります。業務改善は、現在の業務の流れややり方を見直し、ムダを減らして効率化を図る取り組みです。
例えば入力作業の手順を見直したり、チェック項目を統一してバラつきをなくしたりするような改善がこれにあたります。現場で取り組みやすく、比較的短期間で効果が表れやすいのが特徴です。
一方、業務改革は、業務そのものの仕組みやルールを根本から変えるアプローチです。
例えば、FAXや紙で運用していた受発注業務をやめて、クラウド上のシステムに切り替えるような取り組みがそれに該当します。組織のルールや体制まで見直す必要があるため、影響範囲も大きくなります。
まずは足元の業務から着実に見直しましょう。
問題点の洗い出しが必要となる3つのケース
どんな現場にも、「なんとなくやりにくい」「時間がかかっている気がする」といった違和感や非効率がひそんでいます。そうした小さなサインこそが業務改善のヒントです。
ここでは、問題点の洗い出しが特に必要とされる代表的なパターンを3つ取り上げ、それぞれの背景や見分け方を解説します。
業務フローが複雑・属人化している
「この作業はAさんにしか分からない」
「どう進めればいいか分からないけど、とりあえずいつもこうしている」
そんな声が聞こえてくる現場では、業務が属人化している可能性があります。
属人化が進んでいる業務はブラックボックスになりやすく、問題が発生しても原因が追いにくいといった特徴があります。
さらに、担当者が急に休んだり異動・退職したりすると、業務そのものが止まってしまうのも大きなリスクです。
また、人によってやり方が異なっていたり、どこまでが誰の仕事かがはっきりしていない場合も、見直しが必要なサインです。まずは業務の流れを一度整理し、誰でも内容を把握できる状態にしましょう。
ミスやトラブルが頻発している
月末や繁忙期になるとエラーが増える、入力ミスや手戻り作業が多いなどの状態が続いている場合、業務のどこかに無理やムダが隠れている可能性があります。
ミスが発生する原因はさまざまですが、「確認作業が二重になっている」「必要な情報が一箇所に集まっていない」「手順が複雑すぎて覚えきれない」といった構造的な問題が背景にあることも多いです。
仕組みやフローそのものに着目し、「なぜミスが起きているのか」を見直していくことが問題点の洗い出しにつながります。
従業員の不満や業務負荷が高い
「毎日同じ作業で終わってしまう」
「やらなくてもいいことに時間を取られている気がする」
そうした現場の声が聞こえてきたら、改善の余地があるサインです。業務の負担が大きくなるとミスが増えるだけでなく、モチベーションの低下や離職にもつながりかねません。
特に、非効率な作業が慢性的に続いている場合は、本人も気づかないうちに疲労が蓄積しているケースもあります。このような状況では、「どの作業にどれくらい時間がかかっているのか」や「なぜその作業が必要なのか」を確認することが大切です。
従業員の声を丁寧に拾いながら、負担の原因を可視化し、ムダを減らすヒントを見つけましょう。
業務改善で得られる主な効果とメリット
業務改善には手間やエネルギーがかかりますが、その分得られる成果も大きなものです。ここでは、業務改善によって実際にどのようなメリットが起こるのか紹介します。
業務のムダが削減され、生産性が上がる
業務改善を行うと、本当に必要な作業とやらなくてもよい作業が整理され、自然とムダが減っていきます。
例えば、何度も同じデータを入力していたり、メールや口頭で繰り返し確認していた内容が、仕組みの見直しによって不要になるケースもあります。こうしたムダな作業が減ることで本来の業務に使える時間が増え、全体の処理スピードも向上します。
「人が足りない」「時間が足りない」と感じていた業務も、進め方を少し変えるだけで十分に回るようになることはよくあります。
ミスやトラブルが減り、品質が安定する
業務フローを整理して属人化をなくすことで、ミスの発生原因そのものを減らすことができます。また、業務手順や確認方法が明確になれば、「誰が対応しても一定の品質を保てる」状態に近づけることが可能です。
その結果、作業品質が安定し、クレームや手戻りといったトラブルの予防にもつながります。一度整った業務フローは、再発防止という観点でも長く機能しやすく、同じような失敗を繰り返しにくくなるのも大きなメリットです。
こうして業務の品質が高まれば、社内外に対する信頼性も自然と上がっていきます。
担当者の負担軽減と、離職防止にもつながる
人手不足が慢性化する中で、「なんとか回している」状態が続いている現場は多くあります。業務改善を進めて担当者の負担を一部でも軽減できれば、精神的・身体的なゆとりも生まれてきます。
実際に業務を改善した結果、残業が減った、イライラが減った、という声が上がることもあります。無理を重ねた状態が続くと、やがては離職やモチベーションの低下につながりやすく、組織全体のパフォーマンスにも影響を及ぼしかねません。
だからこそ、まずは負担を見える化することが重要です。
業務の標準化が進み、引き継ぎ・教育がラクに
業務改善を通じて業務手順が整理されると、自然と「業務の標準化」も進んでいきます。「標準化」とは、誰が担当しても同じように業務が進められる状態をつくることです。
例えば、業務マニュアルを整備したり、フォーマットを統一したりするだけでも、引き継ぎの負担がぐっと軽くなります。また、新しく入ったスタッフに対しても「この通りに進めればOK」という形があると、教育の手間も最小限で済みます。
属人化していた業務がオープンになり、誰もが状況を把握できるようになることで、チーム全体の安定感も増します。
「特定の人に頼らない仕組みづくり」を目指すうえでも、業務改善は欠かせない取り組みです。
業務改善を成功させる問題点の洗い出し方【5ステップ】
業務に何らかの問題があると気づいたら、次はそれを整理しましょう。ここでは、業務の見える化から真因分析まで、5つのステップで問題点の洗い出し方を解説します。
問題点の洗い出しステップ①:業務全体の「見える化」
まずは現状の棚卸しから始めてみましょう。
業務改善の第一歩は、「そもそも今どんな業務が、どんな流れで行われているのか?」を整理することです。全体像があいまいなままでは、どこにムダや課題が潜んでいるのかも見えてきません。
業務の見える化には、業務分解図や業務フローチャートといった手法が役立ちます。例えば、1つの業務を「誰が」「どんな手順で」「どのくらいの頻度で」行っているのかを図式化するだけでも、全体像がぐっと明確になります。
特定の担当者にしか分からない仕事や、重複している工程がないかなど、隠れていた課題が浮かび上がるきっかけにもなります。
問題点の洗い出しステップ②:現場からのヒアリング・アンケート
図や書類だけでは分からない現場の課題を見つけるには、実際に業務を担当している人の声を聞くことが欠かせません。
かしこまったアンケートである必要はなく、以下のような簡単なもので構いません。
「日々の業務で負担を感じていることはありますか?」
「ムダだと感じる作業はどこですか?」
こうしたシンプルな質問を投げかけるだけでも、具体的な問題点が浮かび上がることがあります。
Googleフォームなどを活用すれば、匿名で気軽に答えてもらえる仕組みをつくることも可能です。大切なのは、形式にこだわるよりも現場の本音をしっかりと引き出すことです。
問題点の洗い出しステップ③:業務時間や件数などの「データ」確認
ヒアリングによって課題感が浮かび上がってきたら、次はそれを裏付ける数値的な根拠を確認します。
例えば以下のようなポイントをチェックしてみましょう。
- どの業務にどれくらい時間がかかっているのか
- 1日/1週間あたりに何件処理しているのか
- 繰り返し発生しているミスやトラブルの頻度
こうした情報をもとに、ボトルネックとなっている工程や、優先的に改善すべきポイントを客観的に見極めることができます。
勤怠管理システムや日報、業務記録など、すでに社内にある情報を活用すれば、大きな負担をかけずに数値を把握できます。
感覚や印象だけで判断するのではなく、「数字」で業務を見てみる視点も取り入れましょう。
問題点の洗い出しステップ④:問題の影響度と優先順位の整理
すべての課題に一気に対応しようとすると、かえって混乱や停滞を招きます。ここでは、改善に着手する順番をしっかり整理することがポイントです。
まずは影響度の高い問題や、改善効果が大きい問題を優先的に取り上げるのが基本です。「どの課題が最も日々の業務に支障をきたしているか」「改善によって他の業務にも良い影響が出そうか」といった観点で整理していきましょう。
タスクの分類には、インパクト×実現性マトリクスなどを活用するのもおすすめです。最初は「すぐに着手できる小さな改善」から進めることで、改善の流れが自然と生まれ、スムーズに定着しやすくなります。
問題点の洗い出しステップ⑤:真因分析(なぜなぜ分析、特性要因図など)
「作業に時間がかかる」や「入力ミスが多い」といった表面的な課題が見えたら、それが“なぜ起きているのか”を掘り下げていく必要があります。
このステップでは、なぜなぜ分析(5Why)や特性要因図(フィッシュボーンチャート)などの手法が役立ちます。
例えば、「入力ミスが多い」→「確認の時間が足りない」→「繁忙期に業務が集中する」→「タスクの割り振りが偏っている」といったように、段階的に根本原因を探っていきます。
ここで原因を取り違えると対症療法で終わってしまうこともあるため、焦らず丁寧に掘り下げることが大切です。本当の原因にたどり着ければ、改善策の効果も高まり、再発防止にもつながります。
問題点の洗い出しに使えるおすすめツール
業務の流れを整理したり、現場の声を拾ったり、それぞれの場面で適したツールを活用することで、精度もスピードも格段に上がります。
ここでは、「業務を見える化したい」「データで裏付けを取りたい」「現場の本音を集めたい」といったニーズに応える、実務で役立つ具体的なツールを紹介します。
「何を使えば効率的か?」と迷っている方は参考にしてください。
業務の流れとムダを可視化するならmayclassの業務分解図
業務分解図は、業務を構成するタスクを細かく洗い出し、それぞれがどのような流れで行われているかを一枚の図で整理するツールです。「Aさんが月初に行う作業」「Bさんがチェックする処理」などを具体的に書き出すことで、全体の流れ・重複・属人化の有無が見えてきます。
特に、複数人でひとつの業務を回している場合には、「誰がどこまで担当しているか」があいまいになりがちです。業務分解図を活用すれば、そうしたあいまいさが明らかになり、見直すべきポイントの発見につながります。
mayclassが配布しているテンプレートを使えば、エクセル上で簡単に図を作成できるため、現場でのヒアリングにも役立ちます。

現場の声を拾うなら|Googleフォーム や kintone
業務改善を進めるうえで欠かせないのが、「現場のリアルな声」を集めることです。そのための手段として、Googleフォームやkintoneといったツールが便利です。
Googleフォームは、無料かつ手軽にアンケートを作成・配布でき、回答の自動集計も可能です。現場の忙しいスタッフにとっても、スマホから短時間で回答できるのは大きなメリットといえるでしょう。
kintoneは、より業務に特化したデータベース型の仕組みを作ることができ、タスクごとの進捗管理やコメントの蓄積にも適しています。「不満に思っていること」「負担を感じている作業」「もっとこうしたい」という声を吸い上げることで、現場に即した改善ポイントが見えてきます。
業務データの可視化・分析をするなら|Looker Studio などのBIツール
業務効率化において重要なのは、データを基にした問題点の洗い出しです。
「どの業務に、どれだけ時間やコストがかかっているか」
「月ごとに業務量がどう変化しているか」
こうした分析を行うには、BIツール(ビジネスインテリジェンスツール)が役立ちます。
GoogleのLooker Studio(旧:データポータル)は、スプレッドシートなどのデータを読み込み、グラフやチャートに自動変換してくれる無料ツールです。時間の推移や傾向を視覚的に捉えやすくなるため、感覚では気づかなかった業務負荷の偏りやムラが見えてくることもあります。
既存の業務記録や日報などの数値データを使って分析したいときは、Excelのピボットテーブルと組み合わせて使うのもおすすめです。
原因を深掘りするなら|なぜなぜ分析テンプレート
問題が起きたとき、「なぜそれが起きたのか?」を掘り下げて考えるのが「なぜなぜ分析」です。ただ口頭やメモだけで進めると、原因があいまいになったり、議論がズレてしまうこともあります。
そこで役立つのが、なぜなぜ分析のテンプレートです。
「主な事象→なぜ①→なぜ②→…」と段階的に原因をたどっていく構成になっており、思考の流れを整理しやすくなります。チームで話し合いながら進める場合にも、視点がずれにくく、全員の認識をそろえるのに便利です。
手書きでもExcelでも構いませんが、最初のうちはフォーマットを活用するとスムーズに進められます。
問題点の洗い出し後、業務改善につなげる3つのポイント
問題点を洗い出すだけでは、業務改善は進みません。ここでは、実際に改善策を検討・実行していく際に押さえておきたい3つの重要ポイントを解説します。
改善アイデアを出す際のコツ(現場との対話・巻き込み)
問題点を洗い出したあとは、「どう改善するか」を考えましょう。 このとき、上からの指示だけで進めると、現場に負担感や抵抗が生まれやすくなります。現場で実際に業務を担っているメンバーが「納得感」を持てることが、改善がうまくいくかどうかの分かれ目です。
例えば、アイデアを募るブレストの場を設けたり、「こんなやり方もあるのでは?」と問いかけるような形で話を広げていくと、自然と現場の声を引き出せます。「こうすればいいはず」と決めつけず、現場の知恵や工夫を活かしながら、少しずつ解決策を育てていく姿勢が大切です。
「業務改善は現場と一緒につくるもの」という意識を持つだけで、チーム内の雰囲気ががらりと変わることもあります。
すぐに全部解決しようとしない。優先度をつけて段階的に
課題がいくつも見つかると、「一気にすべて解決しなければ」と焦ってしまうかもしれません。 しかし、同時に手をつけると現場の負荷も増え、結果としてどれもうまく進まない…という事態になりがちです。
そこで重要なのが、「優先順位を決めて、順番に取り組む」という考え方です。
例えば、「業務への影響が大きいかどうか」「すぐに着手できるか」といった基準で整理し、まずは「成果が出やすいもの」から着手すると、現場でも手応えを感じやすくなります。
小さな改善でも「効果が出た」という実感が得られると、チーム全体のモチベーションが高まり、次の改善にも取り組みやすくなります。進めるときは段階的に行いましょ行いましょう。
改善案の効果測定も忘れずに(KPIの設定)
改善を実行したら、それが「本当に効果があったのか」を振り返ることが大切です。やりっぱなしになってしまうと、改善が定着せず、また元に戻ってしまうリスクがあります。
効果を測るには、あらかじKPI(重要業績評価指標)を設定しておくのが有効です。
例えば、「作業時間が◯%短縮された」「ミスが月△件から×件に減った」といったように、数字で確認できる指標を決めておくと、改善の成果を明確に把握できます。目標を明確にすると関係者と成果を共有しやすくなるだけでなく、次の改善ポイントを見つけるヒントにもなります。
一度きりの改善で終わらせず、継続的な改善サイクルにしていくためにも、効果測定の仕組みを取り入れておきましょう。
問題点の洗い出しこそ、業務改善のスタートライン
「業務改善」と聞くと、「何か特別な取り組みをしなければならない」と構えてしまう人も少なくありません。しかし、実際のスタートはもっとシンプルで、「今の業務の中に、どんなムダや困りごとがあるのか」をはっきりさせることから始まります。
本記事で紹介したように、業務の流れを図にまとめたり、現場の声を聞いたり、数字を確認したりするだけでも、これまで気づかなかった問題が浮き彫りになることがあります。
こうして課題を見える化し、業務改善に向けた第一歩を踏み出しましょう。
ーーー
How to Achieve Results Through Business Improvement: 5-Step Problem Analysis Guide with Tools

業務改善・業務効率化の原則と目標を徹底解説!4原則・3要素・8原則を一挙紹介