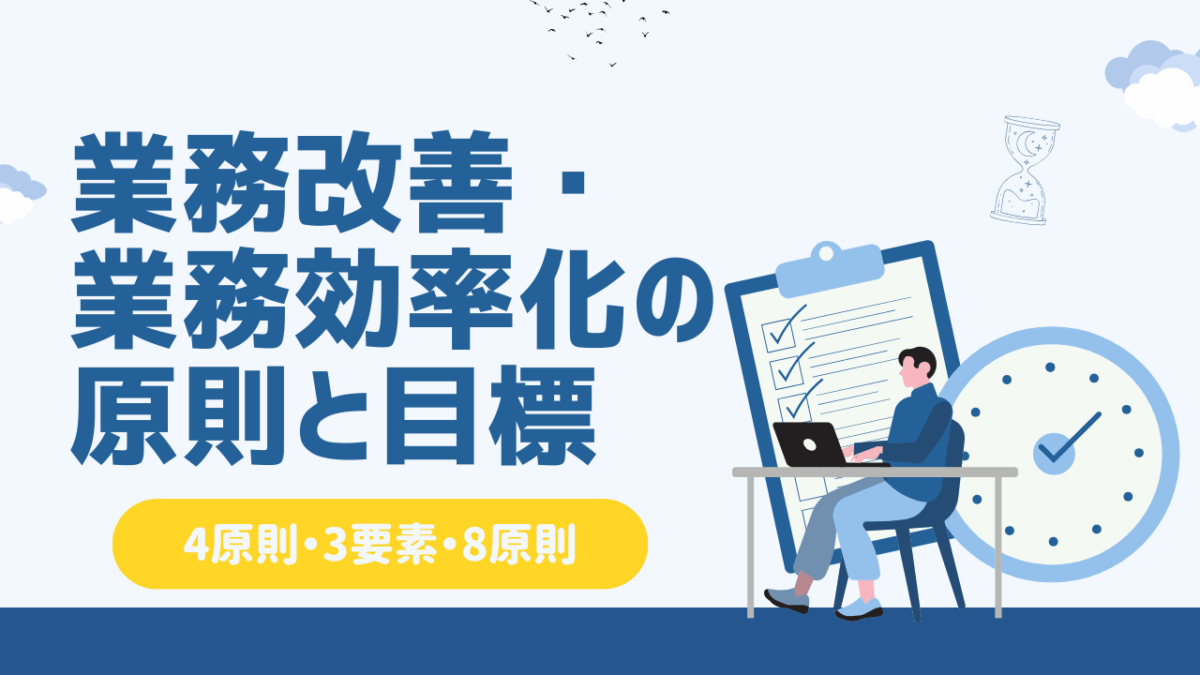近年、日本企業を取り巻くビジネス環境は、かつてないスピードで変化しています。少子高齢化による深刻な人手不足、グローバル市場での競争激化、さらには「働き方改革」やDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進など、企業は日々新たな課題に直面しています。こうした背景のもと、業務改善と業務効率化は単なる時短やコスト削減にとどまらず、企業の成長と存続に不可欠な取り組みとなっています。
業務改善は、現状の業務フローや手順を見直し、課題を解消するためのアプローチです。一方、業務効率化は、限られた時間や人員で最大の成果を出すために、業務の無駄を削減し、生産性を高めることを目的としています。この2つは密接に関連しており、同時に進めることで相乗効果を発揮します。
しかし、やみくもに改善施策を打ち出しても、思うような成果は得られません。重要なのは、明確な原則と具体的な目標を持ち、計画的に取り組むことです。業務改善の4原則、業務改善を支える3要素、そして業務効率化の8原則といった指針を理解すれば、改善の方向性が明確になり、現場レベルから経営層まで一貫した行動が可能になります。
本記事では、企業の競争力を高めるための業務改善と業務効率化の基本フレームワークを整理し、4原則・3要素・8原則を一挙に紹介します。さらに、効果的な目標設定の方法や、改善を持続させるためのポイントについても解説します。
参考:業務改善とは?意味・手法・成功のポイントをわかりやすく解説
本記事は、変化の激しいビジネス環境で企業が持続的に成長するために必要な「業務改善」と「業務効率化」の基本フレームワークを整理したものです。ECRS(排除・結合・入替・簡素化)、人×プロセス×ツールの3要素、効率化8原則など、改善の指針となる考え方を体系的に解説。明確な原則と目標を持って取り組むことで、生産性向上と働きやすさを両立できることを示しています。
業務改善4原則(ECRS)とは
業務改善を成功に導くためには、単なる思いつきや一時的な対応ではなく、方向性を示す明確な指針が欠かせません。その役割を果たすのが、ECRSです。これは、業務効率化を実現するためのシンプルかつ汎用性の高いフレームワークであり、業種や企業規模を問わず活用できます。
ECRSは次の4つの原則で構成されています。
業務改善4原則①:ECRS①:Eliminate(排除)
業務の中に潜んでいる不要な工程やムダな作業を徹底的に取り除きます。これにより、生産性の向上や業務効率化が大きく進みます。
- 例:同じデータを複数システムに二重入力する手間をなくす
- 例:承認フローを簡略化して、無駄な待ち時間を削減する
「やらなくてもよい業務」を明確にすることが、改善の第一歩となります。
業務改善4原則②:Combine(結合)
複数の業務や作業工程をまとめて効率化します。結合によって重複をなくし、シンプルな業務フローを実現できます。
- 例:複数部署で個別に作成していた報告書を共通フォーマットに統合
- 例:会議での進捗報告と週次レポート提出を一体化
マニュアルにおいても、複数の手順書を一つにまとめることで、現場での使いやすさが向上します。
マニュアル作成については、【保存版】マニュアル作成のコツと手順を徹底解説!初心者でもわかる実践ガイドをご覧ください!
業務改善4原則③:Rearrange(入替)
作業の流れや順序を見直し、より効率的な配置に変えることを意味します。
- 例:顧客対応で、FAQやマニュアルを先に提示 → 問い合わせ件数を削減
- 例:倉庫作業でピッキングの順番を変更し、動線を短縮
「作業の順序や担当の入替」によって、無駄な時間や移動を削減し、全体効率を改善できます。
業務改善4原則④:Simplify(簡素化)
業務をシンプルにし、誰でもすぐ理解・実行できる状態を目指します。
- 例:複雑な申請書類を一画面の入力フォームにする
- 例:文章だけのマニュアルを図解やフローチャートで簡潔に表現する
簡素化によって、属人化を防ぎ、新人でも短期間で業務を習得できるようになります。
ECRSの特徴と効果
ECRSの4つの原則は、単独で使うのではなく、相互に組み合わせることで大きな成果を生み出します。例えば、不要な作業を排除(Eliminate)したうえで、残った工程を結合(Combine)し、流れを入替(Rearrange)て、さらに簡素化(Simplify)することで、業務全体が効率的かつ標準化されたものになります。
特にマニュアル管理と組み合わせると、改善内容が現場に定着しやすくなり、属人化を防ぎながら継続的な改善サイクルを回すことが可能です。
企業が業務改善や業務効率化を長期的に実現するためには、このECRSの4原則をバランスよく取り入れ、日常業務に組み込むことが不可欠です。
業務改善4原則の詳細は、業務改善4原則(ECRS)とは?現場で活かせる実践ステップを徹底解説をご覧ください。
業務改善3要素とは
業務改善や業務効率化の取り組みを成功させるためには、複数の視点から課題を捉えることが欠かせません。その中でも特に重要なのが、人・プロセス・ツールという3つの要素です。この3要素がバランス良く機能することで、改善効果は飛躍的に高まります。
業務改善3要素①:人(スキル・モチベーション)
業務改善を実際に進めるのは現場の人です。どれほど優れた仕組みやツールを導入しても、使いこなすスキルや改善意欲がなければ成果は上がりません。研修やOJTによるスキル向上、適切な評価制度や表彰制度によるモチベーション維持が不可欠です。また、改善活動への参加を促すことで、現場からのアイデアが自然と集まる環境をつくることができます。
業務改善3要素②:プロセス(業務フロー・手順)
改善の対象そのものとなるのが業務プロセスです。業務の流れや手順を可視化し、どこに無駄や非効率が潜んでいるのかを明確にすることが第一歩です。フローチャートや業務分解図を活用して現状を把握すれば、業務効率化に向けた改善ポイントを具体的に示すことができます。また、プロセスの見直しは一度きりではなく、定期的な更新が必要です。
業務改善3要素③:ツール(IT・機器・システム)
業務効率化を加速させるための支援手段がツールです。RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)やクラウドサービス、業務管理システムなどを活用すれば、定型業務の自動化や情報共有の迅速化が可能になります。ただし、ツールの導入だけでは不十分で、人材の教育やプロセス改善と組み合わせることが重要です。
この3つの要素は、どれか一つが欠けても十分な効果は得られません。例えば、新しいツールを導入しても、使う人の理解やスキルが不足していれば、業務改善にはつながらないでしょう。逆に、ツールと人材育成、プロセス見直しを同時に行えば、業務効率化は大きく前進します。企業が継続的に成果を出すためには、この3要素を総合的に強化し、相互に連動させることが鍵となります。
業務改善3要素の役割や改善を加速させる方法については、業務改善3要素とは?業務効率化を加速させる人・プロセス・ツールの活用法で解説しています。
業務効率化8原則とは

業務効率化を進める際に役立つのが「業務効率化8原則」です。これは、業務プロセスを見直すときの基本的な視点を8つに整理したもので、ムダを排除し、生産性を高めるための指針となります。単独で活用しても効果がありますが、複数の原則を組み合わせることで、より大きな改善効果が期待できます。
業務効率化8原則①:廃止
不要な業務や工程を思い切って取り除きます。「やらなくても成果に影響がない作業」を見極め、完全に無くすことで、無駄な時間やコストを削減できます。
業務効率化8原則②:削減
完全に廃止はできなくても、回数・量・頻度を減らす工夫を行います。たとえば会議時間を短縮したり、報告書の提出回数を減らしたりすることで、業務負担を軽減できます。
業務効率化8原則③:統合
似たような作業や重複している工程をまとめ、一元化します。複数部署で別々に管理している資料を統合すれば、情報共有のスピードが格段に上がります。
業務効率化8原則④:簡素化
複雑な手順や承認フローをできるだけシンプルにします。工程を少なくすることで作業時間を短縮できるだけでなく、ミスの防止にもつながります。
業務効率化8原則⑤:標準化
作業方法や手順を統一し、属人化を防ぎます。標準化された業務は再現性が高く、品質も安定。新人教育や引き継ぎもスムーズに行えます。
業務効率化8原則⑥:分離
業務の流れを細かく見直し、役割や機能を分けることで効率化を図ります。たとえば「計画」「実行」「確認」を分離することで、それぞれの責任範囲が明確になり、作業がスムーズに進みます。
業務効率化8原則⑦:順序入替え
作業の並び順や工程の順序を見直し、より効率的な流れに変えます。前後の順番を変えるだけで、待ち時間や移動時間を減らせるケースがあります。
業務効率化8原則⑧:IT活用・自動化
最後に、人が行っている作業をシステムやツールで自動化します。RPAやマクロ、業務管理システムを導入することで、ヒューマンエラーを防ぎつつ業務のスピードを大幅に向上させられます。
これら8つの原則は互いに関連しており、組み合わせて活用することで最大の効果を発揮します。例えば「廃止」と「標準化」を同時に進めれば、不要な作業をなくしたうえで残った業務の品質を一定に保つことができます。企業が長期的に成長するためには、この8原則を業務改善の指針として定着させ、継続的に運用していくことが重要です。
業務効率化8原則の全体像や実践方法は、業務効率化8原則完全ガイド!無駄をなくし生産性を高める具体的手法をチェックしてください。
業務効率化の目標設定の重要性
業務改善や業務効率化の原則や方法が分かっても、最終的な成果は「目標設定」の質によって大きく左右されます。どれだけ優れた施策を計画しても、目標が曖昧であれば方向性がぶれ、効果測定もできません。明確で測定可能な目標を設定することが、改善活動を確実に前進させる鍵となります。
特に有効なのが、KGI(重要目標達成指標)とKPI(重要業績評価指標)を組み合わせる方法です。KGIは最終的に達成すべきゴール、KPIはその進捗を測る中間指標です。例えば、次のように設定します。
- KGI:顧客対応にかかる時間を30%削減する
- KPI:問い合わせ初期対応までの平均時間を2時間以内に短縮する
このように具体的な数値を設定することで、業務改善や業務効率化の成果が明確になります。
さらに、目標設定にはSMART法を活用すると効果的です。これは、目標を次の5つの観点で設計するフレームワークです。
- Specific(具体的であること)
- Measurable(測定可能であること)
- Achievable(達成可能であること)
- Relevant(関連性があること)
- Time-bound(期限が設定されていること)
例えば、「問い合わせ対応の質を高める」という漠然とした目標ではなく、「3か月以内に問い合わせ対応の平均時間を3時間から2時間に短縮する」という形にすれば、達成状況を客観的に評価できます。
業務改善や業務効率化の取り組みは、設定した目標によって進むべき道筋が決まります。現場での施策を積み重ねるだけではなく、数値や期限を伴う明確なゴールを持つことで、組織全体が同じ方向を向いて動けるようになります。企業が成果を最大化するためには、まず目標設定の質を高めることが不可欠です。
業務効率化の目標設定や指標例については、業務効率化の目標設定完全ガイド!SMART法・KPI/KGI・指標例まで徹底解説に詳しくまとめています。
業務改善と業務効率化を成功に導くための進め方
業務改善と業務効率化は、単発の取り組みで終わらせるのではなく、組織文化として定着させることが重要です。これまで紹介してきた4原則は改善の方向性を示し、3要素は改善活動を支える基盤、8原則は現場で実行するための具体的な手段となります。そして、目標設定はそれらを行動に移し、成果を測定するための羅針盤です。
実践に移す際は、まず自社の現状を客観的に分析しましょう。業務フローの可視化やヒアリングを通じて、どこに非効率や無駄があるのかを洗い出します。その上で、どの原則や要素を優先的に取り入れるべきかを判断し、小さな改善から着手して徐々に範囲を広げていくことが効果的です。
また、業務改善や業務効率化は一度成功しても、時間の経過や市場環境の変化によって再び課題が発生します。そのため、定期的な振り返りや改善提案制度を活用し、継続的に取り組む体制を整えることが不可欠です。経営層だけでなく、現場スタッフ全員が参加しやすい仕組みを作ることで、改善活動は長期的に続きます。
今から始められる第一歩として、自社の業務を細分化して見える化することをおすすめします。業務分解図などのツールを使えば、現状把握から改善策の立案までスムーズに進められます。効率化のための課題が明確になれば、最適な施策も見えやすくなります。
業務改善と業務効率化は、正しい方向性と明確な目標、そして継続的な取り組みがあってこそ効果を発揮します。自社に合った改善サイクルを確立し、組織全体の成長につなげていきましょう。
業務改善や効率化は、正しい原則と目標設定があってこそ効果を発揮します。自社の業務を客観的に見える化し、改善ポイントを明確にするなら「業務分解図 」がおすすめです。
現状分析から改善提案までサポートしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

ーーー
Principles and Goals of Business Improvement and Work Efficiency: 4, 3, and 8 Key Principles Explained
▼こちらの記事もおすすめ▼
業務効率化は“数値化”から始まる!成果を見える化する方法と実践ステップ
【図解でわかる】生産性向上と業務効率化の違いとは?意味・目的・施策を徹底比較!
【保存版】営業資料の作り方を徹底解説!成果につながる構成・デザイン・伝え方のコツとは?