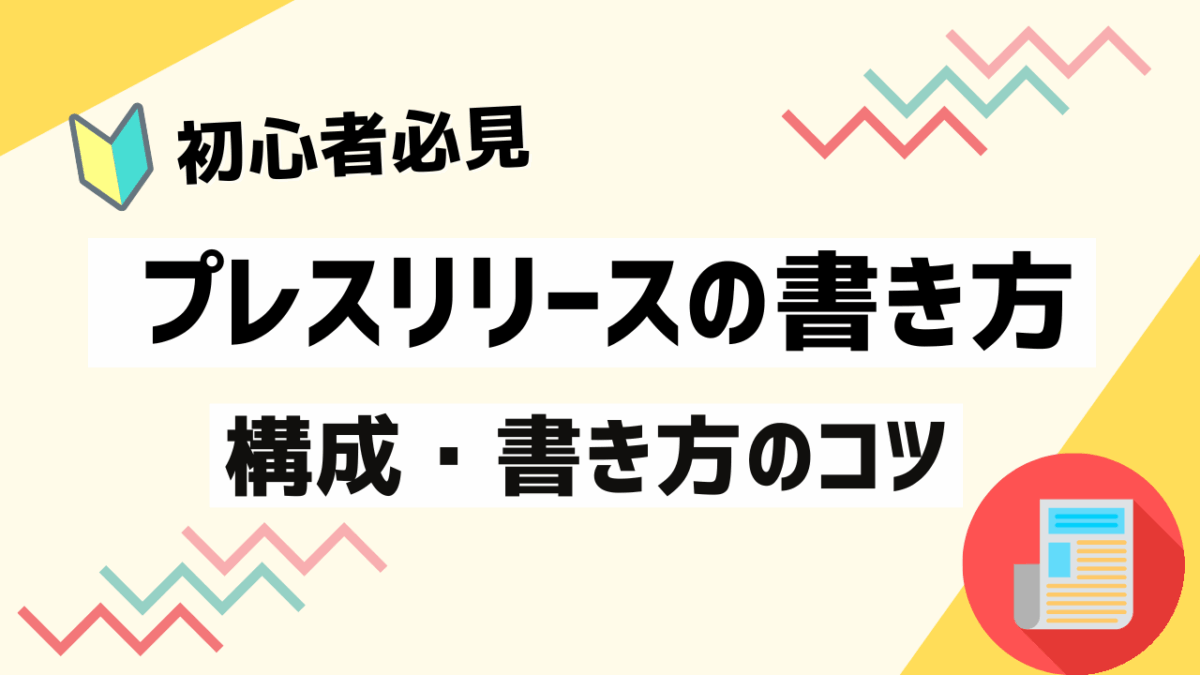プレスリリースは単なる情報発信ではなく、企業の「想い」や「意図」を世の中に正しく届け、共感や信頼を生むための重要な広報手段。だからこそ、書き方ひとつで伝わり方が大きく変わります。しかし、何を書けばいいのか、どんな構成が正解なのか。初めての作成では、誰もが迷うものです。
本記事では、プレスリリースの役割や基本構成、初心者でも失敗しない書き方のコツを丁寧に解説します。
プレスリリースの基本構成(タイトル・リード文・本文・会社概要)と、読み手に伝わる書き方のコツをわかりやすく解説した記事です。ニュース性の出し方、NG例、改善ポイントも整理されており、初心者でも「伝わるリリース」を作れる実践的な内容になっています。
プレスリリースとは?目的と役割を知ろう
「プレスリリース(ニュースリリース)」とは、企業や団体が新しい製品・サービスの発表、イベント開催、組織の動きなどの情報を、報道関係者に向けて公式に発信する文章です。新聞やテレビ、ウェブメディアなどに掲載されることで、より多くの人に情報を届けられるという特徴があります。
広報活動の“起点”となる文書
プレスリリースは、いわば「企業からのニュースレター」。
広告のようにお金を払って掲載してもらうのではなく、“報道に値する情報”として、メディアに取り上げてもらうことを目的としています。
つまり、広告よりも信頼度が高く、第三者の言葉として広がるため、ブランド認知や信頼構築、問い合わせの増加などにもつながるのが特徴です。
なぜ今、プレスリリースが重要なのか?
SNSの普及や情報発信の多様化により、ユーザーが情報を選ぶ時代になりました。そんな中で、企業が「自分の言葉」で正しく情報を発信する手段として、プレスリリースは再注目されています。
特にスタートアップや中小企業にとっては、「知ってもらう第一歩」としての意味合いも強く、うまく活用すれば無料でメディアに掲載されるチャンスもあるのです。
広報と広告の違いは?
| 項目 | 広報(プレスリリース) | 広告 |
| 費用 | 基本的に無料(自社で作成し配信) | 掲載に費用がかかる |
| 情報の信頼性 | 第三者の視点で紹介されるため高い | 企業発信のため低め |
| 目的 | 認知拡大・信頼構築 | 商品の販売・申込の促進 |
| 発信方法 | メディアに情報提供し、取り上げてもらう | 掲載枠を購入して直接発信 |
こうした違いを理解しておくことで、「なぜこの情報をプレスリリースとして出すのか」という意図も明確になります。
プレスリリースの基本構成と書き方

プレスリリースは「型」がある程度決まっている文書です。
初めて書く人はこの型に沿って、必要な情報を一つずつ埋めていくことで、一定の完成度のものが作れます。以下に、代表的な6つの構成要素と、それぞれの書き方・例文を紹介します。
プレスリリースのタイトル
最も重要なパートであり、記者が読むかどうかを判断する「入り口」です。30〜40文字程度を目安に、何が起きたのかを端的に伝えます。誰にとって、どんな意味があるニュースなのかを明確にしましょう。
【悪い例】
「新サービスを始めました」→これだけでは、何のサービスか、誰に向けたものか分かりません
【良い例】
「高齢者向け冷凍弁当サービス『まごころ便』が全国配送を開始」→具体的に記載することで、サービス内容と新しい動きがすぐ分かります。
リード文(冒頭の要約)
冒頭2〜3行で、記者が概要を把握できるようにします。「誰が」「いつ」「どこで」「何を」「なぜ」「どのように」という5W1Hの要素を簡潔に盛り込みます。
【例文】
株式会社〇〇(本社:東京都、代表取締役:田中一郎)は、2025年5月1日より、高齢者向け冷凍弁当サービス『まごころ便』の全国配送を開始しました。本サービスは管理栄養士が監修し、手軽に栄養バランスの取れた食事をとれることが特徴です。
プレスリリース本文(詳細説明)
リード文で伝えた内容をより詳しく説明するパートです。以下のような構成で書くと読みやすくなります。
背景と課題
なぜこのサービス・取り組みが必要とされているのかを明確に伝えるパートです。
・業界の現状や社会的な動き、顧客からの要望など、「なぜ今なのか」「なぜ必要なのか」を示します。
・読者(メディアや顧客)が関心を持つ“問題意識”を共有することで、共感を得やすくなります。
・例:「○○業界では人手不足が深刻化しています。特に中小企業では〜」
発表の内容
今回発表する商品・サービス・イベントなどの具体的な内容を説明します。
・新サービスの概要や、開始日、提供エリア、対象者などの事実ベースの情報を簡潔に書きます。
・できるだけ数字や固有名詞を使い、誰が読んでもイメージしやすい表現を心がけましょう。
・例:「2025年6月1日より、東京都内の全店舗で〜」
特徴や利点
同種のサービスや競合との違いを示し、自社の優位性や魅力を伝えます。
・他社にはない独自の機能やこだわり、開発背景などを入れると説得力が増します。
・実際に使ったユーザーの声(簡単なコメントや感想)を入れるとリアリティが出ます。
・例:「ユーザーの約85%が“使いやすい”と回答」など
データやコメント
信頼性や客観性を高めるための材料です。
・数値データ(アンケート結果・導入実績・市場規模など)を使うと説得力が増します。
・社内のキーパーソンや代表者、外部有識者などのコメント(30~100字程度)も効果的です。
・例:「私たちが目指したのは、誰もが簡単に使えるサービスです(代表取締役 ○○)」
会社概要(情報提供元)
どんな企業が情報を発信しているのかを簡潔にまとめるパートです。会社の信頼性を担保する意味でも、設立年や所在地、事業内容などは明記しましょう。
【例:会社概要】
会社名:株式会社〇〇
所在地:東京都新宿区〇〇丁目〇〇番地
代表者:代表取締役 田中一郎
設立:2010年4月
事業内容:高齢者向け食品の開発・販売
公式サイト:https://example.co.jp
お問い合わせ先
記者が取材や質問をしたい場合に備えた連絡先です。電話番号やメールアドレスは、すぐに連絡が取れるものを記載します。
【例:お問い合わせ先】
株式会社〇〇 広報担当:佐藤美咲
電話:03-1234-5678
メール:pr@example.co.jp
参考資料・画像・動画(あれば)
可能であれば、商品写真、図表、ロゴ、動画リンク、PDF資料などを添付します。
素材があることで、記者が記事化しやすくなり、掲載される確率が上がります。
【資料例】
- 商品の正面写真
- 利用シーンを写した画像
- イベントチラシ(PDF)
書き出しに悩んだら「テンプレート」を活用しよう
初めてプレスリリースを書くと、「どこから手をつけていいかわからない」「書き方が合っているか不安」という声がよく聞かれます。ですが、最初からうまく書けなくても問題ありません。多くの人が、最初は型をなぞりながら感覚を掴んでいきます。
大切なのは、「何となく」で書き始めるのではなく、構成の型に沿って、要点を一つずつ整理することです。プレスリリースのフォーマットはある程度決まっており、それに基づいたテンプレートを活用すれば、必要な情報を漏らさずに書くことができます。
テンプレートをどう活用すれば良いか
テンプレートは「丸写しするもの」ではなく、「文章の流れや要素を参考にし、自社情報に置き換えていくための土台」です。
一度でも書いた経験があれば、次回以降は修正・改善しながらレベルアップができます。
また、企業の広報ページや、プレスリリース配信サービス(PR TIMES、共同通信PRワイヤーなど)に掲載されている他社のリリース事例も、大いに参考になります。最初は「構成や書き方の模倣」から始めるのが、最短の学習方法です。
プレスリリースのよくある失敗と改善ポイント
プレスリリースは「正しく伝えるための文章」です。しかし、初めて書く場合、思わぬところで読みにくくなったり、記者にとって扱いにくい内容になってしまうことがあります。
ここでは、よくある失敗例と、その改善方法について紹介します。
プレスリリース失敗例①:タイトルに要点が書かれていない
【失敗例】
「新サービスをリリースしました」
何のサービスかが伝わらず、読者の関心を引けません。
【改善ポイント】
具体的な「何を」「誰に向けて」「どんな新しさがあるか」を盛り込みましょう。
【改善例】
「飲食店向け発注管理アプリ『OrderMate』、無料プランを新たに開始」
プレスリリース失敗例②:ニュース性が伝わらない
【失敗例】
「革新的で圧倒的に便利な、史上最高のサービスが登場!」
【改善ポイント】
主観的な表現を避け、事実を簡潔に書くことが信頼につながります。
記者が記事にしやすいよう、情報の根拠を明記しましょう。
【改善例】
「スマートフォン対応の電子契約サービス、利用企業数が1,000社を突破」
プレスリリース失敗例③:書きたいことを詰め込みすぎ
【失敗例】
・話題が散漫で、主題が分からない
・1文が長く、何を伝えたいのか分かりづらい
【改善ポイント】
1つのリリースには1つの主題に絞りましょう。複数のトピックがある場合は別のリリースに分けることも検討してください。また、1文は60〜80文字程度を目安に区切りましょう。
プレスリリース失敗例④:読み手(メディア側)の視点が抜けている
【失敗例】
・自社目線の説明に終始している
・業界の外部からは理解しづらい専門用語が多い
【改善ポイント】
広報の文章は、「初めてその情報を見る第三者」に向けて書く必要があります。業界の外の人が読んでも理解できるかどうかを意識しましょう。わかりづらい言葉には補足説明を加えましょう。
プレスリリース失敗例⑤:基本情報が抜けている
【失敗例】
・会社情報や担当者連絡先の記載がない
・リリース日やサービス開始日が明記されていない
【改善ポイント】
プレスリリースは、記者がそのまま記事に使えることが理想です。誰が出した情報か、問い合わせ先はどこか、いつの出来事なのか、といった基本要素は必ず記載しましょう。
書いたあとは必ず「読み返し」
プレスリリースは提出して終わりではありません。
一度書いたら「誰が読んでも内容が理解できるか」を意識して見直しましょう。できれば第三者(社内の別の人など)に読んでもらい、文章のわかりにくさや情報の漏れがないかチェックを受けるのが理想的です。
初めてのプレスリリース作成で悩んだら?外注という選択肢も
プレスリリースには「構成」「文章力」「ニュース性の判断」など、慣れていないと難しく感じる要素が多くあります。
実際、初めて取り組んでみて「時間がかかる」「自信がない」「社内で確認に手間取る」といった悩みを抱える人も少なくありません。そんなときは、外部の専門家に依頼する=外注という選択肢も検討に値します。
こんなときは外注を検討してみましょう
以下のような状況に当てはまる場合、無理に自社で完結させるよりも、外注した方が効果的です。
- そもそもどんな内容をリリースすべきか分からない
- 書いた原稿に自信が持てない
- 社内に広報の専門知識を持つ人がいない
- 社長や上司の確認に時間がかかり、締切に間に合わない
- 本業が忙しく、リリース作成に手が回らない
プレスリリース作成を外注するメリット
- 短時間でプロ品質の文章が手に入る
構成や表現に迷う時間がなくなり、スピーディーに完成度の高いリリースが作れます。 - ニュース性の判断や情報の整理を任せられる
客観的な視点で「何が伝えるべき情報か」を整理してもらえるため、伝わる内容に仕上がります。 - 記者が求めるフォーマットに仕上げてもらえる
記事にしやすいリリースは、採用される可能性も高まります。
プレスリリース作成を外注するデメリット
- 自社の情報をうまく伝えきれないと、意図と異なる文章になる可能性がある
- 社外の人に内容を共有する準備(ヒアリングや資料提供)が必要になる
- 外注費用が発生する(1本数万円〜が相場)
外注を検討する場合は、過去の実績や、どのように情報を引き出してくれるか(ヒアリング力)を確認することが大切です。
外注と内製を使い分ける考え方
すべてを外注に頼る必要はありません。
例えば、重要な発表や記者会見に関わるリリースは外注し、定期的なお知らせは自社で対応するといった、目的に応じた使い分けも有効です。
「手を抜けない場面でプロの力を借りる」という発想で、外注を前向きな選択肢として検討してみてください。
プレスリリースを作成しよう
プレスリリースは、企業やサービスの価値を社会に伝えるための重要な手段です。しかし、初めて作成する場合には「書き方がわからない」「ニュース性の判断がつかない」といった壁に直面しやすいのも事実です。そのようなときは、まずは「基本の構成」に沿って、必要な情報を一つずつ整理することから始めてみてください。構成要素が明確になっていれば、文章力に自信がなくても伝わるリリースをつくることは可能です。
それでも難しさを感じたり、重要な発信で失敗したくないと感じたら、外注という選択肢を検討するのも良いでしょう。プロに任せることで、短時間で質の高い成果物を手に入れることができ、社内のリソースを本業に集中させることもできます。
プレスリリースは、一度出して終わりではなく、継続して情報を届けていく活動でもあります。まずは1本書いてみる。そして、改善していく。その繰り返しが、広報力の底上げにつながります。無理せず、必要に応じて外部の力も活用しながら、自社の「伝える力」を少しずつ磨いていきましょう。
ーーー
How to Write a Press Release: Structure, Writing Tips, and Examples
プレスリリース作成ならmayclassにお任せ
mayclassでは、新商品・新サービスの発表、イベント告知、企業の取り組みなど、目的に応じた構成と訴求ポイントを整理し、報道関係者・メディアに届く文章を設計。
読み手の目線を意識した「見出し・リード・本文」構成で、ニュースとして取り上げられやすい内容に仕上げます。
「何を」「誰に」「どう伝えるべきか」が明確になるから、初めての広報でも安心。ご要望に応じて、配信メディアの選定やPR戦略のご相談にも対応可能です。

▼下記記事もおすすめ▼