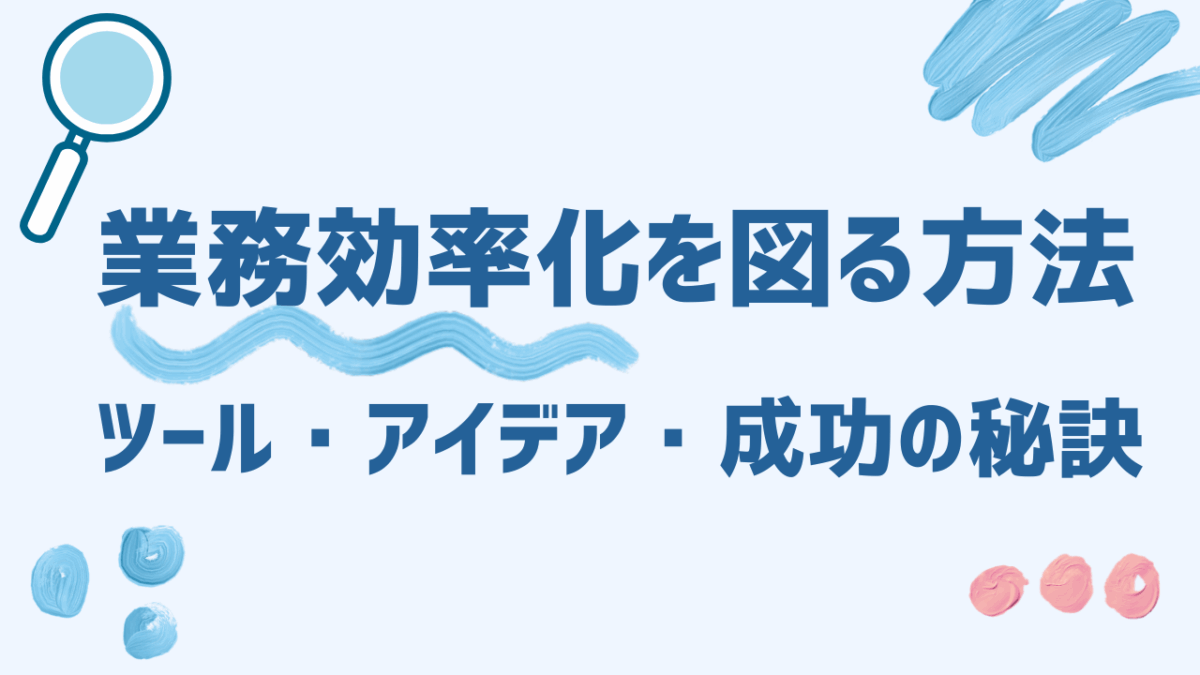少子高齢化による人手不足、働き方改革の推進、そしてデジタル技術(DX)の急速な発展で、企業や個人が取り組むべき課題として「業務効率化」がこれまで以上に注目されています。では、業務効率化を図るには、具体的にどのような方法やツールを使えばよいのでしょうか?
本記事では、業務効率化の背景や必要性をはじめ、基本的な考え方や進め方、すぐに取り入れられるアイデア・ツールまでを徹底解説します。さらに、属人化・ムダ・重複作業といった「見えにくい非効率」を構造的に改善する「業務分解図」の活用方法もご紹介します。明日からすぐ実践できるノウハウを知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
人口減少・DX推進により、業務効率化があらゆる企業で急務となっている背景を解説する記事。人手不足、生産性向上、時間創出の重要性を示し、非効率業務の洗い出し方、改善ステップ、すぐ使える10の効率化アイデア、ツール活用、落とし穴、業務分解図の有用性まで、実践的にまとめたガイドです。
なぜ今「業務効率化」が求められているのか
業務効率化は、もはや一部の先進企業だけが取り組むものではありません。人口減少やデジタル技術の進化といった社会的背景から、中小企業を含むあらゆる業種・業態で急務となっています。ここでは、今「業務効率化」が求められる3つの大きな理由を解説します。
人手不足・働き方改革・DXの波
日本は深刻な労働人口の減少に直面しています。若年層の減少や高齢化の進行により、企業が確保できる人材は年々限られてきており、「少ない人員でどう成果を上げるか」が経営の重要課題となっています。
さらに、政府主導で進められている働き方改革では、長時間労働の是正や多様な働き方の実現が求められており、従来のやり方を見直さざるを得ません。加えて、デジタル技術を活用した業務変革(DX)の流れも加速しています。紙や対面を前提とした業務は見直され、クラウドやAIを使ったスマートな働き方への移行が進んでいます。
このような環境の中で、業務効率化は「コスト削減」や「時短」だけでなく、企業の持続的成長や競争力維持のための前提条件になりつつあります。
生産性の向上が企業成長のカギに
業務効率化は、単なる作業スピードの向上ではありません。生産性(インプットに対するアウトプットの質と量)をいかに高めるかが問われているのです。
例えば、同じ人数・時間で、より多くの成果を出すチームと、時間をかけても成果が出ないチームとでは、企業としての成長速度に大きな差が生まれます。
また、労働集約的な体制から脱却し、付加価値の高い業務へリソースを集中させるためにも、生産性の改善は避けて通れません。
業務効率化は、限られた人材資源を最大限に活用し、成長を加速させるための最も効果的な手段です。
時間的余裕が生む創造的業務の拡大
単純な作業に追われている状態では、クリエイティブな発想や新しい取り組みに時間を割くことはできません。
業務効率化によってルーティン作業や無駄な業務を削減できれば、従業員に「考える時間」「提案する時間」「試す時間」が生まれます。
この時間的余裕こそが、新規事業の創出、顧客満足度の向上、社内イノベーションといった、企業の未来を切り開く力へとつながります。
つまり、業務効率化は「時間を短縮するため」だけではなく、「創造的な仕事にシフトするための土台」でもあるのです。これからの時代、単なる作業の削減ではなく、余白を戦略的に活用することが企業力の差を生み出すポイントとなります。
業務効率化を図るための基本ステップと考え方
業務効率化を成功させるには、ただツールを導入するだけでは不十分です。まず「業務効率化とは何か」を正しく理解し、自社の業務のどこに無駄があるのかを把握したうえで、段階的に改善を進める必要があります。
業務効率化を図るとは?定義と目的の整理
「業務効率化」とは、業務にかかる時間やコストを減らしながら、質や成果を維持・向上させることを指します。ただ単に作業時間を短縮するのではなく、「少ないリソースで最大限の成果を出す」ことが真の目的です。
業務効率化の本質は、ムリ・ムダ・ムラをなくし、価値ある仕事に集中できる環境を整えることにあります。その結果として、従業員の負担軽減・顧客満足度の向上・利益率の改善など、多くのプラス効果をもたらします。
業務効率化を図るうえでの非効率な業務の典型例
効率化を進めるには、まずどこに「非効率」が潜んでいるかを把握することが重要です。以下は、よく見られる非効率な業務の典型例です。
- 属人化:特定の人しかできない業務が多く、休職や退職時に業務が滞る
- 重複作業:複数の部署で同じ情報を別々に入力・管理している
- 紙文化の温存:印刷・手書き・押印・郵送など、アナログ業務が残っている
これらは一見問題がなさそうに見えても、積み重なることで大きな時間的・人的コストを生んでいます。まずは「当たり前にやっていること」を疑い、業務の棚卸しから始めましょう。
業務効率化を図るための3つの基本ステップ
業務効率化は、以下の3ステップで進めるのが基本です。
- 現状把握
すべての業務を洗い出し、「誰が・何を・どのように・どれくらい時間をかけて行っているか」を明らかにします。
Excelや業務分解図などを使って、可視化するのが効果的です。 - ボトルネックの分析
どこにムダがあるのか、どこで作業が滞っているのか、非効率の原因を探ります。
属人化やフローの複雑さ、ツールの使いにくさなど、原因はさまざまです。 - 改善策の設計と実行
不要な作業の削除、ツールの導入、フローの簡略化、担当の再割り振りなど、課題に応じた解決策を設計・実施します。
小さく始めて、改善を繰り返す「スモールスタート&PDCA」が成功のカギです。
このように、業務効率化は「段取り八分」とも言える取り組みです。現状の見える化と冷静な分析が、最も大きな成果を生む出発点になります。次のセクションでは、具体的なアイデアを10個ご紹介します。すぐに実践できるものばかりなので、ぜひ参考にしてみてください。
今すぐ取り入れたい業務効率化を図るアイデア10選
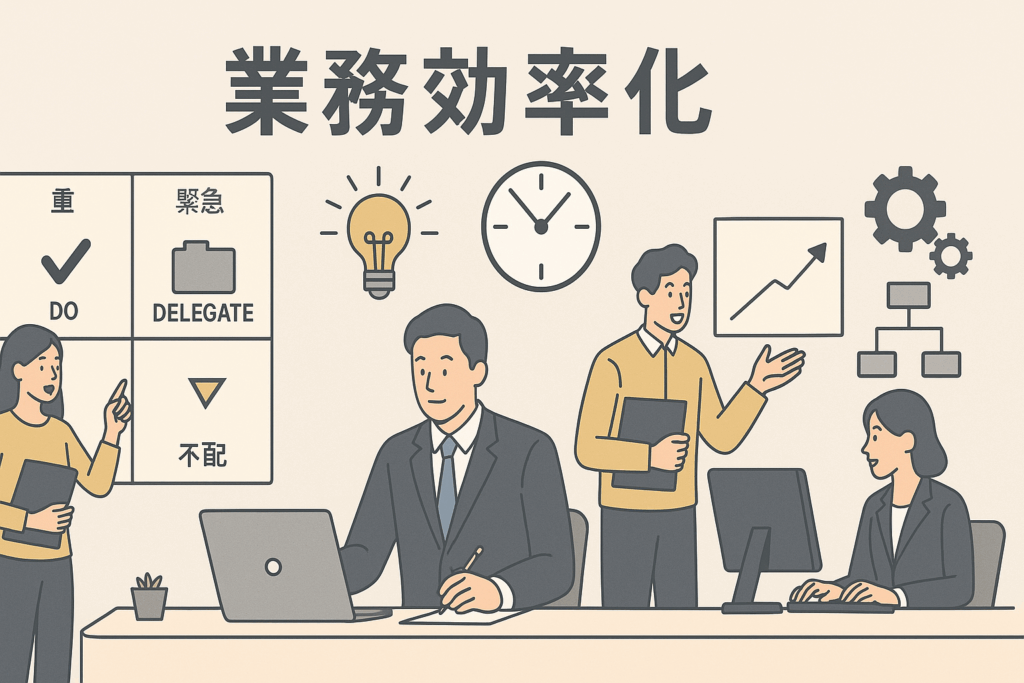
業務効率化を図るには、高価なシステムや大掛かりな改革だけでなく、日々の仕事のやり方を少し見直すだけでも効果が表れます。ここでは、すぐに取り入れられて、かつ現場での実践に強い10のアイデアをご紹介します。
| No. | 業務効率化を図るアイデア | 内容概要 |
| 1 | Eisenhowerマトリクスで優先順位を明確に | 緊急度と重要度でタスクを分類し、やるべき業務を可視化・整理。 |
| 2 | ルーティン業務のテンプレート化 | 毎回ゼロから作らず、フォーマット化して時短・ミス防止・品質統一を実現。 |
| 3 | 会議を15分以内で終えるルールづくり | 議題・目的を明確にし、無駄な会議時間を削減して生産性を向上。 |
| 4 | チャット・Wiki化で情報を一元管理 | 情報の散在を防ぎ、検索性・共有性を高めることで業務の無駄を解消。 |
| 5 | 「やらないことリスト」の導入 | 優先度の低い作業をあえてやめることで、本当に必要な業務に集中。 |
| 6 | 見える化ツールでボトルネックを発見 | 業務フローや分解図でムダな工程・停滞箇所を可視化し、改善の手がかりに。 |
| 7 | タイムブロッキング法で集中時間を確保 | タスクを時間単位でブロックし、重要業務を効率的にこなす習慣を作る。 |
| 8 | ダブルチェック不要な仕組み化 | 自動化・チェックリスト化などでミスを防ぎ、再確認工数を削減。 |
| 9 | タスクの標準化で属人化を防止 | 担当者に依存せず、誰でも同じ手順で遂行できるように業務マニュアルを整備。 |
| 10 | 定型業務のアウトソーシング活用 | 単純作業は外部委託し、社内は付加価値の高い業務に集中する体制を構築。 |
1. 業務効率化を図る「Eisenhowerマトリクス」で優先順位を明確に
Eisenhowerマトリクスとは、タスクを「緊急度」と「重要度」の2軸で4象限に分類し、業務の取捨選択を効率的に行うための思考法です。このフレームワークを使うことで、タスクを「今すぐやる」「スケジュール化する」「他人に任せる」「やめる」と整理でき、ムダな作業や迷いを減らせます。
個人はもちろん、チーム全体で活用することで、仕事の優先順位が共有され、業務のスピードと集中度が大きく向上します。
2. 業務効率化を図るためのルーティン業務のテンプレート化
毎日・毎週発生する定型業務は、テンプレート化することで繰り返しの負担を劇的に軽減できます。
議事録や報告書、メール文面、問い合わせ対応などをあらかじめフォーマット化し、必要事項を埋めるだけにすれば、誰でも短時間で質の高いアウトプットが可能になります。社内ルールとして共通化すると属人化防止にもつながります。
3. 業務効率化を図る会議ルールの徹底(15分以内で完結)
会議は「短く・決定重視」が効率化の鉄則です。
事前にアジェンダと目的を共有し、会議では議論よりも「決めること」に集中。15分で終わらなければ別の方法(チャット、ドキュメント)に切り替えるなど、時間単位の生産性にこだわる運用ルールが成果を生みます。立ち会議や時間制タイマー導入も有効です。
4. 業務効率化を図るための情報共有はチャット・Wiki化で一元管理
メール・口頭・紙といった多様な連絡手段に情報が散在していると、確認のたびに時間がかかります。
SlackやChatworkなどのビジネスチャット、Notionやesa.ioなどの社内Wikiを導入し、情報の集約と検索性の向上を図ることで、ナレッジ共有とタスク管理が一気通貫で行える環境が整います。通知設定やスレッド整理も重要です。
5. 業務効率化を図る「やらないことリスト」の活用
生産性向上の第一歩は「やらないこと」を明確にすること。
過去の慣習で続けている業務、アウトプットに結びつかない確認作業、承認フローの多さなど、やめられる作業は意外と多いものです。「目的に対して本当に必要か?」という視点で精査し、チームで合意を取って削減に踏み切りましょう。
6. 業務効率化を図る見える化ツールでボトルネック発見
業務を見える化すると、「どこにムダがあるか」「誰が負担を抱えているか」が明確になります。業務分解図・業務フロー図・プロジェクト管理ツール(Trello、Backlogなど)を活用し、作業時間・頻度・担当者の偏りなどを定量的に可視化することで、感覚ではなくデータに基づいた改善が可能になります。
7. 業務効率化を図るタイムブロッキングで集中時間を確保
「重要だけど後回しにしがち」な業務を、あらかじめスケジュールに組み込むのがタイムブロッキング法です。メールや打ち合わせに時間を奪われがちな人ほど、自分のための集中時間を先に確保しましょう。Googleカレンダーなどで「思考時間」「資料作成時間」などと明示し、他の予定と干渉しない環境を確保することが業務効率化を図るカギです。
8. 業務効率化を図るためのダブルチェック不要な仕組み化
「ヒューマンエラーを防ぐために人手を増やす」のではなく、ミスが起こらない業務設計が効率化の基本です。チェックリスト、入力制限つきのフォーム、バリデーション付きのスプレッドシートなどを活用し、確認工程そのものを減らしましょう。社内の承認プロセスも「自動化」「条件分岐」を取り入れることで、大幅な時短が可能になります。
9. 業務効率化を図るためのタスクの標準化・属人化の解消
「この仕事はあの人にしかできない」という状態は、効率化の大敵です。
担当者が変わっても同じ手順・品質で業務が進むように、手順書・操作動画・マニュアルの整備を進めましょう。RPAの導入やルールベースの業務整理も、再現性の高い仕組みをつくる上で有効です。教育コストの削減にもつながります。
10. 業務効率化を図る定型業務のアウトソーシング活用
単純作業・反復作業は、必ずしも社内で完結させる必要はありません。
データ入力・集計・チェック・コンテンツ更新などは、外部に委託することで人的リソースをコア業務に集中させることができます。コストだけでなく、セキュリティ・納期・成果物管理なども含めて、戦略的アウトソーシング設計が重要です。
業務効率化を加速させるツール11選【用途別】
業務効率化を図るうえで、ツールの活用は欠かせません。しかし、ただ導入するだけでは意味がなく、「何のために」「どの業務に」使うのかを明確にすることが重要です。ここでは、コミュニケーション・タスク管理・自動化・情報共有の4つのカテゴリ別に、今すぐ使える業務効率化ツールを厳選して紹介します。
| 分類 | ツール名 | 主な用途・特徴 |
| コミュニケーション系 | Slack / Chatwork | 社内チャットツール。即時性・可視性が高く、情報共有のスピードと精度を向上。 |
| Zoom / Google Meet | Web会議ツール。移動時間・コスト削減に貢献し、画面共有・録画・スケジューリングも容易。 | |
| タスク・プロジェクト管理系 | Trello / Asana / Notion | タスクの見える化・進捗共有。直感的UI(Trello)や情報一体化(Notion)で業務全体を管理。 |
| Backlog | 課題・プロジェクト管理に特化。ガントチャートやWiki連携でチーム連携を効率化。 | |
| 自動化・定型作業効率化系 | ChatGPT | 議事録要約、FAQ作成などの文章業務をAIで効率化。思考作業の自動化で創造業務へリソース移行。 |
| RPA(Power Automate 等) | 定型クリック・転記作業を自動処理。Microsoft製品との連携で業務フローを自動化。 | |
| Googleフォーム × スプレッドシート | アンケート・日報収集と自動集計を組み合わせ、入力〜分析のプロセスを一元化。 | |
| ナレッジ・情報共有系 | Notion / esa.io | 社内Wiki・ナレッジベースの構築。編集共有・タグ整理で属人化防止&情報共有を高速化。 |
| Dropbox / Google Drive | クラウドストレージ。ファイルの共有・履歴管理が容易で、誤送信や重複を防ぎながらリモート対応も可能。 |
業務効率化を図るコミュニケーション系ツール
・Slack / Chatwork(社内チャット)
社内外とのやり取りをメールからチャットに切り替えるだけで、情報の即時性・可視性・検索性が格段に向上します。
Slackは外部ツールとの連携も豊富で、Botやリマインダー設定も可能。Chatworkはシンプルで中小企業にも扱いやすく、導入しやすい点が魅力です。
・Zoom / Google Meet(Web会議)
移動不要で会議が可能になるWeb会議ツールは、時間・コストの削減に大きく貢献します。
Zoomは画面共有・録画機能が充実しており、Google MeetはGoogleカレンダーとの連携がスムーズ。短時間で目的達成する「ショート会議」と相性抜群です。
業務効率化を図るタスク・プロジェクト管理系ツール
・Trello / Asana / Notion(タスク管理・進捗共有)
タスクの可視化・進捗確認・期日管理に最適なツール群です。
Trelloはボード形式で直感的に使え、Asanaは業務の依存関係管理にも強みがあります。Notionはドキュメント管理とタスクを一体化できるのが特徴で、情報と業務のハブツールとして活躍します。
・Backlog(プロジェクト管理)
IT・開発現場に強いBacklogは、課題管理・進捗可視化・Git連携などが可能なオールインワン型のプロジェクト管理ツールです。
ガントチャートやWiki機能も備え、複数部署間の連携にも対応。チームでの業務効率化を図るには最適です。
業務効率化を図る自動化・定型作業効率化系ツール
・ChatGPT(文章生成・FAQ作成)
議事録の要約、マニュアルのドラフト作成、FAQの自動生成など、文章業務の時間を大幅に短縮できるAIツールです。
人手で行っていた「考える・書く・整える」作業を効率化し、空いた時間を企画や提案業務に回せるようになります。
・RPA(Power Automateなど)
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)は、定型的なクリック・コピー・転記作業をソフトウェアロボットが代行してくれる自動化ツールです。
Power AutomateはMicrosoft 365と親和性が高く、コストを抑えながら社内業務の自動化が進められます。
・Googleフォーム × スプレッドシート
アンケート・ヒアリング・日報などの入力をGoogleフォームで集め、スプレッドシートで集計・分析。
無料で始められるうえ、入力・集計・可視化を一元化できる仕組みが構築できます。メール通知や条件付き書式との連携も便利です。
業務効率化を図るナレッジ・情報共有系ツール
・Notion / esa.io(ドキュメント共有)
「社内に蓄積されているノウハウを活用できない」課題に対し、Notionやesa.ioは社内Wikiの構築・ナレッジの一元管理に強みがあります。
チームでのドキュメント編集や、タグ・カテゴリーによる情報整理により、ナレッジの属人化を解消できます。
・Dropbox / Google Drive(クラウドファイル管理)
ファイル共有のミスや重複、メール添付による混乱を防ぐには、クラウドストレージによる管理の標準化が効果的です。
Dropboxはファイル履歴や共有リンク設定に優れ、Google Driveは他のGoogle製品とスムーズに連携できます。どちらもモバイル対応でリモート業務にも活躍します。
業務効率化を図る際の落とし穴と注意点
業務効率化を図る取り組みは、企業の生産性や働き方を大きく改善できる一方で、方法を誤ると逆に混乱や不満を招くリスクもあります。ここでは、よくある3つの落とし穴を解説し、業務効率化を図る際に注意すべきポイントを整理します。
業務効率化を図る目的が「ツール導入」になってしまう
ありがちな誤解のひとつが、「ツールを導入すること=業務効率化」だと思い込んでしまうことです。新しいツールを入れても、現場の業務フローが整理されていなければ、逆に操作負担が増える・情報が分散する・使いこなせないといった事態を招きかねません。
効率化の本質は「目的に対して、もっとよい手段を選ぶこと」。
業務効率化を図る際は、ツール導入の前に課題の明確化と業務フローの整理が最優先です。
業務効率化を図るには現場の合意形成・教育が不可欠
効率化施策がトップダウンで一方的に進められると、現場では「仕事が増えた」「ルールが煩雑になった」と受け止められ、形だけで終わるケースが少なくありません。
特に属人化した業務を変える場合は、担当者の不安や抵抗も想定されます。
そのため、業務効率化を図る際には、現場との対話・巻き込み・段階的導入が不可欠です。
研修やマニュアル整備などを通じて「なぜ変えるのか」「どう使うのか」を丁寧に伝えることが、定着のカギとなります。
部分最適に陥り、全体の業務効率化を図ることを見失う
「とりあえず自分の担当業務だけ改善したい」と、個別最適に走ってしまうと、業務全体の流れが分断され、かえって効率が悪くなることがあります。
例えば、営業部門ではチャットが主流なのに、管理部門ではメールが前提になっているなど、連携が取れない非効率が生じるのです。
業務効率化を図るには、チーム横断・部署横断でのフロー可視化が欠かせません。
全体最適を意識し、業務分解図や業務フロー図で構造的に見直す視点を持つことが、失敗を避けるポイントです。
業務分解図を活用した効率化のすすめ
業務効率化を図るうえで、そもそも「何の業務に、どれだけの時間と人がかかっているのか」が把握できていなければ、的確な改善策は打てません。
そこで注目されているのが、業務全体を視覚的に整理できる「業務分解図」です。構造的に業務を見える化することで、属人化やムダの原因が明らかになり、効率化の起点になります。
業務分解図とは?構造的に業務を見える化する手法
業務分解図とは、一つの業務を細かく分解し、「誰が」「どんな作業を」「どの順番で」行っているかを図式化したものです。
例えば、資料作成という業務ひとつをとっても、情報収集、データ加工、レイアウト、確認、修正、提出といった工程に分かれます。
このように業務を構造的に分けて図にすることで、作業量や関与者、重複している工程、手戻りの多い箇所などが可視化され、業務効率化を図るための課題が見つかりやすくなります。
ムダ・重複・属人業務を可視化して効率化の起点に
業務分解図を使うと、特定の人しかできない作業(属人化)や、同じ作業を複数人が別々に行っているケース(重複作業)、必要以上に多い確認・承認フロー(ムダ)などが、客観的に見えるようになります。
例えば、
- 資料提出前の社内確認が3段階ある
- 顧客対応の履歴が2つのツールで分断されている
- 特定の担当者に問い合わせが集中している
といった問題も、図にすれば一目瞭然です。
これにより、「このフローは統合できる」「ここの作業は自動化できる」「この確認は省略できる」など、具体的な改善アクションを導き出しやすくなります。
mayclassの業務分解図サービスで改善施策を設計
業務分解図は、ただ作成するだけでなく、そこから改善施策を導き出し、実行に移すことが重要です。
mayclassでは、専門コンサルタントがヒアリングを行い、業務フローを図式化したうえで、ボトルネックの特定や改善提案までを一貫してサポートします。
自社内での業務効率化を図る取り組みがなかなか前進しない、全体像が把握できないと感じている方には、業務分解図を活用したアプローチが大きな助けとなるはずです。
業務効率化は習慣+仕組み+ツールで定着する
業務効率化を図る取り組みは、単発の施策では終わらず、日常業務に根付かせていくことが何より重要です。そのためには、働き方の習慣、業務の設計、そしてそれを支えるツールの三位一体で改善を進めていく必要があります。
ここでは、業務効率化を定着させるための3つの視点を整理します。
スモールスタートで継続的に改善
業務効率化を図るうえでありがちな失敗が、「一気に全部変えようとする」ことです。
現場の混乱を避けるためにも、まずは一部の業務や部署で小さく始めて、効果を検証しながら他の領域に展開していくのが効果的です。改善は一度きりではなく、現場の声をもとに何度も見直すことで、本当に使える仕組みへと成長します。
ツールだけでなく現場の声も重視
便利なツールを導入しても、現場が「使いづらい」「逆に手間が増えた」と感じれば、すぐに使われなくなってしまいます。
業務効率化を図るには、使う人の声をしっかりと拾い、運用しながら必要に応じて見直す柔軟さが求められます。また、現場のアイデアや気づきをもとに改善のサイクルを回していくことが、実用的な仕組みづくりにつながります。
外部支援の活用も選択肢に
業務効率化を図るには、現状分析やフロー改善、ツール選定などに専門的な視点が求められる場面もあります。そのようなときは、外部の知見を取り入れることで、よりスムーズに効果的な施策を進めることができます。特に、全体像の見える化や改善方針の策定が課題となっている場合は、業務分解図のような手法と外部支援の組み合わせが有効です。
業務効率化を考えている担当者の方は、ぜひmayclassのサービスページをご覧ください。

※業務分解図メール受け取りご希望の際は、お問合せ内容に「業務分解図希望」と記載してください。
▼こちらの記事もおすすめ▼
業務効率化は“数値化”から始まる!成果を見える化する方法と実践ステップ
【図解でわかる】生産性向上と業務効率化の違いとは?意味・目的・施策を徹底比較!
【保存版】営業資料の作り方を徹底解説!成果につながる構成・デザイン・伝え方のコツとは?
ーーー
How to Improve Work Efficiency: Tools, Ideas, and Success Secrets You Can Use Now