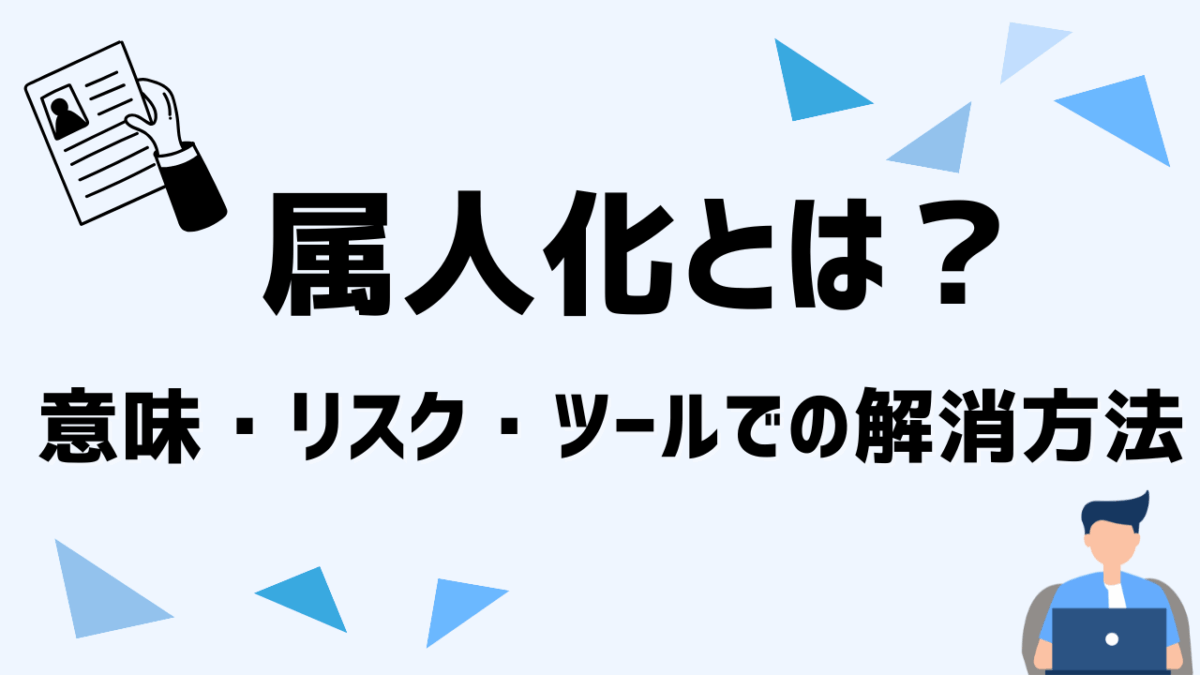「この作業はAさんにしかできない」「担当者が休むと業務が止まってしまう」
そんな経験はありませんか。
ビジネスの現場でよく耳にする「属人化」は、多くの企業が抱える課題のひとつです。放置すると業務の停滞や人材育成の妨げになりますが、うまく活用すれば品質向上や効率化に役立つこともあります。
本記事では、属人化の意味やリスク、解消に役立つツールまで詳しく解説します。
「属人化を解消したいが、どこから手をつければよいか分からない」と感じている方向けの解説&実務ガイドです。属人化の意味や起こる背景、「悪い面」だけでなくメリットとなる側面まで整理したうえで、リスクとデメリット、業務の見える化・マニュアル化・OJT・ITツール活用による解消ステップを具体的に紹介しています!
そもそも「属人化」とは?
属人化という言葉は耳にすることが多いものの、具体的に説明できる人は少なくありません。ここでは属人化の基本的な意味やビジネスシーンでの使われ方、さらに発生する背景について整理します。
属人化の意味とビジネスシーンでの使い方
属人化とは、特定の人に業務が依存してしまい、その人しか対応できない状態を指します。担当者がいないと業務が止まってしまう、あるいは成果物の質やスピードがその人の能力や経験に大きく左右されるのが特徴です。
ビジネスシーンで見られる例としては、次のようなものがあります。
- 経理処理を担当者一人が独自のExcel管理で進めていて、他のメンバーが内容を把握できない
- 営業ノウハウがマニュアル化されず、ベテラン社員の経験や人脈に頼り切っている
- 顧客とのコミュニケーション履歴が特定の担当者のメールや頭の中にしか残っていない
- プロジェクトの進め方が担当者の暗黙知に依存していて、引き継ぎが難しい
このように属人化は業種や規模を問わず起こり得るため、多くの企業で共通の課題となっています。
なぜ属人化が起こるのか?背景と原因
属人化は偶然に生まれるものではなく、組織の体質や環境によって引き起こされます。大きな原因のひとつは、業務手順やルールが文書化されていないことです。マニュアルや仕組みが整っていなければ、担当者が独自のやり方で仕事を進めるしかなくなり、その人しかできない業務が生まれてしまいます。
また、「この仕事は〇〇さんが得意だから任せよう」といった文化も属人化を進める要因です。一見合理的に見えても、知識やノウハウが特定の担当者に集中しやすくなります。その結果、若手や他のメンバーへの共有が進まず、組織としてのスキル蓄積が滞ってしまうのです。
さらに、人員不足や繁忙期の対応も属人化を招きます。「とりあえず手が空いている人に任せる」といったやり方で業務を回せても、そのまま担当が固定化されると依存が深まっていきます。
特に中小企業では限られた人材で多くの業務をこなさなければならないため、担当を分ける余裕がなく、結果として属人化が組織全体に広がるケースも少なくありません。
「なぜ属人化が起きるのか」を正しく理解し、対策を講じることです。
「属人化=悪」とは限らない?悪くないケースも解説
属人化は一般的にリスクとして語られることが多いですが、必ずしもマイナス面ばかりではありません。状況によっては、むしろメリットとして働く場合もあります。
例えば、熟練者が顧客からのクレームやトラブルに迅速に対応できるケースです。経験に基づく判断がすぐにできることで意思決定のスピードが上がり、業務全体の効率が向上することがあります。
また、高度な専門知識やスキルが求められる業務では、特定の担当者が担うことで品質を安定させられます。医療現場や製造業、ITインフラの保守など、専門性が高い分野はその代表例といえるでしょう。
さらに、営業やコンサルティングの現場では、一人の担当者が一貫して対応することで信頼関係を深めやすくなります。顧客が「この人に任せたい」と感じることが企業にとって大きな強みとなるのです。
ただし、これらのメリットは一時的なものであり、長期的には長期的にはリスクに変わる可能性があります。
大切なのは、個人のスキルや判断力を「属人的な強み」として尊重しつつ、それを組織全体で再現できる仕組みに落とし込むことです。そうすれば、属人化の利点を活かしながらもリスクを最小限に抑えることができるでしょう。

属人化によるリスクとデメリット
属人化はその場しのぎでは効率的に見えることもありますが、積み重なると大きな弊害になります。ここからは、具体的にどんなリスクやデメリットがあるのかを解説します。
業務が止まるリスク
属人化が進むと、担当者が不在になっただけで業務が止まる恐れがあります。
例えば、月末の経理処理を一人だけが担っている場合、その人が休暇や病気で不在になると作業が滞り、取引先への支払いが遅れることもあり得ます。
また、情報が担当者の頭の中にしかない状態は部門間の連携を妨げます。営業担当者だけが顧客の最新情報を持っていると、サポート部門が適切に対応できません。このような「情報の断絶」は、結果的に組織全体のパフォーマンスを下げてしまいます。
人材が離職・異動したときの影響
属人化の大きなリスクのひとつが、担当者の離職や異動です。重要な業務が特定の人に依存している場合、その人が突然辞めたり配置転換になったりすると、業務の引き継ぎに大きな負担がかかります。
実際に、プロジェクトの進行が止まったり、顧客対応が滞ったりする事例は少なくありません。さらに、業務のノウハウが後任に十分伝わらないまま業務が進むと、品質低下やミスの増加につながる危険性もあります。企業にとっては売上や信用の低下に直結するケースもあるのです。
組織運営における問題点と課題
属人化は人材育成の妨げにもなります。特定の担当者が業務を抱え込んでしまうと、若手や他の社員が経験を積む機会を失い、組織全体のスキルが底上げされません。
さらに、属人化が当たり前になると「その人がいなければ何も決められない」といった依存体質が組織に根づいてしまいます。その結果、意思決定のスピードが落ち、環境変化への対応力も低下してしまいます。
「属人化は悪くない」?メリットと正しい使い方
属人化という言葉には「組織のリスク」「業務の非効率」といったネガティブなイメージが強くあります。しかし一方で、状況によっては属人化がプラスに作用するケースも存在します。大切なのは、属人化をすべて排除しようとするのではなく、メリットを理解したうえで正しく活かすことです。
ここでは、属人化がもたらすメリットと使い方のポイントを解説します。
熟練者による品質担保・スピード向上
経験豊富な社員が担当することで、業務の品質やスピードが格段に上がることがあります。例えば、顧客からのクレーム対応では、熟練した担当者の判断力や経験がものを言います。マニュアル通りに進めるよりも状況に応じて柔軟に対応できるため、顧客満足度を高められるのです。
また、製造業やITの現場でも同様です。専門的な知識やスキルを持つ担当者が関わることで、作業の効率化やトラブルの早期解決につながり、結果として組織全体のパフォーマンスが向上します。
専門性や裁量を活かした業務遂行
属人化は、その人にしかできない「強み」を発揮する場面を生み出します。例えば、ある営業担当者が特定業界の知見に長けており、業界独自の商習慣や顧客のニーズを熟知している場合、その人に任せることで成果を最大化できます。
裁量を持って仕事を任せられる環境は、担当者のモチベーション向上にもつながります。自分の判断で進められる自由度があることでより責任感を持ち、創意工夫を凝らした成果を出しやすくなるのです。
「任せる」から「仕組みに活かす」への転換がカギ
属人化のメリットが続くのは短期的な場合が多く、長期的に見ればリスクの方が大きくなりがちです。理想的なのは、個人が持つスキルやノウハウを属人的な範囲に留めず、組織全体で共有できる形に変えていくことです。
具体的な方法としては、次のような取り組みがあります。
- 熟練者のノウハウをマニュアルやナレッジベースに落とし込み、誰でも再現できるように整備する
- OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)を通じて若手に段階的に引き継ぐ
こうした取り組みによって、属人化の「強み」を組織全体の財産へと転換できます。
属人化を単に「排除すべきもの」と捉えるのではなく、「活かしながら仕組みに変えていく」視点が重要です。
属人化を解消するための実践ステップ
属人化を解消するためには、「一人に依存しない仕組み」をつくることが欠かせません。とはいえ、いきなりすべてを変えようとしても現場には大きな負担がかかります。段階を踏んで進めることが重要です。
属人化解消ステップ①:業務の可視化・棚卸し
最初に取り組むべきは、どの業務が誰に依存しているのかを「見える化」することです。属人化がどこで起きているのかを把握しなければ、対策は立てられません。
具体的には、業務フローを書き出し、担当者ごとにタスクを整理します。例えば「Aさんしか対応できない仕事はどれか」「その作業はどのくらいの頻度で発生しているか」といった視点で洗い出すと、属人化の度合いが明確になります。
属人化解消ステップ②:業務マニュアルの作成と更新
業務の見える化ができたら、次はマニュアルづくりです。業務手順を文章や図でまとめておけば、誰でも同じ手順で作業を進められる状態をつくります。
ポイントは、最初から完璧を目指さないことです。まずは基本的な手順を簡単にまとめ、実際に使いながら改善していくサイクルを回すと、定着しやすくなります。古いマニュアルはかえって混乱を招くため、継続的に見直す仕組みを整えましょう。
参考:見やすいマニュアルの作り方 3 原則!わかりやすいレイアウトのコツをご紹介
属人化解消ステップ③:チームでの業務分担とOJTの仕組み化
属人化を防ぐには、複数人でカバーできる体制をつくることが必要です。担当を一人に固定せず、チームで分担する形を意識しましょう。
あわせて効果的なのがOJTです。実際の業務を一緒に行いながら知識やスキルを共有することで、「誰かが抜けても業務が止まらない」状態を実現できます。ノウハウが一部の人に偏らず、チーム全体に広がるのが大きなメリットです。
属人化解消ステップ④:SaaS・ITツールで業務の標準化
最後のステップは、ITツールを活用して業務を標準化することです。マニュアルやOJTだけでは、どうしても人によってやり方の解釈に差が出てしまいます。そこでツールを使えば作業の流れをシステムで固定化でき、属人化をより防ぎやすくなるのです。
例えば、タスク管理ツールで進捗状況を共有したり、ナレッジ共有ツールで手順やノウハウを蓄積したりする方法があります。また、自動化ツールを導入すれば、入力や転記といった単純作業を人の手から切り離せるため、担当者に依存しない仕組みを作れるでしょう。
属人化の解消に効果的なツール10選
属人化を防ぐには、「情報を共有できる仕組み」と「業務を標準化できる仕組み」を整えることが欠かせません。ここでは、実際に多くの企業で導入されている代表的なツールを10種類に分けて紹介します。
ナレッジ共有ツール(Notion、Kibela)
Notionは、ドキュメント作成からタスク管理まで幅広く使えるオールインワン型ツールです。チーム内で情報を一元管理できるため、担当者が変わっても必要な情報にすぐアクセスできます。属人化の典型例である「頭の中だけの知識」をチーム全体の資産に変えられるのが強みです。
Kibelaは社内の知識やノウハウを蓄積し、検索しやすい形で共有できるサービスです。特に「過去に誰かが解決したトラブル」を探しやすく、情報が個人に閉じてしまうのを防げます。リモートワークや拠点が分かれている企業に適しています。
参考;Notionでマニュアルを作成する方法!テンプレート活用・データベース連携完全ガイド
業務フロー可視化ツール(例:miro、業務分解図)
miroは、オンライン上でホワイトボードのように業務フローを描けるツールです。業務の全体像を図式化することで、「どの工程が誰に依存しているか」を把握しやすくなります。属人化が起きている箇所を特定しやすく、属人化改善の第一歩に役立ちます。
業務分解図はフレームワークですが、業務を細かく分解して一覧化する方法です。Excelや専用ソフトを使って可視化すると、作業の属人化度合いを定量的に分析できます。シンプルながら効果が高く、属人化対策の入口として有効です。

ドキュメント管理・マニュアル作成ツール(例:Teachme Biz、Stock)
Teachme Bizは写真や動画を使って直感的にマニュアルを作れるクラウドサービスです。文章だけでは伝わりにくい業務も、誰でも再現できる形に落とし込めます。教育コストを削減しつつ、業務品質の標準化を進められるのがポイントです。
Stockはチームの情報をシンプルに蓄積・共有できるドキュメント管理ツールです。チャットでは流れてしまいがちな業務ノウハウや手順をストックしておけるため、必要なときにすぐに参照できます。現場メンバーが迷わず使えるシンプル設計で、マニュアルや業務手順の共有に適しています。
タスク管理ツール(例:Backlog、Asana)
Backlogはプロジェクト管理に特化したツールで、タスクの担当者・期限・進捗をチーム全体で把握できます。「誰が何をしているのか」が明確になることで、特定の人に仕事が集中するのを防げます。開発チームを中心に幅広い業種で導入されています。
Asanaはチームの目標とタスクをひとつのプラットフォームで可視化できるツールです。属人化しがちな進捗管理や情報共有を仕組み化し、誰でも状況を追えるようになります。シンプルな操作性で非IT部門でも使いやすいのが特徴です。
自動化ツール(例:Power Automate、Zapier)
Power Automateはマイクロソフトが提供する自動化ツールで、定型作業を自動化できます。
例えばExcelからのデータ転記やメールの振り分けなど、属人化しやすい日常業務をシステムに任せることが可能です。人為的なミスも減らせるため、標準化を目指しやすいのがメリットです。
Zapierは異なるクラウドサービス同士をつなぎ、自動でデータをやり取りできるツールです。SlackやGoogleスプレッドシート、CRMツールなどを組み合わせて「通知」「記録」「レポート」を自動化すれば、担当者依存を解消できます。
導入時の注意点
ここまで紹介したツールや仕組みは属人化の解消に効果的ですが、導入するだけでは成果につながりません。
ツールや仕組みを導入する際は、次の3つのポイントを意識することが重要です。
- 現場の声を反映させる
- 導入目的を共有し、納得感を持たせる
- 定期的に更新・振り返りを行う
それぞれ解説します。
現場の声を反映させる
実際に業務を担うメンバーの意見を取り入れなければ、現場の実態に合わない仕組みになり、形骸化してしまいます。トップダウンで一方的に決められたツールやマニュアルは「使いづらい」と感じられ、結局活用されないケースが多いのです。
導入前にはヒアリングやアンケートを行い、「どの作業が属人化して困っているのか」「どの機能があれば便利か」といった意見を集めることが大切です。さらに、試験運用(トライアル)を通じて現場での使い勝手を確認すれば、導入後の定着率も高まります。
導入目的を共有し、納得感を持たせる
「なぜこのツールを導入するのか」「どんな課題を解消したいのか」をチーム全体で共有し、納得感を持ってもらうことが重要です。目的が不明確なまま進めると、「新しい業務が増えただけ」「結局誰のための仕組みなのか分からない」と反発を招きかねません。
例えば「案件管理をツールで一元化し、担当者が急に不在でも引き継ぎがスムーズになる」といった導入目的を具体的に伝えれば、現場はメリットを実感しやすくなります。導入説明会やマニュアル配布だけでなく、導入後のフォローアップ研修や相談窓口を設けることで、不安や疑問を解消しながら浸透を図れます。
定期的に更新・振り返りを行う
ツールやマニュアルは一度作って終わりではありません。業務フローや顧客ニーズは常に変化しているため、導入当初は有効だった仕組みも、時間が経つと現場に合わなくなってしまうことがあります。
そこで重要なのが、定期的な更新・振り返りです。半年に一度や四半期ごとなど、あらかじめ見直しのタイミングを設定しておくと、形骸化を防げます。小さな改善を積み重ねることで「使いやすい仕組み」が維持され、属人化解消の効果を長期的に継続できます。
よくある失敗は「導入して終わり」にしてしまうことです。ツールのアップデートを放置したり、古いマニュアルをそのまま使い続けたりすると、かえって混乱を招きます。定期的に利用状況をチェックし、現場からのフィードバックを取り入れましょう。
参考:マニュアルの整理整頓で業務効率UP!最新版への整理・更新テクニック
属人化の「悪くない使い方」と「解消」のバランスが重要
属人化にはリスクがある一方で、熟練者の経験や裁量によって業務品質やスピードが高まるケースもあります。大切なのは属人化を完全に排除するのではなく、活かす部分と仕組みに変える部分のバランスを取ることです。
「属人化を排除」ではなく「活かして解消」へ
属人化をすべてなくそうとするとかえって組織の柔軟性が失われたり、個々人の強みが活かされなくなるリスクがあります。
例えば、ベテラン社員の判断力や顧客との信頼関係は、短期的には組織の大きな武器となるものです。その一方で、ノウハウや成功事例を属人的に留めてしまうと、担当者が離職した際に大きな損失になります。
個人のスキルを活かすと同時に、マニュアル化やナレッジ共有ツールで組織の財産に変えることが必要です。属人化のメリットを残しつつ、リスクを軽減する方向に解消していくことが理想のアプローチといえるでしょう。
現場の声をもとにした仕組み作りが成功のカギ
属人化を解消する仕組みを導入しても、現場に浸透しなければ意味がありません。トップダウンで決められたマニュアルやツールが結局使われずに形骸化する、というのはよくある話です。
大事なのは、実際に業務を担う人たちの声を反映させることです。「どの作業が属人化して困っているか」「どの手順を標準化すれば効率化できるか」といった意見を拾い、仕組みに落とし込むことで、現実的で使いやすいものになります。
さらに、仕組みをつくって終わりにするのではなく、定期的に見直すことも欠かせません。現場の業務フローや顧客ニーズは常に変化するため、アップデートを重ねていきましょう。
属人化の見直しは業務を可視化するところから!
現場に根付く仕組みづくりを実現するためには、業務を可視化し、分解することが不可欠です。
「どの作業が属人化しているのか」「誰でも同じ品質で対応できる手順は何か」を明確にすれば、改善すべきポイントが見えてきます。
私たちmayclassでは、属人化を解消するための業務分解図をはじめとした仕組み化の支援を行っています。現場の声を取り入れながら、実際に使える業務改善をサポートいたします。
属人化の解消にお悩みの方は、ぜひお問い合わせページからご相談ください。

ーーー
[2025 Edition] What Is “Personalization” in Business? Definition, Risks, and How to Solve It with Tools
▼下記記事もおすすめ▼
業務改善・業務効率化の原則と目標を徹底解説!4原則・3要素・8原則を一挙紹介