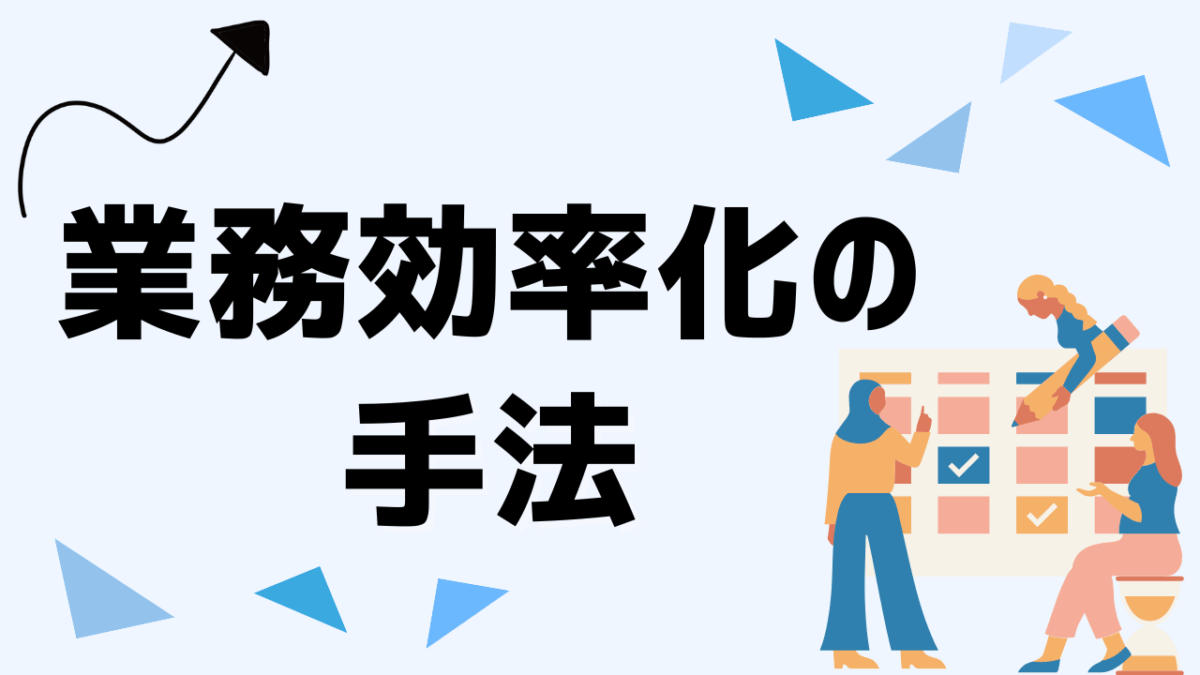「人手不足」「業務の属人化」「生産性の停滞」多くの企業が、日々の業務をもっと効率化したいと感じているのではないでしょうか。とはいえ、「どこから手をつければいいかわからない」「効果的なやり方が見つからない」と悩む声も少なくありません。
この記事では、そうした悩みを解決するために、どんな業務にも応用できる基本的な効率化の考え方から、便利なツールの活用法、マニュアル作成や外注といった具体的な方法まで、幅広くご紹介します。
それぞれのメリット・デメリット、実践のポイントや成功事例も交えて解説しますので、ぜひご活用ください。
ツールを活用した業務効率化手法
業務の効率化を図るうえで、“ツールの導入”は即効性が高く、かつ低コストで始められる方法です。ここでは、代表的な4つのツールについて解説します。
業務効率化の手法①:クラウドサービス(Google WorkspaceやMicrosoft 365など)
クラウドサービスの導入は、業務効率化を図るうえでとても有効です。特にGoogle Workspace、Microsoft 365などを活用すると、データの共有や共同編集がスムーズになり、複数人で同時に作業を進められるため、業務のスピードと正確性がアップします。そうなれば、情報共有や進捗連絡といったメールのやり取りやファイルのバージョン管理にかかる手間を省くことができ、業務全体の生産性が高まります。
また、クラウド上でデータを管理すると、出張先や自宅など場所を問わずアクセスできるので、柔軟な働き方が可能になります。これはリモートワークが定着しつつある昨今のビジネス環境においては、大きな利点だといえるでしょう。
さらに、情報の一元管理ができるのもクラウドサービスの魅力の一つです。たとえば、部署ごとに分散していたファイルやデータを一か所に集約することで、必要な情報にすぐにアクセスでき、検索の手間や時間を大幅に削減できます。アクセス権限の設定やログの管理をすることで、セキュリティ面も安心して利用できます。
業務効率化の手法②:タスク管理ツール(Trello、Asanaなど)
TrelloやAsanaに代表されるタスク管理ツールを導入することで、「誰が・何を・いつまでにやるか」が明確になり、チーム全体での作業はより一層可視化できるようになります。タスクの進捗状況を一覧で把握できるので、作業の漏れや遅延といったリスクを事前に察知することができます。また、直感的な操作性のものも多いので、こうしたツールに慣れていないスタッフでもすぐに使いこなせるところもメリットです。
実際、タスクの期限を設定や、担当者を割り当てるといった管理も簡単に行えるため、日々の業務運営がよりスムーズになります。進行状況をチーム全体で共有できる仕組みは、小規模なチームだけでなく大規模なプロジェクトにおいても成功のカギとなります。
業務効率化の手法③:コミュニケーションツール(Slack、Chartworkなど)
業務効率化のためには、社内コミュニケーションの円滑化も欠かせません。そのために効果的なのが、SlackやChartworkといったチャットベースのコミュニケーションツールです。これらのツールを活用すれば、メールよりも迅速に情報共有ができ、やり取りのスピードが格段に向上します。
たとえば、プロジェクトごとに専用のチャンネルを作成すれば、関連する情報を一か所に集約できます。これまでのようにメールを何通も探す手間がなくなり、確認漏れを防ぐことができます。また、SlackではGoogleカレンダーやTrelloなど、さまざまな外部アプリとの連携も可能で、通知やリマインダーの自動化なども実現できます。
業務効率化の手法④:RPA(Robotic Process Automation)
さらに、定型業務の自動化を図る手段として注目されているのがRPA(Robotic Process Automation)です。RPAを導入することで、請求書の作成や定型メールの送信、データ入力・転記といった反復的な業務をソフトウェアロボットが自動で処理してくれます。特にExcelベースの作業が多い部署では、入力ミスや確認作業にかかる時間を削減できるため、業務の正確性とスピードの両方を向上させることが期待できます。人的リソースを割く必要がなくなるので、スタッフはより創造性を要する業務のほうに集中することも可能になります。これまで人手で対応していた細かな業務を効率化することで、企業全体の業務負担を軽減し、働き方改革にも貢献できる手段として、多くの企業が導入を進めています。
これらすべてのツールにいえることですが、どれを使うべきか選ぶ際は、利用目的や業務内容、既存のITインフラとの相性、使用するスタッフのITリテラシー、使いやすさなど、さまざまな面を踏まえて検討することが重要です。業務の効率化にはどのツールが最適なのか、ニーズに合ったものを選定し、最大限に活用していきましょう。
マニュアル作成と活用による業務効率化手法
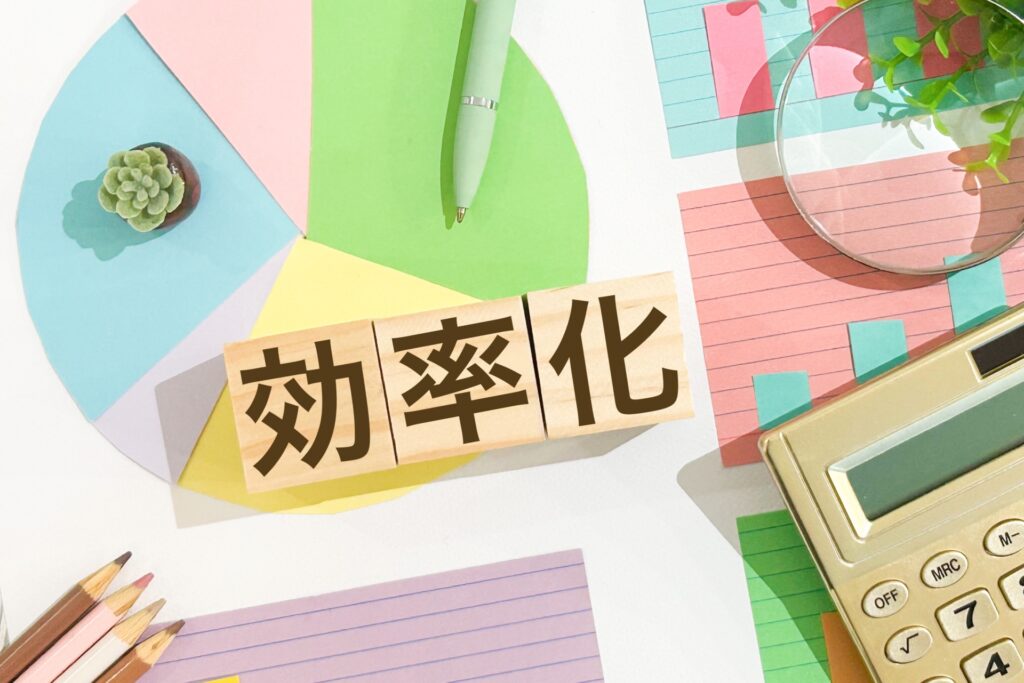
効率化の基本は、「業務の標準化」です。そのカギを握るのがマニュアルです。マニュアルを整備することには、多くのメリットがあります。
まず、誰が業務を行っても一定の品質が保たれるようになり、作業のばらつきが減ります。これは、業務プロセスを明文化することで属人化を防ぎ、組織全体の安定したパフォーマンスにつながるからです。
また、新人がより早く、スムーズに業務に馴染めるようになり、教育にかかる時間やコストの削減にもつながります。マニュアルがあれば、新しく入った社員でも業務手順をすぐに理解し、実務に取り組めるようになるので、先輩社員の指導に割く時間も最小限に抑えられるからです。さらに、担当者の急な退職や長期休暇といった際も、マニュアルがあれば業務の引き継ぎがスムーズに進み、混乱を防ぐことができます。マニュアルは企業にとって単なる文書ではなく、業務の効率化と安定運営のための重要なインフラともいえるのです。
マニュアル作成のポイント
そんな効果的なマニュアルを作成するには、いくつかの重要なポイントがあります。
①誰にでもわかりやすく:基本は、「誰が読んでも理解できるようなわかりやすい言葉で記述する」ことです。専門用語を使う場合には、その意味を簡単な説明を記載しておくとよいでしょう。
②図解やフローチャートを活用する:次は、「図解やフローチャートを活用する」ことです。文章だけでは伝わりづらい手順や構造も、視覚的な情報を取り入れることで明確に示すことができます。特に工程が複雑な作業や、分岐の多いフローを説明する場合に効果的です。
③マニュアルの検索性を高める:マニュアルの検索性も重要な要素です。いくらいい内容のマニュアルを作っても、どこに何が書いてあるのかわかりにくければ、うまく活用されていきません。目次やインデックスを整備し、キーワードやタグ付けをして、必要な情報にすぐにアクセスできる構成にします。こうした工夫ひとつで、使い勝手が大きく向上し、現場での活用頻度も自然と高まります。
④マニュアルは定期的に更新する:マニュアルは一度作って終わりではなく、定期的に内容を見直して更新することが不可欠です。業務の変更や新しいシステムの導入に伴い、マニュアルの内容もアップデートすることで、常に最新かつ実用的な情報を提供し続けることができます。
マニュアルとひと口に言っても、その種類は多岐にわたります。たとえば「業務手順書」は、ある作業をどのように進めるかを詳細に説明したもので、現場での即戦力として活躍します。一方「FAQ」は、よくある質問とその回答を整理する形式で、問い合わせ対応の効率化に有効です。「トラブルシューティングマニュアル」は、問題が発生したときの対処法をまとめたものです。突発的なエラーや障害にも冷静に対応できるよう、判断の指針を与えてくれます。「教育用マニュアル」は、新人研修やOJTでの活用を目的とした資料で、会社のルールや業務の全体像を把握するための出発点になります。目的に応じて適切な形式を選び分けることで、マニュアルの価値を最大限に引き出すことができます。
さらにマニュアルの運用方法も、業務効率に大きく関わるポイントです。近年では紙媒体よりも、クラウドベースの電子マニュアルが主流となりつつあります。GoogleドライブやDropboxなどのストレージサービスを利用することで、必要な人が必要なときにすぐアクセスできる環境が整います。こうしたサービスを活用すれば、アクセス権限を細かく設定することもできます。閲覧のみ許可する人、編集が可能な人、管理権限を持つ人などを区別することで、情報の保護と運用の効率化を両立できます。また、たいていはマニュアルの変更履歴を自動的に記録し、過去のバージョンにさかのぼることができる機能も備わっているため、誤った編集や削除があった場合でも迅速にリカバリーできます。このような電子媒体での運用は、利便性だけでなく、情報の正確性・信頼性を維持するうえでとても効果的です。
マニュアル作成外注のメリット
プロに任せて業務効率化を実現
「マニュアルを作りたいけれど、自社内にはリソースがない」という場合、業務効率化手法のひとつとしてマニュアル作成を外注するのは有効です。マニュアル作成のプロに依頼することで、内容の正確性や構成の完成度が高く、短期間で高品質なマニュアルを手に入れられます。これは、自社で手探りで作成するよりも、業務効率化を加速させる手法と言えるでしょう。
多様な形式対応で業務効率化の幅を広げる
動画マニュアルやWebマニュアルなど、多様な形式に対応できることも外注のメリットです。教育用だけでなく、営業ツールや社内報告資料としても活用でき、さまざまな業務効率化手法として役立つマニュアルを手に入れることができます。
本来業務に集中できる
外注により社内リソースをマニュアル作成に割かずに済むため、担当者は本来の業務に集中できます。特に中小企業や少人数の部署では、限られた人材資源を有効活用する業務効率化手法として非常に効果的です。
マニュアル作成外注に潜むデメリット
コスト負担が発生する
マニュアル作成を外部に依頼すると、数万円から数十万円の費用がかかるのが一般的です。
「自社で作成する手間や時間」と「外注費用」のどちらが効果的か、費用対効果を事前にしっかり検討することが重要です。
単に「高い・安い」だけで判断するのではなく、期待する成果や業務改善効果に見合う投資かどうかを見極めましょう。
自社情報の取り扱いリスクがある
外注するためには、業務内容や自社ノウハウを共有する必要があります。
そのため、情報漏洩リスクを完全にゼロにはできません。
安全に進めるためには、
- 信頼できる業者選定
- 秘密保持契約(NDA)の締結
といった対策が欠かせません。「安いから」と安易に選ぶのではなく、情報管理体制や実績も必ず確認しましょう。
自社の関与は不可欠
外注とはいえ「丸投げ」では、自社に最適なマニュアルは作れません。
具体的には、
- 業務内容の説明
- 原稿確認やフィードバック
- 修正対応
など、打ち合わせやレビューの時間が必要です。「外注すれば自動的に完成する」と期待せず、社内の手間や時間も一定必要であることを理解しておきましょう。これは「無駄な手間」ではなく、成果を最大化するための重要なプロセスと捉えることが大切です。
失敗しないマニュアル作成外注の選び方
マニュアル作成を外注することは、業務効率化を大きく進める手法の一つですが、依頼先選びを誤ると「期待した成果が得られない」「逆に手間が増えた」といった失敗につながることもあります。
ここでは、失敗しないための業務効率化手法としての外注先選定ポイントを詳しく解説します。
業務理解・実績確認
まず重視すべきは、依頼先が自社の業界や業務内容をどれだけ理解しているかです。
業界特有の専門用語や業務フローを理解していない業者に依頼してしまうと、実態とズレたマニュアルが出来上がるリスクがあります。
そのため、過去に同じ業界や類似業務のマニュアル制作実績があるかを確認しましょう。
実績が豊富な業者を選ぶことは、業務効率化手法として確実性の高いパートナー選びにつながります。
制作事例・ポートフォリオ確認
外注先の制作事例やポートフォリオを確認し、自社の期待に見合う品質かどうかを見極めることも重要です。「見やすさ」「分かりやすさ」「実用性」など、実際のマニュアルをチェックすることで、業務効率化に貢献する仕上がりかどうか判断しやすくなります。
期待する成果が得られるかどうかを事前に具体的に確認する手法として、ポートフォリオ確認は必ず行いましょう。
費用・納期の明確化
外注にはコストがかかるため、費用対効果のバランスを見極めることが欠かせません。その際、費用や納期があいまいな業者はリスクが高いため注意が必要です。
「どこまでが料金に含まれるのか」「追加費用が発生する条件は何か」「納品までのスケジュールはどうか」などを明確に提示してくれる業者を選ぶことで、計画的な業務効率化手法として安心して依頼できます。
情報管理体制を確認
マニュアル作成では、業務プロセスや社内情報を外部に共有する必要があるため、情報漏洩リスクへの配慮も重要なポイントです。信頼できる業者かどうかを見極めるために、次のような項目を確認しましょう。
- NDA(秘密保持契約)の締結が可能か
- 情報管理体制やセキュリティポリシーが整備されているか
これらをしっかり確認することで、安全性の高い業務効率化手法として外注を活用できます。
複数社比較
一社だけで決めず、複数の業者から見積もりや提案を取り寄せて比較することも、失敗しない外注選定の重要な業務効率化手法です。比較する際のポイントは以下の通りです。
- 業務理解・実績
- 制作事例・クオリティ
- 費用・納期・対応範囲
- 情報管理体制・セキュリティ
これらを総合的に比較し、最適なパートナーを選ぶことで、自社に最も効果的な外注先を選定できます。
その他の業務効率化手法
マニュアル作成やツール導入だけが業務効率化手法ではありません。ここでは、さらに実践できる具体的な業務効率化手法をいくつかご紹介します。
業務効率化手法①:業務フローの可視化
業務改善の第一歩としておすすめしたい業務効率化手法が、業務プロセスの「可視化」です。業務の流れを図解し、全体像を把握することで、無駄や非効率なポイントを発見できます。
例えば、多段階の承認フローや、同じ情報を何度も転記する作業は、業務全体のスピードを著しく低下させます。こうした課題を見つけたら、プロセスの簡素化やツール導入による業務効率化手法を検討しましょう。
- ワークフローシステム導入による申請・承認業務の一元化
- ステータス管理による確認・催促の手間削減
- RPA活用による定型業務の自動化とミス防止
これらは、業務フロー改善を軸とした業務効率化手法として非常に効果的です。
業務効率化手法②:社内コミュニケーション改善
次に取り組みたい業務効率化手法は、社内コミュニケーションの改善です。会議や報連相を効率化することで、情報共有や意思決定のスピードが向上します。
- 会議の議題共有・時間制限・参加者絞り込み
- 報・連・相のフォーマット整備
- 社内SNSの活用によるナレッジ共有・情報連携
これらは、コミュニケーション改善を通じた業務効率化手法として有効です。
業務効率化手法③:タスク・時間管理の最適化
個人レベルでも取り組める業務効率化手法として、タスク管理や時間管理の最適化があります。
- 緊急度・重要度マトリクスによるタスク整理
- ポモドーロ・テクニックによる集中力維持
- TogglやRescueTimeなどの時間管理ツールによる作業時間の可視化・改善
これらの時間・タスク管理手法は、日々の業務を着実に効率化する効果があります。
業務効率化手法④:職場環境整備
最後に、意外と見落とされがちな業務効率化手法が「職場環境の整備」です。
5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)を実践し、作業環境を整えることで、無駄な動作や探し物の時間を削減できます。
- 5S活動による作業効率アップ
- 快適な照明・温度・デスク環境の整備
- 従業員のモチベーション向上・離職防止
職場環境を整えることは、生産性向上に直結する業務効率化手法として見逃せません。
日々の積み重ねが業務効率化手法としての成果に
ご紹介したように、業務フロー改善、コミュニケーション改善、タスク管理、職場環境整備など、業務効率化手法は多岐にわたります。
どれか一つだけではなく、現場の声を取り入れながら段階的・継続的に取り組むことが、大きな成果を生むポイントです。
業務効率化は、あらゆる側面から自社に合った対策を!
業務効率化においては「これだけやればOK」という万能策は存在しません。ですが、本記事で紹介したツールの活用、マニュアルの整備と運用、さらには外注の活用など、実践的で再現性のある手法を組み合わせることで、自社に合った効率化の道筋がきっと見えてくるはずです。
重要なのは、自社の現状と課題を正確に把握し、それに合った施策を段階的かつ柔軟に導入していくことです。完璧を目指すのではなく、まずは取り組みやすいところから始めることが成功への第一歩。まずは、現場での小さな非効率に目を向け、どの手法が活かせるかを社内で共有してみてください。今すぐにでも取り入れられる方法が、確実な変化を生み出すきっかけになります。
まず、「マニュアル作成で業務効率化を図りたいと考えている」「マニュアル作成なら、今すぐ取り入れられる」「マニュアルを効率よく整備したい」と感じたら、マニュアル作成のプロ集団であるmayclassに一度ご相談ください。専門知識と実績をもとに、貴社の課題に最適な解決策をご提案します。
▼こちらの記事もおすすめ▼