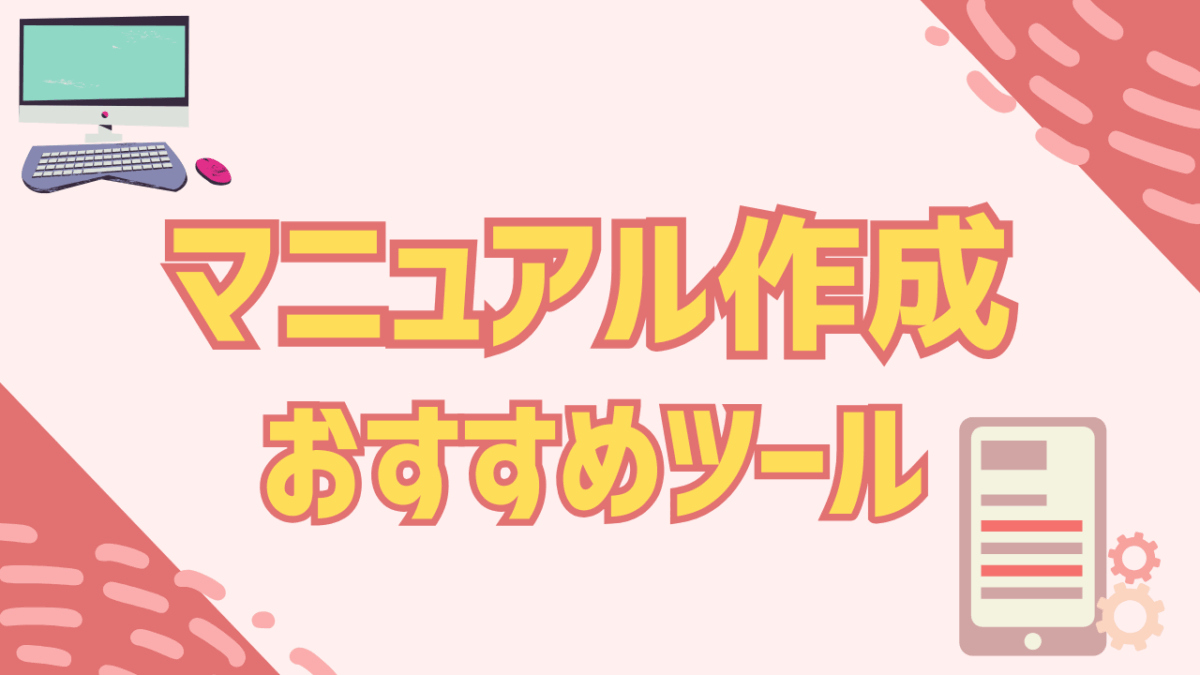業務効率化や人材育成に欠かせないマニュアルですが、作成には多くの時間と労力がかかるのも事実です。そのため、効率的に高品質なマニュアルを作成するには、適切なツールの活用が不可欠です。
本記事では、様々なニーズに対応するマニュアル作成ツールを厳選し、ランキング形式で紹介します。機能、価格、使いやすさ、サポート体制など多角的な視点から比較しているので、自社のニーズに最適なツールを見つける参考にして下さい。
この記事は、業務効率化や人材育成のための「マニュアル作成ツール」を選ぶ・使うための実践ガイドです。
導入目的の整理、必要機能・費用対効果・UI/UX・セキュリティ・サポート・事例のチェックポイントを解説しつつ、おすすめ有料ツール10選と無料ツール3選を紹介。さらに、導入後の体制づくり・テンプレ整備・レビュー/権限設定・更新・効果測定など、ツールを“入れて終わり”にしない運用のコツまで網羅しています。
マニュアル作成ツール選定のポイント

マニュアル作成ツールは、ただ機能が多ければ良いというわけではありません。自社の業務内容や目的にマッチしたものを選ぶことで、現場での定着率や運用のしやすさが大きく変わってきます。以下では、ツール選定時に確認しておきたい重要なポイントを、初心者にも分かりやすく解説します。
1. マニュアル作成ツール導入の目的を明確にする
まず最初に考えるべきは、「何のためにマニュアルを作るのか」という目的です。
操作マニュアル・業務マニュアル・新人教育用・FAQ・トラブル対応ガイドなど、用途によって求められる機能は大きく異なります。
例:
・操作手順を画像付きで解説したい → 画面キャプチャ機能や動画対応が必要
・教育用に使いたい → クイズ機能や進捗管理機能があると便利
目的を明確にすることで、選ぶべきマニュアル作成ツールの方向性が定まります。
2. 必要な機能が備わっているかをチェック
基本的なエディタ機能に加えて、以下のような機能があるかどうかも重要です。
- テンプレート機能:構造化された文書作成を効率化
- バージョン管理:更新履歴の追跡
- アクセス制御:部門ごとの閲覧・編集制限
- 共同編集:複数人で同時編集が可能か
- レビュー・承認フロー:公開前のチェック体制
- 多言語対応:グローバル対応が必要な企業向け
これらの機能が充実していればいるほど、運用も効率化されます。
3. マニュアル作成ツールの費用対効果を見極める
ツールには無料プラン・有料プランがありますが、価格と機能のバランスを見極めることが大切です。
- ユーザー数やストレージ容量によって課金が変動するか
- 初期費用はかかるか
- 無料トライアル期間はあるか
- 年額/月額のプラン選択肢
導入によってどの程度業務効率が上がるかを試算したうえで、費用対効果の高いツールを選びましょう。
4. 操作しやすいマニュアル作成ツールかどうか(UI/UX)
どんなに多機能なツールでも、「使いにくい」「操作方法が分かりにくい」では現場に定着しません。
直感的なUI(ユーザーインターフェース)と、シンプルで迷わないUX(ユーザー体験設計)がなされているかを事前に確認しましょう。
特に、ITリテラシーが高くないスタッフでもストレスなく操作できるかがポイントです。
5. セキュリティに対応したマニュアル作成ツールであるか
マニュアルには社内ノウハウや個人情報、内部手順など機密性の高い情報が含まれることがあります。
そのため、以下のようなセキュリティ機能が充実しているかをチェックしましょう。
- データ通信の暗号化(SSL対応)
- アクセス権限の細分化(ユーザー単位・部門単位)
- クラウドの保存先が信頼できるデータセンターか
セキュリティレベルの低いツールは、情報漏洩リスクに直結します。
6. サポート体制の充実度も確認しよう
導入後に「使い方がわからない」「トラブルが起きた」場合にすぐ相談できる体制が整っているかは大きな安心材料です。
- 専用サポート窓口(チャット・メール・電話)の有無
- 操作ガイドやFAQの充実度
- 導入初期のサポート(オンボーディング支援)の有無
サポートの質が高いツールは定着率も高く、長く使いやすい傾向にあります。
7. 導入事例・口コミ
公式サイトだけでは分からない「実際の使いやすさ」や「現場での活用方法」は、他社の導入事例やユーザーの声が参考になります。
- 同業種の企業での活用実績はあるか?
- 操作性や導入後の変化についてのレビューは好評か?
- 自社と規模が近い企業の成功事例はあるか?
事前にリサーチを行うことで、「導入してから後悔する」リスクを減らすことができます。
マニュアル作成ツールおすすめ10選
ここでは、機能性・価格・使いやすさ・サポート体制など多角的な観点から厳選したおすすめのマニュアル作成ツール10選を紹介します。
マニュアル作成ツール①:Teachme Biz(スタディスト)

- 概要:画像ベースでわかりやすい手順書を簡単に作成できるマニュアル作成ツール。
- 主な機能:画像編集、手順ごとのステップ構成、QRコード共有、多言語対応、アクセス解析。
- 価格:月額50,000円〜(プランによる)
- メリット:現場スタッフでも簡単に操作できる設計。教育・研修にも強い。
- デメリット:コストがやや高め。
- おすすめ:マニュアルのビジュアル化を重視する製造業・飲食業・サービス業。
マニュアル作成ツール②:Kibela(株式会社ビットジャーニー)

- 概要:ナレッジ共有に強い社内Wiki型マニュアル作成ツール。
- 主な機能:Markdownエディタ、タグ管理、社内SNS機能、チーム共有。
- 価格:無料プランあり、有料プランは月額1,100円/ユーザー〜。
- メリット:エンジニアに親しみやすいUI。導入コストも低め。
- デメリット:Wiki形式に慣れていない人には操作が難しい場合あり。
- おすすめ:スタートアップやIT企業でのナレッジ管理に最適。
マニュアル作成ツール③:Dojo(テンダ)
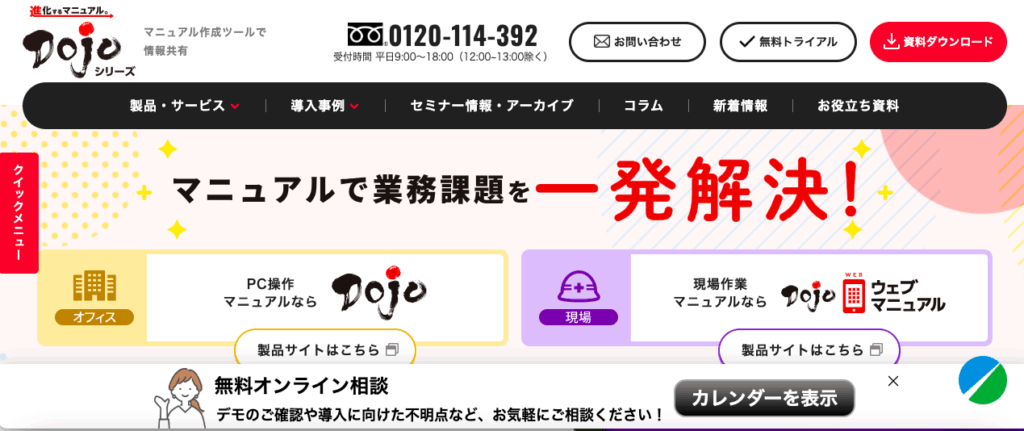
- 概要:マニュアル自動作成機能を備えた操作マニュアル特化型ツール。
- 主な機能:画面キャプチャ自動取得、操作手順書の自動作成、シナリオ形式出力、PDFエクスポート。
- 価格:月額要問い合わせ(オンプレミス/クラウドプランあり)
- メリット:ソフト操作マニュアルの作成が圧倒的に早い。
- デメリット:画像ベースの編集にややクセがある。
- おすすめ:業務システムの操作手順書作成が多い企業。
マニュアル作成ツール④:NotePM(プロジェクト・モード株式会社)

- 概要:社内マニュアル・ナレッジ共有に特化したクラウド型ツール。
- 主な機能:フォルダ階層管理、全文検索、タグ、アクセス権管理、テンプレート。
- 価格:月額500円/ユーザー〜(無料トライアルあり)
- メリット:検索性が高く、組織的な情報管理に向いている。
- デメリット:デザインやUIに若干の古さを感じる。
- おすすめ:マニュアルとナレッジを一元管理したい中小企業。
マニュアル作成ツール⑤:Confluence(Atlassian)
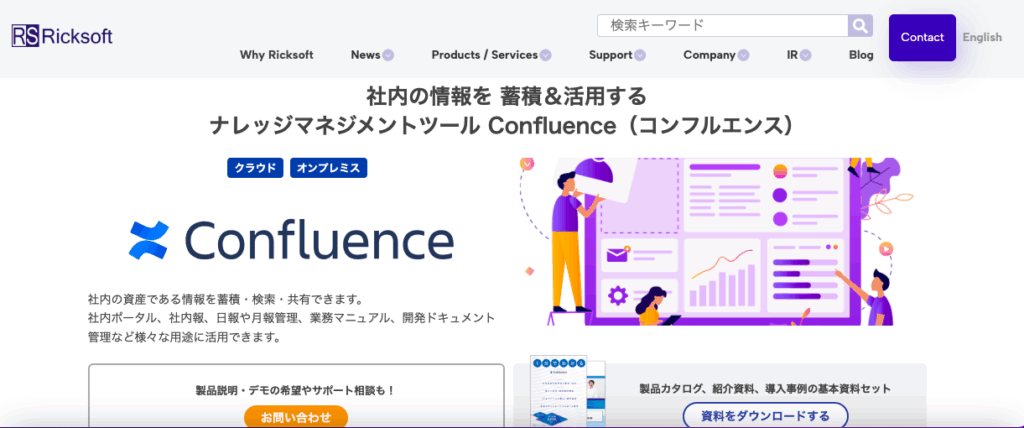
- 概要:ドキュメント・Wiki型のコラボレーションツール。
- 主な機能:テンプレート、多人数同時編集、Jiraとの連携、コメント機能。
- 価格:無料プランあり、有料は月額660円/ユーザー〜。
- メリット:IT系企業に強く、開発業務との連携が得意。
- デメリット:機能が多く、設定に慣れが必要。
- おすすめ:エンジニアチーム・開発部門での利用に最適。
マニュアル作成ツール⑥:トースターチーム(トースターチーム株式会社)

- 概要:日報・マニュアル・業務報告などの情報共有に最適な社内情報ツール。
- 主な機能:簡易エディタ、テンプレート、リアクション機能、閲覧状況の可視化。
- 価格:月額300円/ユーザー〜
- メリット:とにかく操作がシンプルで、現場スタッフでも使いやすい。
- デメリット:機能はやや限定的。
- おすすめ:スモールスタートでマニュアル運用を始めたい企業。
マニュアル作成ツール⑦:Qiita Team(Increments株式会社)

- 概要:社内情報共有とナレッジ蓄積に適したツール。
- 主な機能:Markdown記法、タグ付け、アクセス権限設定、検索機能。
- 価格:月額500円/ユーザー〜
- メリット:エンジニア文化に親しみがある企業にフィット。
- デメリット:非エンジニアには少し学習コストがある。
- おすすめ:開発チーム・IT系スタートアップ。
マニュアル作成ツール⑧:Helpfeel(Nota Inc.)

- 概要:FAQ・ヘルプ作成に特化したナレッジ共有ツール。
- 主な機能:検索最適化技術「意図予測検索」、FAQ作成支援、分析機能。
- 価格:要問い合わせ
- メリット:ユーザーからの問い合わせ削減に直結。
- デメリット:FAQ用途に限定される。
- おすすめ:カスタマーサポートや製品ヘルプを充実させたい企業。
マニュアル作成ツール⑨:Document360
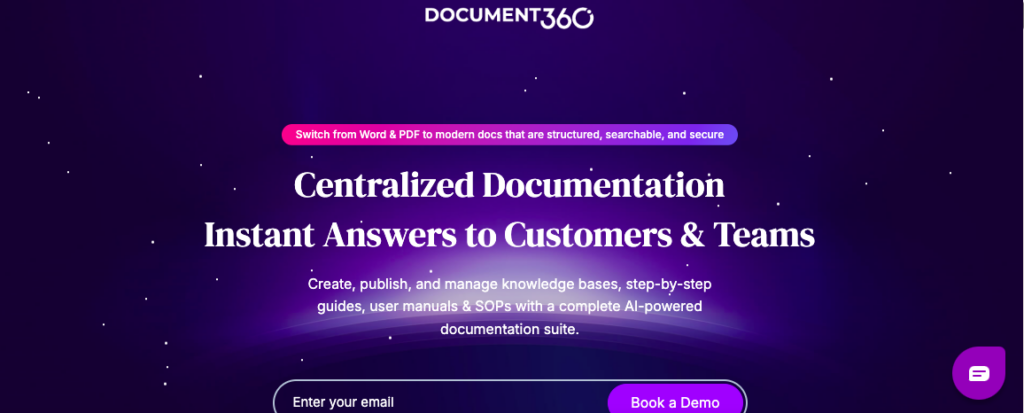
- 概要:オンラインヘルプやナレッジベース構築に優れたクラウド型ツール。
- 主な機能:Markdown、コンテンツ分類、バージョン管理、分析ダッシュボード。
- 価格:月額$99〜
- メリット:多言語対応と分析が強力。
- デメリット:海外製でUI表記にややクセがある
- おすすめ:グローバル対応が必要な中堅〜大企業。
マニュアル作成ツール⑩:SharePoint(Microsoft)
-1024x437.png)
- 概要:Microsoft 365に含まれる文書共有・マニュアル管理向けプラットフォーム。
- 主な機能:ドキュメント管理、チームサイト、アクセス制御、Office連携。
- 価格:Microsoft 365のプランに含まれる(要確認)
- メリット:Microsoft製品との親和性が高く、統合運用が可能。
- デメリット:セットアップや運用にIT知識が必要。
- おすすめ:すでにMicrosoft製品を導入済みの企業。
無料マニュアル作成ツール3選
コストを抑えてマニュアル作成を始めたい方には、無料で利用できるツールも多数あります。ここでは、無料プランでも十分に活用できるおすすめのツールを3つ紹介します。
無料マニュアル作成ツール①:Notion

- 概要:ノート・Wiki・タスク管理など多機能なオールインワンツール。
- 主な機能:ブロック式エディタ、ページリンク、共同編集、コメント、テンプレート。
- メリット:柔軟性が高く、個人からチーム利用まで対応。
- デメリット:構造が自由すぎて慣れるまでに時間がかかる。
- 無料版の制限:一部高度な権限設定や履歴管理に制限あり。
- おすすめ:個人事業主やスタートアップに最適。
無料マニュアル作成ツール②:esa.io

- 概要:チームでの知識共有に最適なMarkdownベースのツール。
- 主な機能:下書き・公開モード、カテゴリ分け、共同編集、タグ、API連携。
- メリット:エンジニアに親しみやすく、書きやすい。
- デメリット:非エンジニアにはややハードルが高い。
- 無料版の制限:2週間のトライアル提供後、有料プランに移行。
- おすすめ:開発チームでのドキュメント共有に。
無料マニュアル作成ツール③:Google ドキュメント

- 概要:Googleが提供するオンライン文書作成ツール。
- 主な機能:リアルタイム共同編集、コメント、バージョン履歴、自動保存。
- メリット:操作が簡単で、Googleアカウントがあればすぐに使える。
- デメリット:構造化やナレッジ管理には不向き。
- 無料版の制限:基本機能は無料で利用可能。
- おすすめ:簡易的なマニュアル作成を始めたい中小企業や教育機関。
参考:Googleドキュメントでマニュアルを作成・共有する方法!効率化のコツとおすすめツールを徹底解説
マニュアル作成ツール導入後の運用と活用
マニュアル作成ツールを導入しただけで「業務効率化が実現する」と考えるのは早計です。ツールの導入はあくまでもスタート地点にすぎません。効果を最大化するためには、社内での運用体制を整え、継続的に改善していく仕組みづくりが不可欠です。以下に、導入後の具体的な運用・活用のポイントを紹介します。
1. マニュアル作成体制の構築
まずは、「誰が・何を・どのツールで」**作成するのかを明確に定めましょう。
たとえば「各部署にマニュアル担当を1名ずつ配置し、月1回のレビュー会を実施する」など、明確な体制を整えることで、属人化や作成漏れを防げます。あわせて、作成・レビュー・承認・公開の流れを標準化しておくことで、スムーズな運用が可能になります。
2. テンプレートの作成と活用
マニュアル作成において重要なのは、「作る人が違っても、読みやすい内容に統一されていること」です。
そのために、あらかじめ見出し構成・フォント・アイコン・用語統一ルールなどを含んだテンプレートを用意しておくと、作成スピードが向上し、品質も安定します。SaaS型ツールであれば、テンプレート機能が用意されていることも多いため、活用を検討しましょう。
3. レビューフローの確立
作成されたマニュアルは必ずレビューを通してから公開することが基本です。
内容の誤りや抜け漏れを防ぐために、作成者以外の第三者がチェックする仕組みを導入しましょう。
さらに、実際の運用現場のメンバーからフィードバックを受け取ることで、「机上の空論」にならない、実用性の高いマニュアルが完成します。
4. アクセス権限の設定
マニュアルの中には、機密情報や内部手順など、誰でも閲覧できるべきでない内容が含まれることもあります。
クラウド型のマニュアル作成ツールであれば、閲覧・編集・公開の権限をユーザー単位やチーム単位で細かく設定することができます。
情報漏えいや誤操作のリスクを防ぐためにも、適切なアクセス管理は不可欠です。
5. 更新頻度の設定とバージョン管理
マニュアルは「作って終わり」ではなく、「更新して育てるもの」です。
業務の変更やシステムのアップデートに応じて、定期的な見直しスケジュール(例:3か月に1回、システム変更時には即時対応など)を設定しましょう。
更新履歴を残す機能を活用すれば、過去の内容を参照しながら正確な差分管理も可能になります。
6. 効果測定と改善
作成・運用されたマニュアルが実際に現場で活用されているかどうかを可視化することも重要です。
たとえば以下のようなデータを定期的にチェックしましょう:
- 閲覧数や検索キーワード
- 「よく見られているマニュアル」や「まったく見られていないマニュアル」
- 問い合わせ件数の変化
- 利用者アンケートによる満足度や改善要望
これらの情報をもとに、現場の声を反映しながらマニュアルの改善を継続していくことで、より価値のあるナレッジ資産へと育っていきます。
自社に最適なマニュアル作成ツールを選ぼう
マニュアル作成は、業務の標準化・効率化・教育の質向上に直結します。そのためには、目的や体制に合った「ツール選び」がとても重要です。この記事を参考に、機能や価格、サポート体制を比較検討し、最適なマニュアル作成ツールを活用してください。
「自社に合うツールが分からない」「導入しても運用できるか不安…」という場合は、外部のマニュアル作成サービスを活用するのもひとつの選択肢です。
業務の棚卸しから構成設計、ツール選定、運用支援まで一貫してサポート可能なmayclassなら、はじめてのマニュアル整備も安心。現場に定着する、実用性の高いマニュアル作成をお手伝いします。

ーーー
[Latest Edition] 10 Best Manual Creation Tools Selected by Professionals (2025)
▼こちらの記事もおすすめ▼
おすすめマニュアル作成アプリ・ツール10選!業務効率化を促進しよう