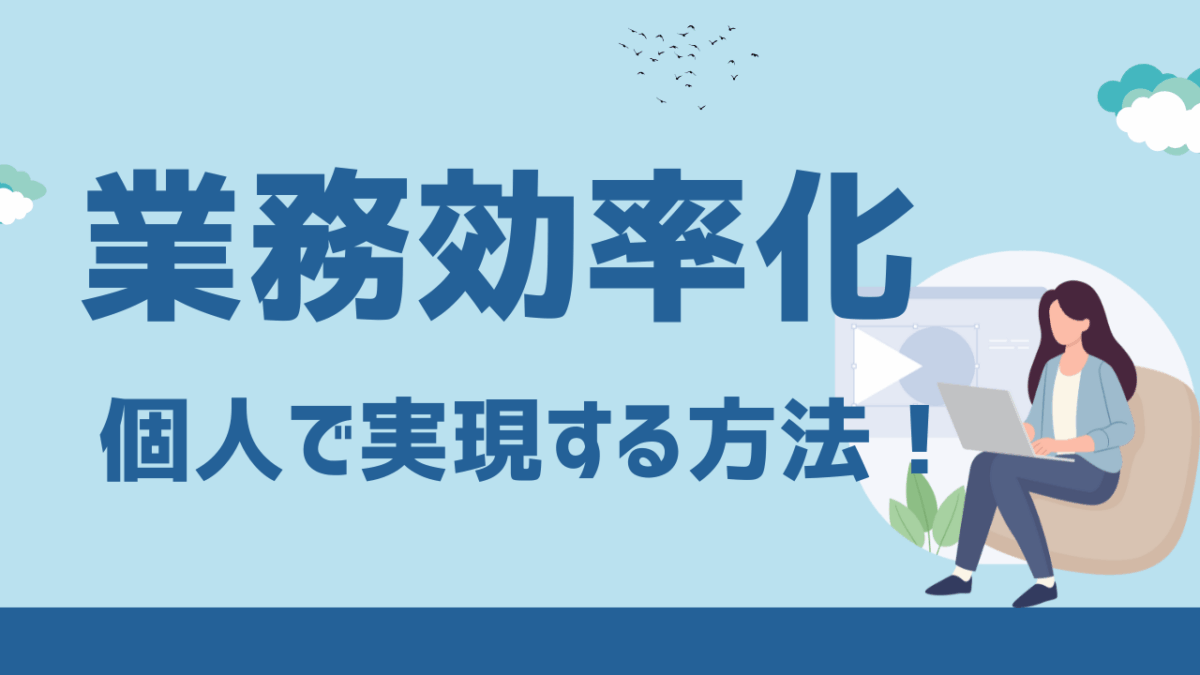「仕事が終わらない」「毎日やることに追われている」「ツールを使っても結局うまく続かない」ーそんな悩みを抱えている人は少なくありません。
業務効率化は“組織全体で取り組む課題”と考えられていましたが、今や一人ひとりが“業務効率化を個人でどう実現するか”が問われています。特に、リモートワークや副業の増加によって、個人の業務効率がそのまま成果に直結する時代です。
この記事では、個人ができる業務効率化の基本から、役立つツール、習慣づくりのコツまでを実践的に解説します。Excelや自動化ツールも活用しながら、「仕事が早くて正確な人」へと変わる方法を一緒に探っていきましょう。
本記事は、「仕事が終わらない」「効率化ツールが続かない」と悩むビジネスパーソン向けに、個人で実践できる業務効率化の基本と実践法を解説しています。
タスク・時間管理、ルーティン化や自動化、ツール活用(Notion・Excel・Zapierなど)を通じて“成果と時間を両立する働き方”を提案。効率化を「時短」ではなく「自分の時間を取り戻す手段」として捉え、成長やキャリアアップにつなげる内容です。
なぜ個人に業務効率化が求められるのか
働き方の多様化(テレワーク・副業・フリーランス)
近年、働き方は大きく変化しています。出社するのが当たり前だった時代から、リモートワーク、またフリーランス、複業や副業など、雇用形態から仕事をする場所までさまざまな形で“働き方を選べる時代”に移りました。
この自由度の高さは魅力的ですが、同時に「自己管理の難しさ」も増しています。上司の目が届かない環境では、タスクの優先順位を自分で判断し、仕事のペースを自ら作り出す必要があります。
たとえばテレワーク中、集中が切れてSNSやメールに時間を取られてしまう人という人も多いのではないでしょうか。また、家で仕事をしていると、ちょっとした家事や家族の声かけによって中断してしまうということもあるでしょう。
業務効率化とは、そうした“見えないロス”を減らし、限られた時間で成果を出す力を鍛えることです。
成果主義の拡大と個人の生産性向上ニーズ
企業の評価制度も変わりつつあります。かつては「長時間働く=頑張っている」と評価されることもありましたが、今では「限られた時間でどれだけ成果を出せるか」が重視されています。
その背景には、ITの進化と競争の激化があります。AIや自動化ツールが普及する中、単純作業は機械に任せ、人は“付加価値を生み出す仕事”に集中しなければ生き残れません。
つまり、個人の業務効率化は「評価を上げるためのスキル」でもあり、「キャリアを守るための武器」でもあるのです。
業務効率化がプライベートの時間創出につながる
効率化の本当の目的は、「仕事を早く終えること」ではなく「時間を取り戻すこと」です。
たとえば1日30分のムダを減らせば、1週間で2.5時間、1か月で10時間以上の時間が生まれます。その時間を資格取得や運動、家族との時間にあてれば、人生の満足度は確実に上がるでしょう。 “効率化=我慢”ではなく、“自分らしい時間の確保”なのです。
個人でできる業務効率化の基本ポイント
タスク管理を徹底する(ToDo・優先順位付け)
多くの人が抱える共通課題が「やるべきことの整理ができていない」ことです。
頭の中だけでタスクを覚えていると、忘れたり、優先順位を誤ったりして、結果的に時間を浪費します。
そのため、まずはToDoリストの可視化から始めましょう。
「今日やること」「今週中にやること」「長期的に取り組むこと」を分けて書き出します。
さらに有効なのが「アイゼンハワー・マトリクス」です。これはタスクを「緊急度」と「重要度」で4つに分類する方法で、次のように考えます。
- 緊急かつ重要:すぐやる(例:今日の会議資料作成)
- 重要だが緊急でない:計画的に進める(例:スキルアップの勉強)
- 緊急だが重要でない:人に任せる、または短時間で片づける(例:簡単な報告メール)
- どちらでもない:削る(例:目的のないSNSチェック)
この考え方を使うだけで、優先順位の迷いがなくなり、仕事のスピードが確実に上がります。
時間管理術を取り入れる(ポモドーロ・時間ブロッキング)
仕事を効率よく進めるには「時間の管理」も重要です。人は長時間集中し続けることが難しいため、集中と休憩のリズムを設計する必要があります。
有名なのが「ポモドーロ・テクニック」です。 25分集中+5分休憩を1セットとし、4セット終えたら15〜30分の休憩を取ります。 短時間集中を繰り返すことで、集中力が途切れにくくなり、「ダラダラ作業」から抜け出せます。タイマーアプリ(例:Tide、Forestなど)を使うと続けやすくなります。
もう一つおすすめなのが「時間ブロッキング」です。 Googleカレンダーなどに“作業ブロック”をあらかじめ予約しておき、その時間は他の予定を入れないようにします。
「9:00〜10:30は資料作成」「10:30〜11:00はメール対応」といった形でブロックしておくと、時間の見通しが立ちやすく集中が途切れません。
これらの時間管理術は、スケジュールを「守る」だけでなく、「決断のエネルギーを節約する」目的もあります。1日の計画が明確になれば、悩む時間が減り、その分だけ行動に集中できるのです。
無駄を減らす仕組みづくり(ルーティン化・自動化)
業務の中には、メール送信、データ集計、ファイル整理といった毎日繰り返す定型作業が少なからずあります。こうした作業は、できるだけ「考えずにできる」状態を目指しましょう。
まずはルーティン化です。「朝出社したら最初にタスク確認」「昼前にメール返信」「夕方に進捗整理」など、行動の順番を固定化するだけで、判断に使う脳のエネルギーを減らせます。
次に自動化です。 Excelなら「マクロ」や「関数」、Googleスプレッドシートなら「Google Apps Script(GAS)」を使えば、日々繰り返す作業を自動化できます。
例えば、毎日同じフォーマットの報告書を作るなら、GASを使ってスプレッドシートの内容を自動メール送信するよう設定すれば、普段5分かかっている作業を5秒で終えることができます。
さらに、プログラミングが苦手な人でも使えるノーコード自動化ツール「Zapier」なら、「フォーム入力→スプレッドシート自動記録」「新しいメール→Slack通知」などをワンクリックで設定できます。
これらは最初に仕組みを作る手間はありますが、長期的には“時間を生み出す投資”になります。
業務効率化に役立つおすすめツール
タスク管理・プロジェクト管理ツール(Notion、Trello、Todoistなど)
タスクや進捗を整理するツールは、個人の生産性を大きく左右します。
Notion

ドキュメント・タスク管理・データベースを一体化できる万能ツールです。自分専用の「仕事管理ダッシュボード」を作成でき、日報・アイデアメモ・ToDo管理をすべて一箇所にまとめられます。
チーム共有も簡単で、プロジェクト進捗の見える化にも役立ちます。
参考:Notionでマニュアルを作成する方法!テンプレート活用・データベース連携完全ガイド
Trello

「かんばん式」でタスクをカード化し、進捗を“見える化”するのに優れています。
たとえば「やること」「進行中」「完了」の3列を作り、カードを動かしていくだけでタスク状況がひと目でわかります。
Todoist

シンプルながら強力なToDo管理アプリで、期限や優先度の設定、繰り返しタスクなども直感的に扱えます。スマホ・PC間の同期もスムーズで、日常の仕事整理にも最適です。
情報整理・メモツール(OneNote、Evernote)
効率化の基本は「探す時間を減らすこと」です。必要な情報がどこにあるか分からない状況は、最も大きなロスです。
OneNote
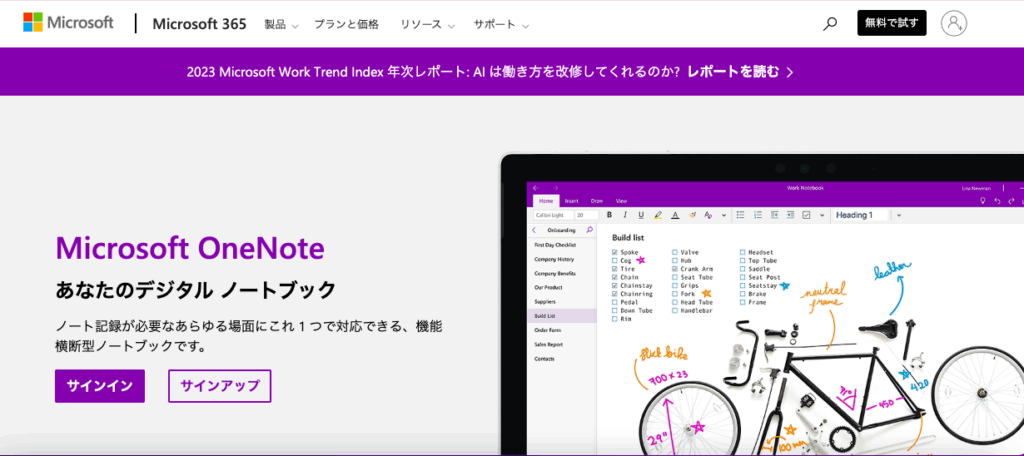
Microsoft 365ユーザーにとって最適なメモ管理ツール。WordやExcelとの連携がスムーズで、会議メモから資料作成メモまで一元化できます。
手書きメモも取り込めるため、紙のノート派にも移行しやすいのが特徴です。
参考:OneNoteでマニュアル作成!テンプレート活用で効率的に仕組み化する方法
Evernote
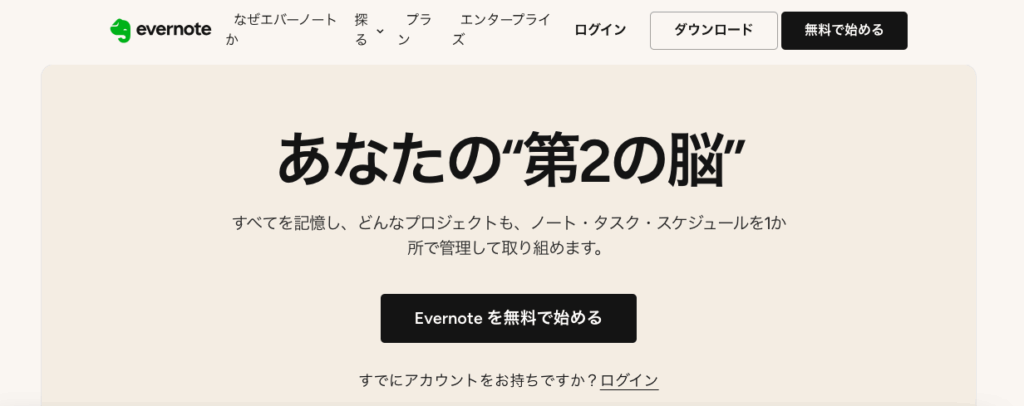
情報の“倉庫”として優秀なツールです。テキスト・画像・PDF・音声など、あらゆる形式の情報を保存でき、検索精度も高いところが使い勝手がいい点です。データをどこに入れたか忘れてしまっても、探す時間がゼロになります。ビジネスアイデアや議事録を一箇所にまとめておくと、思考の整理が格段に早くなります。
自動化・時短ツール(Google Workspace、GAS、Zapier)
Google Workspace(旧G Suite)
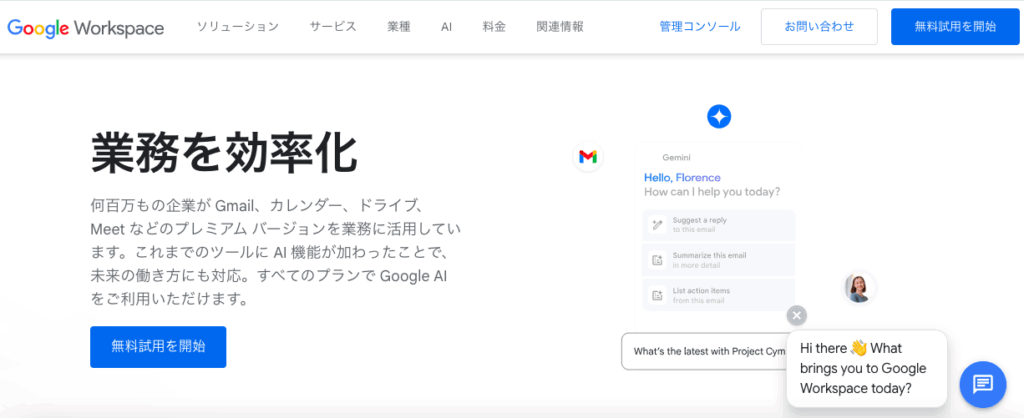
業務効率化の宝庫です。 Googleスプレッドシートやドキュメント、フォームなどを連携させれば、社内の情報共有を一気に効率化できます。
GAS(Google Apps Script)

Google製品間を自動で連携させるスクリプト機能です。 たとえば、フォーム入力結果を自動で集計→メール通知する、日報をスプレッドシートから自動生成するなど、アイデア次第で業務を大幅に省力化できます。
参考:GASによる業務効率化とは?メリット・活用シーン・導入ステップを解説
Zapier、IFTTT

プログラム不要の自動化をしたい場合におすすめのツールです。「SlackでメンションされたらToDoリストに追加」「フォーム入力で顧客リスト更新」などをクリックだけで設定できます。 まさに“デジタル秘書”のように仕事を支えてくれます。
個人が取り入れやすい業務効率化習慣
朝一の集中タイムを活用する
脳科学的に、朝は最も集中力が高い時間帯だといわれています。仕事の初めにまずメールを開くという人も多いかと思いますが、この最も集中している時間帯に、何も考えずにできるメールチェックや雑務をやるのはもったいないことです。
午前中の1〜2時間を「思考が必要な仕事(企画・分析・執筆など)」に充てるだけで、1日の生産性が劇的に上がります。
また、朝一に“最も重い仕事”を終えることで、心理的負担も減り、午後以降が軽く感じられます。 これは「イート・ザ・フロッグ」という考え方で、「最も嫌なことを先に片づけると、その後が楽になる」という効率化の鉄則です。
デジタル断捨離と環境整備
業務効率化を妨げる最大の敵は、「情報の散らかり」です。 パソコンのデスクトップに無数のファイルが並び、スマホからはひっきりなしに通知音が鳴る…。このようなデジタル上のノイズは、目には見えなくても確実に集中力を奪っています。 これが、いわば現代の「デジタル疲れ」です。
そこで意識したいのが「デジタル断捨離」です。 デジタル断捨離とは、パソコンやスマホの中にある不要なデータ・アプリ・通知を整理し、作業に必要なものだけを残すこと。情報を減らすことで、思考のスペースを増やすのです。
たとえば、週に一度はデスクトップやダウンロードフォルダを整理し、不要なファイルは削除またはクラウドに移します。メールボックスも同様に、古いスレッドやメルマガをアーカイブしておくと検索効率が格段に上がります。
スマホは、仕事に不要なアプリの通知をオフにし、SNSのチェック時間を決めましょう。それだけで、集中が途切れる回数がぐっと減り、1日の作業密度が変わります。
また、仕事用とプライベート用でアカウントやデバイスを分けるのも効果的です。オンとオフの境界をデジタル上でも明確にすることで、頭が切り替わりやすくなり、無意識のストレスを防げます。
もちろん、物理的な環境整備も同じくらい大切です。 机の上に常に資料やケーブルが山積みでは、集中する前に疲れてしまいます。 使うものだけを手の届く範囲に置き、不要なものは引き出しや棚に。 照明を少し明るくし、椅子の高さを自分に合わせるだけでも、集中の持続時間が伸びることがあります。
デジタルも現実も“整理する”という点では同じです。モノと情報を減らすことで、思考がシンプルになり、判断スピードも上がります。 デジタル断捨離は、単なる片づけではなく、「集中力を取り戻すための仕組みづくり」のひとつです。
アウトプット前提のインプット(学習効率化)
個人で業務効率化を進めるうえで欠かせないのが、「学んだことをどう活かすか」という視点です。 どれだけ知識を詰め込んでも、実際の仕事に使えなければ意味がありません。忙しい日々の中で成果を上げるためには、“学習効率”──つまり「学びを最短で成果に変える力」が必要です。
効率のいい人は、インプットとアウトプットを切り離して考えません。 たとえば、Excelの新しい関数を学んだなら、その日のうちに報告書や集計に使ってみる。 ツールの使い方を知ったなら、翌日のミーティング準備で実際に使ってみる。 このように、学んだ内容をすぐ実践に落とし込むことで、知識を「使えるスキル」として定着させているのです。
また、“実践→振り返り→改善”の流れを繰り返すことで、理解度が深まり、次に似た状況に出会ったときも迷わず動けるようになります。 これは単にスキルを覚えるだけでなく、“問題を自分で解決できる力”を育てることにつながります。学ぶだけで行動に移さないと、人はすぐに忘れてしまうものです。 「あとで使うかもしれない知識」より、「今すぐ使えるスキル」に変えるほうが、圧倒的にコスパが高いのです。
学習効率を高めるとは、“必要な知識を必要なときに使えるようにしておくこと”。それが、結果的に仕事のスピードと質を同時に上げる「個人の業務効率化」につながるのです。
業務効率化で得られるメリット
成果の質とスピードが上がる
業務効率化の最大の成果は、仕事のスピードと質が同時に向上することです。
作業プロセスが整理され、ムダな手戻りや確認の抜けが減ることで、1つひとつのタスクに集中できる時間が増えます。結果として、同じ時間でもより多くの成果を生み出せるようになり、仕事の完成度そのものも上がります。
たとえば、タスク管理を徹底した人ほど「優先順位の判断」に迷う時間が減ります。 また、テンプレートや自動化を取り入れることで、毎回ゼロから考える必要がなくなり、「考えるべき仕事」にエネルギーを集中できます。
この“集中の質”こそが、成果の精度を引き上げるカギなのです。 単に早く終わらせるのではなく、「正確さ」と「再現性」を両立できるようになります。 チェックの時間を十分に取れることでミスも減り、納期前のバタつきや修正対応も少なくなります。
結果として、上司やクライアントからの信頼も高まり、「この人に任せれば安心」と思われる存在になるでしょう。効率化とは、“スピードを上げる技術”であると同時に、“信頼を積み重ねる習慣”でもあるのです。
ストレスや残業の削減
多くの人が感じる日々のストレスの正体は、「タスクが多いこと」ではなく「全体が整理されていないこと」にあります。 終わりの見えない仕事、優先順位が不明確なタスク、いつまでに何をすべきかわからない状況は、脳に大きな負担を与えます。
業務効率化によってスケジュールやタスクが“見える化”されると、頭の中がスッキリし、必要以上の焦りが消えます。 ToDoリストやカレンダーで仕事を「見える形」にするだけで、心理的な安心感が得られるのです。
さらに、タスクを細分化して「今日はここまで」と区切る習慣をつけると、終業後も仕事を引きずりにくくなります。結果的に残業が減り、ワークライフバランスが整い、疲労やストレスの慢性化を防ぐことができます。
厚生労働省の調査によると、長時間労働が続く人ほど集中力が低下し、作業効率が20〜30%落ちるというデータもあります。 つまり、効率化は“働く時間を削る”というより、“集中できる時間を確保する”ことなのです。
効率化の先にあるのは、単なる時短ではなく心の余裕です。仕事が整うと生活も整い、パフォーマンスの質が長期的に安定します。
自己成長やキャリア形成にプラス
業務効率化を続ける人ほど、自分の「仕事の組み立て方」を常に見直しています。 これは単なる“時短テクニック”ではなく、“自己成長の習慣”そのものです。
効率化を意識すると、自然と「何に時間をかけるべきか」「どの業務を改善すべきか」を考えるようになります。 この“振り返りの思考”が、成長を加速させます。
たとえば、Excelの関数を活用して作業を自動化した経験があれば、次はGoogle Apps ScriptやZapierのような高度な自動化にチャレンジする──そうした積み重ねがスキルアップの連鎖を生みます。
また、効率化を通じて「自分で仕事を設計できる力」が身につくのも大きな利点です。与えられたタスクをこなすだけでなく、業務フロー全体を最適化できる人は、チームや組織にとって貴重な存在です。 上司や同僚からの信頼が厚くなり、リーダー職やプロジェクトマネージャーといった新たな道も開けるでしょう。
こうした力は職場が変わっても通用します。ツールや環境が違っても、効率化の原理原則は普遍的だからです。「自分の時間を設計できる人」は、どんな職場でも成果を出せるということが、長いキャリアを支える最大の資産になります。
効率化は、単なる“早く終わらせる技術”ではなく、“成長をデザインする思考”でもあります。 時間をうまく使える人は、自分の人生をもうまく使える。だからこそ、業務効率化はキャリアアップの基盤であり、将来の選択肢を広げる力になるのです。
業務効率化は小さな習慣から始めよう
業務効率化は特別なスキルではありません。 毎日の中で少しずつ「仕組み」を整えることが、最も確実な方法です。「朝の30分を集中時間にする」「ToDoリストを毎朝更新する」「Excelのショートカットを1つ覚える」このような個人レベルでの業務効率化を積み重ねることで、やがて“圧倒的に仕事ができる人”をつくります。
業務効率化とは、仕事を削ることではなく、“自分の時間を取り戻す”ことです。 その第一歩を、今この瞬間から始めてみましょう。
参考:業務効率化に役立つエクセルツール&機能12選|時短・ミス削減を実現する使い方とは?
ーーー
How to Achieve Work Efficiency as an Individual:
Habits and Tools to Get Work Done Faster and More Accurately
業務改善・業務効率化ならmayclass
現場の悩みは、放っておいても自然に解決するものではありません。
Tōka(トーカ)は、AIと人の力を掛け合わせ、業務を“透過(可視化)”し、“灯火(改善の方向性)”をともす業務改善サービスです。
AIが業務データを整理・分析し、専門アドバイザーが現場の声を反映。「課題を正確に見つけ」「無理なく続けられる改善」を一緒に設計します。
「課題の整理から手伝ってほしい」
「AIを使って業務改善を進めたい」
そんな方に丁寧にサポートいたします。

▼下記記事もおすすめ▼
Geminiで画像生成はできる?使い方・特徴・無料版と有料版の違いを徹底解説