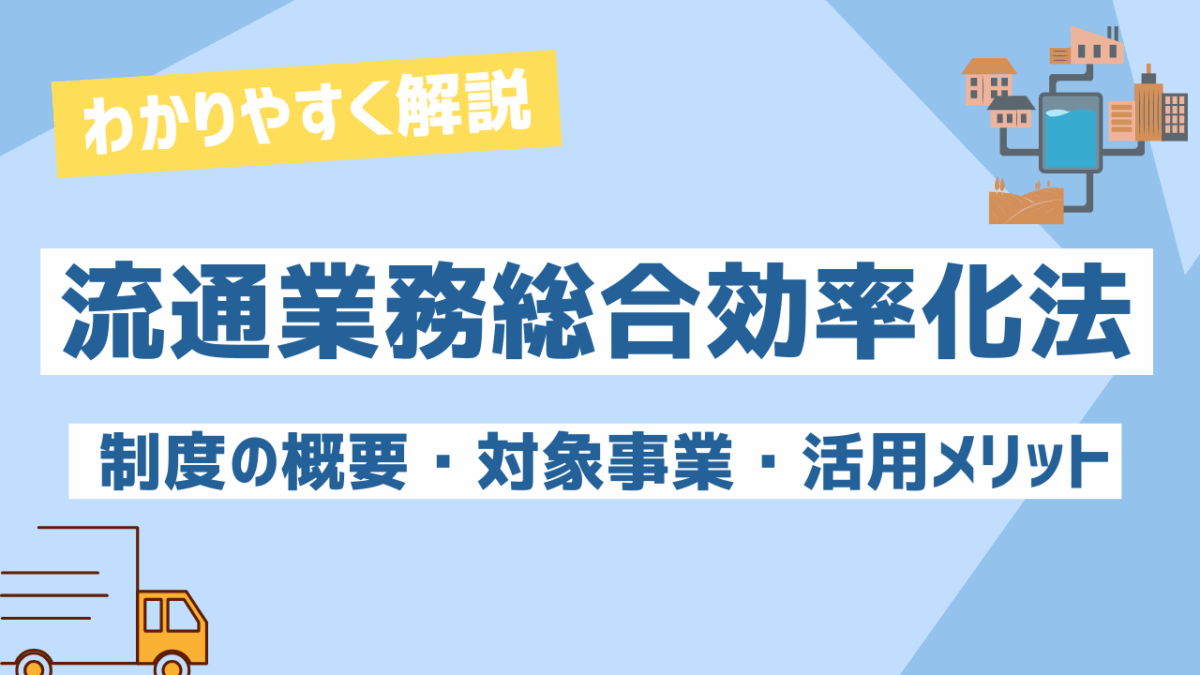近年、「物流2024年問題」や脱炭素社会の実現に向けた動きが加速する中、企業の物流・流通体制に対する見直しが急務となっています。こうした背景から注目されているのが、「流通業務総合効率化法」です。
この法律は、物流業務の効率化と環境負荷の軽減を両立させることを目的とした制度で、認定を受けた事業には税制優遇や補助金といったさまざまな支援が用意されています。荷主、運送事業者、倉庫業者などが連携し、共同配送やモーダルシフト、物流拠点の集約といった取り組みを通じて、持続可能な物流ネットワークの構築を目指す企業にとって、大きなチャンスとなる制度です。
本記事では、流通業務総合効率化法の概要から対象事業、認定のメリット、取得までの流れ、さらには実際の活用事例までをわかりやすく解説します。物流の効率化と環境対応を両立したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
物流2024年問題の対応が求められるなか、「流通業務総合効率化法」は物流の効率化と環境負荷削減を同時に実現するための国の制度として注目されています。物流拠点の集約、共同配送、モーダルシフト、IT活用など複数企業の連携施策が認定対象となり、税制優遇・補助金などの支援が受けられます。制度の概要、対象、メリット、申請手順、活用ポイントまでをわかりやすく解説しました。
流通業務総合効率化法とは

流通業務総合効率化法(正式名称:流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律)は、物流に関する施設整備や業務の効率化を促進するために制定された国の制度です。物流拠点の統合や共同配送の導入など、複数の事業者が連携して行う流通業務の高度化を支援することで、環境負荷の軽減や人手不足への対応を目指します。
認定を受けた事業には、税制優遇や補助金、金融支援といったさまざまなインセンティブが用意されており、国土交通省が中心となって制度の運用・審査を行っています。
この制度は特に、サプライチェーン全体での最適化を図りたい企業にとって有効な手段となっており、持続可能な物流体制の構築やカーボンニュートラル実現の後押しとなる重要な施策です。
制度の目的と背景(物流2024年問題、環境対策)
流通業務総合効率化法が注目される背景には、物流業界を取り巻く深刻な課題があります。その一つが「物流の2024年問題」です。これは、働き方改革関連法によるトラックドライバーの時間外労働規制が2024年に本格施行されることで、ドライバー不足や輸送能力の低下が懸念される問題です。これにより、従来の物流体制では対応が困難になりつつあります。
また、地球温暖化対策として、物流業界にも温室効果ガスの排出削減が求められています。輸送効率の向上やモーダルシフト(鉄道・船舶への転換)によって、環境負荷を抑えた持続可能な物流体制を築く必要があります。
こうした背景を踏まえ、国は複数企業が連携した物流効率化の取り組みを後押しするため、本制度を整備しました。効率化と環境対応を同時に進めるための施策として、企業の成長と社会的責任の両立を支援しています。
誰が対象となるのか(事業者・物流施設など)
流通業務総合効率化法の対象となるのは、物流に関わる幅広い事業者や施設です。主な対象は以下のとおりです。
まず、荷主企業(メーカーや小売業者など)が挙げられます。自社で商品を製造・販売し、物流を外部委託している企業でも、物流の集約や共同配送といった効率化の取り組みに主体的に関わることで、制度活用の対象になります。
次に、運送事業者や倉庫事業者といった物流を担うプレイヤーです。配送の合理化や保管機能の統合、モーダルシフトの導入など、実行力のある改善を行う事業者が支援の対象となります。
さらに、物流拠点や流通センターを新設・統合する企業も、認定の対象です。物流施設の集約により、無駄な輸送や在庫を削減することで、全体の流通業務の効率化が期待されます。複数企業が連携してプロジェクトを推進するケースも多く、単独では制度活用が難しい中小企業でも、他社と協力して効率化の成果を上げることが可能です。
関係する法律・国土交通省の役割
流通業務総合効率化法は、2005年に制定された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」(通称:流通業務総合効率化法)に基づく制度です。物流業界の課題解決や環境対策を国の政策として推進するための法的な枠組みとして位置づけられています。
この法律の主な目的は、流通業務に関わる施設や業務を一体的・効率的に運営する体制を整え、物流の最適化を図ることです。具体的には、複数の事業者が連携して行う物流施設の集約や共同配送の取り組み、ITやモーダルシフトを活用した輸送の効率化などが想定されています。制度の実施主体は国土交通省であり、認定の審査・評価・認可を担っています。また、制度の活用にあたっては、地方自治体や経済産業省などの他の行政機関、商工会議所、物流団体とも連携しながら支援体制を整えています。
企業がこの制度を活用する際には、国土交通省のガイドラインや認定フローに基づいた申請が求められ、実際の運用においても行政との密接な連携が重要となります。
流通業務総合効率化法の対象となる事業
流通業務総合効率化法では、物流の最適化と環境負荷の低減を目的として、さまざまな事業活動が対象となります。特に、複数の事業者が連携して取り組む効率化プロジェクトが重視されており、認定を受けることで税制優遇や補助金の対象にもなります。
物流拠点の集約・共同配送の取り組み
同一エリア内に複数存在する物流拠点を統合し、拠点間の無駄な移動や重複作業を削減する取り組みは、代表的な対象事業です。また、異なる荷主企業同士が共同で配送を行う「共同配送」は、トラックの積載効率を高めるとともに、CO2削減にも大きく貢献します。特に都市部での配送効率改善に効果的です。
モーダルシフトやITを活用した効率化事業
環境負荷の大きいトラック輸送から、鉄道や船舶などへの「モーダルシフト」は、法の趣旨に合致した取り組みのひとつです。また、輸配送の最適化に向けてIoT・AI・クラウドシステムなどを活用したIT化も、効率化事業として対象となります。これにより、業務の見える化・自動化が進み、持続可能な物流体制を構築することが可能になります。
荷主・運送事業者・倉庫事業者の連携プロジェクト
物流の効率化は、荷主企業・運送会社・倉庫業者の連携なくして成り立ちません。業種や立場を超えたプロジェクトが認定の対象とされており、関係者が協力して業務フローを見直し、共同で改善策を講じる体制づくりが重視されています。このような連携は、法制度の活用にとどまらず、業界全体の競争力向上にもつながります。
認定を受けるメリット
流通業務総合効率化法に基づいて認定を受けると、企業にとってさまざまな経済的・社会的なメリットが得られます。制度の利用は、単なる助成措置にとどまらず、企業の成長戦略や環境対応の一環としても活用可能です。
税制優遇(固定資産税の軽減など)
認定事業者は、物流拠点や配送センターなどの特定施設にかかる固定資産税の軽減措置を受けることができます。例えば、新設や集約した物流施設に対して一定期間、税負担が軽くなることで、初期投資に対するハードルを下げる効果が期待されます。また、その他の減税制度との併用により、コスト面でのメリットを最大化することも可能です。
補助金・融資の活用が可能に
認定を受けた事業は、国や地方自治体が提供する補助金や低利融資の対象となります。これにより、物流システムのIT化や設備投資に必要な資金を確保しやすくなり、事業推進のスピードが向上します。認定は、公共性の高いプロジェクトであることの証明にもなり、資金調達の場面での信用力向上にもつながります。
環境対応やSDGs文脈での企業価値向上
持続可能な社会の実現に貢献する取り組みとして、認定制度の活用は企業の社会的評価にも大きく寄与します。とくに、CO2削減や廃棄物削減など環境対策に積極的な企業は、ESG投資やSDGs経営に取り組む大手企業・投資家からの注目を集めやすくなります。法認定は、単なる制度活用にとどまらず、企業ブランディングや採用活動においても有効なアピールポイントになります。
流通業務総合効率化法に基づく認定取得の流れ
制度を活用するには、国土交通省または所轄自治体に申請し、正式な認定を受ける必要があります。以下では、認定取得までのステップと注意点を整理します。
認定申請の手順と必要書類
申請の第一歩は、事業計画の策定です。計画には、取り組む内容(例:共同配送、モーダルシフトなど)や期待される効果(例:CO2削減率、効率改善度)を明記します。提出書類としては、事業計画書、施設の図面、運用体制の概要、関係事業者との協定書などが求められることが一般的です。
また、計画内容が法の目的に合致しているかどうかを示す説明資料も重要です。申請書類の準備には時間を要するため、早めの着手が望まれます。
審査基準と所要期間
審査では、計画の実現可能性、環境・効率への貢献度、関係事業者との連携体制などが評価されます。内容に不備や不明瞭な点があると、追加説明や修正対応が必要になることもあります。
審査期間は自治体や案件の内容によって異なりますが、概ね1か月〜3か月程度を想定しておくとよいでしょう。制度利用を検討する場合は、事前にスケジュールに余裕を持って準備を進めることが重要です。
自治体・専門機関との連携の重要性
申請手続きや計画作成の段階で、自治体や商工会、物流専門家などとの連携を図ることで、認定取得の精度とスピードが格段に高まります。制度の細かな解釈や、採択されやすい計画の立て方についてアドバイスを受けられることが多いため、積極的に外部の知見を活用するのが有効です。
流通業務総合効率化法を活用するためのポイント

補助金ありきで考えないこと
制度を活用する企業の中には、「補助金をもらえるから」という理由だけで取り組むケースもありますが、これは本質的な活用とは言えません。目的はあくまで、物流の効率化と環境負荷の軽減を図ることにあります。補助金はあくまでそのための後押しであり、制度の主旨を理解したうえで、自社の将来につながる取り組みを計画することが重要です。
自社の課題と照らし合わせて制度を選ぶ
流通業務総合効率化法は、さまざまな事業形態・連携方式に対応している柔軟な制度です。共同配送、モーダルシフト、IT導入など、自社が抱える課題や改善したいポイントに合わせて、制度のどの枠組みが最適かを見極める必要があります。制度に合わせて取り組みを変えるのではなく、自社の課題を起点に制度をどう活用できるかを考えることが、実効性の高い計画につながります。
事前相談と専門家の活用でスムーズに申請を
制度を活用するうえでの申請手続きや計画立案は、専門的な知識が求められる場面も多くあります。申請書類の準備が煩雑で、何から始めればよいかわからないという企業も少なくありません。こうした場合には、国土交通省の地方整備局や自治体の相談窓口、または物流・申請支援に強い専門家に事前相談を行うことで、スムーズな準備が可能になります。制度の最新動向や審査傾向も把握できるため、採択率向上にもつながります。
流通業務総合効率化法で持続可能な物流体制を構築しよう
効率化と脱炭素の両立を目指す制度活用の意義
物流業界は、慢性的な人手不足とドライバーの労働時間規制、さらには環境負荷低減という複雑な課題に直面しています。流通業務総合効率化法は、これらの問題を同時に解決し、持続可能な体制への移行を後押しする制度です。単なるコスト削減ではなく、社会的責任を果たしながら自社の競争力を高める手段として、制度の活用には大きな意義があります。
共同配送やモーダルシフトの導入、ITによる業務効率化など、各施策は環境対応と業務改善の両輪で動きます。制度を上手に活用すれば、長期的な経営基盤の強化にもつながるでしょう。
中小企業こそ活用すべき制度としての可能性
大手企業と比べてリソースが限られる中小企業にとって、流通業務総合効率化法は非常に心強い制度です。補助金や税制優遇、専門機関の支援といった仕組みを活用することで、単独では難しかった取り組みも現実のものになります。
特に中小企業同士の連携による共同配送や倉庫機能の統合など、スケールメリットを生むプロジェクトにおいて制度の後押しは効果的です。自社の課題に対して前向きに取り組む姿勢があれば、制度は強力な支援ツールとなります。
制度活用から業務改善の実行まで、mayclassがサポートします
流通業務総合効率化法は、単なる認定制度ではなく、企業の物流改革を後押しする大きなチャンスです。しかし、制度の理解や申請、実際の業務改善プロジェクトの設計・実行までを一貫して進めるには、専門的な知見と現場感が求められます。
mayclassでは、業務の可視化から改善プランの策定、ツール導入支援まで、現場に根づく業務改善をトータルでサポートしています。制度活用とセットで、持続可能な物流体制の構築を本気で目指したい方は、ぜひ一度ご相談ください。

ーーー
What Is the Comprehensive Logistics Efficiency Act? Overview, Target Businesses, and Benefits Explained
▼こちらの記事もおすすめ▼
業務効率化は“数値化”から始まる!成果を見える化する方法と実践ステップ