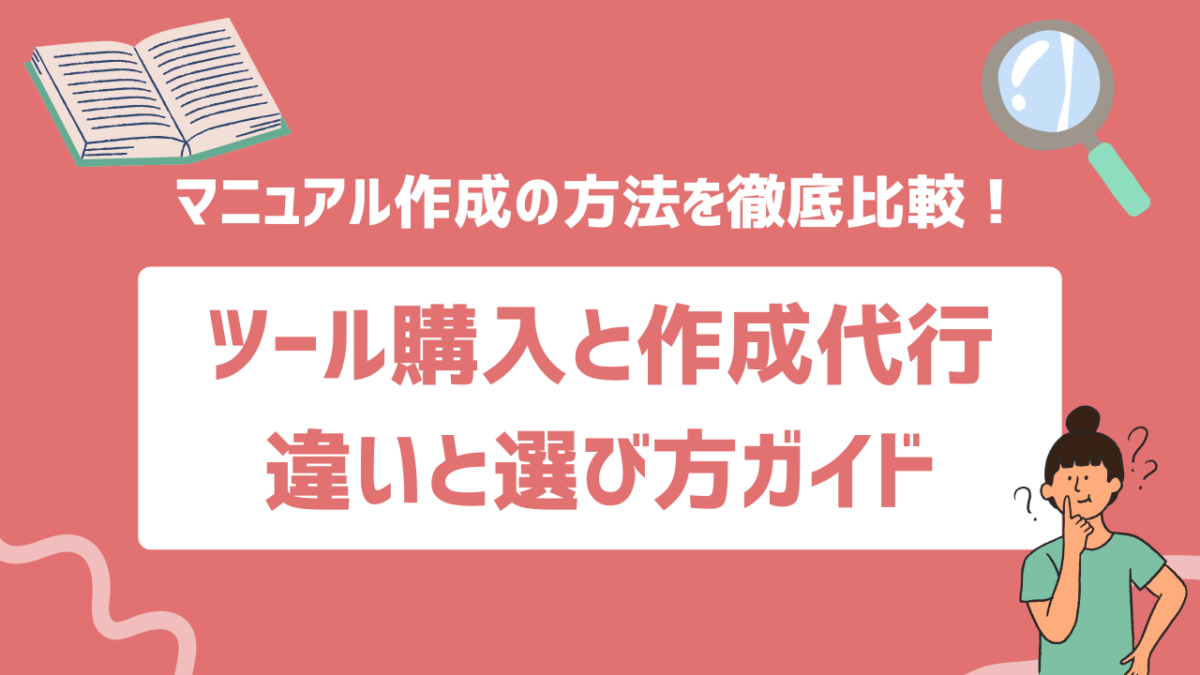業務の効率化やマニュアルの整備を進める際、「ツールを購入して自社で作成するべきか」「専門業者に作成を代行依頼するべきか」で悩むことはありませんか?それぞれにはメリットとデメリットがあり、業種や企業規模によって最適な選択肢が異なります。
本記事では、ツール購入と作成代行の違いを徹底比較し、それぞれの特徴や活用法、選び方のポイントを解説します。自社に合った効率的な方法を見つけ、生産性向上を実現するための参考にしてください!
この記事では、「自社でマニュアルを作る」か「外部に代行を頼む」かで迷っている方向けに、それぞれのメリット・デメリットをわかりやすく比較しています。
自作なら自由度が高くコストを抑えられますが、時間とスキルが必要。代行なら短期間で高品質に仕上がりますが、費用や打ち合わせが発生します。
「どちらの方法が自社に合うかわからない」「効率よくマニュアルを整備したい」という方におすすめの記事です。
ツール購入と作成代行の違いとは?
マニュアルを作成する方法は、大きく分けて「マニュアル作成ツールを購入し自社で作成する方法」と「マニュアル作成を外注する方法(作成代行)」の2つがあります。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
マニュアル作成ツール購入の特徴
ツール購入とは、クラウド型やオンプレミス型のマニュアル作成ソフトを導入し、社内スタッフがマニュアルを作成・運用する方法です。マニュアル作成ツールを導入することで、自社の業務に適したマニュアルを自由に作成・管理できる柔軟性があります。
代表的なマニュアル作成ツールの例
クラウド型:Teachme Biz、NotePM など
オンプレミス型:Adobe RoboHelp、MadCap Flare など
クラウド型はインターネットを通じてどこからでもアクセスでき、複数人での同時編集やリアルタイムの更新が可能なため、リモートワークやチームでの管理に適しています。一方、オンプレミス型は社内サーバーに導入するタイプで、セキュリティ管理を厳格にしたい企業に向いています。
メリットとしては、
- 初期費用が比較的低く、手軽に導入できる:サブスクリプション型のツールが多く、低コストで始められるため、導入のハードルが低い。
- 必要なときに社内で編集・更新が可能:業務の変化に合わせて柔軟にマニュアルを更新できるため、情報の鮮度を保ちやすい。
- 自社独自の仕様に合わせたカスタマイズがしやすい:業務フローや社内ルールに沿ったオリジナルのマニュアルを作成できる。
- 多様なフォーマットに対応:PDF、HTML、動画など、用途に応じた形式でマニュアルを作成できるツールも多い。
- 検索性・アクセス性が向上:クラウド型ツールでは、キーワード検索やタグ付けにより、必要な情報にすぐにアクセスできる。
などが挙げられます。
デメリットとしては、
- 専門知識がないと、わかりやすいマニュアルを作るのが難しい:文章作成スキルやデザインセンスが求められるため、担当者の能力に依存する。
- 社内での教育や管理が必要:ツールの使い方やマニュアルの適切な作成手順について、社員教育を行う必要がある。
- 担当者のスキルや業務負担によってクオリティが変動する:経験の浅い担当者が作成すると、内容に一貫性がなくなり、品質にばらつきが生じる可能性がある。
- ツールの選定・導入に時間がかかる場合がある:最適なツールを選ぶために比較検討が必要で、試行錯誤を重ねることが求められる。
- ランニングコストが発生する:クラウド型の場合、月額または年額の料金がかかるため、長期的なコスト負担を考慮する必要がある。
などが挙げられます。
マニュアル作成ツールについては、【最新版】現場が選んだ!マニュアル作成ツールおすすめ10選(2025年版)でも詳しくご紹介しています。こちらも併せてご覧ください。
マニュアル作成代行の特徴
マニュアル作成代行とは、プロの専門家にマニュアル作成を依頼し、業務フローに最適化された高品質なマニュアルを外注する方法です。社内リソースの負担を軽減し、短期間で統一された分かりやすいマニュアルを手に入れることができます。
メリットとして
- 専門知識を持ったプロが作成するため、質の高いマニュアルが手に入る:業界のノウハウを持つ専門家が作成するため、構成やデザインが最適化され、誰にとっても理解しやすいマニュアルが完成します。
- 社内で作るよりも早く、効果的なマニュアルが納品される:専門のマニュアル作成会社に依頼することで、社内で試行錯誤しながら作成するよりも短期間で完成するため、スピーディーに活用できます。
- 社内のリソースを使わずに済むため、他の業務に集中できる:マニュアル作成のために社員の時間を割く必要がなく、本来の業務に集中できるため、生産性向上にもつながります。
- 業務フローを整理し、より効率的な運用が可能:専門家が業務プロセスを分析し、最適なマニュアル構成を提案するため、マニュアル作成を通じて業務改善にもつながることがあります。
- 多言語対応や動画マニュアルの作成も可能:グローバル展開をしている企業では、多言語対応のマニュアルが必要な場合がありますが、作成代行ではこれらにも柔軟に対応できます。
などが挙げられます。
デメリットとしては
- マニュアル作成の専門家に依頼するため、それなりのコストが発生する:社内で作成する場合に比べて初期費用がかかるため、予算の確保が必要です。
- 修正・更新のコストがかかる:一度完成したマニュアルの改訂が必要になった際、追加の費用が発生する場合があります。
- 社内でマニュアルを随時更新するのが難しく、追加費用が発生することも:マニュアルの内容を頻繁に更新する必要がある場合、外注先に依頼するたびにコストが発生するため、長期的な運用計画が求められます。
- 社内の独自ノウハウの反映に時間がかかる:外部の専門家が作成するため、自社の独自のルールや文化を正しく反映するには、十分な情報共有が必要となります。
などが挙げられます。
導入・運用の違い
| 項目 | ツール購入 | 作成代行 |
| 初期費用 | 比較的低い(サブスク型が多い) | 高い(プロに依頼するため) |
| 作成負担 | 社内スタッフが対応(時間・スキルが必要) | 外部のプロに任せられる |
| 導入スピード | 運用開始まで時間がかかる | 短期間で利用可能 |
| 品質 | スタッフのスキル次第でばらつきが出る | 高品質なマニュアルが納品される |
| 運用・更新 | 社内で自由に編集可能 | 追加費用がかかる場合がある |
マニュアル作成ツール購入が向いているのはこんな人
ツールを購入してマニュアルを作成する方法は、社内に知識やリソースがある企業に適しています。まず、マニュアル作成のスキルを持つスタッフが社内にいる場合、ツールを活用することで効率的に作成・更新が可能です。特に、既存の業務手順を理解し、それを整理して分かりやすく伝えるスキルがある社員がいる場合は、ツールを活用した方がスムーズです。
また、長期的な運用を見据えて、自社仕様のマニュアルを作成・管理したい場合にも適しています。マニュアルを自社独自のルールや文化に基づいて作成し、必要に応じて柔軟に改訂できるため、常に最新の情報を維持しやすくなります。さらに、初期コストを抑えたい企業にもおすすめです。ツールの導入には多少の費用がかかるものの、作成代行に比べると一般的に低コストで済みます。また、一度導入すれば追加コストなしで社内の誰でもマニュアル作成が可能になるため、コストパフォーマンスが高い選択肢となります。
マニュアル作成代行が向いているのはこんな人
作成代行は、社内リソースが不足している、または専門的な知識が必要な企業に適した選択肢です。マニュアル作成の時間やノウハウが社内にない場合、プロの専門家に依頼することで、質の高いマニュアルを短期間で手に入れることができます。特に、専門的な業務や複雑なプロセスを伴う場合は、プロの視点で整理・構築されたマニュアルが業務効率化に大きく貢献します。
また、短期間で高品質なマニュアルを完成させたい場合も作成代行が有効です。自社で作成しようとすると、構成の考案や文章作成に時間がかかり、担当者の負担が大きくなることがあります。一方、作成代行では経験豊富な専門家が短期間で完成させるため、スピーディーに活用できるようになります。
さらに、社内リソースを確保しながら業務を進めたい場合にも作成代行は有効です。マニュアル作成を自社で行うと、担当者が本来の業務と並行して対応しなければならず、負担が増大します。外部に依頼することで、社内のリソースを他の重要な業務に集中させることができ、全体的な生産性向上につながります。また、多言語対応や動画マニュアルなど、特殊なフォーマットを求める場合も、専門家に依頼することでより高品質なコンテンツを作成することが可能です。
ツール購入と作成代行、どちらを選ぶべきか?

ここからはマニュアル作成ツールの購入と作成代行の選定基準について解説します。
選定基準1:目的とゴールの明確化
マニュアル作成や業務効率化の目的を定めることが重要です。教育用として従業員の研修に活用するのか、業務手順書として日常の業務標準化に役立てるのかを明確にし、それが短期的な導入なのか、長期的な運用を視野に入れたものなのかを決めることが大切です。
選定基準2:社内リソースとスキルの有無
社内にマニュアル作成のスキルや十分な時間があるかどうかを判断する必要があります。自社スタッフにスキルと時間がある場合、ツール購入により継続的に管理できる可能性があります。しかし、専門知識やリソースが不足している場合、プロの代行サービスを利用することで、質の高いマニュアルを短期間で作成することができます。
選定基準3:予算とコストパフォーマンス
コスト面も重要な要素です。初期費用を抑えたい場合、ツール購入の方が低コストで導入できます。しかし、長期的な運用を考えた場合、代行サービスを利用することで、時間削減による費用対効果が高くなる可能性があります。
選定基準4:対応範囲やフォーマットの特異性
紙媒体、Webマニュアル、動画コンテンツ、多言語対応など、作成するマニュアルがどのような形式を求められているかによって、ツールや代行の選択肢が変わってきます。
例えば、コストを抑えつつ社内でノウハウを蓄積したい中小企業ではツール購入が適しています。一方で、業務の専門性が高く、短期間で高品質なマニュアルが必要な大企業では、作成代行を活用することで効率的な業務推進が可能になります。
自社に適した方法でマニュアルを作成しよう
ツール購入と作成代行には、それぞれ異なるメリットとデメリットがあり、自社のリソースや目的に応じた適切な選択が業務効率化の鍵となります。本記事で紹介した基準やポイントを参考に、マニュアル作成の最適な方法を選び、業務改善を進めましょう。
ーーー
Manual Creation Methods Compared: How to Choose Between Tools and Outsourcing Services
見やすくわかりやすいマニュアルを作成するならmayclass
mayclassでは、経験豊富な業務改善アドバイザーが、貴社のニーズに合わせたマニュアルを提供します。
1.プロによるヒアリング
マニュアル作成のプロが、貴社の業務内容を丁寧にヒアリングします。これにより、業務の特性やニーズを正確に把握し、適切な内容を盛り込むことができます。
2.優先度に基づくマニュアル化
業務の優先度を見極め、重要な業務から順次マニュアル化を進めます。これにより、最も必要な情報を早急に整備し、業務の効率化を図ります。
3.わかりやすいデザイン
マニュアルのデザインにおいて、視覚的にわかりやすいレイアウトやフォーマットを提案します。これにより、情報が整理され、読者が理解しやすくなります。
mayclassと共に、業務の効率化を図り、組織の成長を加速させましょう。

▼こちらの記事もおすすめ▼
【業務マニュアル作成のコツ】完璧な目次の作り方ガイド!項目例もご紹介
見やすいマニュアルの作り方 3 原則!わかりやすいレイアウトのコツ