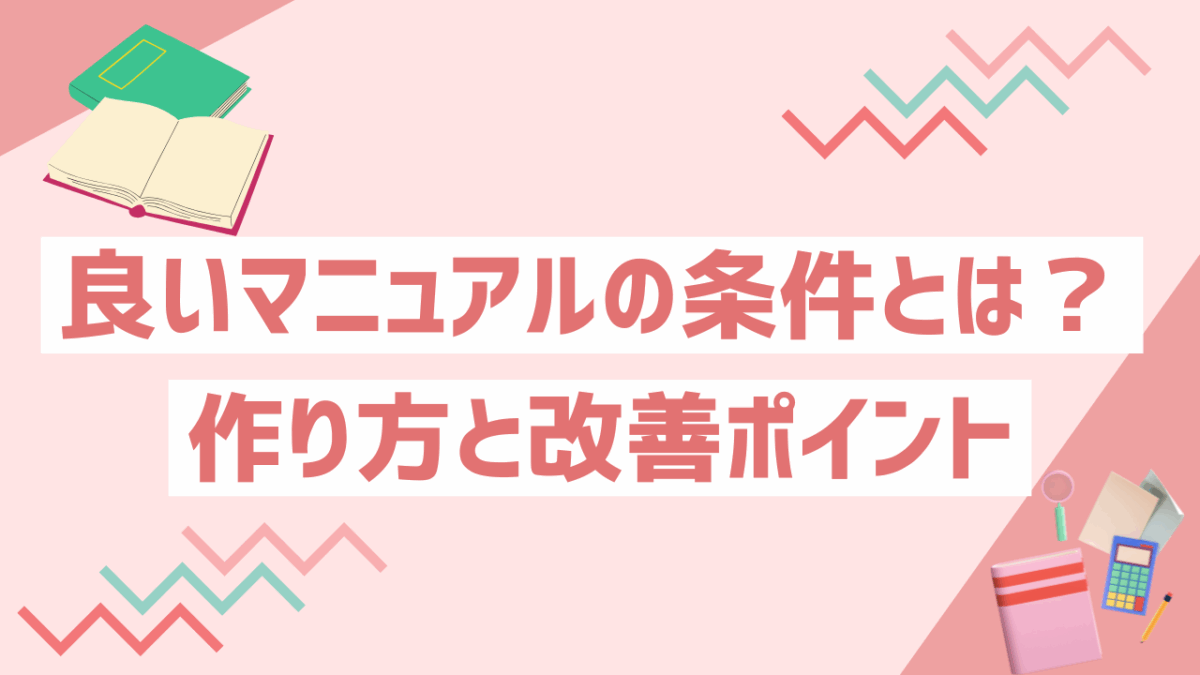マニュアルは「読むもの」ではなく「使うもの」です。しかし、現場ではせっかく作ったマニュアルが開かれないまま眠っていたり、内容が古くて参考にならないといった声が少なくありません。中には「マニュアル通りにやったのに失敗した」「結局ベテランに聞かないと分からない」といった不満も聞かれます。つまり、ただ存在しているだけでは意味がなく、「実際に役立つマニュアル」でなければなりません。
本記事では「良いマニュアル」の条件を整理し、その作り方と改善のポイントを徹底的に解説します。単なる文書作成ではなく、業務効率化や人材育成を支える仕組みとしてマニュアルを捉えることが大切です。良いマニュアルを作成したい、改善したいとお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。
「現場で本当に使われる“良いマニュアル”とは何か」と、その作り方・運用のポイントを整理しました。
マニュアルは「読むもの」ではなく、新人でもその場で迷わず作業でき、誰が見ても同じ品質で仕事を再現できる“仕組み”として捉えることが重要です。単なる説明書ではなく、業務の標準化・教育・品質維持を支える“現場のインフラ”であるという視点が、良いマニュアルづくりの第一歩です。
良いマニュアルの条件とは?
良いマニュアルとは「誰が読んでも迷わず作業できるマニュアル」です。新人が初めてその業務を担当するとしても、ページを開いた瞬間に流れが理解でき、手順通りに作業を進められる状態を目指す必要があります。ここで重要なのは、文章の正確さや丁寧さだけでなく、情報の整理方法や見やすさ、さらに更新のしやすさまで含めて設計されているかどうかです。
例えば、業務フローが複雑なコールセンター業務を考えてみましょう。コールセンターでは、顧客からの問い合わせ内容が多岐にわたります。次に何を確認するべきか迷ったとき、良いマニュアルがあれば即座に確認でき、適切な対応に結びつきます。逆に、分厚い冊子に断片的な情報が散らばっているだけでは、緊急時に開いても役に立ちません。
つまり、良いマニュアルは「業務を標準化し、誰が担当しても同じ品質で作業を再現できる仕組み」として機能することが条件になります。この視点を持つことが、質の高いマニュアルを作り上げる第一歩となるのです。
なぜ「良いマニュアル」が必要なのか
業務を円滑に進め、組織全体のパフォーマンスを高めるためには、属人的なやり方に頼るのではなく、誰もが同じ基準で行動できる仕組みが欠かせません。その基盤となるのが「マニュアル」です。単なる手順書にとどまらず、作業の再現性を高め、品質のばらつきを防ぎ、新人教育や人材育成を効率化する役割も果たします。つまり、良いマニュアルがあるかどうかは、組織の効率性や安定性、ひいては顧客満足度に直結する重要な要素なのです。
業務効率化・標準化におけるマニュアルの役割
企業活動において、業務が人に依存してしまうと、担当者が不在のときに作業が滞ったり、成果物の品質にばらつきが出たりします。例えば製造業では、マニュアルがなければ作業員ごとに異なる方法で製品を作ってしまい、品質の安定性を欠く原因になります。また、飲食店業においても、同じ品質の料理を提供するうえで、当然レシピは不可欠ですが、表現の仕方も重要です。「適量の塩を振る」とだけ書かれたマニュアルを想像してください。人によって「適量」の感覚は違います。その結果、料理の味がばらつき、顧客満足度が下がる原因になります。これを「小さじ1/2の塩を加える」と数値化すれば、誰が調理しても同じ味を再現することができます。
マニュアルは作業を標準化し、誰が対応しても一定の成果を出せるようにする役割を持っているのです。
また、教育の現場においてもマニュアルは欠かせません。指導係が新入社員に一から口頭で説明し続けるのは大きな負担ですが、良いマニュアルがあれば「まずはこれを見ながらやってみて」という教え方が可能になります。学習者側も、実際に手を動かしながら学ぶことによって理解度が格段に上がります。
つまり、良いマニュアルは組織全体の生産性を底上げするインフラとも言えるのです。
マニュアルが使われない理由と課題
一方で、せっかくマニュアルがあっても、現場で活用されていないというケースも多く存在します。その理由としては、「文章が専門的で難しく、読む気になれない」「説明が抽象的で、結局どうすればいいのかが分からない」「図や写真がなくイメージが湧かない」といったものです。さらに「情報が古く、現状と乖離している」というケースも珍しくありません。あいまいな記述が多く、不十分な情報が多い…、こうした課題が重なると「マニュアルは役に立たない」という評価につながり、誰も参考にしなくなり、結果として使われないマニュアルとなってしまいます。
良いマニュアルの5つの特徴
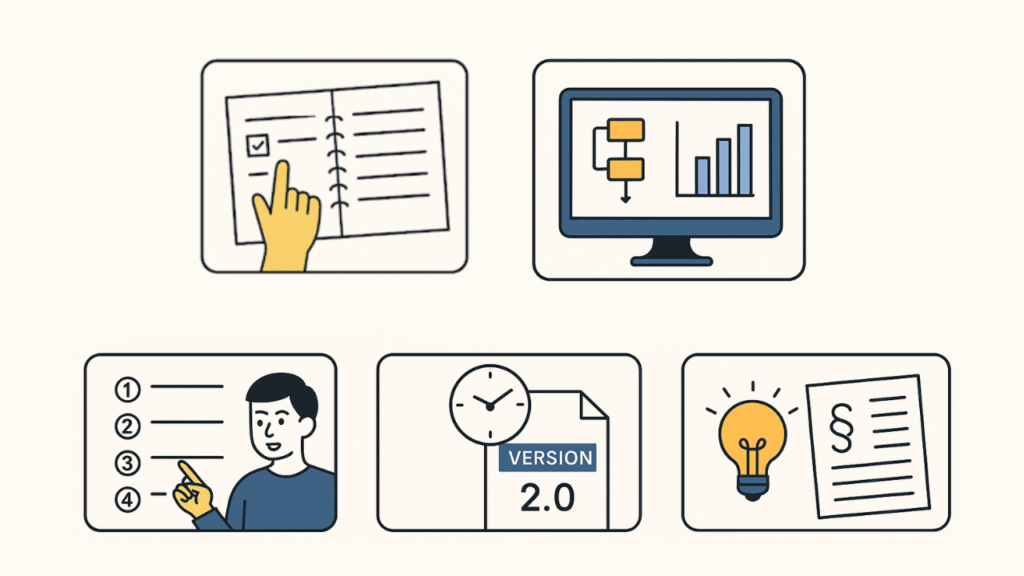
マニュアルと一口に言っても、その質には大きな差があります。単に手順を羅列しただけのものでは、現場で活用されず形骸化してしまうケースも少なくありません。一方で、誰もが理解しやすく、現場の業務をしっかり支える“良いマニュアル”は、組織全体のパフォーマンスを大きく底上げします。では、現場で本当に役立つマニュアルにはどのような共通点があるのでしょうか。ここでは、良いマニュアルに欠かせない5つの特徴を整理しながら解説していきます。
誰でも理解できる明確な言葉で書かれている
良いマニュアルは、専門知識がなくても理解できる明快な言葉で書かれています。「確認する」「保存する」「押す」といった具体的な動作を記載し、抽象的な表現を避けることが大切です。
例:曖昧な表現と具体的な表現
- ✖ 悪い例:「設定を適切に調整する」
- 〇 良い例:「画面右上の『設定』ボタンを押し、チェックボックスに✓を入れる」
また、略語や専門用語を使う場合は、必ず説明を添えることが必要です。IT分野のマニュアルでは「API」や「キャッシュ」といった言葉が頻繁に使われますが、初心者にとっては理解の妨げになります。注釈や補足説明を入れることで、誰でも読み進められるマニュアルになります。
図解や画像で視覚的に理解できる構成
文字だけの説明では限界があります。例えばソフトウェアの操作手順を言葉だけで説明されても、多くの人は途中で混乱してしまいます。また、Excelでの関数入力手順を「セルに関数を入れて…」と文章で説明しても、初心者には分かりにくいものになります。そこでキャプチャ画像やフローチャートを加えると、直感的に理解できるようになります。特に作業画面をそのまま示すスクリーンショットは効果的です。
| 例:ExcelでのSUM関数 1. セルA10を選択 2. 数式バーに「=SUM(A1:A9)」と入力 3. Enterキーを押す |
さらに、複雑な工程は動画で補足すると理解度が大幅にアップします。飲食店の調理手順や工場の設備操作など、動作が伴う業務は特に動画が役立ちます。視覚情報を取り入れることで、文章を補完し、記憶への定着率も高まります。
手順が時系列で整理されている
実際の作業手順に沿って時系列で整理されていると、読んだ人がそのまま行動に移しやすくなります。例えばシステム設定の手順を解説する場合は、以下のように順を追って説明します。
| 例:アカウント登録の流れ 1. 登録フォームを開く 2. 氏名・メールアドレスを入力 3. 確認メールを開き、URLをクリック 4. パスワードを設定する |
このように順を追って説明すると、誰でも迷わず作業を進められます。
もし順序が前後していたり、前提条件が後から出てきたりすると、読み手は混乱します。結果として「結局この通りにやってもうまくいかない、同じようにならない」という事態を招いてしまいます。良いマニュアルは、読み手がそのまま手を動かせる「シナリオ」のように構成されていることです。
更新履歴やバージョン管理が徹底されている
マニュアルは、一度作ったら終わりではありません。業務の流れや使用するツールは、常に変化しています。そのため、更新履歴やバージョン番号を明示し、最新情報であることを保証することが欠かせません。そうすることで、現場で「どの情報が正しいのか」を迷うことがなくなります。
例えばクラウドシステムのUIが変わった場合、古いマニュアルを参考にすると操作画面が一致せず混乱を招きます。「2025年8月更新」「バージョン1.3」など記載し、定期的な更新と明確なバージョン管理を行いましょう。これが、マニュアルを「生きた情報」として維持する秘訣です。また、履歴を残すことで「どの部分が変わったのか」がひと目で分かります。
目的や背景も明記されており「なぜやるのか」がわかる
良いマニュアルは、単に「こうしてください」と手順を指示するだけではなく、「なぜその作業が必要なのか」も記載されています。
例えば、品質管理マニュアルで「製品Aを組み立てる際には、工程チェックをする」と書いてあるとします。すると作業者はそれだけでは「面倒な作業だな」と思うかもしれません。しかし「不良品を未然に防ぎ、顧客からのクレームを減らすために工程チェックを行う」という目的や背景を明記すれば、納得感を持って作業に取り組めるのです。
目的が明確になると、応用力も高まります。突発的なトラブルが起きたときも「この工程の目的は〇〇だから、代替手段として△△をすればいい」と判断できるようになります。つまり、背景を説明することで「作業の意味」が伝わり、単なる手順書から「学びのあるマニュアル」になっていくのです。

良いマニュアルを作るための具体的ステップ
マニュアルは一度に完璧なものを作り上げる必要はありません。大切なのは「どのような手順で作成・改善していくか」というプロセスを明確にすることです。場当たり的に書き進めるのではなく、対象者の設定から構成、現場での検証、そして定期的な更新に至るまでの流れを踏むことで、初めて“現場で使われるマニュアル”が完成します。
ここからは、良いマニュアルを作り上げるための具体的なステップを順に解説していきます。
Step1:対象読者(ユーザー)を明確にして、良いマニュアルの方向性を定める
まず大切なのは「誰が読むのか」を明確にすることです。新人社員が読むのか、ベテラン社員が補助的に使うのか、外部委託スタッフが利用するのかによって、必要な説明のレベルが変わります。新人向けなら用語解説や基本知識を丁寧に盛り込む必要があり、経験者向けなら要点を絞って「作業のチェックリスト」のように応用的な情報に重点を置きます。このように、対象者に合わせた設計が効果的です。
Step2:業務の流れを業務分解図で整理し、良いマニュアルの土台を作る
いきなり文章を書き始めると抜け漏れが生じやすくなります。まず業務の流れを図解し、どの工程が存在し、どこで判断が必要なのかを整理することが重要です。
以下のような業務分解図を作ることで「どの範囲をマニュアル化すべきか」「どこに重点を置くべきか」が明確になります。これにより、全体像を見失わずに作成を進められます。
| 例:業務分解図(飲食店のオーダー対応) 注文を受ける → オーダーをキッチンに伝える → 調理する → 提供する → 会計するこの流れを図式化すると、どこにマニュアルを設けるべきかが明確になります。例えば「会計する」工程にはレジ操作マニュアルが必要で、「調理する」工程にはレシピマニュアルが必要です。 |
Step3:テンプレートやフォーマットを統一する
マニュアルごとに書き方がバラバラだと、読む人が混乱します。例えば、あるマニュアルでは注意事項が赤字で強調されているのに、別のマニュアルでは脚注で書かれていると、一貫性がなく理解しにくくなります。テンプレートを用意し、見出しの付け方や画像の配置ルール、注意書きの表現方法を統一することで、読みやすさが大幅に向上します。
<統一する要素>
・手順は「番号付きリスト」で表記
・注意事項は赤字または「注意」アイコンをつける
・図解は手順の直後に配置する
Step4:初稿作成後、現場でレビューを実施
机上で考えたマニュアルは、実際に使ってみると不十分な点が必ず見つかります。初稿を作成したら現場のスタッフに実際に使ってもらい、フィードバックを得ることが欠かせません。現場レビューを通じて「読み手がどこでつまずくのか」「説明不足な箇所はどこか」が浮き彫りになります。その改善を繰り返すことで、実用性の高いマニュアルに仕上がります。
| 例:現場レビュー 工場の新しい作業マニュアルを作成した際、実際に作業員に試してもらったところ「軍手をはめる手順が抜けている」という指摘がありました。現場レビューを行ったからこそ分かる改善点です。このフィードバックを反映することで、より安全で実用的なマニュアルになります。 |
Step5:定期的な更新ルールを設けて、良いマニュアルを維持する
マニュアルは完成した瞬間から古くなり始めます。業務フローやシステムの更新があるたびに見直しが必要です。更新頻度や担当者をあらかじめ決めておくことで、常に最新の状態を維持できます。例えば「半年ごとに担当部署が内容を確認し、改訂点があれば必ず更新する」というルールを決めておくと良いでしょう。この更新日は、マニュアル冒頭に明記するしておくことも重要です。また、更新履歴を記録することで「どこが変更されたのか」が分かりやすくなり、現場の混乱を防げます。
良いマニュアルを支えるツール・フォーマット紹介
マニュアルを効果的に活用するためには、内容の工夫だけでなく「どのようなツールやフォーマットで作成・運用するか」も重要なポイントです。紙やExcelだけで管理していた時代と比べ、近年はクラウドサービスや動画ツールなど多様な選択肢が登場し、マニュアルの在り方そのものが進化しています。これらをうまく組み合わせることで、作成の手間を減らし、常に最新の状態を保ち、さらに現場に浸透しやすい形で共有することが可能になります。
ここでは、良いマニュアルを支える代表的なツールやフォーマットの活用方法を紹介していきます。
クラウド型マニュアル作成ツール(例:Teachme Biz、NotePM)
クラウド上でマニュアルを管理すれば、常に最新版にアクセスできます。画像や動画を簡単に組み込めるため、直感的に理解できるマニュアルを短時間で作成できます。さらに、アクセス権限を設定すれば部署ごとに必要な情報だけを共有することも可能です。例えばTeachme Bizでは、写真や動画を簡単に追加でき、スマホからでもマニュアルを確認できます。飲食チェーン店でのオペレーションマニュアルや、コールセンターでのトークスクリプト管理に活用されています。
業務分解図を活用したマニュアル設計(例:mayclass)
業務分解図を活用すると、業務の全体像と各工程のつながりが一目でわかります。どの工程にマニュアルが必要かを明確にできるため、効率的にマニュアルを設計できます。例えば新人教育に必要な部分だけを重点的にマニュアル化する、といった戦略的な活用も可能です。
mayclassの業務分解図は、業務フローを可視化しながらマニュアル設計ができます。例えば「採用活動」のプロセスを分解し、「募集→面接→内定→入社手続き」といった形で整理することで、それぞれに対応したマニュアルを作成できます。

動画・画像ツールとの組み合わせで理解度アップ
文章や図解だけでなく、実際の操作や作業を動画で示すと理解度が飛躍的に高まります。特にソフトウェアの操作や製造業の機械操作などは、ZoomやLoomなどの動画を見ながら同じ動作を繰り返すことで習熟が早まります。スクリーンキャプチャや簡単な録画ツールを組み合わせれば、コストをかけずに効果的なマニュアルを作ることができます。
良いマニュアルが組織にもたらす価値
マニュアルは単なる作業手順書ではなく、組織全体の生産性や安定性を支える基盤でもあります。現場の誰もが同じ基準で業務を行えるようになれば、教育にかかる時間を短縮できるだけでなく、特定の人に依存しない仕組みが整い、事業継続性も高まります。さらに、マニュアルを通じて知識やノウハウを蓄積・共有できれば、組織の成長を後押しする「知的資産」としても機能します。
ここでは、良いマニュアルがもたらす具体的な価値を3つの側面から見ていきましょう。
教育コストの削減と即戦力化
新人研修では一から教える時間を大幅に削減でき、マニュアルを見ながら実践するだけで即戦力になれる環境を作れます。教育担当者が同じ説明を何度も繰り返す必要がなくなり、その分の時間を別の業務やフォローに充てられるようになります。
| 例:新人研修 IT企業での新人研修では、従来は先輩社員が一週間かけて説明していた内容を、マニュアルと動画にまとめたことで、2日で業務に参加できるようになった。教育コストが削減されるだけでなく、即戦力化のスピードも格段に上がった。 |
属人化の防止と業務継続性の向上
特定の人にしかできない業務が減り、誰でも同じ成果を出せる体制が整います。属人化が解消されることで、担当者が異動や退職をしても業務が滞らずに済みます。特に中小企業では属人化がリスクになりやすいため、マニュアルの整備が事業継続に直結します。
| 例:中小企業での属人化解消 特に中小企業の経理業務では、新卒採用などを定期的に行っておらず、長年担当しているベテラン社員の経験値で業務を進めがち。そのため、その社員が突然退職すると業務が回らなくなることがある。しかし、経理マニュアルを整備していたある企業では、新任者でもすぐに業務を引き継ぐことができ、トラブルを防ぐことができた |
社内ナレッジの蓄積と可視化
社内のノウハウは人に依存しやすいものですが、マニュアル化することでナレッジとして残ります。つまり、マニュアルは組織の知識を蓄積し、共有する資産となります。単なる作業手順の集まりではなく、組織の「知的財産」として機能するのです。ナレッジが見える化されることで、新しいアイデアや改善提案が生まれやすくなります。さらに、マニュアルがあることで「これはもう改善されているか」「どこまで実践されているか」といった確認も容易になります。
| 例:ナレッジ共有の流れ 個人の経験 → マニュアルに記録 → クラウドにアップ → 全社員が参照可能 |
良いマニュアルを作成しよう!
「良いマニュアル」は単なる業務の説明書ではなく、組織全体の生産性と学習を支える重要な資産となります。明確な言葉、わかりやすい構成、定期的な更新という基本を押さえることで、誰にとっても役立つマニュアルを作ることができます。そして、目的や背景を加えることで「読む」だけでなく「理解できるマニュアル」へと進化させることができます。自然と誰もが現場で使われる”良いマニュアル”を目指し、今日から改善に取り組んでみてください。
マニュアル作成ならmayclassへご相談ください
mayclassでは、業務の可視化や改善に特化したサービスを提供しており、マニュアル作成や運用の仕組みづくりをトータルでサポートしています。属人化の解消や業務効率化を進めたい企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

ーーー
What Makes a Good Manual? How to Create and Improve Manuals That Work On-Site
▼こちらの記事もおすすめ▼
おすすめマニュアル作成アプリ・ツール10選!業務効率化を促進しよう