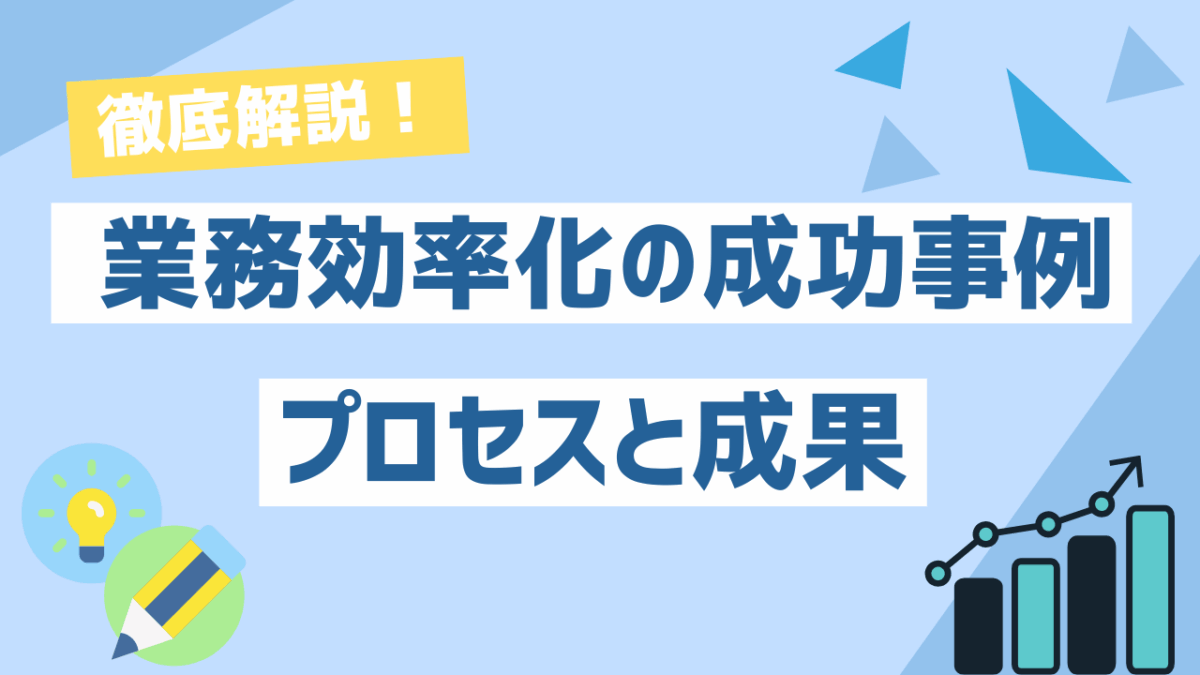業務の無駄を減らし、生産性を高めたい——多くの企業が抱えるこの課題で必要不可欠な取り組みが「業務効率化」です。とはいえ、具体的に何をどう進めれば成果につながるのか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。本記事では、実際に業務効率化に成功した企業の事例を紹介しながら、改善プロセスや導入ツール、得られた成果をわかりやすく解説します。自社に活かせるヒントを見つけたい方は必見です。
業務のムダを減らし、生産性を高めたい担当者向けの記事です。
改善の進め方・導入ステップ・活用ツールをわかりやすく紹介。TrelloやRPAなどのITツール、マニュアル整備による仕組み化など、現場に合った効率化の方法が学べます。
「どこから手をつければいいかわからない」「ツールを導入しても成果が出ない」と悩む方におすすめです。
業務効率化が企業にもたらすメリットとは?
企業が成長し続け、競争力を維持・強化していくうえで、「業務効率化」は避けて通れないテーマです。市場の変化が激しく、あらゆる業種でスピードと柔軟性が求められる今、無駄な業務プロセスを抱えたままではビジネスのチャンスを逃しかねません。業務効率化は単なる“作業の短縮”ということではなく、企業全体の生産性向上、コスト削減、そして社員の働きやすさの実現などさまざまなメリットにもつながります。
業務効率化によるコスト削減
まず、わかりやすいメリットとして挙げられるのがコスト削減です。業務プロセスを見直し、重複して行っている作業やムダのある業務を排除することで、人件費がおさえられます。また、手作業で行っていた定型業務は、自動化することで担当者の工数を削減でき、残業時間の削減にもつながります。さらに、業務の属人化を防ぎ、誰もが同じ水準で仕事ができるように仕組み化すれば、トラブル発生時の対応や引き継ぎもスムーズになり、時間的・金銭的ロスを防ぐことができます。
業務効率化による生産性向上
効率化することで社員一人ひとりがより価値の高い業務に集中できるようになれば、企業全体としてのアウトプットも自然と高まります。不必要な確認作業や情報のやりとりが減り、チーム間の連携がスムーズになることで、スピーディーな意思決定やアクションが可能になります。これによって市場の変化や顧客ニーズへの対応スピードが上がり、競争優位性も高まります。
業務効率化がもたらす社員満足度の向上
社員の満足度も見逃せないメリットです。働きやすい環境が整えば、仕事へのモチベーションや組織への帰属意識が向上し、優秀な人材の定着や離職率の低下にもつながります。煩雑でストレスがかかる業務が少なくなることで、クリエイティブな仕事や成長につながる仕事に時間を割けるようになり、働く意味を実感しやすくなるのです。
業務効率化に取り掛からないことには、明確なリスクがあります。非効率なプロセスを放置したままでは、他社に比べて対応が遅れ、商機を逃す可能性が高まくなります。また、社内のリソースが非生産的な作業に使われ続けることで、本来注力すべき戦略業務や新規事業に十分な時間を割けなくなる恐れもあります。すると結果的に、利益率の低下や社員の不満の蓄積を招き、企業の成長を阻害する要因にもなります。特に近年では、少子高齢化による労働力不足、コストの高騰、DX(デジタルトランスフォーメーション)の加速によって、“限られた人員や資源で、最大限の成果を上げる”ことは、あらゆる業界や業界で求められています。そういった課題を解決するもっとも有効な手段となり得るのが、業務効率化なのです。
業務効率化は、企業の根幹を支える重要な戦略のひとつです。コスト削減、生産性の向上、社員満足度の向上といったメリットは、すべてが相互に関係し、企業の競争力強化につながっていきます。
業務効率化の成功事例3選:業界別の取り組み

ここでは、実際に業務効率化を導入し成果を上げた企業の事例を業界ごとに紹介します。業種や業務内容によって課題やアプローチは異なりますが、どの企業も「業務の見える化」や「ツールの活用」「プロセスの標準化」を軸に改善を進めています。自社の状況と照らし合わせながら、取り入れられるヒントを探してみてください。
事例1:製造業A社の生産管理効率化
中堅の製造業A社では、長年使い続けていた紙ベースの生産管理がボトルネックになっていました。生産スケジュールの調整や在庫の把握に時間がかかり、無駄な在庫や納期遅れが発生することもしばしばありました。そこで、A社は生産管理にITシステムを導入。受注から出荷までの流れを一元管理できるようにしました。その結果、作業時間を30%削減。以前は手作業で行っていた記録・集計作業も自動化され、現場スタッフの負担が大幅に軽減されました。また、在庫管理の自動化によって過剰な在庫を抱えるリスクも減り、倉庫コストの最適化にもつながっています。業務の見える化が進んだことで、現場の判断スピードも上がり、全体の生産性が向上しました。
事例2:サービス業B社のバックオフィス業務改善
人材サービスを提供するB社では、経費精算や勤怠管理など、バックオフィスの業務量が増え続けていたことが課題でした。とくに経費精算は、紙の申請書に上司の押印が必要なアナログな運用で、処理に多くの時間がかかっていました。そこでB社は、クラウド型の経費精算ツールを導入。スマートフォンやPCからの申請が可能になり、申請〜承認〜仕訳までを一貫してデジタル化しました。導入前と比較して、経費精算の処理時間は50%短縮され、経理部門の負担も大きく軽減。ミスや確認作業も減り、月末処理のピーク時でも対応がスムーズになりました。また、承認フローの見直しと併せて、業務マニュアルの整備やペーパーレス化も進行。結果として、部門間のコミュニケーションも改善され、業務の流れが全社的に効率化される形となりました。
事例3:小売業C社の店舗運営の効率化
全国に複数店舗を展開する小売業C社では、各店舗での業務品質にばらつきがあり、顧客対応や在庫管理に時間がかかるなどの課題を抱えていました。特に新人スタッフの教育に時間がかかり、即戦力化が難しい状況でした。そこでC社は、業務マニュアルの標準化と教育プログラムの見直しに取り組みました。業務ごとの手順を動画やチェックリストで明確にし、スタッフが誰でも同じレベルで業務をこなせる体制を構築。また、OJT中心だったトレーニングにオンライン学習を組み合わせて、スタッフの育成期間を40%短縮することに成功しました。さらに、顧客対応時間の短縮にもつながり、結果として店舗全体の運営コストが削減。標準化によって本部と店舗の連携も取りやすくなり、キャンペーンや施策の展開スピードもアップしました。
今回の事例に共通するのは、「現場の課題を正しく把握し、それに合った改善策を選んでいること」です。業種や企業規模に関係なく、効率化の余地は必ず存在します。重要なのは、現場の声を反映させながら無理のない形で導入し、実行後も運用改善を続ける姿勢です。
業務効率化を実現するための外部ツール・サービス活用
業務効率化を進めるうえで、外部ツールやサービスを活用するという視点も欠かせません。自社のみの手作業による業務には限界があり、人的リソースにも制約があります。ITツールや外部の専門サービスを活用すれば、短期間で大きな成果を得ることも可能です。ここでは、効率化に役立つ代表的なツールの種類と、その活用メリット、導入時に注意すべきポイントを紹介します。
効率化を支える主なツールの種類
1. タスク管理ツール(例:Trello、Asana)
タスクの進捗管理や担当者の割り振り、期日の設定が可視化できるツールです。複数のメンバーでプロジェクトを進める際、誰が何を担当していて、今どの段階にあるかがひと目で分かるため、進行の遅れや抜け漏れを防ぐことができます。特にTrelloはカンバン方式で直感的に操作でき、Asanaはより複雑なプロジェクト管理に適しています。
2. 自動化ツール(例:RPA、UiPathなど)
繰り返し発生する単純な業務は、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)で自動化できます。例えば、請求書発行、データ入力、定型レポート作成などを人の手で行っている場合、RPAを導入すると作業時間を大幅に短縮できます。業務上のミスも減り、精度も高くなります。
3. コミュニケーションツール(例:Slack、Microsoft Teams)
社内外のコミュニケーションを円滑にするには、チャットツールやビデオ会議機能が充実したツールが有効です。Slackはリアルタイムなやり取りに優れていて、チャンネルごとに会話を整理できるのが特徴です。Microsoft TeamsはOfficeツールと連携しやすい点が強みで、資料の共同編集や会議スケジューリングも簡単です。
4. データ管理ツール(例:クラウド型ERP、CRM)
売上、在庫、顧客情報など、企業の重要なデータを一元管理できるツールも業務効率化に直結します。ERP(基幹業務システム)は業務全体を統合し、情報の分断や二重管理を防ぎます。また、CRM(顧客管理システム)は、顧客対応の質を高め、営業活動の効率化に役立ちます。
外部サービスを利用するメリット
外部サービスの活用は、社内だけでは得られない価値があります。最大のメリットは、自社リソースを有効活用しつつ、専門的な知識や技術を補える点です。例えば、RPA(Robotic Process Automation)の導入を専門業者に依頼すれば、業務分析からシナリオ構築、運用まで一括してサポートしてくれます。すると、自社の負担を減らしながら、クオリティの高い成果が期待できます。また、外部ツールを導入すると、業務の標準化や属人化の解消も進みます。ルール化や仕組み化ができていれば、新しい社員の育成もスムーズになり、業務継続性の向上にもつながります。コスト面においては、一見費用がかかるイメージがありますが、中長期的にはコストパフォーマンスの向上につながるケースがほとんどです。人的コストやミスによる損失を減らし、スピーディーに成果を出すことで、投資以上のリターンを得られる可能性があります。
業務効率化ツール導入時の注意点
ただし、便利なツールやサービスも、やみくもに導入してもうまくいきません。重要なのは「目的に合ったツールを選定すること」です。選定する際には、以下のポイントをチェックしましょう。
・自社の業務課題に合っているか
・操作性やUI(ユーザーインターフェース)が現場になじむか
・サポート体制や導入後のフォローは整っているか
・コストに見合う機能があるか
また、導入後に定着させるには「社内教育」も欠かせません。使い方の研修やマニュアル整備、導入直後の数週間のサポート体制などを用意しないと、せっかくのツールも活用されずに終わってしまいます。現場とのコミュニケーションを密に取りながら、段階的に慣れてもらう仕組みを整えることが成功の鍵です。業務効率化の成果は、ツールやサービスを「導入した」だけでは得られません。適切な選定と導入プロセス、そしてその後の運用・改善があって初めて効果を発揮します。
業務効率化ツールについては業務効率化ツールの比較ガイド!おすすめツールと導入ポイントの完全ガイド でも詳しくご紹介しています!ぜひ、参考にしてください。
業務効率化を成功させるためのプロセスとポイント
業務効率化を成功させるために大切なのは「自社に合った効率化」を段階的かつ継続的に進めていくことです。そのためには、明確な手順を踏んだうえで、全社的な視点から取り組まなくてはなりません。ここでは、業務効率化を定着させるための5つのステップとそれぞれの実践ポイントを紹介します。
業務効率化のステップ1:現状の課題把握
最初に行うべきは、現在の業務の「見える化」です。業務フローを可視化することで、どこに無駄や非効率があるのか、どの業務が属人化しているのかといった課題が浮き彫りになります。ポイントは、感覚ではなく事実ベースで現状を把握するという点です。どの業務に何分かかっているのか、誰がどんな作業をしているのかを記録・分析することで、改善の土台が整います。
業務効率化のステップ2:具体的な目標設定
現状の課題が明らかになったら、次は「どこを、どのくらい、どう変えたいのか」という具体的な目標を設定します。「作業時間を○%短縮」「人為的なミスを○件削減」「残業時間を月△時間以内に抑える」といった定量的な目標です。曖昧な理想論ではなく、数値で評価できる目標を設定することが改善活動を成功させる鍵になります。目標が明確であればあるほど、施策の方向性や効果検証も行いやすくなります。
業務効率化のステップ3:効率化の手段の選定
次に考えるのは「どうやってその目標を達成するか」です。この段階では、自社のリソースで対応できることと、外部委託やツール導入が効果的な領域の切り分けが重要です。例えば、すでに述べた通り日々の勤怠管理や経費精算のような定型業務は、クラウドツールやRPAで効率化しやすい領域です。一方で、業務改善そのものの設計や運用ルールの見直しといった構造的な課題は、社内の理解が必要なため内製するほうが向いているケースもあります。コストと効果のバランスを見極めながら、最適な手段を選びましょう。
業務効率化のステップ4:導入と運用の実施
効率化の手段が決まったら、いよいよ導入のフェーズです。ここで重要なのは「いきなり全社的に導入する」のではなく、まずは小規模なテスト導入から始めることです。現場の反応や課題を見極めたうえで、徐々に展開することでスムーズに定着させていくことができます。また、導入時には計画的な進行管理も必要です。スケジュールを立て、役割を明確にし、ツール導入時の研修やマニュアル整備も同時に進めましょう。現場の声を聞きながら柔軟に調整する姿勢が、失敗を防ぐポイントです。
業務効率化のステップ5:成果の振り返りと継続改善
導入が完了したら、終わりではありません。むしろここからが重要です。業務効率化の成果が本当に出ているのか、目標に対してどこまで達成できたかを定期的に検証する仕組みが必要です。その際、導入前後での数値比較(作業時間、コスト、ミスの件数など)を行い、改善の成果と課題を洗い出しましょう。その結果をもとに、さらなる改善策を練ることが「継続的な効率化」につながります。変化の早い時代においては、業務プロセスも“常に見直し続ける”姿勢が求められます。社員からのフィードバックを積極的に取り入れ、小さな改善を積み重ねることが、効率化を企業文化として根づかせるための近道です。
業務効率化は、単なる「時短」の取り組みではなく、企業の競争力を高めるための根本的な改革です。5つのステップを丁寧に実行することで、目先の改善だけでなく、長期的な企業価値の向上へとつながっていきます。
業務効率化は“仕組み化”がカギ。プロの力を活用する選択を
業務効率化は、コスト削減、生産性の向上、社員満足度の改善など、企業の成長を支える多くのメリットをもたらします。変化の激しい時代だからこそ、現場のムダや属人化を見直し、再現性のある「仕組み」に落とし込むことが重要です。
本記事で紹介したように、実際の成功事例からは、業種を問わず効率化のヒントが得られることがわかります。しかし、どんなに良い手法も「自社に合った形」で取り入れなければ成果にはつながりません。そのためには、業務を正確に可視化し、誰もが理解できる形で共有・定着させることが不可欠になります。
ーーー
Work Efficiency Success Stories: Process Improvements and Achievements Explained
業務マニュアルを“活きた仕組み”に変える、プロの支援を活用しよう
業務マニュアルの整備と運用の仕組み化の分野におけるプロ集団であるmayclassは、単なるマニュアル作成にとどまらず、現場にフィットする“活きた業務マニュアル”の構築を支援しています。「どこから着手すればいいかわからない」「社内でマニュアルを整備するリソースがない」という方は、当社のような専門会社に相談することで、効率化のスタートが格段にスムーズになります。業務効率化は一度で終わるものではなく、継続的な改善が求められます。まずは身近な課題から着手し、必要に応じて外部の力も借りながら、自社に最適な効率化の仕組みを築いていきましょう。

▼下記記事もおすすめ▼
【保存版】業務効率化フレームワーク15選!生産性向上のポイントとは?