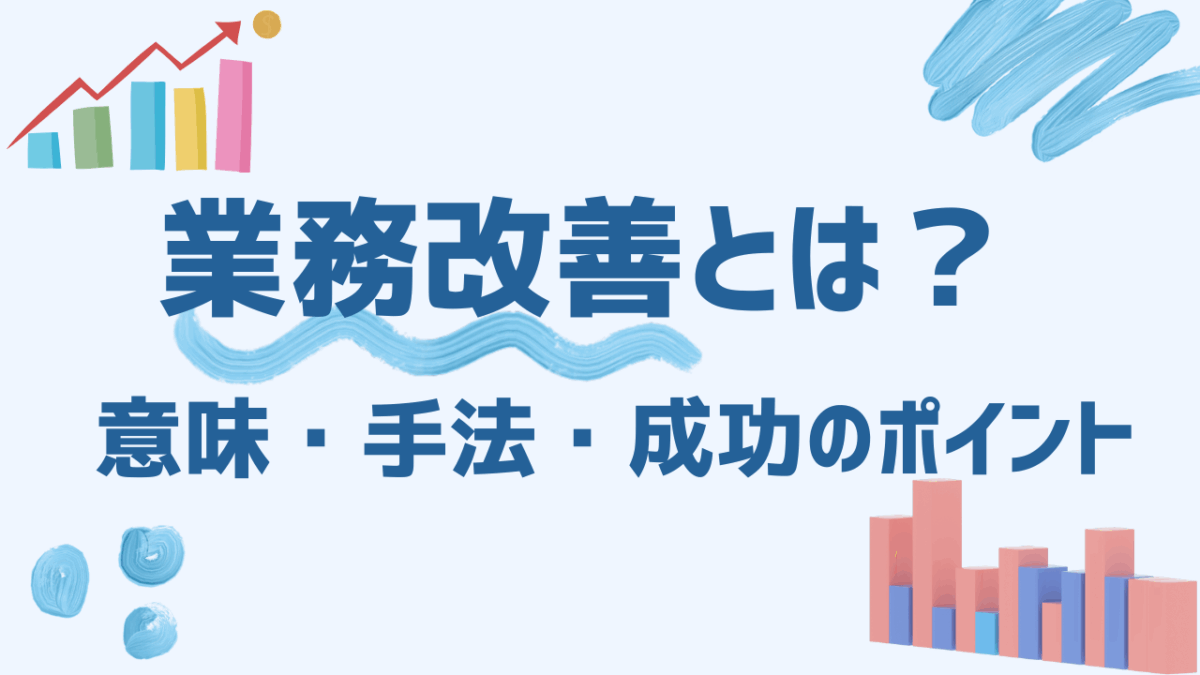「毎月の報告資料作成に時間がかかって残業が増えている」「業務が属人化していて、誰が何をしているか分からない」
このような悩みを抱える企業は少なくありません。こうした状況を根本から見直す手段として注目されているのが「業務改善」です。業務改善とは業務のムダや非効率を洗い出し、生産性を高めつつ、社員の働きやすさも両立させるための取り組みです。単なる効率化にとどまらず、組織の構造そのものを見直す視点が求められます。
本記事では、業務改善の基本的な考え方から代表的な手法、活用すべきツール、つまずきやすい落とし穴まで、実務に役立つ形でわかりやすく解説します。
本記事は、非効率な業務や属人化に悩む企業向けに、「業務改善」の基本と進め方を解説しています。業務改善とはムダや手戻りをなくし、生産性と働きやすさを両立するための取り組みで、現状分析・課題特定・改善策の試行・PDCAの4ステップが重要です。DXやSaaS、RPAなど技術の発展により改善可能な領域が広がっており、属人化やアナログ業務のリスクにも触れながら、導入すべきツールや方法を紹介します。
業務改善とは?基本的な意味と目的を理解しよう
業務改善という言葉を聞いたとき、単なる「効率化」と同じ意味に捉えられることがあります。しかし実際には、業務改善とは業務の流れや役割分担、情報の伝達方法などを含めて、仕事の進め方そのものを見直す取り組みのことを指します。
業務改善の定義と「カイゼン」との違い
業務改善とは、日々の業務に存在するムダ・ムリ・ムラを見つけ出し、それらを取り除くことで作業の手間やミスを減らし、業務をスムーズに進められる状態を目指す活動です。具体的には、業務フローの見直し、担当者の役割整理、情報共有の仕組み改善などが含まれます。
よく似た言葉に「カイゼン(Kaizen)」がありますが、こちらは製造業の現場で広まった考え方で、現場主導による小さな工夫を積み重ねて改善を進める文化を指します。
一方、業務改善は部署を横断したプロセス全体や、業務設計そのものの見直しまで含めるため、より上流工程からの改善が求められる点が特徴です。
業務改善の目的は「生産性」と「従業員満足度」の両立
業務改善の最終的な目的は、生産性を高めると同時に、従業員が無理なく働ける環境を整えることです。
たとえば、手作業で行っていた請求処理をツールで自動化すれば、作業時間は削減できます。しかしその一方で、現場がそのツールを使いこなせなければ、かえって作業が増えてストレスになる可能性もあります。
本当に意味のある業務改善とは、ムダを省くだけでなく現場の負担を減らし、「手間が減って助かった」と感じられるような仕組みに整えることです。
業務改善が必要とされる理由
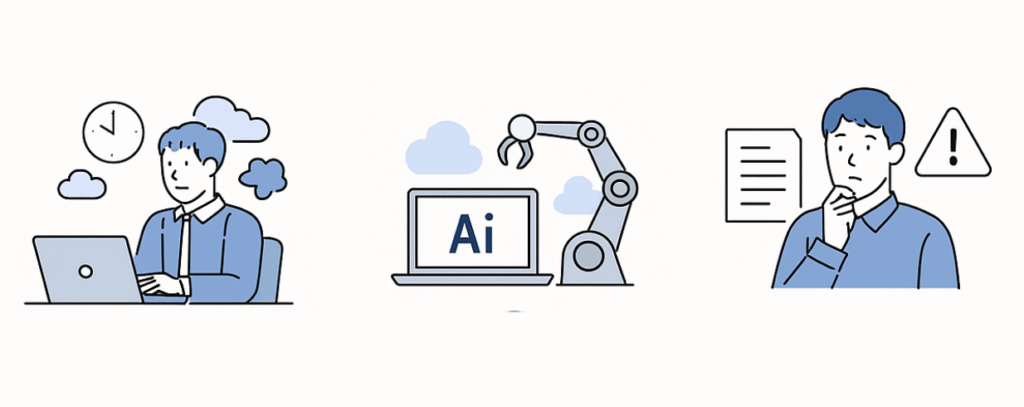
なぜ今、業務改善が求められているのでしょうか。その背景には、社会全体の構造変化やテクノロジーの進展、そして働き方の多様化といった、複数の要因が重なっています。
従来のやり方を続けているだけでは、持続的な成長や人材の定着が難しくなっている今、業務の見直しは多くの企業にとって避けて通れないテーマとなっています。
人手不足・残業削減・離職率改善などの社会背景
総務省の「労働力調査」によると、日本の生産年齢人口(15~64歳)は減少を続けており、この傾向は今後も加速すると見られています。人手が足りないなかで、企業は限られたリソースでどのように業務を回すか、という難題に直面しています。
同時に、「働き方改革関連法」の施行によって、企業には長時間労働の是正や柔軟な勤務体制の構築といった対応が求められるようになりました。こうした状況下では、従来の手作業や属人的な業務をそのまま維持することが大きな負担となります。
非効率な作業や特定の人にしか対応できない業務が放置されると、「残業が減らせない」「引き継ぎがうまくいかない」といった問題が発生しやすくなり、やがては人材の離職やモチベーション低下にもつながります。特に優秀な人材ほど、無駄の多い環境や改善が進まない職場から離れてしまう傾向があります。
こうしたリスクを未然に防ぎ、現場が働きやすく、持続可能な状態を維持していくためにも、業務改善の取り組みは今の時代に不可欠なものとなっているのです。
参照元:国土交通白書 2024 第1節 本格化する少子高齢化・人口減少における課題
DX・テクノロジーの進展により改善可能な範囲が拡大
業務改善の手段は、ここ数年で大きく広がっています。背景にあるのは、クラウドサービスやRPA(定型作業の自動化ツール)、AIといった技術の発展です。以前は手作業に頼らざるを得なかった業務も、今ではツールを活用することで効率的に見直せるようになりました。
たとえば、紙の書類で回していた申請業務を、SaaS型のワークフローシステムに置き換えると、承認フローをオンラインで完結できるようになります。担当者の手間が減るだけでなく、処理状況がひと目でわかるため、業務が止まる場面も減っていきます。
また、RPAを使えば、毎日のデータ転記や報告書の作成など、決まった手順の作業を自動化できます。チャットボットの導入によって、問い合わせ対応の負担を減らす事例も増えています。これまで「仕方ない」としていた作業にも、改善の余地が生まれてきました。
技術を活用することで、「人が手を動かすしかない」と思われていた業務にメスを入れることができるようになっています。現場の工夫と組み合わせることで、改善の幅は確実に広がっています。
属人化・アナログ業務のリスク顕在化
「この業務はAさんにしか分からない」「担当が休むと作業が止まってしまう」といった属人化の問題は、多くの企業で見過ごされがちです。ノウハウが特定の個人に集中すると、異動や退職によって業務の継続性が損なわれるおそれがあります。
また、業務手順が明文化されておらず、口頭や感覚的に進められている場合は作業の質がばらつきやすく、ミスの温床にもなりかねません。紙ベースで行われるアナログ業務も同様に、情報の抜け漏れや保管・検索の手間といった非効率を生み出します。
こうしたリスクに対応するためには、まず業務内容や流れを「見える化」し、誰が見ても同じように作業できる状態を整えることが欠かせません。クラウド上でのデータ管理やワークフロー化といったツール導入によって、属人性を排除し、引き継ぎやチーム間連携がしやすい環境を構築することが求められます。
属人化やアナログ作業を放置すると、いずれ現場が回らなくなる場面が出てくるでしょう。そうならないためにも、早めの対応が安定した組織づくりにつながります。
業務改善の代表的な進め方とは?
業務改善を効果的に進めるには、「課題を見つけてツールを入れる」といった単発的な対応では不十分です。一度にすべてを変えるのではなく、課題の把握・改善策の試行・定着という順を追って取り組むことが、現場に無理なく浸透させるポイントです。
ここでは、業務改善を進めるうえでの基本ステップを4つに分けて解説します。
ステップ1:現状分析(As-Isの把握)
まず取り組むべきは、「今の業務がどうなっているか」を正確に把握することです。
担当者ごとの作業内容や手順、必要なツール、かかっている時間、関与している部署などをできる限り細かく洗い出します。
この段階では「誰が・何を・どうやって」行っているかを客観的に見える化し、ムダや属人化、手戻りの原因などを洗い出します。無駄な工程や非効率なやり取り、属人化している作業が可視化されやすくなります。
ステップ2:課題の特定と改善目標の設定
現状を明らかにしたら、どの部分に問題があるのか、何が作業の遅れや手戻りの原因になっているのかを見極めます。
たとえば、「入力作業に時間がかかりすぎている」「確認・承認に日数がかかっている」といった具体的な課題を明文化することが大切です。そして、「作業時間を30%削減したい」「社内の申請処理を2日以内に収めたい」など、数値化できる改善目標を立てることで、後の評価・検証がしやすくなります。
ステップ3:改善案の設計と試行導入(PoC)
課題が明らかになったら、具体的な改善策を設計します。新しい業務フローの構築、ツールの導入、作業の分担変更など、方法は多岐にわたります。
ただし、一気に全社導入するのではなく、まずは一部部署・業務で試験的に導入する「PoC(Proof of Concept)」を実施しましょう。小規模で始めることで、改善の効果や運用面での課題を早期に発見し、本格導入に向けた調整や見直しがしやすくなります。
ステップ4:定着・評価・再改善のサイクルを回す(PDCA)
改善策を導入したあとは継続的に効果を検証し、必要に応じて見直すプロセスが欠かせません。
ここで重要なのが、PDCA(Plan→Do→Check→Act)サイクルを回し続けることです。現場の変化に応じて調整しながら、改善を続ける仕組みを育てていくことが大切です。評価のためには、業務ごとのKPI(例:作業時間、エラー件数、対応スピードなど)をあらかじめ設定しておくと、定量的な判断がしやすくなります。
業務改善を支えるおすすめツール7選
業務改善を進める際、「どのように見直せばいいか分からない」「改善をどう仕組みに落とし込めばいいか悩んでいる」といった声も少なくありません。こうした課題を整理したり、作業負担を減らしたりするには、見える化や自動化をサポートするツールを取り入れるのが現実的な解決策となります。
ここでは、目的別に実務で使いやすい7つの代表的なツールを紹介します。
業務分解図 by mayclass|業務の見える化と改善起点の整理に
業務の流れや担当範囲を細かく分解し、図で整理できる無料のテンプレートです。
業務が誰に、どれだけ分散しているのかを視覚的に把握できるため、属人化や非効率の発見につながります。改善対象を明確にしたい場合や、上司への説明資料としても活用できます。
おすすめシーン:業務が属人化している、改善の出発点が定まらない企業
miro|チームで使えるホワイトボード型業務可視化ツール
オンライン上で付箋や図表を共有・編集できるホワイトボードツールです。
部署横断で業務フローを整理したい場面や、アイデア出し、ワークショップでの可視化に役立ちます。コメント機能やテンプレートも豊富で、遠隔チームとの協働にも対応しています。
おすすめシーン:プロジェクト立ち上げ時の業務整理、部門横断のワークショップ
Power Automate|日常業務を自動化するRPAツール
Microsoft社が提供するRPA(Robotic Process Automation)ツールで、Excel・OutlookなどのMicrosoft製品と連携しやすいのが特長です。
データ入力、通知、ファイル整理といった定型業務を自動化することで、時間と人的コストを削減できます。ノーコードで設定できるため、ITに詳しくない現場でも導入しやすい点も魅力です。
おすすめシーン:日常的な事務処理を効率化したい現場
WinActor|日本企業に強い国産RPAツール
NTTグループが開発した、国産のRPAツールです。
日本語の帳票や独自システムとの親和性が高く、経理・人事・総務などのバックオフィス業務に広く導入されています。サポート体制も充実しており、大手企業を中心に多くの導入実績があります。
おすすめシーン:紙やExcel中心の業務が残る企業、IT部門が少ない中小企業
Notion|業務マニュアルや議事録も一元管理
ドキュメント、データベース、タスク管理などを一つの画面で整理できるオールインワンツールです。
業務マニュアルの作成・共有、議事録の保管、ToDo管理まで一元化でき、情報の分散や属人化を防げます。ページ間のリンクや検索機能も充実しており、チーム内の情報共有を効率化します。
おすすめシーン:新人教育、属人化防止、ナレッジの共有整備
Slack|即時コミュニケーションで情報ロスを防ぐ
ビジネス向けチャットツールとして広く使われているSlackは、プロジェクトごとのチャンネル管理や外部連携機能が豊富です。
リアルタイムでやりとりできるため、メールよりも迅速な情報共有が可能になり、意思決定のスピードが向上します。通知や検索機能も優れており、情報の取りこぼしを防ぐ仕組みが整っています。
おすすめシーン:メール文化から脱却したい企業、リモート中心のチーム運営
Backlog|プロジェクト管理を誰でも簡単に
タスク管理や進捗確認、課題の共有などを1つのツールで行える国産のプロジェクト管理ツールです。
UIがシンプルで分かりやすく、エンジニアだけでなく営業や事務職のチームでもスムーズに導入できます。ガントチャートやコメント機能も備えており、メンバー間のタスク認識を揃えるのに適しています。
おすすめシーン:複数メンバーで案件を進める、進捗の遅れを可視化したいチーム
業務改善に役立つフレームワーク
業務改善を実現するには、目の前の課題を整理し、「どこに原因があるのか」「どう手を打つか」を冷静に見極めることが大切です。そこで活用したいのが、実務に役立つフレームワークです。
フレームワークについては下記記事で詳しく記載しています。ぜひ参考にしてみてください!
【保存版】業務効率化フレームワーク15選!生産性向上のポイントとは?
業務改善の落とし穴と注意点
業務改善は、現場の負担を減らし、生産性を高めるための有効な手段ですが、「思ったような成果が出なかった」「現場が混乱してしまった」といった失敗例も少なくありません。
この章では、業務改善で陥りやすい失敗のパターンと、それを防ぐための注意点を3つに分けて見ていきます。
現場の声を無視した改善は逆効果
改善案を経営層や管理部門だけで決定してしまうと、実際の現場業務とかけ離れた内容になりがちです。
現場の実情を踏まえずに仕組みやフローを変更すると、「やりにくくなった」「余計な作業が増えた」と反発を招く可能性があります。改善を根づかせるには、現場の声を丁寧にすくい上げ、納得のうえで進めることが欠かせません。
業務改善はトップダウンではなく、現場との対話によって進めるべきものです。
ツール導入だけで終わると失敗しやすい
「RPAを入れたから」「チャットツールを導入したから」といった表面的な対策では、根本的な改善につながらないことが多くあります。
ツールはあくまで手段であり、目的や使い方が明確でないまま導入すると、現場で活用されずに放置されてしまうこともあります。導入前には「なぜ必要なのか」「どの業務にどう使うのか」を明確にし、導入後も使い方の教育や運用ルールの整備を並行して進めることが重要です。
短期成果を急ぎすぎず「継続性」を意識する
業務改善は、すぐに劇的な成果が出るものではありません。
短期間で結果を求めすぎると、負荷だけが増えて定着せず、「改善疲れ」を招いてしまうおそれもあります。小さな成功を積み重ねながら、中長期的な視点で取り組む姿勢が重要です。
継続的な改善サイクルが仕組みとして定着すれば、業務改善は一過性で終わらず、日々の業務の中に根づいていくでしょう。
業務改善とは「小さな変化の積み重ね」
業務改善は、いきなり完璧な仕組みを作ることではなく、「どこにムダや偏りがあるのか」に気づくことから始まります。その第一歩としておすすめなのが、業務分解図テンプレートを使った業務の可視化です。部署ごとの業務を図に整理することで、属人化や重複作業が明確になり、改善ポイントが自然と見えてきます。
まずは、身近な業務を1つだけ取り出して「見える化」してみましょう。

ーーー
What Is Business Improvement? Meaning, Methods, and Success Factors Explained
▼こちらの記事もおすすめ▼
業務効率化は“数値化”から始まる!成果を見える化する方法と実践ステップ