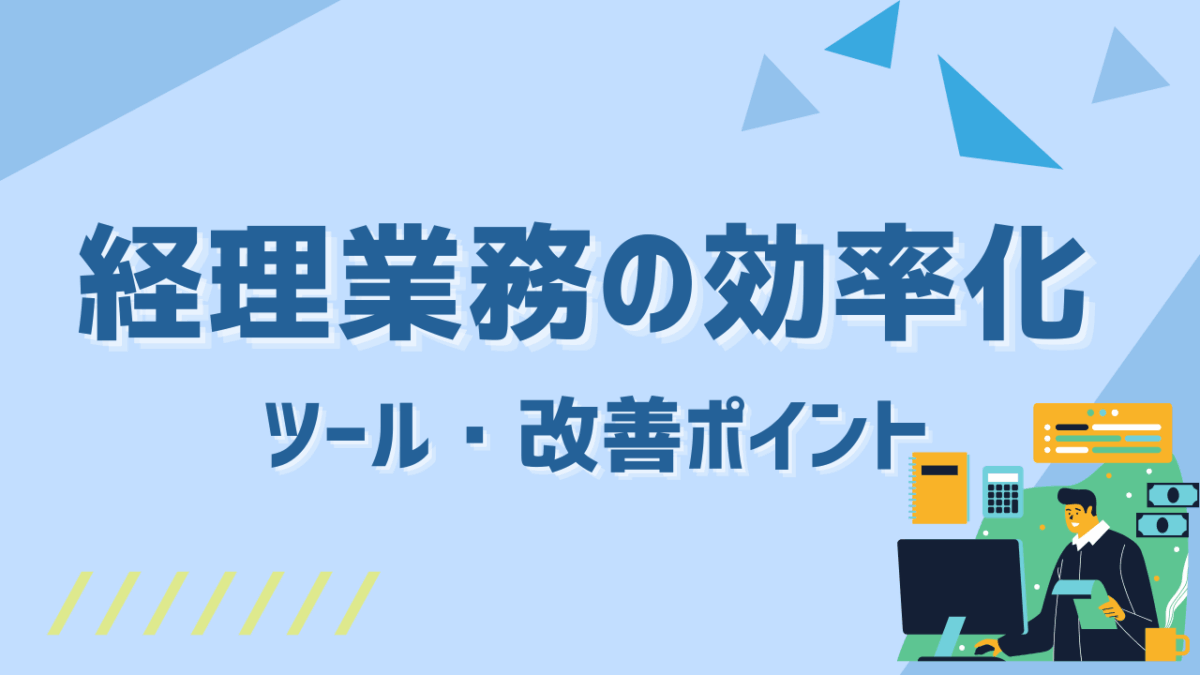毎月の締め作業、請求書処理、経費精算。経理業務は企業活動に欠かせない重要な部門ですが、その一方で「非効率」が深刻な課題となっています。たとえば、紙ベースの処理やエクセルによる手作業が多い現場では、人的リソースが圧迫され、ミスのリスクや確認作業の手間が増大し、慢性的な残業を招いてしまうことも少なくありません。
こうした状況を放置すれば、経理部門の疲弊だけでなく、会社全体の意思決定スピードやガバナンスにも悪影響を及ぼします。今こそ、経理業務の業務効率化に本気で取り組むことが求められているのです。
本記事では、経理業務における非効率の原因を整理し、業務効率を高めるためのツールや改善ポイント、実際の成功事例までを徹底解説します。
この記事は、経理業務の非効率(手作業・属人化・ミス多発)に悩む経理担当者・管理部門向けに、効率化の重要性と改善手法を解説する実践ガイドです。課題整理、ツール選定、業務フロー改善、成功事例、失敗しないポイントまで網羅し、経理を“作業部門”から“戦略部門”へ進化させるための道筋を示します。
なぜ経理業務の効率化が求められるのか?
経理業務は企業の数字を支える要であり、正確さが求められる反面、非効率な手作業や属人化といった課題を抱えやすい分野です。これらの問題を放置すると、単なる作業負担の増加にとどまらず、企業全体の経営リスクにもつながりかねません。
ここでは、経理業務に潜む課題と、それがもたらすリスクについて詳しく見ていきます。
経理業務の主な課題(属人化・手作業・入力ミス)
経理業務は「正確性」が求められる一方で、属人化やアナログ作業が進行しやすい領域でもあります。たとえば、特定の担当者しか分からない処理ルールや勘定科目の判断が存在すると、担当者の異動や退職が大きなリスクになります。
また、紙の伝票やエクセル入力による手作業が中心の場合、ミスの発生率が高く、チェック作業に二重三重の工数がかかることも珍しくありません。業務が煩雑で、データの入力・転記・集計に多くの時間が割かれてしまい、本来取り組むべき分析や戦略的業務に時間を割けない現状があるのです。
業務効率の低さがもたらすリスクとは?
経理業務の効率が悪い状態を放置すると、企業全体に次のような悪影響が及びます。
- 決算や請求処理の遅延による信用低下
- 残業常態化による人材の疲弊・離職
- 数字の信頼性低下による経営判断ミス
とくに成長企業や多拠点展開を進める企業では、経理の遅れが経営のスピードダウンにつながる恐れもあります。業務効率化は単なる“楽をする手段”ではなく、経営を安定させるための“戦略的施策”として位置づけるべきなのです。
経理業務の効率化がもたらす3つのメリット
経理業務の効率化は、単なる作業時間の短縮だけでなく、企業全体の成長や安定性にも大きく寄与します。業務の精度向上や、経営判断に必要なデータの迅速な提供、さらには人材活用の最適化など、得られる効果は多岐にわたります。
ここでは、経理部門における業務効率化の主なメリットを3つに整理してご紹介します。
業務時間の削減と残業の減少
経理業務の業務効率化を進めることで、単純作業にかかる時間を大幅に短縮できます。たとえば、手作業で行っていた仕訳や請求書処理を自動化すれば、月末月初に集中していた作業が分散され、残業時間の削減にも直結します。
特に中小企業では、1人の経理担当が多くの業務を兼務しているケースも多く、効率化によって「ひとり経理」の負担軽減にもつながります。
ミスやトラブルの削減による信頼性向上
経理業務では、小さな入力ミスが大きな損失やトラブルにつながるリスクがあります。手作業が多ければ多いほど、確認工数も増え、ヒューマンエラーのリスクも高まります。
業務を仕組み化・自動化することで、入力ミスや計算ミスの発生率を低下させることができ、業務の正確性・信頼性が向上します。結果として、社内外のステークホルダーからの信用も高まるでしょう。
戦略業務への時間投資が可能に
経理担当者の役割は、単なる帳簿管理だけではありません。効率化によってルーチン業務に費やしていた時間を削減すれば、資金繰りのシミュレーション、経営レポートの作成、原価分析など、より付加価値の高い業務に時間を使えるようになります。
これは企業全体にとって、経理部門を“守り”から“攻め”のポジションに進化させる大きな転機になるのです。
経理業務を効率化するおすすめツール
経理業務の業務効率化を実現するうえで、適切なツール選定は欠かせません。ここでは、多くの企業で導入が進むおすすめのツールを7種類に分けて紹介します。
| ツールカテゴリ | 代表的なサービス名 | 特徴 | 業務効率化のポイント |
| 会計ソフト | ・freee ・マネーフォワードクラウド | 銀行やカードと連携、自動仕訳、UIが直感的 | 手入力の削減、帳簿作成の自動化 |
| 請求書・経費精算ツール | ・楽楽精算 ・Staple | 申請~承認~仕訳まで一元化、スマホ対応も可能 | 経費精算の手間・ミス削減 |
| ワークフローシステム | ジョブカンワークフロー | 申請ルートの可視化、滞留や属人化を防止 | 承認フローの標準化・迅速化 |
| 文書管理・電子契約ツール | クラウドサイン | 契約書の電子締結・検索・保存が簡単 | 印刷・郵送・保管業務の削減 |
| RPAツール | ・UiPath ・PowerAutomate | データ転記や集計を自動処理、複数システム連携も可能 | 定型業務の自動化、省力化 |
| チャットボット・AIツール | ChatGPTなど | 社内問い合わせ対応や仕訳補助に活用可能 | 人的対応の軽減、資料作成支援 |
| クラウドストレージ | ・Google Drive ・Box | ファイル共有・管理が容易、アクセス制御も可 | 情報の一元化とチーム連携強化 |
会計ソフト(例:freee、マネーフォワードクラウド)
クラウド会計ソフトは、仕訳・帳簿作成・決算対応までを一元管理でき、経理業務の基幹を大幅に自動化します。銀行口座やクレジットカードと連携することで、手入力の手間を削減。会計知識が浅い人でも使いやすいUI設計も魅力です。
請求書・経費精算ツール(例:楽楽精算、Staple)
紙やエクセルで管理していた請求書・経費申請をクラウド上で一括管理できるツールです。申請〜承認〜仕訳までを自動で処理でき、確認作業や誤入力の手間が激減します。モバイル対応しているツールも多く、外出先からも利用可能です。
ワークフローシステム(例:ジョブカンワークフロー)
経理関連の申請・承認フローを見える化し、承認遅れや属人化を解消します。申請経路が明確になり、滞留の原因も特定しやすくなります。稟議書や支払依頼などもペーパーレスで完結できます。
文書管理・電子契約ツール(例:クラウドサイン)
契約書や請求書の管理をデジタル化することで、印刷・郵送・ファイリングといった煩雑な作業を削減。締結プロセスの短縮に加え、文書の検索性や改ざん防止にも優れています。テレワーク体制にも最適です。
RPAツール(例:UiPath、Power Automate)
定型的で繰り返しの多い経理業務(例:データの転記、CSVの集計、帳票の作成)をロボットが代行してくれます。システム間の連携も可能で、業務フロー全体の自動化・省力化が可能になります。
チャットボットやAI補助ツール(例:ChatGPTの活用)
経理に関するFAQ対応や、簡単な仕訳提案、業務手順の確認などにAIチャットボットを活用することで、社内問い合わせ対応の工数を削減できます。ChatGPTのような生成AIを使えば、文書作成や資料要約にも応用が可能です。
クラウドストレージ(例:Google Drive、Box)
請求書や契約書、経費申請の控えなどのファイルをクラウド上で管理することで、情報の一元化と共有がスムーズに。アクセス権限の管理や履歴追跡など、セキュリティ面でも安心して利用できます。
経理業務の業務効率を上げる具体的な改善ポイント
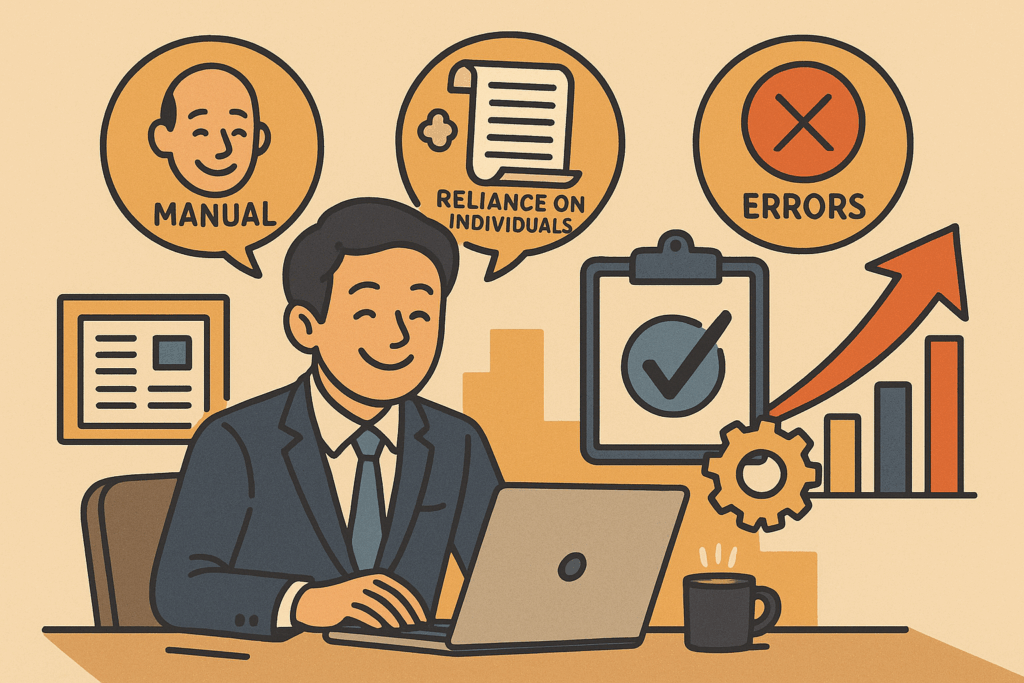
ツールの導入だけでは、経理業務の業務効率化は不十分です。根本的な効率向上のためには、業務の仕組みそのものを見直すことが重要です。以下では、実践的かつ効果の高い改善ポイントを4つ紹介します。
業務フローの見直しと標準化
業務効率が低い現場では、非効率な手順や担当者ごとのやり方のバラつきが放置されがちです。まずは、現在の経理業務のフローを棚卸し・可視化し、ムダや重複を洗い出しましょう。
そのうえで、誰が担当しても一定の品質を保てるよう、業務手順の標準化(マニュアル化)を進めることが重要です。標準化は、引き継ぎや教育の効率化にもつながります。
ペーパーレス化と電子化の推進
紙の書類を前提とした処理は、印刷・押印・保管・郵送などの工数を生み出し、ミスや紛失のリスクも伴います。そこで推奨されるのが、請求書・契約書・稟議書などのペーパーレス化です。
電子帳簿保存法への対応を進めることで、法令順守と業務効率化を同時に実現できます。加えて、リモートワーク対応や検索性の向上といったメリットもあります。
チェック体制の自動化
ミスを防ぐためのチェック業務は必要ですが、人手による確認は時間と労力がかかります。ツールやシステムを活用すれば、入力内容の整合性や申請ルートの自動チェックが可能になります。
たとえば、ワークフローシステムやRPAを活用することで、確認漏れや二重入力といったヒューマンエラーを最小限に抑えることができます。
データ一元管理による無駄の排除
経理業務でよくあるのが、同じ情報を複数の場所に保管していたり、最新データが社内で共有されていないといった「情報の分断」です。これを解消するには、クラウド型のシステムやストレージを活用して、データの一元管理を実現することが有効です。
リアルタイムで情報にアクセスできる環境を整えることで、確認作業や社内問い合わせの時間を減らし、全体の業務スピードを向上させることができます。
業務効率化には、業務効率化は“数値化”から始まる!成果を見える化する方法と実践ステップ の記事もおすすめです。
経理業務の業務効率化でよくある失敗と注意点
経理業務の効率化は大きな成果を生む一方で、やり方を誤ると逆に混乱や形骸化を招くこともあります。ここでは、よくある失敗パターンとその回避ポイントを解説します。
システム導入だけで終わる
便利なツールを導入しただけで満足してしまい、業務フローやルールの見直しをせずに運用するケースです。既存のやり方を残したままツールだけが増えると、かえって作業が複雑化し、業務効率は向上しません。
ツール導入はあくまで手段であり、目的は業務の最適化です。運用ルールの整備やフローの再構築とセットで行うことが大切です。
現場の声を無視した改革
経理業務の多くは現場の担当者が日々運用しています。そのため、現場の意見を反映しないトップダウンの効率化施策は、形だけ導入されて使われない、という結果になりがちです。
改善案の検討段階から現場の意見を吸い上げ、スモールスタートでのテスト導入を経てフィードバックを得るプロセスが欠かせません。
属人化が解消されない設計
効率化を進めたはずなのに、特定の人しか操作できないツール、特定の人しか判断できないプロセスが残ると、業務は属人化したままです。これは引き継ぎや拡張性の面で大きなリスクになります。
操作マニュアルの整備や役割の明確化、権限管理の見直しなどを通じて、誰でも対応できる体制を整えることが重要です。
経理業務の業務効率化は「仕組み化」と「ツール活用」がカギ
経理業務の効率化は、単なる時間短縮ではなく、企業全体のパフォーマンスを底上げする大きな施策です。ポイントは、日々の業務に潜む非効率を可視化し、最適なツールを導入しながら、継続的に仕組みを整えていくことにあります。
一方で、システムを入れただけで満足してしまったり、現場の声を無視したまま運用を進めると、効果は出にくくなります。だからこそ、現状を丁寧に見直し、小さく始めて、現場に根づく改善を続けていく姿勢が重要です。
まずは、業務の棚卸しを行い、どこに無駄や手間があるのかを洗い出すことから始めてみましょう。すぐにできる第一歩として、無料の業務可視化ツールや業務フロー図作成サービスを活用するのもおすすめです。
経理部門の業務を、もっとスマートに、もっと戦略的に変えていきましょう。
経理業務の可視化なら、mayclassの「業務分解図」
どこから手をつけるべきかわからない、そんなときはMayclassの「業務分解図」をご活用ください。
経理業務を含む社内の業務を棚卸しし、マニュアル作成や効率化の優先順位を見える化します。

※業務分解図メール受け取りご希望の際は、お問合せ内容に「業務分解図希望」と記載してください。
▼こちらの記事もおすすめ▼
Excelマニュアル作成の完全ガイド|誰でもできる効率アップの方法
【完全ガイド】Wordでマニュアル作成する方法!デザイン・レイアウトの工夫もご紹介
【保存版】マニュアル作成のコツと手順を徹底解説!初心者でもわかる実践ガイド
ーーー
How to Drastically Improve Accounting Efficiency: Tools and Optimization Tips