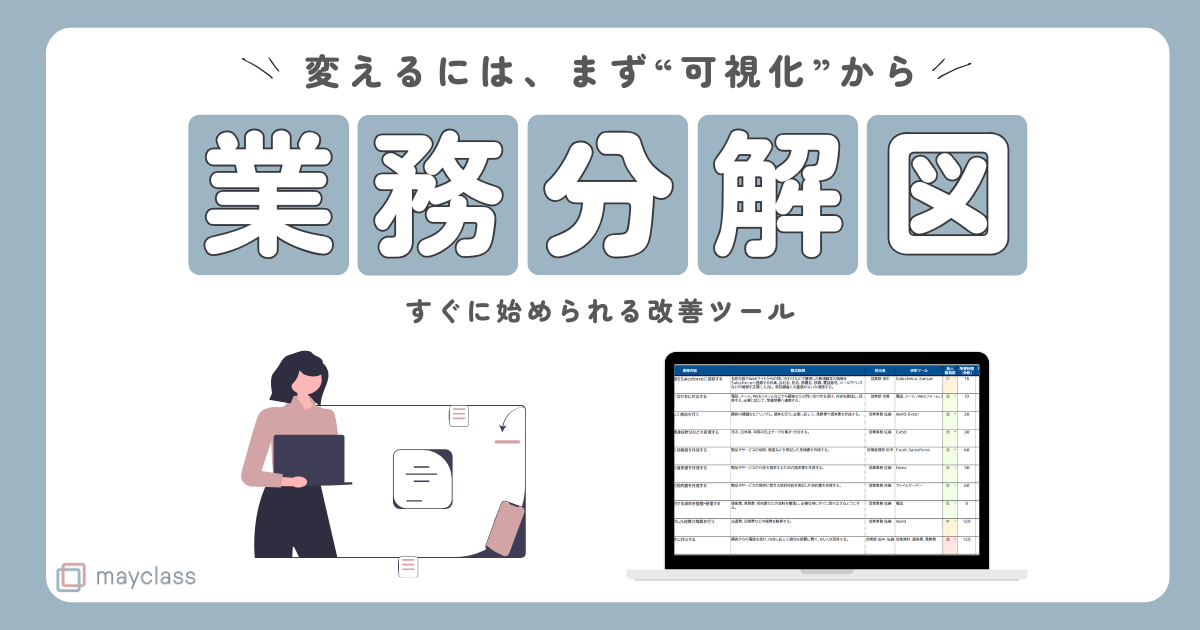「この業務、結局誰がやってるの?」「新人にどう教えればいいのか毎回悩む…」
そんな課題を抱える企業にこそ知ってほしいのが「業務分解図」です。業務分解図とは、業務全体をツリー構造で階層的に整理・可視化する手法です。
作業の流れや役割の分担が一目でわかる“業務の地図”を描くことで、現場の混乱をなくし、業務の標準化・改善・教育が一気にスムーズになります。
業務分解図とは?
「なんとなく回っているけど、全体像は誰も把握していない…」
「引き継ぎに時間がかかり、新人教育がうまくいかない…」
そんな現場の“もやもや”を解消するのが、「業務分解図」です。
業務分解図とは、日々の業務を構造化し、可視化するためのツールです。
一つひとつの作業を整理して見える化することで、非効率な業務や属人化の温床を洗い出し、改善の第一歩を踏み出すことができます。
業務分解図を作成する目的
業務分解図は、業務改善やDX推進の第一歩として非常に有効です。ここでは、業務分解図を作成する目的を4つの視点から整理します。
1. 複雑化した業務を可視化し、DX化すべき領域を明確にするため
多くの企業では、業務が属人化したり増え続けたりする中で、全体像が見えづらくなっています。
さらに、業務分解図の作成は、マニュアル作成や業務改善・DX推進の基盤にもなり、その後の資料設計・教育プログラム構築まで一気通貫で支援できる土台となります。業務の洗い出しの結果、どこをデジタル化すべきか(DXの優先ポイント)が明確になります。
2. 業務の全体像を把握し、ムダやボトルネックを特定するため
業務分解図を作ることで、「誰が・どの業務を・どう進めているのか」が可視化されます。
その結果、重複している作業や無駄な工程、業務の中で時間がかかっている箇所=ボトルネックが明らかになります。
これは業務改善を始める上での、いわば“診断”にあたるステップです。
3. 最適なツール導入で、業務効率化・コスト削減を図るため
業務を細かく分析することで、「ここは自動化できる」「ここにツールを入れると効果的」といった改善の打ち手が見えてきます。
このプロセスを通じて、業務効率の向上とコスト削減を両立することができます。
4. 担当者の役割分担を明確にし、人員配置を最適化するため
業務内容とその手順を明確にすることで、「この作業は誰がやっているのか」「1人に業務が集中していないか」といった担当範囲の偏りや曖昧さを解消できます。
結果として、適材適所の人員配置が可能になり、チーム全体の生産性向上につながります。
業務分解図が特に必要な企業とは?
業務分解図は、以下のような業務の見えづらさや属人化、改善の行き詰まりを感じている企業に特におすすめです。
マニュアル作成にハードルを感じている
「どこから手をつければいいかわからない」「そもそも業務が整理されていない」といった理由で、マニュアル化が進まない企業には、業務分解図が非常に有効です。業務を一つひとつ洗い出し、手順や目的を整理することで、そのままマニュアルや研修資料にも転用できます。
マニュアル化すべき業務が把握できていない
日々の業務が曖昧なまま属人的に進められている企業では、「何をマニュアルにするべきか」の判断がつきません。業務分解図を作ることで、繰り返し発生する業務や複雑な手順を可視化し、マニュアル化の優先順位が見えてきます。
AIやツールを活用したいが導入ポイントが不明
「AIを使って業務を効率化したい」と考えていても、どの業務を自動化すべきか、どこが人の手で残すべきかを判断するのは簡単ではありません。業務分解図は、AI導入やDX推進の“地図”としても機能し、最適なツール選定や導入順序を明確にしてくれます。
業務が属人化している
「○○さんじゃないと分からない」「その人が休むと業務が止まる」といった状態は、企業のリスクでもあります。
業務分解図を使えば、誰が・何を・どのように行っているのかが見えるようになるため、属人化を解消し、チーム全体で業務を共有できる体制づくりが可能になります。
情報伝達に時間がかかっている
「この業務、どこまでが自分の仕事?」「どの部署が次に担当するの?」といった業務の“境界線”が曖昧な状態では、連携ミスや情報の行き違いが頻発します。
業務分解図によって、業務の流れや役割分担を全社的に共有できるようになり、連携の質が飛躍的に向上します。
業務プロセスが煩雑
業務が多岐にわたる中で、どこが問題の本質なのかが見えない企業にとって、業務分解図は課題の“発見ツールです。業務全体を見える化することで、ムダや重複、停滞箇所をあぶり出すことができます。
引き継ぎに時間がかかり教育コストが高い
「新人が定着するまでに何か月もかかる」「OJT任せで人によって教え方が違う」…
そんな状況に対して、業務分解図は一目で業務の全体像をつかめる“教育の地図”として機能します。
そのままマニュアル化できるため、教育時間の短縮と質の均一化を実現できます。
業務効率を改善したいがどこから手を付けていいか分からない
漠然と「もっと効率よくしたい」と考えていても、改善の切り口が見つからない。そんなときこそ、まずは業務分解図で現状を正しく把握することがスタート地点になります。
“見える化”された業務をもとに、改善の優先順位をつけていくことができます。
業務分解図の4つの特徴
業務分解図には、実務で使いやすくするための工夫がいくつも盛り込まれています。ここでは、特に重要な4つの特徴をご紹介します。
1. 業務を段階的に分解し、構造を“見える化”できる(階層化・詳細化)
業務分解図では、業務を「大分類→中分類→小分類」といったツリー構造で整理していきます。
たとえば「営業」という大きな業務の中に、「見積作成」「契約対応」などの中分類を作り、さらにその中に「見積内容の確認」「顧客への送付」などの具体的な作業を記入します。
こうすることで、業務全体の構造と、個別作業のつながりが一目で把握できるようになります。
2. “目的”や“関係性”もあわせて整理するから、改善に役立つ(多角的な情報整理)
ただ作業を並べるだけでなく、各業務ごとに「目的」「担当者」「成果物」「関係する他の業務」なども記載できるようになっています。
これにより、単なるチェックリストではなく、改善や分析に使える実践的な情報整理ツールとして活用できます。
3. 誰でも直感的に理解できる“やさしいデザイン”
業務分解図は、現場の誰が見ても理解できるように、専門用語を使わず、シンプルでわかりやすいレイアウトを心がけています。
「業務可視化ツールは難しそう…」という方でも、Excel感覚で手軽に扱えるのが特長です。
4. 業種や職種を問わず“自由にカスタマイズできる”テンプレート形式
提供される業務分解図テンプレートは、汎用性が高く、会社や部門ごとの業務内容に応じて自由に編集可能です。
必要に応じて、列を追加したり、情報を取捨選択したりできるので、小規模チームから大規模組織まで柔軟に対応できます。
業務分解図の使い方

すでにある業務をこの分解図に当てはめていくことで、見落としていた業務や、重複している作業が見えてきます。そのうえで、不要な業務の削減や、役割の再設定、作業手順の見直しといった改善活動につなげることができます。
ダウンロードしたExcel形式の業務分解図テンプレートは、以下の手順で利用します。
Step 1|業務を「大分類」に入力
まず、会社全体の業務を、大きなカテゴリに分類します。このとき、頭の中だけにある作業や個人メモ、ベテランにとって当たり前すぎて説明されていない業務(=暗黙知)も含めて、徹底的に洗い出すことが重要です。
現場ヒアリングやマニュアル確認を通じて、実態を正確に可視化することがスタート地点です。
- 例:営業、経理、人事、製造など
- テンプレートの「大分類」の列に入力します。
Step 2|大分類をさらに細かく分解する
次に、大分類した業務の内容を入力します。
- 例:
- 大分類:営業
- 業務内容:顧客情報登録、問い合わせ対応、見積作成、契約書作成
- テンプレートの「業務内容」の列に、具体的な業務名を入力します。
Step 3|各業務の詳細な手順を入力する
「業務内容」の具体的な作業手順を入力します。
- 例:
- 業務内容:見積作成
- 業務詳細手順:
- 顧客からの依頼内容を確認する
- 必要な情報を収集する
- 見積書を作成する
- 上長の承認を得る
- 顧客に提出する
- テンプレートの「業務詳細手順」の列に、手順を1つずつ明確に記述します。
Step 4|業務に関する補足情報を入力する
必要に応じて、業務の目的、手順の補足、背景、注意点などを入力します。
- 例:
- 業務内容:見積作成
- 顧客からの依頼内容を確認する
- 補足:
- 電話、メール、Webフォームなどから顧客からの問い合わせを受け、内容を確認し、回答する。
- 必要に応じて、関連部署へ連携する。
- テンプレートの「業務補足説明」の列に入力します。
Step 5|その他の項目も入力する
- 担当者: 各業務の担当者を明確にします。
- 使用ツール: 各業務で使用しているツール(ソフトウェア、システムなど)の具体名を入力します。
- 新人難易度: 新人の方が習得する際の難易度を入力します(低/中/高から選択)。
- 所要時間: 各業務にかかる時間(分数)を入力します(単位も件/回/日から選択)。
- 頻度: 各業務の実施頻度を入力します。(例:毎日5件、月1回など)
- 課題・問題点: 各業務に関する課題や問題点を具体的に入力します。(例:手入力のため時間がかかり、ミスも発生しやすい)
- マニュアル等関連書類: 各業務に関するマニュアルや手順書の有無を選択します。
- 資料URL: 関連資料のURLがあれば入力します。
Step 6|作成した業務分解図を見て課題を発見する
- 完成した業務分解図を見ながら、業務の流れや担当者の役割分担などを確認します。
- 非効率な部分、改善できる部分、課題などを洗い出します。
【入力のポイント】
・業務は、可能な限り細かく分解することが重要です。
・各項目は、具体的に記述することで、より正確な分析が可能になります。
・関係者で協力して入力することで、より網羅性の高い業務分解図を作成できます。
mayclassの想い〜「働き方」をもっと、意味あるものに〜
mayclassは企業の生産性向上と従業員の働きがい向上を同時に実現することを目指し、「業務分解図」サービスを提供しています。
従来の業務プロセスは、属人化や非効率な作業が常態化している場合が多く、企業の成長を阻害する要因となっています。また、従業員にとっても、単純作業の繰り返しや長時間労働は、モチベーション低下や離職率上昇につながる可能性があります。
mayclassは、「業務分解図」サービスを通じて、これらの課題を解決し、企業と従業員双方にとって価値のある働き方を創造することで、持続可能な成長と働きがいのある社会の実現に貢献したいと考えています。
業務分解図で業務を“見える化”しよう
業務改善・マニュアル整備・新人教育・DX推進。
すべての出発点は、業務を分解して理解することです。
📥 業務分解図テンプレートでまずは1つの業務から整理してみませんか?
※業務分解図メール受け取りご希望の際は、お問合せ内容に「業務分解図希望」と記載してください。
ーーー
[Free Template Available] What Is a Business Process Map? Why Every Company Needs One