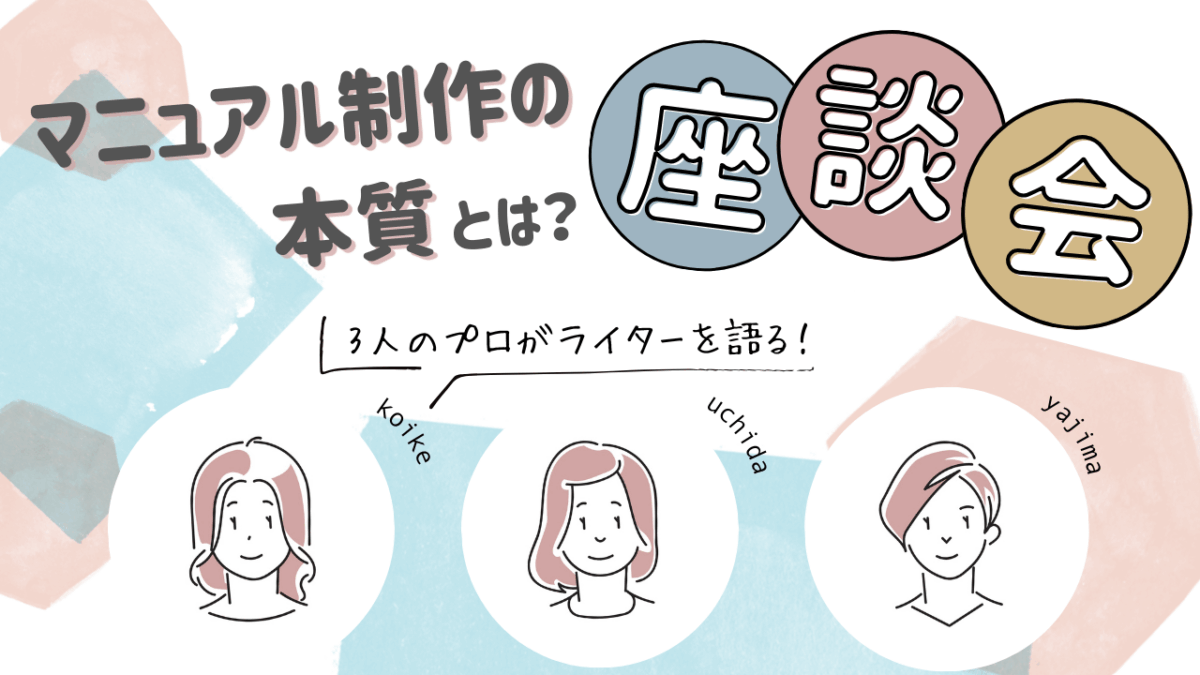「マニュアル」を作るライターと聞いて、どんな仕事を思い浮かべますか?ただの文章整理?手順書作り?実はその先にあるのは、「人を動かす仕組み」を作るという、深くて実践的な世界。
本記事では、実際にマニュアルライターとして活躍する3名に、キャリアの始まりから、仕事の本質、求められるスキル、そして現場で得た気づきまでを伺いました。業務設計・情報整理のプロとして、見えない価値をどう届けているのか。そのリアルをお伝えします。
マニュアルライターって“文章を書く人”と思われがちですが、実は「人が迷わず動ける仕組み」をつくるプロ。この記事では、3人の現役ライターが、仕事を始めたきっかけから、現場で感じたリアル、必要なスキルまで本音で語っています。業務をどう聞き出し、どう構造化し、どう“使える形”に仕上げていくのか。普通のライターとはひと味違う、マニュアル作りの奥深さがわかる内容です。
偶然から始まったキャリア――3人がこの職に惹かれた理由
――皆さんがマニュアルライターとして活動するようになったきっかけから伺ってもいいですか?
小池:友人から「マニュアルを作っている会社があるけど興味ない?」と紹介されたのが、この仕事との出会いでした。ライター歴も長く、これまでの経験を活かせるかもしれないという思いと、新しい分野に挑戦することで自身のライターとしての幅が広がるのではという期待もあり、気負わずにスタートしました。
内田:私は、noteに掲載していたプロフィールをきっかけに声をかけていただきました。最初は「マニュアル作成ってどんな仕事なんだろう?」と戸惑いもありました。普段は経営者へのインタビューや、ストーリー性の強い記事を多く手がけていたため、あまり馴染みのない分野だったからです。
ですが、代表から「マニュアルライターとは何か」というお話を伺う中で、その奥深さに次第に引き込まれていきました。情報を実務で“使える形”に落とし込むという作業は、自分にとって大きなチャレンジであり、同時にやりがいのある仕事だと感じています。
矢嶋:私もnote経由で声をかけていただいたのがきっかけでした。前職では、企業向けの通信教育テキストの企画・編集をしていたこともあって、業務マニュアルにも近い部分があるかもしれないと感じたんです。
実務で気づいた、マニュアル作りの奥深さと意義
――実際にマニュアル作成に関わる中で、印象的だった経験や気づきはありますか?
内田:以前、編集者として働いていた職場で、マニュアルが一切ないまま先輩が退職してしまい、その後の業務引き継ぎが機能せず、大きな混乱を招いたことがありました。その人が積み重ねてきた仕事が“なかったこと”のように扱われてしまったことがとても辛く、「仕事の知識を形にして残すこと」の重要性を痛感しました。
以来、マニュアルは単なる手順書ではなく、“仕事の記憶”であり、次に繋ぐための重要な資産であると感じるようになりました。
矢嶋:私も実際に作ってみて驚いたのは、想像以上に設計力が求められるということです。ただ書けばいいのではなく、再現性や業務改善の視点を含めて構造化する必要があり、その奥深さに圧倒されました。
小池:マニュアル作成もしたことはありますが、“本当のマニュアル”は私が想像していたマニュアルとは全く別物だと感じました。単に説明するだけでなく、「誰が読んでも、迷わず行動できる」ように落とし込む力が求められるんですよね。やってみて初めて、その難しさと面白さを実感しました。
矢嶋:「マニュアルがあることで人が安心して働ける」「辞めずにすむかもしれない」と思えたことが、この仕事に意味を感じるきっかけでした。最初は軽い気持ちで始めたつもりでしたが、今は責任とやりがいを強く感じています。
“伝える”だけでは足りない――実務を支える設計力
――マニュアルライターの仕事は、普通のライターとどう違うのでしょうか?
矢嶋:一番の違いは、文章を書いた“その先”に必ず「アクション」があることです。マニュアルは読まれるだけで完結せず、必ず何かを“やってもらう”ことが目的。そのためには、ただ分かりやすいだけの文章ではなく、「再現性」を徹底的に設計する必要があります。
内田:本当にそう思います。マニュアルは“行動を促す設計図”です。操作や業務手順を「誰でも同じように実行できる」状態にまで落とし込まなければならない。正直、最初は「これはライティングというより、資料設計や業務構築に近いのでは?」と驚きました。
小池:私も全く同じ感覚でした。実際、マニュアルライターとしての仕事では、単なる文章化にとどまらず、業務全体を「構造化」することが求められます。相手の話を深く聞き取り、情報を整理し、業務フローに合わせて可視化していく。その中でも特に大きな役割を果たすのが、「業務分解図」なんですよね。業務分解図があるだけで、業務全体の全貌を捉えられ、マニュアルへの落とし込みも一気に進みます。まさに“見えない業務の地図”です。
内田:業務分解図は、単なる整理ツールではなく、現場を整えるための“土台”ですよね。特に、言語化されていない業務が多い現場では、その存在がマニュアルの質を大きく左右します。そしてその作成には、ライターというよりコンサルタントに近い視点が必要です。
矢嶋:お客様がうまく説明できないことをこちらが引き出す場面も多いですよね。だから、ヒアリングというより「カウンセリング」に近いこともあって。実際、「話していたら頭が整理されました」と言われることもよくありますし、私たちが話を聞く時間そのものに価値を感じていただけることも多いです。
小池:インタビューというより、“一緒に整理していく対話”に近い感覚ですね。こちらが質問を投げかけることで、「あ、そういえばそこ考えてなかったな」とか、「これって当たり前すぎて言ってなかったかも」といった気づきがどんどん出てきます。
実はその時間自体がすごく大事で、マニュアルのためのヒアリングではあるけれど、それ以上に、お客様自身が業務や考えを見つめ直すきっかけになっていると感じます。過去に、インタビューだけでもして欲しい、壁打ち相手になって欲しいという依頼もあったぐらいです。
マニュアルは完成すればいいというものでもなくて、実際に現場で“使ってもらえるかどうか”がすべて。だから、ホワイトスペースのとり方、太字や色の使い方まで、見た目の伝わりやすさにも細かく気を配っています。読み手のことを考えると、全体フロー、心構え、失敗例など多くの情報も必要です。そういう意味では、私たちの仕事って“文章を書く人”というより、“行動につながる設計をする人”に近いんじゃないかなと思っています。
矢嶋:まさに、「情報を整理して、相手に合わせてわかりやすく整えて、実際に動いてもらうところまで導く」。それがマニュアルライターの役割で、いわゆる普通のライターの仕事とは違うなと感じます。
マニュアル制作に求められるのは、“書く力”より“構造力”
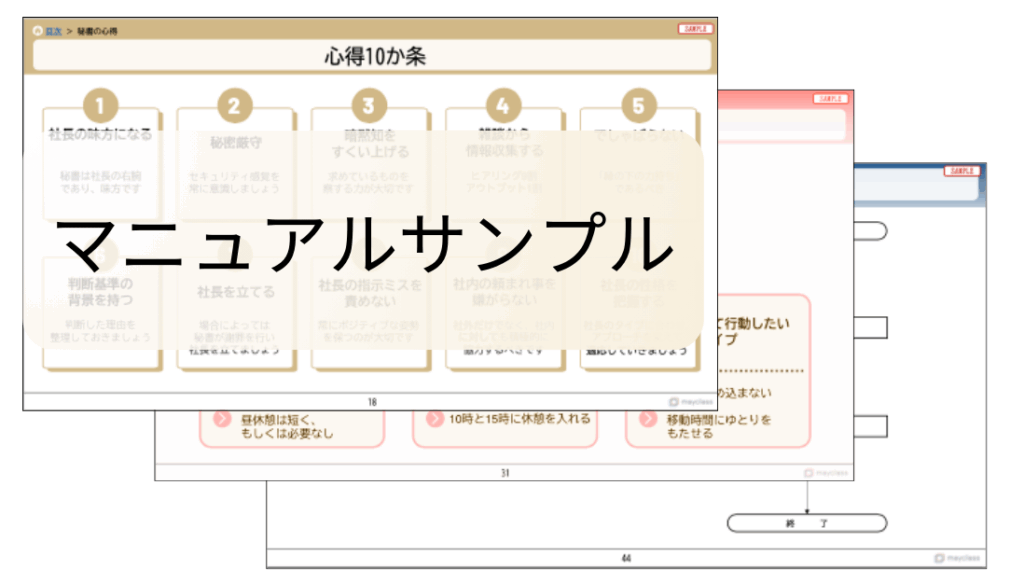
――マニュアルライターに求められるスキルは、具体的にはどのようなものでしょうか?
内田:マニュアルは、単に「わかりやすく書く」だけじゃなくて、読む人が迷わず動けるように設計する必要があります。だから、文章力だけじゃ足りないんですよね。たとえば新人が入社したとき、「ここは自分で判断しなくていい」という部分をマニュアルでしっかり押さえておけば、自由に発想すべきところに集中できます。AIのように定型業務は自動化されていく中で、マニュアルが整っていれば、創造性が求められる仕事にエネルギーを使いやすくなります。
矢嶋:その視点、すごくわかります。情報が整理されていない業務を構造化し、「これなら誰が見てもできる」という状態にしておくことが重要です。次の人がスムーズに業務に入れるように準備しておくことは、業務の引き継ぎや運用の効率化に直結します。
参考:マニュアル作成が上手い人の共通点とは?社内で重宝されるスキル、今すぐ真似できるコツも紹介
現場に届ける価値――実感するやりがいと向き合う課題
――実際にマニュアルライターとして働く中で、やりがいを感じる瞬間や、逆に大変だったことはありますか?
内田:やりがいを感じるのは、マニュアルを通じて「職場に安心感を生む環境づくり」に貢献できる点です。誰かが辞めても業務が止まらず、次の人が迷わずに仕事を引き継ぐことができる。そんな仕組みを作れることに、マニュアルライターとしての意義を感じています。
矢嶋:私は「情報を整理して“見える化”できた時」が一番の達成感ですね。ぐちゃぐちゃだった業務がすっきり整った時、「これなら次の人も絶対できる!」と思えるのが気持ちいいです。誰かが次の一歩を踏み出せる土台を作れるのは大きなやりがいですね。
小池:長く担当している企業では「マニュアル作成はもう小池さん」と言われるくらいになっています(笑)。いろんな部署の業務に関わって、次々とマニュアルを整えていく中で、その会社の一員のように信頼される感覚が嬉しいですね。
先ほど、マニュアルを作成したこともあるとお話ししましたが、当時は、どうしても自己流でまとめてしまって、体系的に整理できていなかったんですよね。でも今は、業務分解図をベースに構造化して作るので、自分でも「これは使える」と思えるマニュアルに仕上げられる。その過程自体にもやりがいを感じています。
内田:逆に苦労したこともありますよね? 私は営業経験ゼロだったので、実はマニュアルを作る作業そのものよりも、お客様への対応に本当に苦戦しました。単なるインタビューではなく、態度や言葉遣いといった営業や接客的な要素が大きな比重を占めてると思います。
矢嶋:お客様と定期的にやり取りする密な関係になりますし、1回インタビューして終わりじゃなく、関わり続ける。だからこそ、マニュアルライターにとっては、マニュアル作成以上に、作る過程でのお客様との関係づくりがとても重要な業務だなと、私も思いました。
小池:「マニュアル作成=手順を正確に記載すること」と思いがちですが、全然違います。マニュアルを“完成させる”までのプロセス全体が仕事なんですよね。しかも、正解がない中で、自分なりに構造を組み立てることは、エネルギーを使います。
内田:それだけに、うまくいったときの満足感は大きいですね。「これがあれば、現場が回る」と言っていただけたら、もう最高です。
マニュアルは業務資産。プロに任せるべき理由とは
――では最後に、企業の方に向けて伝えたいことがあればお願いします。
内田:「マニュアルは自分たちで作れそう」と思われる企業さんも多いと思います。最近はAIやマニュアル作成ツールも多くありますし。でも実際は、そう簡単じゃないと思うんです。特に“設計”の部分は、やっぱり人の力が必要です。
小池:ツールだけだと、情報がただ溜まってるだけの状態になることも多いんですよね。私もノウハウが溜まったツールを使ったことがあり「すごい情報量!」と思っても、何がどこにあるのか全然わからなかったことがあります。結局、読む側に届かなければ意味がないんですよね。
矢嶋:社内で作るとどうしても「本業の片手間」になりがちですよね。優先順位は高いはずなのに後回しになり、いつまでも完成しないということもよく耳にします。プロに頼めば、限られた時間で完成まで一気に進めることができ、結果的に効率的です。
内田:自分たちの仕事を客観視することも、案外難しいんですよね。私たちみたいな“外部の人間”が入ることで、初めて言語化される部分も、実はたくさんあると思うんです。主観だけでは、いいマニュアルを作ることは難しいです。
矢嶋:うまく言語化できないままAIに投げても、結局「読みにくいマニュアル」ができてしまうという失敗もありますよね。情報整理は、話を“聞いてもらうこと”そのものに価値がある。だから私たち、ちょっとカウンセラーみたいな仕事している気がします。
小池:もう「マニュアルライター」じゃなく「マニュアルコンサル」の方が私たちライター目線でもしっくりきます。
内田:設計から伴走して、構造化して、提案して、文章にして、見せ方まで整えて。これはもう立派な“専門職”ですよね。だからこそ、企業さんには「プロに任せることで、業務全体が変わるかもしれない」ということを知っていただきたいです。
矢嶋:マニュアルは“誰でも作れる”ように見えて、実は“誰にでも作れない”ものなんですよね。だからこそ、プロに頼む価値がある。結果的に、早くて、正確で、わかりやすい。迷っている企業さんがいたら、「一度試していただきたい」と、素直に思います。
まとめ
「マニュアル作りは書けば終わり」ではありません。
現場で“使える”形に整え、行動につなげる。再現性を持たせ、組織にノウハウを定着させる。そのためには、文章力だけではなく、「構造化」「設計力」「対話力」といった専門スキルが求められます。
本記事で語られた3人のプロの声からもわかるように、マニュアル制作はライティングを超えた業務支援のプロセスそのものです。
だからこそ、迷っている企業こそ一度、“マニュアルのプロ”に任せてみてください。そこには、業務改善の第一歩、そして組織の土台を支える力があります。
ーーー
A Manual Is the Blueprint of Work: Insights from Three Professionals on Its True Purpose
マニュアル作成はmayclassにお任せ!
マニュアル作成を検討しているなら、mayclassにぜひご相談ください。
mayclassでは、マニュアルの企画・構成・制作まで一括でサポートしています。
専門ライターが御社の業務内容や目的を丁寧にヒアリングし、現場で本当に使える実践的なマニュアルを作成いたします。
業務の属人化を防ぎ、誰が見ても迷わず行動できる内容に仕上げることで、教育コストの削減や業務効率化にもつながります。
新規導入からリニューアルまで、お気軽にご相談ください。

▼こちらの記事もおすすめ▼
業務効率化ツールの比較ガイド!おすすめツールと導入ポイントの完全ガイド