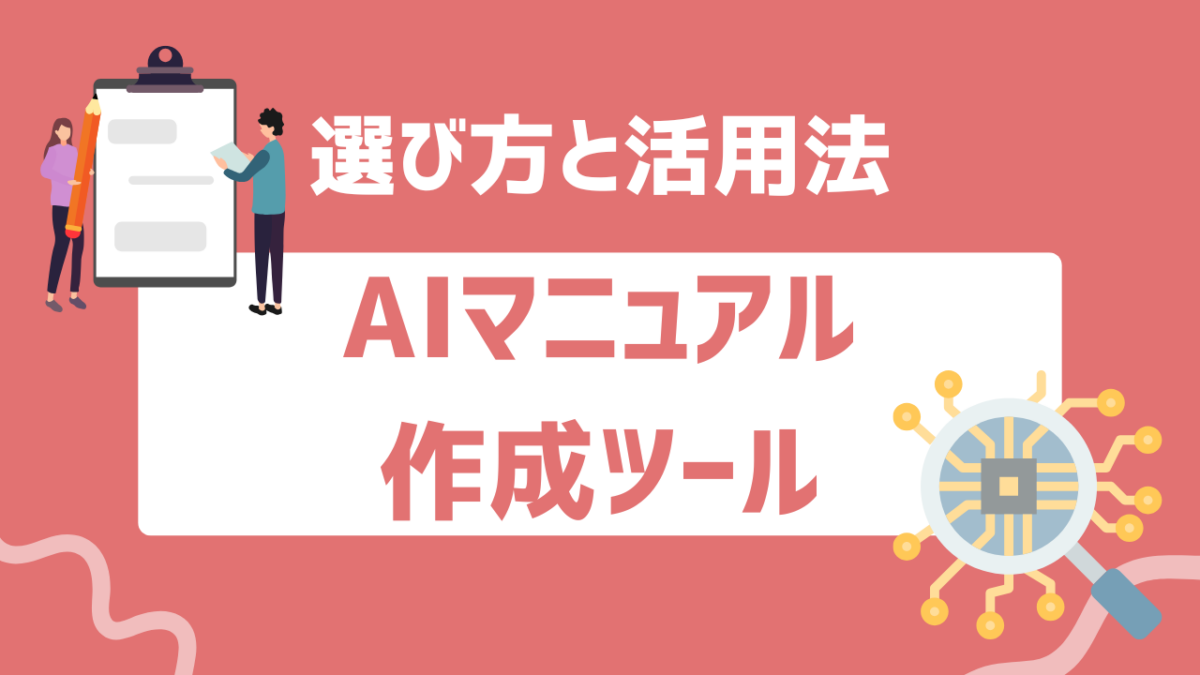マニュアル作成に悩んでいませんか? AIツールを活用すれば、時間とコストを大幅に削減しながら、高品質なマニュアルを作成できます。本記事では、無料・有料のおすすめAIマニュアル作成ツールを、機能、価格、メリット・デメリットの観点から比較・解説。さらに、AIツール導入時の注意点や活用事例も紹介します。AIの力を活かしてマニュアル作成を効率化し、ビジネスの成長を加速させましょう。
AIでマニュアル作成を効率化したい人向けの記事です。
ChatGPTやGemini、Canvaなど、現役ライターが実際に使うおすすめAIマニュアル作成ツールを比較し、機能・価格・注意点をわかりやすく解説。
プロンプトの作り方や導入ステップ、AI活用のコツまでまとめており、
「AIで早く・正確に・伝わるマニュアルを作りたい」企業担当者におすすめです。
現役マニュアルライターがおすすめする!使えるAIツール
今や、文章作成や情報整理、資料づくりといった業務においてAIを活用するのは当たり前になりつつあります。マニュアルや各種ライティング業務に従事するmayclassのライターに聞いた、おすすめのAIツールとその活用方法を紹介します。
① よく使われているツールは?
最も多くの人が利用しているのは、ChatGPT(無料・有料)です。文章作成や構成、企画案の立案、文章の校正など、ライティング関連の作業に幅広く活用されています。無料と有料をうまく使い分け、費用対効果を見ながら使うのが一般的です。
その他、Googleの生成AI「Gemini」や、日本語対応に強い「Felo」、デザインに便利な「Canva」、文字起こしに特化した「Notta」、図解やアイデア整理に役立つ「Napkin」なども併用されています。
② AIツールでマニュアルを作成するメリット
AIツールを活用すれば、アウトラインの作成や要約、資料作成が瞬時に可能になります。これにより、大幅な時間短縮が実現できます。また、「この目次、どう思う?」といった壁打ち相手としても機能し、表現のバリエーション提案や言い回しの整理などにも強みを発揮します。
③ AIをマニュアル作成に使う場合のデメリット
AIの日本語表現にはやや不自然な傾向があります。また、ローカルな情報や専門分野では誤情報が含まれることも。長文や全体構成の精度は人間の手で補う必要があります。さらに、出力の質はプロンプトの書き方によって大きく変わり、個人情報や企業データの取り扱いも慎重にしなければいけません。
④ 情報収集はどこから?
AIツールに関する情報収集には、X(旧Twitter)やYouTubeでの情報収集が主流です。また、セミナーやイベントへの参加、IT感度の高い同僚・知人との情報共有も重要な情報源になります。
AIに任せきりにするのではなく、「どう指示するか」「どこまで任せて、どこを人間が調整するか」を見極める力が求められます。
AIツールを活用したマニュアル作成の効率化
以下では代表的な機能と活用方法を紹介します。
プロンプト作成のコツ
AIツールを活用して質の高いマニュアルを作成するには、「プロンプト(AIへの指示)」の作り方が非常に重要です。AIは指示された内容に忠実に応じて出力を行うため、あいまいな命令では意図通りの成果物にならないこともあります。以下のポイントを押さえることで、AIの出力をより実用的なものに近づけることができます。
目的を明確にする
AIに指示を出す際は、「何を求めているのか」を明確に伝えることが基本です。
例:「この業務手順を新人にもわかりやすく説明してください」「専門的なトーンで、丁寧に書き直してください」など、目的やトーンを具体的に伝えることで、出力のブレを防げます。
具体的なフォーマットを指定する
「箇条書きで」「表形式で」「200文字以内で要約」など、出力の形を指定することで、AIはより意図に沿った形で情報を整理してくれます。特にマニュアルでは、視認性の高い形式を求める場面が多いため、フォーマット指定は非常に有効です。
追加指示で修正を繰り返す
一度で完璧な出力が得られることは少なく、プロンプトに対するAIの応答を見ながら、細かな修正を加えていくのが一般的です。
例:「この部分をもっと具体的にしてください」「言葉づかいをやさしくしてください」など、段階的な指示を重ねることで、より精度の高いマニュアルが完成します。
AIが得意なこと、苦手なことを理解しよう
AIの強みを生かしつつ、弱点を人間が補うことで、マニュアル作成の質と効率を両立させることができます。すべてをAIに任せるのではなく、役割を明確に分担することが大切です。
AIに向いている作業
決まった形式の文章作成、手順の下書きや構成案の作成、用語の統一や文章の整形、翻訳や表現の言い換えなどの反復作業に向いています。
人間に向いている作業
内容の正確性や専門性の確認、実際の利用者に合わせたトーンや表現の調整、マニュアルとしての完成度や伝わりやすさの最終チェックなどが向いています。
AIをうまく活用するためには、プロンプトの工夫と、人による細やかな調整の両方が不可欠です。AIは強力なサポートツールですが、最終的な品質管理は人の目と判断で行うことが、現場で活用できる実用的なマニュアル作成につながります。
AIマニュアル作成ツールの種類と選び方
テキスト生成と編集
ChatGPTのようなAIは、文章の作成や構成を迅速に行えるツールです。指示を出すだけで、短時間で高品質な文章を生成できます。
【活用例とプロンプト例】
- 初心者向けのガイドや手順書:「製品Aの初期設定方法をわかりやすく説明してください」
- 既存マニュアルのリライト:「この文章を簡潔で専門的なトーンに書き直してください」
図表やリストの作成支援
マニュアルに欠かせない図表やリストも、AIで効率よく作成可能です。文章から情報を抽出し、表やリストとして出力することで、情報を視覚的に整理できます。
【活用例とプロンプト例】
- フローチャート作成:「以下の操作手順をフローチャートで説明してください」
- 比較表の生成:「製品A、B、Cの主な仕様を比較する表を作成してください」
スタイルやフォーマットの統一
マニュアル全体のトーンやフォーマットを統一する際にも、AIは効果的です。特に複数人で作成する場合に役立つでしょう。
【活用例とプロンプト例】
- 文体の統一:「この文章をフォーマルなトーンに変更してください」
- 構成の再整理:「この段落を箇条書きにしてください」「セクションにタイトルを追加してください」
- 翻訳と簡易表現:「この文章を英語に翻訳してください」「やさしい日本語に変えてください」
業界や企業に合わせたカスタマイズ
有料な場合が多いですが、カスタマイズ可能なAIツールなら、業界ごとの専門用語や社内ルールにも対応可能です。独自データを学習させることで、より精度の高いマニュアル作成が可能になります。
【活用例】
- 業界特化型の用語対応(ヘルスケア、IT、製造業など)
- 社内マニュアルの作成(システム操作手順書、業務フローの自動生成など)
目的別おすすめAIマニュアル作成ツール【徹底比較】
| ツール名 | 用途 | メリット | デメリット | 公式サイト | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | 文章作成、構成案、企画、校正、情報収集 | 素早く構成作成でき、多様な表現が可能。有料版は画像生成やコード実行にも対応 | 表現に違和感が出ることがあり、確認や工夫が必要 | https://openai.com/chatgpt | 無料(GPT-3.5)/有料(GPT-4:$20/月) |
| Gemini | 文章作成、メール文面、情報調査 | Googleサービスと連携し、作業がスムーズ | 日本語は、一部機能や出力品質において、ChatGPTに劣ることも | https://gemini.google.com/ | 無料/Google One加入で有料版利用可(¥2,900/月) |
| Felo | 文章作成、情報整理 | プレゼン作成、思考整理、画像生成を自動で支援 | 学術性・信頼性が求められる用途には不向き | https://felo.ai/ja/search | 無料/有料 |
| Canva | 資料・画像作成 | デザインが統一される/テンプレ豊富 | 細かい調整が難しい | https://www.canva.com/ja_jp/ | 無料/有料(¥1,500/月〜) |
| Napkin | 図表作成、メモ整理 | テキスト入力でビジュアルを自動生成 | シンプル設計のため、複雑な操作には不向き | https://napkin.one/ | 無料(一部有料) |
| Notta | 音声の文字起こし | 精度が高い | 有料でないと文字数などの機能制限あり | https://www.notta.ai/ja | 無料プランあり/有料(月¥1,200〜) |
ChatGPT(OpenAI)
用途: 文章作成、構成案、企画、校正、情報収集
メリット: アウトライン作成が早く、壁打ちにも適しており、多様な表現が得られます。有料版では画像生成(DALL·E)やコード実行、ブラウジング、メモリ機能などが利用可能です。
デメリット: 表現が不自然になることがあり、出典やファクトチェックが必要。質問(プロンプト)の工夫によって出力品質が大きく変わります。
公式サイト: https://openai.com/chatgpt
価格: 無料(GPT-3.5)/有料(GPT-4:$20/月)
Gemini(Google)
用途: 文章作成、メール文面、情報調査
メリット: Google Workspaceと統合されており、GmailやGoogleドキュメント、スプレッドシートとシームレスに連携可能。
デメリット: 日本語対応の一部機能や品質面では、ChatGPTより劣ることも。
公式サイト: https://gemini.google.com/
価格: 無料/Google One加入で有料版(¥2,900/月)
GeminiについてはGeminiとは?無料版でできること、特徴と便利な使い方、他のAIとの違いをわかりやすく解説でも詳しくご紹介しています。併せてご覧ください。
Felo
用途: 文章作成、情報整理
メリット: プレゼン資料の自動生成やマインドマップ作成が可能。キーワードに基づいた画像生成にも対応。
デメリット: 学術的・信頼性重視の情報検索には不向き。
公式サイト: https://felo.ai/ja/search
価格: 無料/有料プランあり
Canva
用途: 資料・画像作成
メリット: デザインが統一されやすく、豊富なテンプレートが使える。
デメリット: 細かな調整がやや難しい。
公式サイト: https://www.canva.com/ja_jp/
価格: 無料/有料(¥1,500/月〜)
Napkin
用途: 図表作成、メモ整理
メリット: テキストを入力するだけで、AIが自動でビジュアルコンテンツを生成。
デメリット: シンプルさを重視しており、複雑な管理(タグやフォルダなど)には不向き。
公式サイト: https://napkin.one/
価格: 無料(一部有料機能あり)
Notta
用途: 音声の文字起こし
メリット: 高精度な音声認識で文字起こしが可能。
デメリット: 無料版では文字数などの機能に制限あり。
公式サイト: https://www.notta.ai/ja
価格: 無料プランあり/有料(月¥1,200〜)
AIマニュアル作成ツール導入のステップ
1.ニーズの明確化
まず、自社のマニュアル作成における課題や目的を整理します。たとえば「作業時間を短縮したい」「問い合わせ件数を減らしたい」「品質のばらつきをなくしたい」など、具体的な課題を把握することで、AIツールに求める機能が明確になります。
2.ツール選定
整理したニーズをもとに、無料プランの有無や操作性、コスト、拡張性などを比較し、自社の業務に合ったAIツールを選定します。はじめは小規模に試せるツールを選ぶとスムーズです。
3.データ準備
ツールを活用する前に、既存のマニュアルやFAQ、業務手順書などを整理します。情報の重複や古い内容を見直し、これまで文書化されていなかった口頭ノウハウも書き出して、AIが扱いやすい形に整えておきます。
4.トライアル導入
選んだツールを実際の業務で使い、どのような指示でどのような出力が得られるかを確認します。実用性や精度、修正の手間などを評価し、改善点を洗い出すことで、導入効果を見極めます。
5.本導入
トライアルの結果をもとに本格導入へ移行し、社内での活用ルールを整備します。利用する業務の範囲や標準プロンプト、テンプレートを共有し、セキュリティやガイドラインも明確にすることで、組織全体での定着を図ります。
AIツールが難しいときは、プロのライターに依頼しよう
AIは、マニュアル作成に便利なツールですが、上手に活用するには、プロンプトの習得など“使う技術”が必要であり、情報収集といった学習コストも必要です。そんな時はマニュアル作成の専門家であるプロに依頼するのが結局時短になり、効率的です。
プロに依頼するメリット
AIでは対応が難しいニュアンスの調整や業界用語の使い分けなど、専門知識と経験を活かした高品質なマニュアル作成が可能です。構成や流れを整え、使いやすいドキュメントに仕上げます。
時間とコストの最適化
試行錯誤や修正にかかる時間を削減でき、結果的にコストパフォーマンスも向上します。
最新ツールの活用提案も可能
プロのライターはAIツールや業界トレンドにも精通しており、効率的な運用方法を提案できます。
AIと人の力でマニュアル作成を革新しよう
AIマニュアル作成ツールを活用すれば、時間とコストの削減だけでなく、高品質かつ一貫性のあるマニュアルの作成が可能になります。目的に合った方法を選び、AIと人の力を組み合わせて、マニュアル作成を効率化しましょう。
ーーー
Save Time and Cost with AI Manual Creation Tools: How to Choose and Utilize Them
マニュアル作成ならmayclassへ
mayclassでは、マニュアル作成の専門家が貴社のニーズに合わせたマニュアルを提供します。
- プロによるヒアリング
業務内容を丁寧にヒアリングし、特性を的確に捉えたマニュアルを作成。 - 優先度に基づくマニュアル化
重要な業務から優先的に対応し、早期の業務改善を実現。 - わかりやすいデザイン
読みやすく、視覚的にも整理されたフォーマットを提案。

▼こちらの記事もおすすめ▼
【業務マニュアル作成のコツ】完璧な目次の作り方ガイド!項目例もご紹介