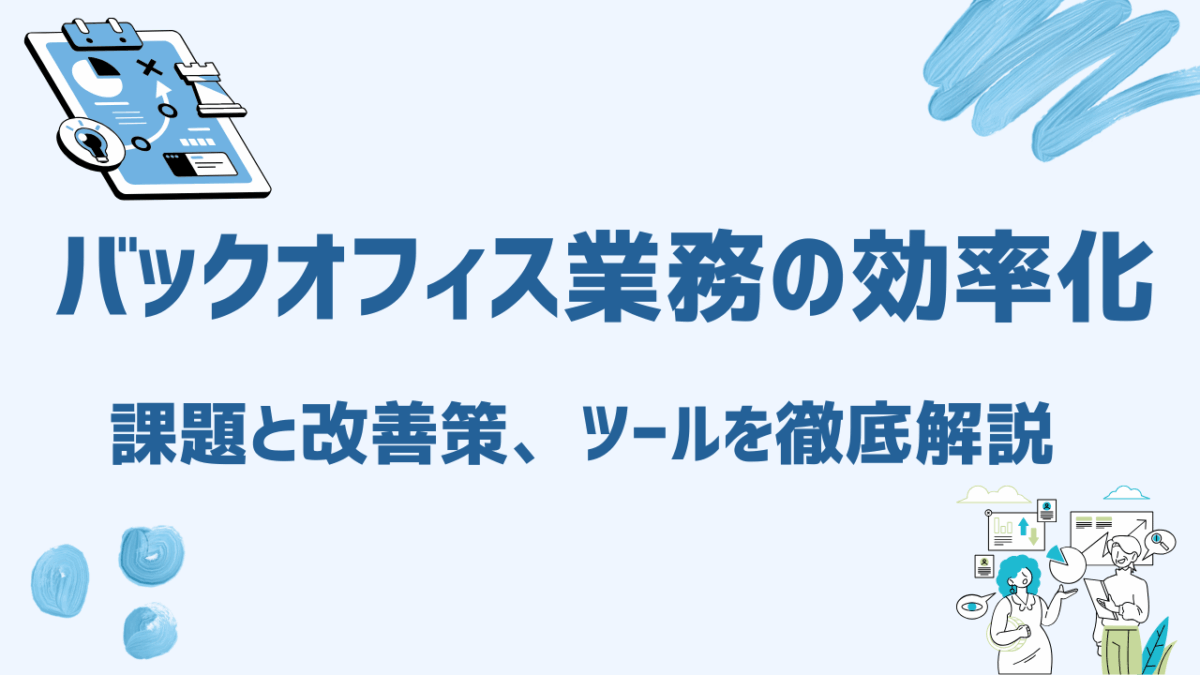バックオフィス業務は、経理・人事・総務・情報システムなど、企業を裏側から支える重要な役割を担っています。
ところが現場では、紙の書類や属人的な手順、二重入力や承認の遅れなど、非効率な仕組みがいまだに多く残っているのが実情です。その結果、コア業務に時間を割けず、経営のスピードや生産性を阻害してしまうケースも少なくありません。
本記事では、バックオフィス業務を効率化する方法について解説します。
バックオフィスの非効率に悩む企業向けに、業務改善の具体策をわかりやすく解説した記事です。紙文化・属人化・承認遅延などの課題を整理し、可視化・標準化・電子化・自動化・アウトソーシングといった実践しやすい改善手法を紹介。生産性向上や働きやすさの実現に役立つ総合ガイドです。
バックオフィス業務を効率化する具体的な方法
バックオフィスを効率化するには、明確な手段を選び、計画的に取り組む姿勢が求められます。近年はテクノロジーの進化やクラウドサービスの普及によって、中小企業でも手軽に取り入れられる効率化策が増えてきました。
ここでは、バックオフィス業務の効率化で実践しやすい5つの方法を解説します。
業務プロセスの可視化と標準化
バックオフィス業務は「誰がどの順番で何をしているのか」が見えにくく、担当者に依存してしまうケースが多くあります。また、属人化が進むと担当者が不在の際に業務が止まるなどのリスクが発生します。
まず取り組むべきは、業務プロセスの可視化です。フローチャートや業務分解図を用いて手順を整理し、重複作業や無駄な工程を洗い出しましょう。
そのうえで誰でも同じ品質で業務を遂行できるよう標準化ルールを整備すれば、引き継ぎや教育もスムーズになります。
ペーパーレス化・電子承認の導入
申請や承認を紙の書類で行っていると、印刷・押印・回覧などに時間がかかり、承認の遅れが生じやすくなります。また、紙の書類は保管や検索も煩雑で、情報共有が難しいのも課題です。
電子承認システムやクラウドストレージを導入すれば、場所を問わず申請や承認が可能になり、処理スピードを大幅に改善できます。検索性やセキュリティも高まり、過去データの活用も容易に行えるようになります。
RPA・自動化ツールの活用
経費精算のチェックや請求データの入力、勤怠集計など、定型的で繰り返し発生する作業はRPAで自動化できます。
人が行うと時間がかかる単純作業をツールに任せることでヒューマンエラーを防ぎ、担当者はより付加価値の高い業務に集中できるのです。
小規模から導入できるクラウド型の自動化サービスも増えているため、コストを抑えながら効率化を進められるでしょう。
クラウドサービスによる情報共有
バックオフィス業務では、経理・人事・総務など複数の部署が関わるケースが多く、情報が分散しやすいという課題があります。メール添付や紙の書類を使ってやり取りしていると最新版の管理が難しく、確認作業に余計な時間を取られることも少なくありません。
クラウドサービスを活用すれば、リアルタイムでデータを共有・更新できるため、常に最新情報にアクセスできます。勤怠管理や経費精算、契約書管理などの業務でもクラウド化が進んでおり、テレワーク環境でもスムーズに業務を回せる点が大きなメリットです。
さらにアクセス権限を細かく設定できるため、セキュリティ面でも安心して利用できます。
アウトソーシングの活用
ツール導入やシステム化では解決が難しい場合に役立つのが、専門家や外部サービスへのアウトソーシングです。
特に、給与計算や社会保険手続き、税務申告といった高度な専門知識が必要な業務は外部に委託することで、正確かつ効率的に処理できます。
繁忙期のみ業務量が増えるようなケースでも、アウトソーシングを活用すれば必要なときだけ外部リソースを確保でき、固定人件費を抑えることが可能です。
委託にあたっては、業務範囲・成果物・責任分担を契約で明確にしておき、トラブルを防ぎましょう。
なぜバックオフィス業務の効率化が必要なのか
バックオフィス業務は、売上や顧客に直結するフロント業務とは違い、一見すると間接部門と捉えられがちです。
しかし実際には、経理・人事・総務などが円滑に回っていなければ、企業活動そのものが滞ってしまいます。にもかかわらず、多くの企業では効率化が後回しにされており、慢性的な非効率が放置されがちです。
ここでは、バックオフィスの効率化が求められる背景を解説します。
バックオフィスが企業経営に果たす役割
バックオフィスは目立たない存在ではありますが、企業の経営基盤を支えるために欠かせない役割を担っています。
主な機能は以下の4つです。
- 経理
- 人事・労務
- 総務
- 情報システム
どのような役割があるのか、それぞれ解説します。
経理
経理は資金繰りや経営判断の根拠となる数字を整備する部門です。売上や経費を正確に処理することはもちろん、月次・年次の決算を迅速にまとめることが重要です。
さらに、税務や監査対応など法令遵守の観点でも重要な役割を果たしています。
人事・労務
人事・労務は社員の採用や教育、評価制度の運用を通じて組織の力を引き出すと同時に、労働基準法や社会保険制度といった法令を守る役割も担います。
勤怠管理や給与計算に加え、福利厚生を整える業務は社員の働きやすさを支え、モチベーションや離職防止にもつながります。
総務
総務は契約や備品管理、社内文書の整備などを通じて事業活動を支えます。オフィス環境の整備や安全衛生の管理も担当するため、全社員が安心して働ける職場づくりに欠かせない部門です。
多岐にわたる業務を一手に担う「縁の下の力持ち」ともいえるでしょう。
情報システム
情報システムは、企業の土台となるIT環境を守る部門です。パソコンやネットワーク、業務システムの運用やセキュリティ管理を幅広く担当し、各部門が安心して業務に集中できる環境を支えています。
DXの進展に伴い、経営の意思決定にも深く関わる領域です。
バックオフィス業務のよくある課題(属人化・紙文化・二重入力・承認遅延など)
バックオフィスが企業の経営基盤を支えるために欠かせない一方で、多くの企業のバックオフィス業務には共通する課題があります。代表的なのは、属人化による業務停滞です。
特定の担当者しか手順を把握していないと休暇や退職によって処理が止まり、請求書や給与計算が遅れるケースは珍しくありません。
紙文化も依然として根強く、申請や承認を紙で行っていると書類が承認者の机に積み上がり処理が遅れるだけでなく、回覧中に紛失するリスクさえあります。
さらに、複数のシステムや帳票に同じ情報を繰り返し入力する二重入力も大きな非効率の要因です。営業部門で入力したデータを経理部門が再入力する、といった重複作業は時間と労力がかかります。
承認フローの複雑さから書類が滞留し、支払い遅延や契約の停滞につながる「承認遅延」もよくある問題です。
これらの課題を放置すると、生産性の低下だけでなく社員のモチベーション低下や経営上のリスク拡大にもつながります。
バックオフィスの効率化はコスト削減にとどまらず、企業が安定的に発展していくための大切な取り組みといえるでしょう。
バックオフィス業務効率化によって得られるメリット
バックオフィス効率化の取り組みは、単なる事務作業の短縮にとどまりません。企業全体の競争力や社員の働きやすさにつながる大きなメリットがあります。
ここでは、バックオフィス業務を効率化することのメリットを詳しく解説します。
ムダを減らし生産性を高める
紙書類の回覧や二重入力といった無駄な作業を削減すると、処理速度はアップします。
たとえば、経費精算をクラウド型のシステムに移行した企業では、以前は1週間かかっていた承認作業が数日に短縮され、経理部門の残業時間も減少しました。
さらに、RPAを活用して勤怠データの集計や請求書処理を自動化したケースでは、担当者が毎月20時間以上のルーティン作業から解放され、データ分析や改善提案といったより価値の高い業務に集中できるようになっています。
効率化は単なるスピードアップではなく、社員の時間をより生産的に使える環境づくりにつながります。
ただし導入にはコストがかかるため、対象業務の選定を誤ると逆に非効率になる点には注意しましょう。
コストを最小限に抑え経営を強化する
バックオフィスの効率化は、間接コストの削減にもつながります。
紙・印刷・郵送にかかる費用はもちろん、人件費の抑制にも効果的です。特にアウトソーシングを活用すれば、これまで社内で抱えていた固定的な人件費を変動費に切り替えられ、景気や繁忙期の波に応じて柔軟に対応できます。
また、電子帳簿保存法の改正により、クラウド会計ソフトの導入はコスト削減だけでなく法令を守るうえでも役立ちます。
さらに、効率化により経営数字がタイムリーに把握できるようになれば、投資判断や戦略策定もスピードも上がります。単なるコスト削減にとどまらず、経営基盤を強化し、利益率向上につなげられる点が大きなメリットです。
働きやすい環境を整え社員の満足度を向上させる
バックオフィスの効率化は、社員の労働環境を改善し、組織全体の働きやすさを高める取り組みにもなります。紙の申請や承認を電子化すればわざわざ出社してハンコを押す必要もなくなり、在宅勤務やフレックスタイムもぐっと取り入れやすくなります。
また、煩雑な処理が減ることで「業務がスムーズに進む」という実感が得られ、モチベーションの維持や離職率の低下にもつながります。
バックオフィス業務と効率化ツール
バックオフィス業務の効率化には多くのメリットがありますが、「どの業務から取り組めば効果が出やすいのか」と迷う方も少なくありません。ここでは、代表的なバックオフィス業務と、それを効率化できる主要なツールをご紹介します。
経理・会計業務(請求書処理、経費精算など)
経理・会計はバックオフィス業務の中心であり、効率化の効果が出やすい分野です。請求書処理や経費精算を紙やExcelで行っていると、入力や確認作業が煩雑になり、承認フローも滞りがちです。
そこで活躍するのが、クラウド会計ソフトや経費精算システムです。以下に、ツールの例を詳しく紹介します。
参考:経理業務の業務効率を劇的に上げる方法とは?ツール・改善ポイントまで徹底解説!
経理・会計業務の効率化ツール例

銀行口座やクレジットカードとの自動連携で仕訳が一部自動化されます。請求書の受取機能(“受取請求書”)を使えば、Web共有された請求書やURLで送付された書類を自動で取り込み、仕訳までスムーズに進めることが可能です。帳簿の可視化、経営指標のダッシュボードなども備えており、中小企業や個人事業主に人気です。

法人・個人双方に対応しており、操作性が比較的やさしいのが特徴です。確定申告対応、経営分析、帳簿の共有機能など、会計・税務周りの業務をまとめて管理できます。クラウド型なので最新版機能も順次反映され、複数部署でのデータ共有もしやすい設計です。

日本で長く会計ソフトとして定着している「弥生」のオンライン版。使い慣れた帳簿形式を踏襲しつつ、クラウド対応でいつでもどこでもアクセス可能。補助科目やレポート機能が強く、既存の弥生製品ユーザーにとってもスムーズに移行できる点がメリット。
人事・労務管理(勤怠管理、給与計算、入退社手続き)
勤怠管理や給与計算は毎月必ず発生し、処理に時間を取られる典型的なバックオフィスの業務です。紙のタイムカードや手作業による集計では、入力ミスや計算ミスが起きやすく、社員の不満やトラブルにつながることも少なくありません。
これを解決するのが、勤怠管理システムや給与計算ソフトです。以下に代表的なツールを挙げ、その特徴と公式サイトを紹介します。
参考:人事業務を効率化!マニュアル作成で実現する効率化と生産性アップの秘訣とは?
人事・労務業務の効率化ツール例

勤怠打刻、給与計算、人事労務を一つのプラットフォームで管理できるオールインワン型。入社手続き(オンボーディング)やマイナンバー管理、年末調整なども対応。UIが洗練されていて操作性が高いのもメリット。

出退勤の打刻からシフト作成、休暇申請・承認などまでカバー。多様な勤務形態(フレックスタイム・変形労働等)やシフトパターンも柔軟に設定でき、スマホ打刻も対応。導入コスト・導入ハードルが低く、中小企業にも人気。

細かい勤怠実績管理に強み。打刻方法が複数あるほか、自動休憩時間の設定や打刻忘れ防止など細かな調整が可能。残業・深夜割増対応もあり、実務的なニーズに応える仕様。
総務業務(契約書管理、備品発注、社内文書管理)
総務部門は契約書の管理から備品の発注、社内文書の整備まで幅広い業務を担っており、「何でも屋」と呼ばれることもある部署です。その反面、担当者ごとに管理方法が異なったり、紙やExcelに依存することで情報が散在しやすく、属人化が進みやすいのが課題です。こうした業務には、クラウド型の契約管理サービスやワークフローシステムが大きな効果を発揮します。
参考:総務業務を効率化するマニュアル活用術|属人化を防ぎ、業務の質を底上げ
総務業務の効率化ツール例

日本発の電子契約サービスで、契約締結から管理までをオンラインで完結できます。紙の契約書に比べて大幅な時間短縮とコスト削減が可能で、法的効力も安心。更新期限のアラート機能や、契約の進捗状況を一元管理できる点も強みです。
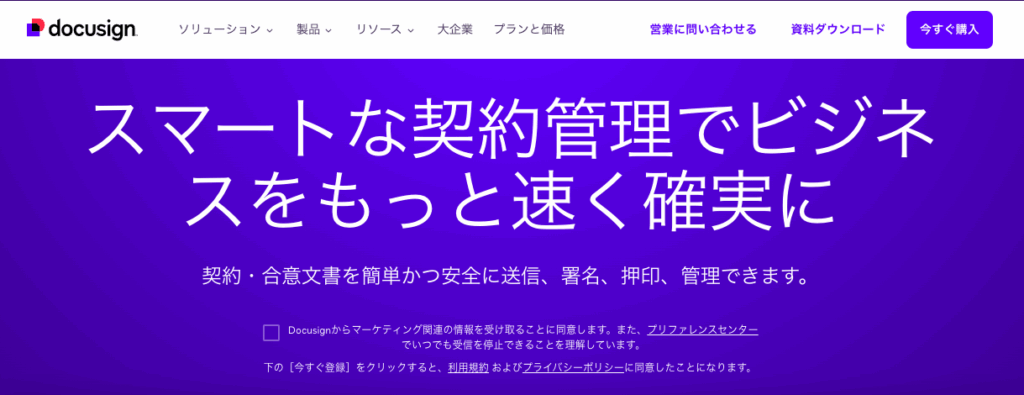
情報システム管理(ID管理、問い合わせ対応)
社員のアカウント発行や権限設定、PCやソフトウェアに関する問い合わせ対応なども、バックオフィスで頻繁に発生する業務のひとつです。担当者が手作業で対応していると、申請から利用開始までに時間がかかり、業務立ち上げの遅れやセキュリティリスクにも直結します。こうした課題を解決するには、ID管理の自動化ツール や ヘルプデスク支援システム の導入が効果的です。
情報システム管理のツール例
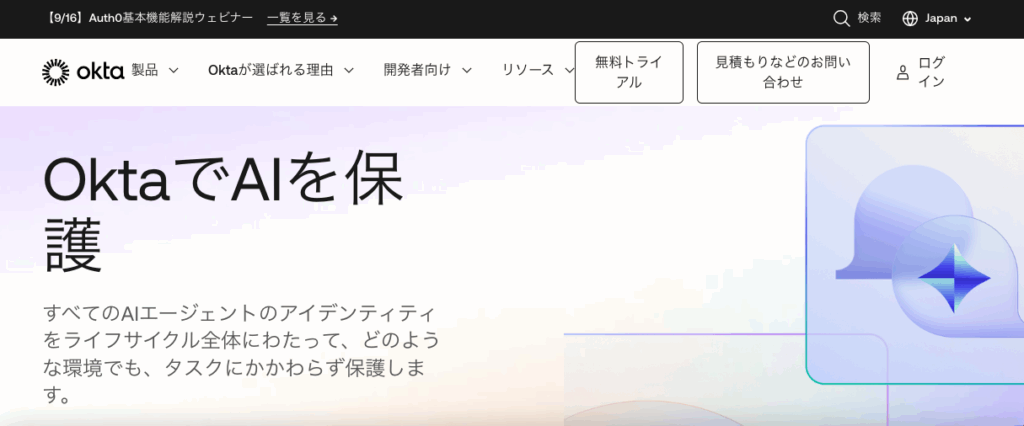
世界的に利用されているIDaaS(Identity as a Service)。入社時のアカウント発行、退社時のアクセス削除を自動化でき、クラウドアプリとのシングルサインオン(SSO)も可能です。セキュリティ強化と業務効率化を両立できます。
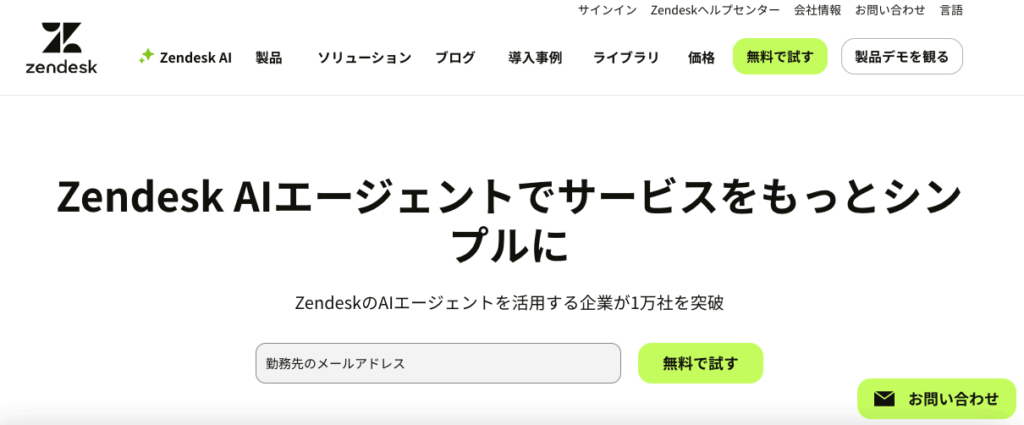
世界的に広く利用されているカスタマーサポートプラットフォーム。問い合わせチケットの自動振り分け、FAQデータベース、チャットサポート機能を備え、社内ヘルプデスクとしても導入可能です。担当者の工数削減と対応品質向上を両立できます。
バックオフィス効率化を成功させるためのポイント
効率化の対象業務が明確になったら、次は実際の取り組み方が重要です。ツールを導入しただけでは思ったほど効果が出ないケースも多く、現場の理解や運用体制が整っていなければ改善は定着しません。
ここでは、バックオフィス効率化を成功させるために押さえておきたいポイントを4つ解説します。
現状の課題を正しく把握する
最初に欠かせないのは、現状の業務フローを客観的に把握することです。「なんとなく非効率に感じる」といった曖昧な状態のまま改善を始めると、的外れな施策に時間とコストをかけてしまいかねません。
次のような方法を取り入れると、改善すべき箇所が明確になります。
- 業務フローを図式化して手順を見える化する
- 各工程にかかる時間や担当者を把握する
- 現場担当者へのヒアリングでボトルネックを明確化する
たとえば「請求書処理の承認に3人を経由しており、1件あたり平均2日かかっている」など、業務量やコストも含めて数値化できれば改善策の効果測定もしやすくなります。
小さな業務から段階的に改善する
一度にすべてを改革しようとすると現場が混乱してしまうため、小さく始めて成功体験を積み上げることが重要です。
具体例としては以下のような業務が挙げられます。
- 日常的に処理件数が多い「経費精算」や「勤怠管理」
- 電子帳簿保存法やインボイス制度など、法令改正に伴い対応が迫られている業務
こうした業務から着手すれば短期間で改善効果を確認できるうえ、コンプライアンス強化の面でも説得力を持たせられます。小規模な成功を社内に広めることで「効率化は役立つ」という共通認識が生まれ、他部門へもスムーズに展開できるようになるでしょう。
ツール導入と運用ルールの整備をセットで進める
新しいツールやシステムを導入しても、ルールが整備されていなければ運用はうまくいきません。むしろ現場が混乱し、「使いにくいから元に戻したい」といった声が上がることすらあります。
たとえば、次のような仕組みを導入と同時に設定しておくと効果的です。
- 承認権限の明確化(例:〇万円以上は部長承認が必要)
- 処理期限やリマインドの仕組みを設定
- 利用マニュアルや研修を用意して周知徹底
ツールとルールをセットで導入すれば、現場の混乱を防ぎ、安定した業務運用が可能になります。
社員を巻き込んだ業務改善文化をつくる
効率化はシステム部門や一部の担当者だけで進めても長続きしません。だからこそ、現場の社員を巻き込み、日々の業務の中で自然に改善に参加できる仕組みを整えることが重要です。
具体的には以下のような仕組みが考えられます。
- 改善提案制度やアンケートを設け、現場の声を集める
- 提案を実際の施策に反映し、社員にフィードバックする
- 成果を数値や事例で全社共有する
「経費精算の承認にかかる時間を半減できた」「残業時間を15%削減できた」など、具体的な成果を伝えることで、社員は効率化の効果を実感しやすくなります。改善の手応えが広がれば、一度きりの取り組みではなく、組織文化として少しずつ定着していくでしょう。
バックオフィス業務を効率化しよう
バックオフィス業務は表舞台に出ることは少ないものの、企業活動を支える要です。属人化や紙書類の多用、承認遅延などの課題を放置すると、生産性だけでなく社員のモチベーションやリスク管理にも影響します。
そのため、業務プロセスの可視化・標準化、ペーパーレス化、RPAやクラウドサービスの活用、さらにはアウトソーシングの導入などを組み合わせて検討することが欠かせません。こうした取り組みを通じて無駄を減らしながら生産性を高め、コスト削減や法令遵守、働きやすい環境づくりを同時に進められます。
重要なのは一度に全てを変えようとするのではなく、現状を丁寧に把握し、取り組みやすい業務から段階的に改善していく姿勢です。小さな成功の積み重ねが、最終的に大きな成果へと結びつくでしょう。
業務効率化はmayclassにお任せ!
mayclassは、業務分解図やflowzooをはじめとする独自のフレームワークとツールを活用し、企業の業務を徹底的に可視化・最適化します。
アカデミックな知識を持つAI専任アドバイザーが在籍しており、最新のAI活用からマニュアル整備、業務改善まで一気通貫でサポート可能。属人化の解消やバックオフィスの効率化、現場定着までを伴走支援します。
「どの業務から効率化すべきか分からない」
「既存のツールが活用しきれていない」
「AIを使った業務改善に興味がある」
そんな課題をお持ちなら、ぜひ一度mayclassにご相談ください。
効率化の第一歩は“見える化”から。
私たちが御社の成長を全力でサポートします。

ーーー
How to Streamline Back-Office Operations: Challenges, Solutions, and Recommended Tools
▼下記記事もおすすめ▼
Geminiとは?無料版でできること、特徴と便利な使い方、他のAIとの違いをわかりやすく解説
Gemini Storybookとは?機能・使い方・料金・商用利用を完全ガイド
Geminiで画像生成はできる?使い方・特徴・無料版と有料版の違いを徹底解説