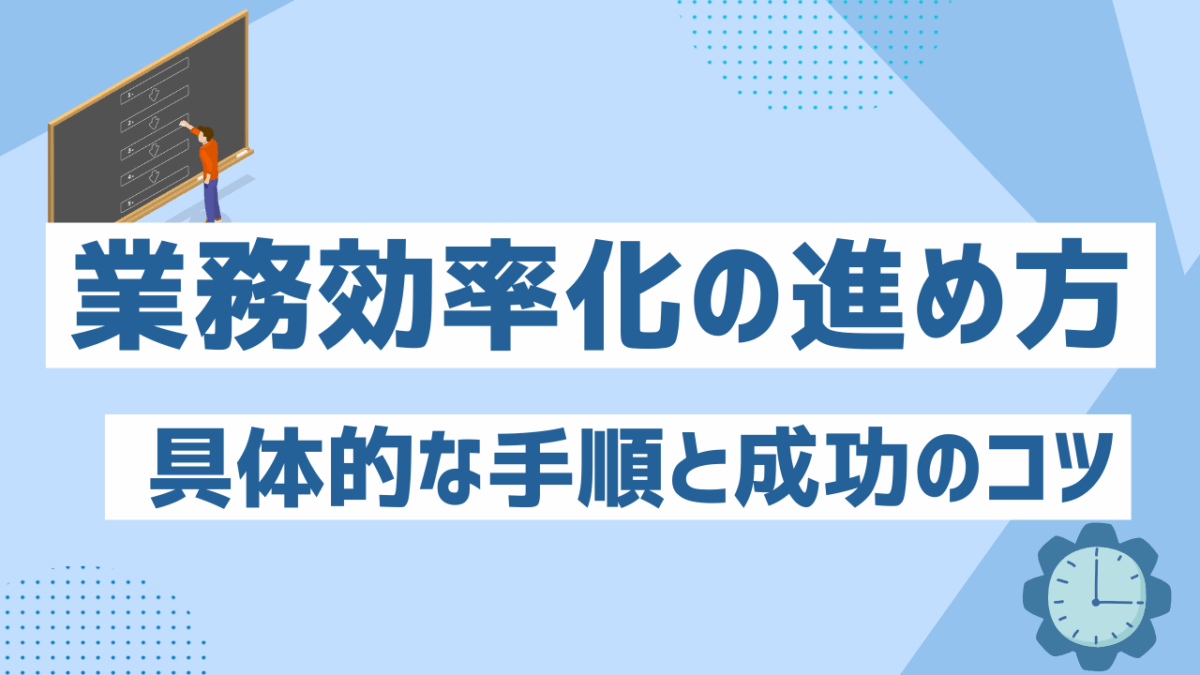「業務効率化を進めたいけど、具体的にどう進めればよいのかわからない…」そんな悩みを抱える企業担当者やチームリーダーは少なくありません。ムダな作業を減らし、生産性を高めるには、″正しい進め方”を理解することが欠かせません。
本記事では、業務効率化の基本ステップと実践方法をわかりやすく解説。現状把握から課題の整理、優先順位のつけ方、ツール導入やフロー改善のポイント、さらに継続的に成果を出す仕組みづくりまで、初心者でもすぐに取り組める具体例を交え、成功につながる業務効率化の進め方を紹介します。
業務効率化を進めたい担当者向けに、現状把握から課題整理、優先順位のつけ方、改善方法、ツール活用までを体系的に解説。無駄削減・生産性向上を実現する具体的なステップと実践例をまとめ、初心者でも正しく効率化を進められる内容です。
業務効率化の進め方を理解する
企業や組織で業務効率化を進めるうえで、最初の重要なステップが「だれもが共通の認識で理解していること」です。効率化という言葉はよく耳にしますが、人によってイメージが異なり、「とにかく早く終わらせること」や「人員削減につなげること」など、狭い意味で捉えられることがあります。
正しく理解をせずに進めても、期待した成果が出なかったり、現場に負担を与えて逆効果になってしまうこともあります。
そのため、まずは「業務効率化とは何か」をしっかり押さえたうえで、効率化がもたらす効果を多面的に理解することが大切です。
業務効率化とは何か
「業務効率化」とは、単に作業時間を短縮することだけを指すものではありません。むしろ重要なのは「限られた時間やコストをどう使って、最大限の成果を生み出すか」という視点です。
例えば、ある社員が毎日1時間かけて手入力でデータをまとめているとしましょう。これを効率化する方法は複数あります。システムを導入して自動化するのも一つ、フォーマットを統一して入力作業を削減するのも良い方法でしょう。大切なのは、単純に「早く終わらせること」ではなく、その作業の付加価値を高め、全体として成果が最大化されることなのです。
さらに、効率化は「人間が手を抜く」という意味ではありません。むしろ逆で、「人間が頭を使うべき業務に集中できるよう環境を整えること」が目的です。”ルーチンワークはツールに任せ、判断や創造力が求められる業務に人材を活かす”それが効率化の本質です。
業務効率化が企業にもたらす効果
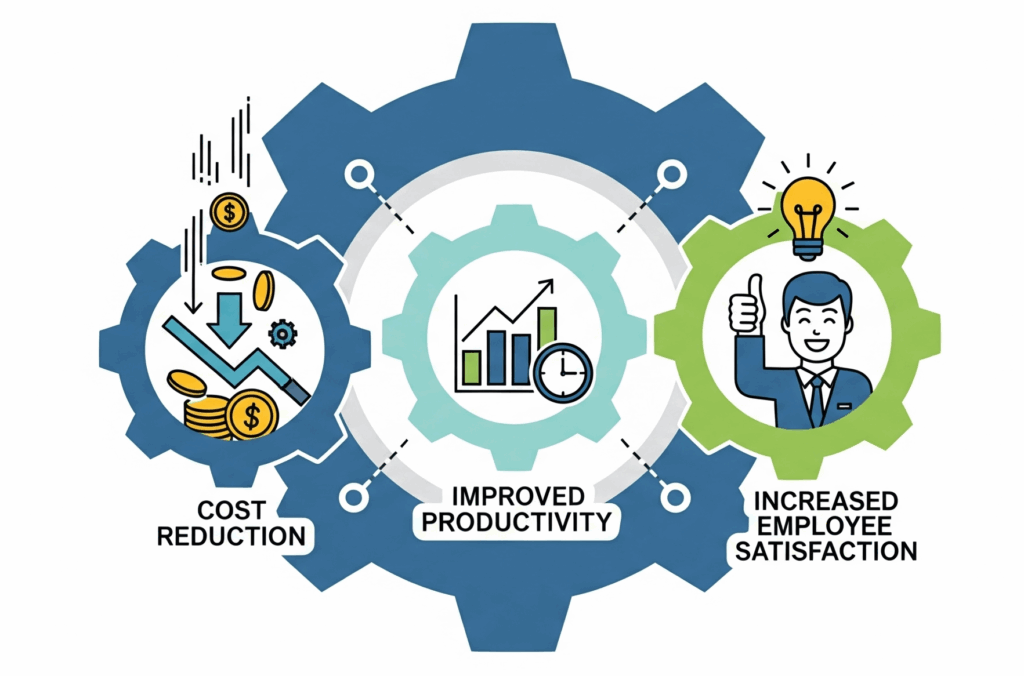
業務効率化の効果①:コスト削減
業務効率化の効果は多方面に及びます。最もわかりやすいのは「コスト削減」です。重複作業を減らしたり、承認プロセスを見直したりするだけで、人件費や時間の無駄が減ります。ある中小企業では、請求書処理を紙からクラウドシステムに切り替えたことで、月末の処理時間が従来の5分の1に短縮され、残業代の削減にも直結しました。こうした具体的な改善は、会社全体の固定費を抑えることにつながります。
業務効率化の効果②:生産性向上
次に挙げられるのが「生産性向上」です。効率化によって社員が本来の業務に集中できるようになると、売上に直結する活動に時間を使えるようになります。例えば、営業担当者がデータ入力に追われていると新規顧客の開拓に時間を割けませんが、その入力を自動化できれば、営業本来の仕事に注力でき、結果として売上増加に結びつきます。つまり効率化は単なる「省力化」ではなく「成長のための投資」でもあるのです。
参考:【図解でわかる】生産性向上と業務効率化の違いとは?意味・目的・施策を徹底比較!
業務効率化の効果③:社員満足度の向上
見逃せないのが「社員満足度の向上」です。非効率な業務は社員のストレスの根源になりがちです。毎日のように同じエラーを修正させられたり、意味のない会議に時間を取られたりすると、モチベーションが下がります。逆に、無駄が削減されスムーズに業務が回るようになると、「働きやすさ」を実感しやすくなります。ワークライフバランスの改善にもつながり、離職防止や採用力の強化といった副次的な効果も期待できます。
こうした効果は単独で現れるのではなく、相乗効果を生み出します。コストが削減されれば資金を新規事業に投資でき、生産性が向上すれば売上が伸び、社員が満足すれば定着率が高まり、長期的に安定した成長基盤を築くことができるのです。
業務効率化の進め方【基本ステップ】
具体的に業務効率化を進めるにあたって「とりあえずツールを入れてみる」「他社がやっている方法を真似する」といったアプローチをとる企業は少なくありません。しかし、単に施策を導入するのではなく、組織に合った段階的な進め方を取り入れることが大切です。次からは、業務効率化を成功させるための基本ステップに基づいて、どう実践すればよいのかを順に整理していきます。
業務効率化の進め方①:現状把握と課題の洗い出し
最初のステップは「現状を正しく把握すること」です。
効率化というと、「残業を減らしたい」「ツールを導入したい」といった解決策にいきがちですが、何より先に「今どの業務が、どのように、どのくらいの時間とコストをかけて行われているのか」を把握する必要があります。
具体的には、まず業務フローを可視化しましょう。
紙に書き出す、フローチャートを作成する、業務日報からデータを拾い出すなど、方法はさまざまあります。重要なのは「感覚ではなく、事実に基づいて把握する」ことです。社員が「この作業は5分くらい」と思っていても、実際には10分以上かかっていることがよくあります。数字として見える化することで、改善の優先順位が明確になります。
課題の洗い出しでは、無駄な二重チェックや属人化した業務など「本来は減らせる作業」に注目するとよいでしょう。現場の声を集めることも欠かせません。効率化はトップダウンで押しつけるよりも、実際に業務を担っている社員の不満や困りごとを吸い上げるほうが成功につながります。
課題の洗い出しについては、業務改善で成果を出す!問題点の洗い出し完全ガイド【5ステップ+実用ツール】でも詳しくご紹介しています。こちらも併せてご覧ください。
業務効率化の進め方②:業務の優先順位を決める
課題が見えたら、次は「優先順位づけ」です。効率化したい業務がいくつも出てくると、「どれから手をつければよいのかわからない」という状況に陥ります。洗い出した課題に対して優先順位をつけます。すべての課題を同時に解決しようとすると現場に大きな負担がかかり、途中で挫折してしまうこともあります。そのため、効果が大きいものや取り組みやすいものから着手するのが賢明です。たとえば、承認に時間がかかっている場合はワークフローの見直しから始めるといった具合です。
ここで役立つのが「インパクト」と「実現可能性」という2つの軸です。
インパクトとは、その業務を改善することでどれだけ大きな効果が得られるかを指します。時間の削減、人件費の圧縮、売上への影響など、多面的に評価します。実現可能性とは、改善に必要なコストや工数、技術的なハードルなどを考慮したものです。この2軸で課題を整理すると、「すぐに取り組むべきもの」「後回しにするもの」が明確になります。
例えば、毎日繰り返しているデータ入力の手作業を、システムを導入してRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)で自動化するのは、効果も大きく、実現もしやすいケースです。一方で、コストや導入負荷が大きいため、優先度は低くなることがあります。効率化は「やりやすいところから成果を出す」ことが肝心です。
業務効率化の進め方③:効率化の方法を選定する
優先度が決まったら、具体的に「どう効率化するか」を決める段階になります。業務の手順を変更したり、外部リソースを活用したりと複数の選択肢を比較検討することが重要です。ここで初めて、ツール導入やフロー改善といった施策を検討します。
効率化の方法は大きく分けて、①ツールやシステムの導入、②業務フローそのものの見直し、③人材の活用や外部リソースの導入、の3つがあります。詳細はこの後に解説しますが、この段階では「現状の課題に合った方法はどれか」を冷静に判断することが重要です。
よくある失敗が「最新のITツールを導入すれば解決するはず」と短絡的に決めてしまうことです。ツールはあくまで手段であり、目的ではありません。課題が「承認プロセスの複雑さ」であれば、まず承認ルートを簡略化するのが先決で、ツール導入はその補助にすぎません。自社の現場に合わない方法を無理に採用すると、逆に混乱を招きかねません。
業務効率化の進め方④:小さく試し改善を繰り返す
効率化の施策の成功のポイントは、一度に大規模な変化を起こすのではなく、まずは一部のチームやプロセスで試し、効果を検証した上で全社に展開する「小さく始めて改善を繰り返す」ことです。これが「PDCAサイクル(Plan→Do→Check→Act)」です。
全社に一気に新システムを導入すると、操作方法がわからない社員が続出し、現場が混乱する恐れがあります。そのため、まずは一部の部署や少人数のチームで試し、使い勝手や効果を検証しながら改善を加え、そのうえで段階的に拡大するのが安全です。
また、効率化の施策は「一度やって終わり」ではなく、環境や組織の状況は常に変化します。市場環境が変われば優先すべき業務も変わりますし、社員の働き方や技術の進化に合わせて新しい方法を取り入れていかなければなりません。継続的に試行錯誤を重ねる姿勢が、長期的な成果を生み出します。
基本ステップを押さえることの重要性
ここでの基本ステップ、「現状把握」「優先順位づけ」「方法の選定」「小さく試して改善」は、一見すると当たり前のようですが、実際には抜け落ちがちなプロセスです。特に「現状把握」と「小さな試行」は軽視されやすく、失敗の原因になっています。
この効率化の基本ステップを踏むことで、場当たり的な対応ではなく、再現性のある改善が実現します。また、組織としての学習も蓄積され、次の改善に活かすことができます。
業務効率化の具体的な方法
具体的にどう改善すればいいのかのという段階になると、方法は大きく分けて3つあります。
ITツールやシステムを導入する方法、業務フローそのものを改善する方法、人材活用や外注を取り入れる方法です。それぞれの特徴と、どんなシーンで有効なのかを理解しておくと、自社に合ったアプローチを選びやすくなります。
業務効率化を進めるには目標設定も重要です。業務効率化の目標設定完全ガイド!SMART法・KPI/KGI・指標例まで徹底解説も併せてご覧ください。
ツール導入による業務効率化
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)は、定型的で繰り返し行う作業を自動化できる仕組みです。例えば、請求書データをシステムに入力したり、決まったルールでファイルを整理したりする作業を、ソフトウェアが人間の代わりに処理します。これによって、今まで数時間かかっていた作業が数分で終わるというケースも珍しくありません。
クラウドサービスの導入も効果的です。ファイル共有をクラウドに一本化することで「最新版がどれかわからない」といった混乱を防ぎ、リモートワーク環境でもスムーズに業務が進みます。また、AIの活用も進んでおり、チャットボットによる問い合わせ対応や、需要予測をAIで行う仕組みなど、企業の負担軽減に直結する例が増えています。
ただし、ツール導入には当然、初期費用や学習コストが伴います。そのため「課題に合ったツールかどうか」を見極めることが重要です。最新の機能が多いからと導入しても、現場が使いこなせなければ返って非効率を生み出してしまいます。
参考:業務効率化ツールの比較ガイド!おすすめツールと導入ポイントの完全ガイド
フロー改善による効率化
ツール導入よりも即効性があるのが「業務フローそのものの見直し」です。多くの企業では、長年の慣習で承認プロセスが複雑化していたり、同じ内容を二重三重にチェックしていたりすることがあります。こうした無駄を整理するだけでも大きな改善効果が得られます。
例えば、出張申請の承認ルートが課長→部長→役員→総務というように長すぎる場合、申請者も承認者も余計な手間を強いられます。これを課長と部長の承認に簡略化するだけで処理スピードは大幅に改善されます。
また、業務マニュアルの整備も効果的です。作業手順が明文化されていないと、人によって方法が異なり、品質にばらつきが出ます。マニュアルを共有しておけば新人教育の時間短縮にもつながり、属人化の防止にもなります。
人材活用・外注による業務効率化
すべての業務を自社で抱え込む必要はありません。専門性が求められる業務や、社内のリソースを割きづらい業務は、外部に委託するのも選択肢です。経理処理やITシステムの運用保守、人事関連の手続きなどは、アウトソーシングの代表例です。
また、クラウドソーシングを活用して、一時的な業務を外部のフリーランスに任せることもできます。例えば、大量のデータ入力や翻訳作業などは、短期間だけ外注すればコストを抑えつつスピーディに進められます。
こうした人材活用は「社内のリソースを本来注力すべき業務に集中させる」効果があります。ただし、委託先の品質管理や情報セキュリティへの配慮は欠かせません。信頼できるパートナーを見極めることが成功のカギとなります。
業務効率化の進め方で注意すべきポイント
業務効率化を進めるとき、気をつけておかないと逆効果になる落とし穴があります。ここでは特に注意したい3つのポイントを取り上げます。
ツール導入だけに頼らない
これまで述べた通り、「効率化=新しいシステムを導入する」と考えてしまいがちですが、ツール導入は万能薬ではありません。ツールの導入や活用そのものが目的化してしまうと、現場の課題に合わずに定着しないケースがよくあります。まずは業務フローの改善や無駄の削減から着手して、あくまでもツールはそれを補完する手段として使うのが正しい進め方です。
現場社員の意見を取り入れる
業務効率化は、現場で働く社員の協力がなければ成り立ちません。上層部である管理者やリーダーが一方的にルールややり方を決めて押しつけても、使いにくさや不満が募り、非効率になります。現場の声を集め、試行段階で社員を巻き込むことで「自分たちの業務が改善されている」という実感が生まれ、定着しやすくなります。
定量的に効果を測定する
効率化の成果を評価するときは、感覚ではなくデータで判断することが大切です。「なんとなく楽になった気がする」だけでは、効果があるのかどうかがあいまいです。改善前後の処理時間やコストを数値で比較し、効果を可視化することで、次の改善につなげることができます。
業務効率化を継続するための仕組みづくり
効率化は一度実施して終わりではありません。継続的に取り組むことで、組織文化として根付かせることができます。そのためには、続けられる仕組みづくりが欠かせません。
定期的な業務フローの見直し
一度効率化が実現したフローでも、時間が経つとまた無駄が生まれることがあります。そのため、定期的に業務フローを棚卸しし、現場の状況に合っているかを確認しましょう。この見直しによって、改善のサイクルを維持できます。
マニュアル・ナレッジ共有の徹底
業務効率化で得られた知見は、属人化させず組織全体に共有することが大切です。マニュアルやナレッジベースを整備し、誰でもアクセスできる状態にしておくことで、新しい社員や外部のスタッフであってもすぐに効率的な方法を実践できます。
業務改善を評価する文化を根付かせる
効率化の取り組みを継続させるには、改善を「評価する文化」をつくることも重要です。小さな工夫でも成果があれば表彰したり、会議で共有したりすることで、社員が主体的に改善を考えるようになります。組織全体で「改善は当たり前」という雰囲気をつくることが、長期的な成功につながります。
業務効率化の進め方を押さえて成果につなげよう
業務効率化は、単なる「時間短縮」や「コスト削減」にとどまるものではありません。正しい進め方を押さえれば、社員が働きやすくなり、企業の成長を支える基盤づくりにつながります。
重要なのは、現状を見極め、優先度をつけ、最適な方法を選び、小さく試して改善を重ねること。そして、継続的に仕組みとして定着させることです。
本記事の基本ステップや具体的な方法を参考に、自社に合った効率化の取り組みを進めてみてください。業務の質とともに社員の満足度も向上し、組織全体の成果につながるはずです。

ーーー
[Complete Guide] How to Promote Work Efficiency: Step-by-Step Process and Success Tips
▼下記記事もおすすめ▼
Geminiとは?無料版でできること、特徴と便利な使い方、他のAIとの違いをわかりやすく解説
Gemini Storybookとは?機能・使い方・料金・商用利用を完全ガイド
Geminiで画像生成はできる?使い方・特徴・無料版と有料版の違いを徹底解説