日々の業務に追われる中で、「非効率な作業が多い」「属人化が進んで引き継ぎが難しい」「改善活動をしても効果が長続きしない」と感じている方は少なくありません。
こうした課題に向き合うときに頼りになるのが、業務改善のフレームワークです。フレームワークを活用すれば、感覚や経験に依存せずに課題の本質を整理でき、再現性のある形で解決策を導き出せます。
本記事では、業務改善に役立つ代表的なフレームワークを7つ取り上げ、それぞれの特徴や活用シーンを具体的に解説していきます。
「改善したいけれど何から手をつければいいか分からない」方向けに、業務改善に役立つ7つのフレームワークをまとめて解説するガイドです。業務分解図・PDCA・ECRS・なぜなぜ分析などの基本から、優先順位のつけ方や活用ポイント、ツールとの組み合わせ、実際の企業事例までを紹介し、「思いつきの改善」ではなく、誰がやっても再現できる業務改善の進め方がイメージできる内容になっています。
なぜ業務改善にフレームワークが必要なのか?
業務改善を進めようとしても、「なんとなく効率が悪そうだから直そう」「自分なりに工夫してみよう」といった属人的なやり方に偏りがちです。これでは成果が一時的にとどまり、他のメンバーや別の部署に再現できません。
そこで役立つのがフレームワークです。改善の手順や視点を「型」として整理することで、課題の整理や解決策の検討がスムーズに進み、誰が取り組んでも同じような成果を得やすくなります。
ここでは、現場担当者が実務で直面しやすい課題に対して、なぜフレームワークが必要なのかを整理して解説します。
感覚的な改善は再現性が低い
「この方法なら効率が上がるはず」と思いつきで試した改善は、担当者の経験や勘に依存するため、効果が一過性に終わるケースが少なくありません。
たとえば、ある人が作業手順を省略して効率化したとしても、その背景や判断基準が共有されていなければ、別の人が再現することは難しいです。
フレームワークを使えば、改善のプロセス自体を「型」として残せるため、誰が取り組んでも同じ成果を得やすくなります。
課題の「見える化」によって本質的な解決が可能に
業務改善がうまくいかない大きな理由のひとつは、課題が曖昧なまま取り組んでしまうことです。「忙しい」「作業が多い」といった表面的な感覚だけでは、根本原因の特定には至りません。
フレームワークを用いると、業務フローや作業の流れを整理して可視化できるため、「どの工程で時間がかかっているのか」「どこに重複や無駄があるのか」といった具体的な問題点を把握できます。
改善プロセスをチームで共有・定着させるための道具として有効
業務改善は一人の努力だけでは長続きしません。現場全体で取り組み、改善の知見を共有・定着させることが大切です。
フレームワークは共通の基準や考え方をチームに提供するため、メンバー同士が同じ目線で議論しやすくなります。さらに、改善の手順や成果を文書化・図解化することで、新人教育や引き継ぎにも活用できます。
業務改善に役立つフレームワーク7選
ここでは、現場で活用しやすく、属人化の解消や効率化に直結しやすい7つの代表的なフレームワークを紹介します。
業務改善フレームワーク①:業務分解図|業務の棚卸しと属人化の解消に有効
業務分解図は、仕事を細かい作業単位に分解し、全体像を「見える化」する手法です。「誰が、どの作業を、どれくらいの時間で行っているのか」を棚卸しすることで、属人化している工程や重複業務を明確にできます。
たとえば、ある社員しか対応できない作業を洗い出してマニュアル化すれば、引き継ぎや教育がスムーズになり、業務リスクを下げられます。

業務改善フレームワーク②PDCAサイクル|継続的な改善の基本フレーム
Plan(計画)→Do(実行)→Check(検証)→Act(改善)のサイクルを回す、もっとも基本的な改善手法です。小さな取り組みを試して結果を検証し、次の改善につなげる流れを繰り返すことで、継続的な改善が可能になります。
現場で「改善活動をやって終わり」にしないための仕組みとして有効です。
業務改善フレームワーク③ECRS|業務プロセスの見直しを体系的に進める
ECRSは、Eliminate(排除)・Combine(統合)・Rearrange(順序変更)・Simplify(簡素化)の4つの視点から業務を見直すフレームワークです。「この作業は本当に必要か」「別の作業とまとめられないか」と問い直すことで、無駄を省き効率化を実現できます。
日常業務の中で手間が多いと感じる部分に適用すると効果的です。
業務改善フレームワーク④5W1H|業務分析と手順見直しのベースとして活用
「Who(誰が)」「When(いつ)」「Where(どこで)」「What(何を)」「Why(なぜ)」「How(どのように)」の6要素で業務を整理する方法です。単純ながら、業務手順を確認したりマニュアルを作成したりする際の基本ツールとして有効です。
作業の目的や担当者を明確にできるため、無駄な工程を省きやすくなります。
業務改善フレームワーク⑤なぜなぜ分析(5Whys)|根本原因の特定に有効
問題が発生した際に「なぜ?」を5回繰り返して問い直し、根本原因を突き止める手法です。
たとえば「納期遅延が発生した」→「なぜ?部品が届かなかった」→「なぜ?発注が遅れた」…と掘り下げることで、表面的な対応にとどまらず、再発防止につながる改善策を考えることができます。
業務改善フレームワーク⑥マトリクス分析(重要度×緊急度)|改善の優先順位を可視化
改善すべき課題が多すぎると、どれから着手するか迷ってしまいます。
マトリクス分析は、課題を「重要度」と「緊急度」の2軸で整理し、優先順位を明確にするフレームワークです。優先度の低いタスクに時間を割かず、本当に取り組むべき改善から着手できるようになります。
業務改善フレームワーク⑦バリューチェーン分析|業務の価値貢献度から改善ポイントを特定
バリューチェーン分析は、業務を「どの工程がどの程度価値を生み出しているか」という視点で整理する手法です。売上や顧客満足に直結しない作業を見つけやすく、コスト削減や業務の重点化に役立ちます。
特に「成果につながっているのか分からない業務が多い」と感じるときに活用するといいでしょう。
業務改善フレームワークを活用するポイント
フレームワークは便利な取り組みですが、知識として知っているだけでは十分に効果を発揮できません。
実際の業務に落とし込み、チームで継続的に活用していくためには、いくつかのコツがあります。ここでは現場で取り入れるときに意識しておきたいポイントを整理します。
目的に応じて使い分ける
フレームワークは万能ではなく、それぞれ得意とする目的があります。
たとえば「業務の棚卸しをしたい」ときには業務分解図、「改善活動を続けたい」ときにはPDCA、「無駄を省きたい」ときにはECRSが効果的です。目的を明確にしないまま使うと、せっかくのフレームワークが単なる形式的な作業に終わってしまいます。
まずは「何を解決したいのか」をはっきりさせたうえで選びましょう。
1人ではなくチームで行うことが前提
改善を担当者1人で進めると、どうしても主観に偏りがちです。チームで一緒にフレームワークを活用すれば、さまざまな視点から意見が出るため、より客観的で納得感のある改善案がまとまります。
さらに、複数人で取り組むことで改善の意識が共有され、現場に浸透しやすくなるという効果も期待できます。
定性情報と定量情報を併用する
「作業が大変そう」「この工程は手間が多い」といった感覚的な意見だけでは、改善の根拠としては不十分です。
現場の声(定性情報)に加えて処理件数や作業時間といった数値データ(定量情報)を組み合わせて分析することで、改善効果を客観的に示し、納得感のある提案につなげられるでしょう。
業務改善フレームワークとあわせて活用したいツール
フレームワークは思考や議論を整理するための「型」ですが、実務に落とし込むにはツールを組み合わせると効果が一層高まります。
ここでは、現場でよく使われる代表的なツールを紹介します。
業務フロー可視化ツール(例:miro)
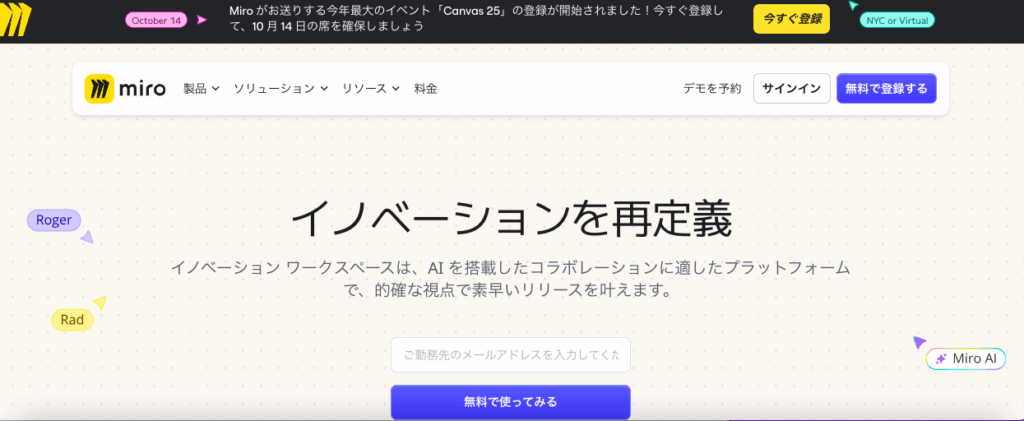
オンラインで業務の流れを図解し、関係者とリアルタイムに共有できるツールです。
付箋や矢印を使って業務プロセスを整理できるため、ECRSや業務分解図とあわせて使うと効果的です。「どこに手間がかかっているのか」「無駄な工程はどこか」をチーム全員で確認でき、改善案の合意形成がスムーズに進みます。
業務フロー作成ツール(例:Lucidchart)
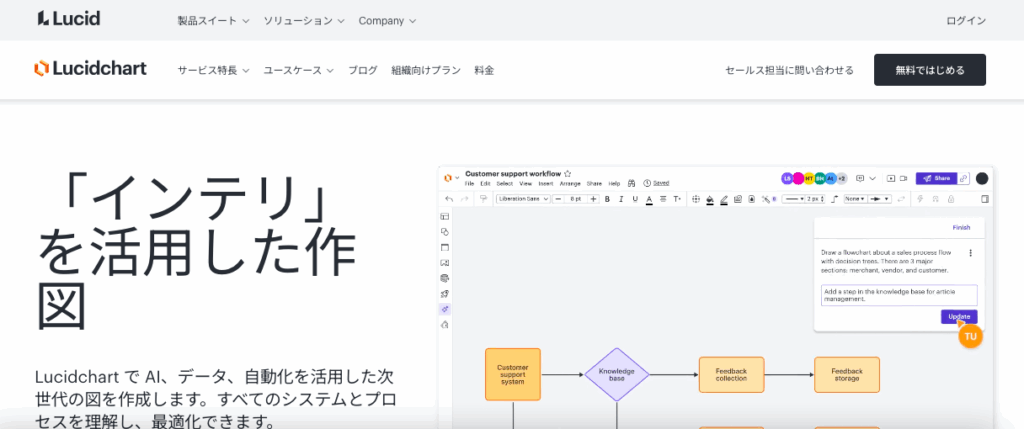
複雑な業務プロセスを整理する際には、専用のフロー図作成ツールが便利です。
ExcelやPowerPointでも描けますが、専用ツールを使うと工程ごとの関係性をわかりやすく表現できます。業務の可視化が進むことで、属人化していた作業を他のメンバーに引き継ぎやすくなるのがメリットです。
業務自動化ツール(例:Bizrobo!)

RPAツールの一つで、繰り返し作業や定型業務を自動化するのに適しています。
フレームワークで無駄な作業を特定したあと、その業務をRPAで自動化すれば、改善効果をさらに高めることができます。
マニュアル整備ツール(例:Teachme Biz)

改善した手順をそのまま現場に定着させるには、マニュアル化が欠かせません。Teachme Bizのようなマニュアル整備ツールを使えば、写真や動画を使って手順を直感的にまとめられます。
新人教育や引き継ぎに活用でき、改善の成果を一時的なものにせず、組織に根付かせることが可能です。
実践事例:フレームワークを活用して改善に成功した企業例
フレームワークは理論だけでなく、実際の現場で効果を発揮してこそ意味があります。
ここでは、小売業・製造業・サービス業といった身近な業界で、フレームワークを活用して改善に成功した事例を紹介します。
例①:業務分解図+ECRSで属人化を解消(小売業)
ある小売業界の企業では、在庫管理業務が特定の社員に依存しており、その社員が休暇や退職をする際に大きなリスクとなっていました。
そこで、まず業務分解図を作成して在庫管理の作業を細かく棚卸し。その後、ECRSを用いて「削除できる工程はないか」「統合できるタスクはないか」を検討するプロセスを進めました。
最終的に作業フローを簡素化でき、複数の社員が対応できる体制を整備。属人化のリスクを抑えつつ、引き継ぎにかかる時間も大幅に短縮されています。
ECRSについては業務改善4原則(ECRS)とは?現場で活かせる実践ステップを徹底解説で詳しくご紹介しています。併せてご覧ください。
例②:なぜなぜ分析(5Whys)で根本原因を突き止め再発防止へ(製造業)
ある製造業の現場で、機械が突然停止するトラブルが発生しました。表面的な原因は「ヒューズ切れ」でしたが、単なる部品交換では同じトラブルが繰り返される可能性が高いため、なぜなぜ分析を使って掘り下げていきました。
- なぜ機械が止まったのか? → ヒューズが切れた
- なぜヒューズが切れたのか? → 潤滑油が不足していた
- なぜ潤滑油が不足していたのか? → オイルポンプが適切に働いていなかった
- なぜオイルポンプが働かなかったのか? → 金属くずが詰まっていた
- なぜ金属くずが詰まったのか? → ストレーナー(濾過器)が設置されていなかった
5回の「なぜ」を繰り返すことで、真の原因は「ストレーナーが設置されていなかったこと」であると突き止めました。その結果、部品交換という一時的な対応ではなく、ストレーナーを取り付けるという根本的な対策を実行でき、同様のトラブルを防ぐことにつながりました。
例③:バリューチェーン分析で低価格と体験価値を両立(家具小売業業)
家具小売業界では、従来は大型家具を完成品で販売していたため、倉庫スペースや輸送コストが高くつく課題がありました。そこで、バリューチェーン分析を用いて業務を分解した結果、物流活動に大きな改善余地があることが判明しました。
具体的には、家具を「組み立て式」で販売する仕組みに変更。商品をパーツの状態で倉庫や店舗に運ぶことで、保管効率が高まり輸送コストも削減できました。
また、顧客自身が組み立てを行うスタイルにより「自分で作り上げた」という体験価値も提供でき、ブランドへの愛着を強める効果も得られたといいます。
業務改善フレームワークで「感覚頼り」からの脱却を
業務改善は「なんとなく非効率だから直そう」という感覚的な取り組みでは、効果が一時的に終わってしまうことが少なくありません。
フレームワークを活用することで、改善の精度と再現性を高め、組織全体に定着させることが可能です。
業務改善の精度と再現性を高めるには型が必要
安定した成果を出すには、「型」に沿って考えることが不可欠です。フレームワークを使えば、誰が取り組んでも同じ手順で課題を整理でき、属人的にならず再現性のある改善が実現できます。
まずは自社の課題に合いそうなフレームワークを一つ選び、小さな改善から試してみると良いでしょう。
現場への浸透を促すには可視化+ツール活用がカギ
改善の方法を共有しなければ、せっかくの取り組みも定着しません。業務フローを図解したり、改善後の手順をマニュアル化したりして「誰でも見てわかる状態」にすることが重要です。
業務改善ならmayclassへご相談ください
mayclassでは、業務の可視化や改善に特化したサービスを提供しています。属人化の解消や業務効率化を進めたい企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

ーーー
7 Frameworks for Business Improvement: Practical Tools for Visualizing and Solving Issues
▼こちらの記事もおすすめ▼
業務改善・業務効率化の原則と目標を徹底解説!4原則・3要素・8原則を一挙紹介


