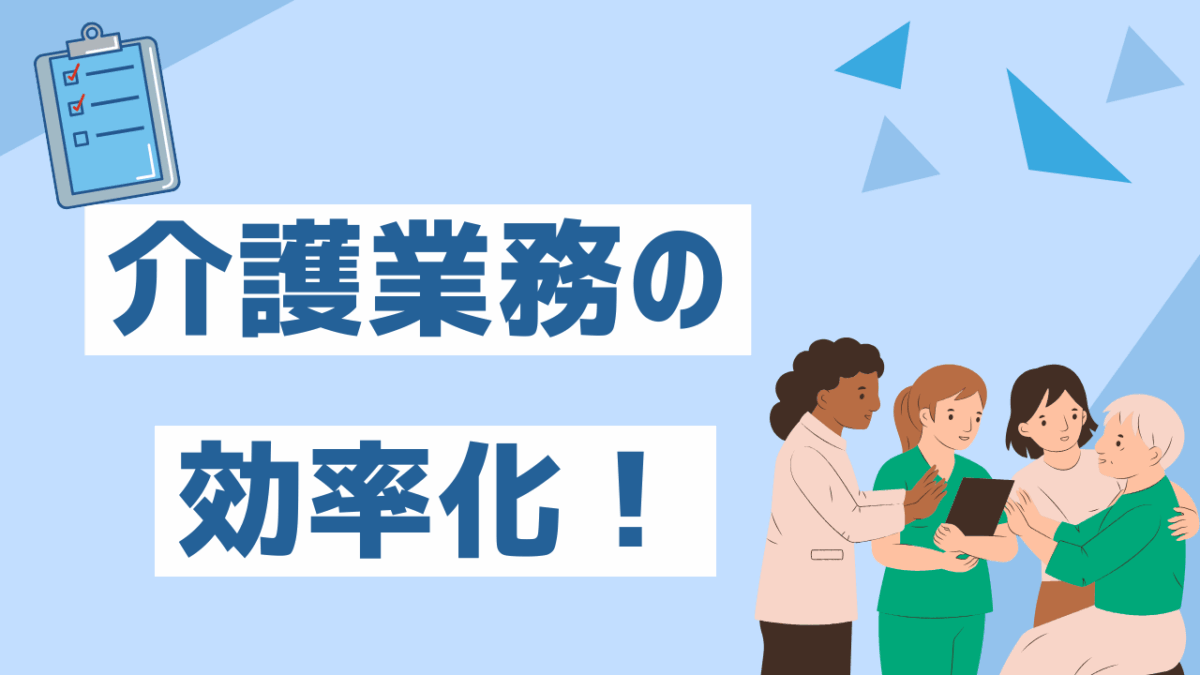少子高齢化が加速するなか、介護業界は深刻な人手不足や業務の属人化といった課題に直面しています。特に現場の負担は年々増加し、スタッフの離職やサービス品質の低下が社会問題となりつつあります。こうした背景から、介護現場における「業務効率化」の重要性がこれまで以上に高まっています。
業務効率化は単なる時短やコスト削減だけでなく、「利用者の満足度向上」や「働きやすい職場づくり」にも直結する取り組みです。介護業務の流れを見直し、ICTツールの導入や業務フローの標準化などを進めることで、限られた人員でも質の高いケアを提供できる体制を整えることができます。
本記事では、介護業務を効率化するための具体的な施策や活用すべきツール、導入のステップについて詳しく解説します。現場の負担を減らし、持続可能なケアを実現するためのヒントを得たい方は、ぜひ最後までご覧ください。
介護現場の深刻な人手不足と属人化を解消するため、業務効率化が重要視されています。業務フローの可視化・標準化、ICT活用、情報共有の改善、マニュアル整備などを行うことで、スタッフの負担軽減とサービス品質向上を実現する取り組みを解説した記事です。
介護業務を効率化する5つの具体策
介護現場の効率化を実現するには、単にツールを導入するだけでは不十分です。現場の業務フローを根本から見直し、誰もが同じ水準で業務を行えるような「仕組み化」が求められます。以下では、介護業務の効率化に直結する5つの具体的な施策をご紹介します。
業務フローの可視化と標準化
まず最初に取り組みたいのが、業務フローの可視化と標準化です。
現場では「誰が」「どのタイミングで」「何をするのか」が人によって異なることが多く、これがミスや非効率の原因になります。業務の流れを図式化し、ムダや重複作業を洗い出すことで、改善の余地が見えてきます。
標準化された手順書やマニュアルを整備することで、スタッフ全員が同じ判断基準で行動でき、新人教育の負担も軽減されます。
ICT・介護記録ソフトの導入
業務効率化において、ICTの活用は今や不可欠です。介護記録ソフトを使えば、紙での記録やExcel入力に比べて入力作業が大幅に簡素化されます。入力ミスの削減やデータの一元管理も可能となり、情報の共有スピードも格段にアップします。
例えば、タブレット端末を使ってその場で記録を入力できるようにすれば、記録作業の「持ち帰り」が不要となり、現場の時短とストレス軽減につながります。
紙からデジタルへの移行
依然として多くの介護現場で使われている紙ベースの資料や書類。これらをデジタル化するだけでも業務効率は大きく向上します。紙の管理は紛失や情報共有の遅れといったリスクがあり、探し物に時間を取られることも多く見られます。
デジタル化により、検索性が向上し、遠隔地との情報共有もスムーズに。保管スペースの削減や、個人情報のセキュリティ強化といった副次的なメリットもあります。
情報共有・申し送りの見直し
申し送りや引き継ぎが口頭やメモで行われている場合、情報の抜け漏れや伝達ミスが発生しやすくなります。業務効率化を図るには、情報共有の手段とルールを見直すことが重要です。
チャットツールや専用アプリを活用すれば、過去のやり取りをすぐに確認でき、伝達ミスを防ぐことができます。また、申し送りフォーマットの統一や、チェックリスト化も有効です。
マニュアル整備とOJTの最適化
新人や異動スタッフの教育に時間がかかることも、介護業務の非効率の一因です。ここで効果を発揮するのがマニュアルの整備とOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)の最適化です。
業務内容を具体的に記したマニュアルや動画などを用意しておくことで、誰でも一定レベルの業務が行えるようになります。また、OJTも計画的に進めることで、教育にかかる時間と属人化のリスクを軽減できます。
マニュアルについては、【サンプル例あり】介護業務マニュアルの作り方と活用法|現場で役立つ実践ガイドの記事もご覧ください!
介護業務効率化に役立つおすすめツール
| カテゴリ | 主な目的 | 代表的なツール例 |
| 介護記録・ケアプラン作成 | 記録業務の簡略化、データの一元管理 | ほのぼのNEXT、LIFE連携システム |
| 情報共有ツール | スタッフ間の迅速な連絡、申し送りの効率化 | LINE WORKS、カイポケ |
| スケジュール・シフト管理 | 勤怠管理、シフト作成の省力化 | ジョブカン、勤革時 |
| 見守りセンサー・IoT機器 | 夜間巡視や安全確認の自動化、スタッフの負担軽減 | 眠りSCAN、A.I.Viewlife |
介護現場の業務効率化を実現するうえで、ツールの導入は非常に有効な手段です。人の手に頼っていた業務の一部を、デジタルツールやICT機器が補うことで、スタッフの負担を減らし、より質の高いケアに時間を充てられるようになります。ここでは、実際に現場で活用されている介護業務効率化に役立つツールを4つのカテゴリに分けて紹介します。
介護記録・ケアプラン作成ツール(例:ほのぼのNEXT、LIFE連携システム)
日々の介護記録やケアプランの作成は、スタッフにとって時間と手間のかかる業務です。これらを効率化するには、介護記録ソフトの導入が非常に有効です。
例えば「ほのぼのNEXT」は、ケア記録・バイタル・サービス提供実績などを簡単に入力・管理できるシステムで、多職種間の情報共有も可能です。レセプトや給付管理との連携もスムーズで、事務作業の負担軽減にも貢献します。
一方「LIFE連携システム」は、厚労省が推進する科学的介護情報システム(LIFE)に対応しており、アセスメント結果やケアの効果測定を自動で出力できます。これにより、PDCAサイクルを取り入れた質の高いケア計画が立てやすくなります。
これらのツールを活用することで、紙ベースの記録よりも検索性・集計性に優れ、介護業務全体の生産性向上につながります。
スタッフ間の情報共有ツール(例:LINE WORKS、カイポケ)
介護業務を効率的に回すためには、スタッフ間の情報共有が円滑であることが不可欠です。「LINE WORKS」は、一般的なLINEの操作感をベースに、業務用として使えるチャットや掲示板、予定表などを備えており、導入ハードルが低いのが特徴です。スマートフォンから手軽に申し送りや緊急連絡を行うことができ、既読確認やファイル添付なども可能です。
「カイポケ」は、介護業界に特化した業務支援サービスで、記録・請求・情報共有・職員管理などを一元的にカバーしています。特に「スタッフ掲示板」機能では、事業所内の情報共有がスムーズになり、紙や口頭による伝達ミスを防ぐ効果が期待できます。
いずれのツールも、リアルタイムな連携と情報の記録性に優れており、ミス防止・業務のスピードアップに寄与します。
スケジュール・シフト管理ツール(例:ジョブカン、勤革時)
介護現場のシフト管理は複雑になりやすく、スタッフの勤務希望や人員配置のバランス調整に多くの時間が割かれます。
「ジョブカン」は、クラウド型の勤怠・シフト管理ツールで、スタッフが自分のスマートフォンからシフト希望を提出したり、打刻を行ったりできるため、紙やExcelでのやり取りが不要になります。複雑なシフトパターンや夜勤・早番なども設定でき、管理者の作業も大幅に軽減されます。
「勤革時」も同様にクラウド型で、リアルタイムで勤怠状況を確認できる点が強みです。労働時間の自動集計、アラート通知などの機能もあり、法令遵守や労務リスクの軽減にもつながります。どちらも介護業務の効率化を支えるインフラとして、導入する施設が増えています。
見守りセンサー・IoT機器の活用(例:眠りSCAN、A.I.Viewlife)
夜間の巡視や体調確認といった業務は、スタッフにとって大きな負担となります。見守りセンサーやIoT機器を活用することで、こうした負荷を軽減しつつ、利用者の安全も確保できます。
例えば「眠りSCAN」は、ベッドに設置したセンサーで呼吸や体動を検知し、利用者の睡眠状態をリアルタイムでモニタリングできます。離床や異常時にはアラートを出すため、不要な巡回を減らしつつ、必要なタイミングではすぐに対応できる体制が整います。
「A.I.Viewlife」は、AIカメラを用いた映像見守りシステムで、離床や転倒リスクを高精度に検知することができます。現場の人手が限られていても、安全管理が行き届いた環境を維持できる点が大きなメリットです。
これらの機器は、業務の効率化と利用者の安心を両立させるための重要なテクノロジーといえます。
介護業務効率化を進めるステップ
介護業務の効率化は、一朝一夕に実現できるものではありません。重要なのは、現場の課題を正しく把握し、目的に応じた改善策を段階的に進めていくことです。ここでは、介護現場で業務効率化を進めるための4つの基本ステップを紹介します。
現状の業務課題を洗い出す
業務効率化の第一歩は、今抱えている課題の明確化です。例えば「同じ作業に時間がかかっている」「情報共有にミスが多い」「人によってやり方が異なる」など、現場で起きている問題をスタッフの声や業務の流れから丁寧に拾い上げましょう。ここで重要なのは、表面的な症状だけでなく、根本原因まで掘り下げる視点を持つことです。
効率化の目的・指標を明確にする
改善の方向性を定めるためには、効率化の目的と成果を測る指標を設定する必要があります。たとえば、「記録時間を1日30分短縮」「申し送りの伝達ミスをゼロにする」など、具体的な目標を設定することで、取るべきアクションが明確になります。目的が曖昧なままだと、改善施策も場当たり的になり、効果が出にくくなってしまいます。
スタッフと一緒に改善策を検討・導入する
業務効率化は、現場で働くスタッフの協力なしには成り立ちません。実際に業務を担っている職員と共に改善策を考えることで、実用性の高いアイデアが生まれやすくなります。また、現場からの納得感も得やすく、導入後の定着スピードも向上します。ツールの選定や業務フローの変更なども、トップダウンではなくボトムアップの視点を取り入れることがポイントです。
定着までのフォローアップ体制を整える
効率化の施策を導入しても、それが現場に根づかなければ意味がありません。導入後こそ、マニュアルの整備や定期的な振り返り、使い方のレクチャーなど、フォローアップ体制をしっかり整えることが大切です。必要に応じて、改善の再設計を行い、より現場に合った形に調整していく柔軟性も求められます。介護業務の効率化は「導入して終わり」ではなく、「定着させて成果を出す」ことがゴールです。
介護業務効率化は「人のゆとり」を生む投資
介護業務の効率化は、単なる時短や省力化にとどまるものではありません。それは、スタッフ一人ひとりに「ゆとり」を生み出し、結果として利用者へのサービス品質を高めるための投資です。限られた人員・時間のなかで、より良いケアを提供し続けるためには、業務そのものを見直し、継続的に改善していく姿勢が求められます。
目先の効率ではなく、持続可能な仕組み化を
業務効率化というと、すぐに効果が出るテクニックやツールに目が向きがちですが、重要なのは持続可能な仕組みを作ることです。標準化された業務フローや、誰でも活用できるマニュアル、継続的に見直せる仕組みが整ってはじめて、本当の意味での効率化が実現します。
ICTと人の力を融合させる視点が重要
介護の現場においては、ICTやIoTといった技術の導入が進んでいますが、それだけで業務が劇的に改善されるわけではありません。テクノロジーの力を活かしながらも、最終的には現場の人の知識や経験、思いやりがあってこそ、質の高いサービスが実現します。機械と人、それぞれの強みを融合させる視点が今後ますます重要になります。
まずは「できることから」小さく始めよう
介護業務効率化に取り組む際は、すべてを一度に変えようとせず、身近な課題から少しずつ改善を進めることが成功の鍵です。例えば、申し送りの方法を見直す、記録業務にICTを導入するなど、小さな変化が積み重なることで、大きな成果へとつながっていきます。
もし、貴社で介護業務の効率化に取り組みたいとお考えであれば、現場を可視化し、ツール活用やマニュアル整備まで支援できる専門家の力を借りるのもひとつの選択肢です。無理なく、現場に根づく改善を進めていくための第一歩を、今日から踏み出してみてはいかがでしょうか。
介護現場の効率化を支援するツールやサービスを探している方へ
mayclassでは業務可視化・マニュアル整備など、介護現場の仕組みづくりを支援しています。現場に合わせたご提案をご希望の方は、お気軽にご相談ください。

ーーー
How to Improve Efficiency in the Nursing Care Industry: Tools and Practical Methods
▼こちらの記事もおすすめ▼
業務効率化は“数値化”から始まる!成果を見える化する方法と実践ステップ