「マニュアルはあるのに、なぜか使われていない」
そんな声を現場からよく聞きます。業務の標準化や教育のために整備されたはずのマニュアルが、実際には活用されず、形式だけが残ってしまう。それはなぜなのでしょうか?
今回は、業務マニュアルに関わる3名のメンバーによる座談会を実施。
mayclassで日々、業務分解やマニュアル設計に取り組む立場から、それぞれが過去に経験してきた「マニュアルのある/ない現場」について語りました。
マニュアルは本当に必要なのか、使われないのはなぜなのか、そして、“使われるマニュアル”にするために、何がポイントになるのか。現場のリアルな声から、マニュアル運用のヒントを探ります。
マニュアルがないと困る?
小池:「マニュアルがないと困る」とよく言われますが、実際の業務現場ではどのような支障があるのでしょうか?皆さんが経験されたケースを伺えますか?
重永:私は以前の職場で実感しました。業務を進めるうえで「人に聞くしかない」状況が常態化しており、覚えるべき内容も多かったため、都度誰かに確認する必要があって非常に非効率でした。
矢嶋:教える側の立場でも課題は大きいですね。何度も同じ説明を繰り返すことになったり、教える内容に個人差が出たりする。口頭での伝達には限界があり、結果的に全体の業務効率が下がってしまいます。
小池:受け手も、「言われた通りにやったつもりなのに違っていた」ということがあると、業務への自信を失ってしまう。そのたびに確認の時間も発生して、さらに非効率になっていきますね。
矢嶋:だからこそ、現場で“実際に機能する”マニュアルの存在が重要です。業務手順や判断基準が明文化されていれば、教える側・教わる側双方の負担が減り、属人化やムダなやりとりも削減できます。
重永:言い換えると、マニュアルが存在しない状態では、“迷いの連鎖”が起きるんですよね。誰に聞くべきか、何が正解なのかが曖昧になり、結果として業務が個人に依存しやすくなります。引き継ぎや育成もうまくいきません。
小池:やはり、業務を安定的に回すうえで「使われるマニュアル」が現場には不可欠だと感じますね。ただし、単に作るだけでなく、内容が現場に適しており、日常的に運用されていることが前提です。
「あるけど使われないマニュアル」が現場のリアル
小池:今はmayclassでマニュアルの大切さを実感していますが、あらためて皆さんがこれまで働いてきた職場では、マニュアルはどういう扱いでしたか?
重永:営業をしていた時、一応マニュアルのようなものはありました。ただ営業トークは人によってスタイルが違うので、読んでも結局「誰に聞くか」が先になってしまって。マニュアルがあっても、現場ではほとんど使われてなかったですね。
矢嶋:私が以前担当していた業務でも、マニュアル自体はありました。ただ、実際の現場では想定外のことが多すぎて、全部に対応するのは難しい。特に初動対応のような「迷う場面」において、流れだけでも書かれていると、それがあるだけで安心できたのを覚えています。
とはいえ、マニュアルや手順書が「作って終わり」になってしまっているケースは本当に多いと感じます。更新されず、現場で使われず、結局“形だけある”という状態に。せっかく作ったのに、それが実際に活用されていないというミスマッチが起きていると思います。
小池:「あるけど使われない」というのは、多くの現場に共通している課題かもしれませんね。私も以前、ナレッジ共有ツールを使っていた職場があったのですが、情報が多すぎて検索しづらかったり、更新されないまま古い内容が残っていたりして、結局は人に直接聞いた方が早いという状況になっていました。情報が整っていても、運用がうまくいっていないと結局活用されないんですよね。
なぜマニュアルの運用は定着しないのか?
矢嶋:マニュアルの運用は、実務の中では優先順位がどうしても低くなりがちです。現場の人は本業の業務に追われていて、マニュアル更新は「サブ業務」的な位置づけになってしまう。例えば「今年度はマニュアル作成を目標にしよう」と目標に掲げて完成したら、それで満足してしまうパターンが多い。作ったこと自体がゴールになって、運用や改善までは手が回らないんですよね。
重永:私もmayclassに入るまで「マニュアルは更新するもの」と思っていなかったです。作って終わりという感覚がありました。例えば、Web記事は更新するのが当たり前だけど、マニュアルは“完成品”という意識がありますよね。
小池:マニュアルを更新するという業務自体が必要だと思いますし、場合によってはそれを専門に担う部署や担当を設けてもいいのではと思います。マニュアル作成や更新を外部に依頼するのもおすすめです。
矢嶋:本来マニュアルも、業務と同じように日々変化するものです。Web記事やサービス紹介ページがアップデートされていくように、マニュアルも改善・更新を前提とした運用が必要です。
マニュアルが「助けになる瞬間」が必ずある
矢嶋:私は旅行関連の仕事で現地対応をしていた時に、夜中1人でトラブル対応する場面がありました。そういう時は、マニュアルがあるととても心強いです。例えば、フライトの遅延などが発生した際に、状況に応じた対処法が事前に明記された資料があると、それを見ながら冷静に対応できます。誰にも相談できない状況でも、「これに沿って動けば大きく間違わない」という安心感がありました。実際、現地でスムーズにお客様対応ができたのは、そうした準備のおかげだったと思います。
小池:マニュアルが“相棒”になるような瞬間ですね。私もナレッジ共有ツールを使っていた時は、そこに過去の事例やQ&Aがまとまっていたのはとても助かりました。検索すれば必要な情報が出てくるので、自分で判断がつかないときも一歩踏み出す材料になりました。情報がたくさんある分、検索しづらさや、更新状況に注意が必要という課題もありましたが、いざというときの支えになっていたのは間違いありません。
古い、探せない、分かりづらいマニュアルは「ないのと同じ」
小池:せっかく作ってあるのに使われないマニュアルにはどんな特徴がありますか?
重永:大きく3つですね。「探しにくい」「情報が古い」「わかりにくい」。どれか1つでも当てはまると、使ってもらえなくなります。
矢嶋:内容自体が正しかったとしても、更新日が古いだけで「この情報、信用していいのかな?」と思ってしまう。チェックされていない印象が不安を生みます。
小池:マニュアルの信頼性だけでなく、企業全体の信用にも影響しそうですね。
矢嶋:そうなんです。マニュアルが更新されていないのに、「業務はきちんと回っている」とは言いづらい。管理の甘さを感じてしまいます。
「マニュアルがあると考えなくなる」?
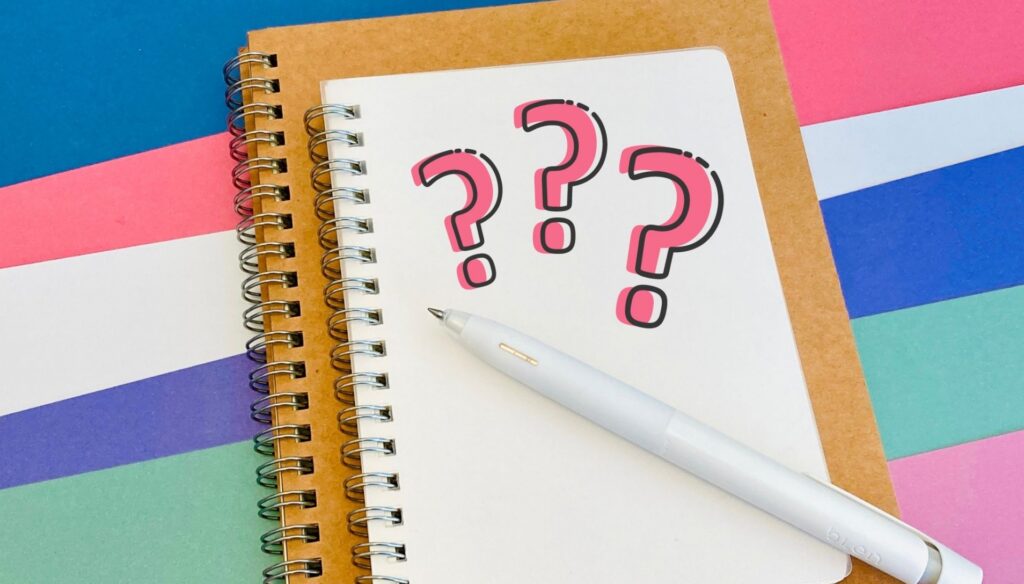
小池:一部では「マニュアルがあると、社員が自分で考えなくなる」という声も聞かれますが、お二人はこの意見についてどう思われますか?
重永:私はまったく逆の立場です。マニュアルがあるからといって思考停止になるとは限りません。むしろ、“基本が明文化されている”からこそ、応用を考える余地が生まれると思っています。ゼロから手探りで考えるよりも、ベースがあることで安心して判断できる場面は多いです。
矢嶋:同感です。マニュアルは「現場対応を縛るもの」ではなく、「共通認識の出発点」だと考えています。基本的な流れや判断基準が共有されていれば、その上で状況に応じた判断がしやすくなりますし、経験の浅いスタッフでも迷わず動けるようになります。
小池:マニュアルがあるからこそ、「このケースはどう判断すべきか」と一歩踏み込んで考えることができそうですね。
重永:そうなんです。重要なのは、マニュアルが“判断を止める道具”ではなく、“判断を支える土台”であるという考え方。業務において一人ひとりが考える余地を持つためにも、その前提となる「共通の基準」が必要です。
矢嶋:「マニュアル通りにしか動けない人材」になってしまうのではなく、「マニュアルを活用して、より良い判断ができる人材」を育てる。その前提を整えるのが、マニュアルの本来の役割だと思います。
小池:マニュアルの存在が“考えなくさせる”のではなく、“考えるための土台”を築いてくれる。まさに、印象が変わる視点ですね。
完璧なマニュアルは必要?最低限でもいい?
小池:では、実際の現場では「完璧に作り込まれたマニュアル」と「最低限必要な情報だけのマニュアル」、どちらがより役立つと感じますか?
重永:完璧を目指すこと自体は理想ですが、例えば、接客や調整業務のように“人”が相手となる業務では、すべてのパターンを網羅するのは難しいです。むしろ現場では、細部まで作り込まれたマニュアルよりも、「使いやすさ」や「現場での判断に寄り添った構成」の方が求められます。
矢嶋:重要なのは、「迷ったときの基準があるかどうか」だと思います。情報が少なくても、判断の軸となるポイントが示されていれば、現場では十分に機能します。すべてを網羅していなくても、最低限のガイドラインがあるだけで、対応に自信が持てます。
小池:つまり、マニュアルの本質は「完璧な正解集」ではなく、「迷いを減らすための指針」として存在するということですね。一方で、マニュアルの内容によっては、ある程度の“完璧さ”が求められるケースもありますよね。アプリやツールの操作手順書のようなマニュアルでは、1枚のスクリーンショットが最新の画面と違うだけでも、ユーザーが戸惑ってしまうことがあります。こうした場面では、正確性や更新頻度の高さが直接、使いやすさにつながる印象です。
重永:おっしゃるとおりです。対象によって“必要な精度”は異なるという視点が重要ですね。手順書のように手元で見ながら作業するようなものは、特に誤解が生じないよう丁寧さが求められます。
矢嶋:だからこそ、すべてのマニュアルに同じ完成度を求めるのではなく、「誰に、どんな場面で、どのように使われるか」を見極めて、目的に応じた設計と運用が必要だと思います。
おわりに
今回の座談会では、マニュアルに対する素朴な疑問から始まり、実際の活用・課題・運用面まで幅広く意見が交わされました。
結論として、「マニュアルは完成させて終わりではなく、変化に合わせて運用し続けるもの」という共通認識が浮かび上がりました。
現場で使われるマニュアルとは、「完璧な正解集」ではなく、「現場の共通認識を支えるベース」なのかもしれません。
マニュアル作成はmayclassにお任せ!
マニュアル作成を検討しているなら、mayclassにぜひご相談ください。
mayclassでは、マニュアルの企画・構成・制作まで一括でサポートしています。
専門ライターが御社の業務内容や目的を丁寧にヒアリングし、現場で本当に使える実践的なマニュアルを作成いたします。
業務の属人化を防ぎ、誰が見ても迷わず行動できる内容に仕上げることで、教育コストの削減や業務効率化にもつながります。
新規導入からリニューアルまで、お気軽にご相談ください。
▼こちらの記事もおすすめ▼
マニュアルは“業務を動かす設計書”!伝えるから、動かすへ 〜プロ3人が語るマニュアル制作の本質〜


