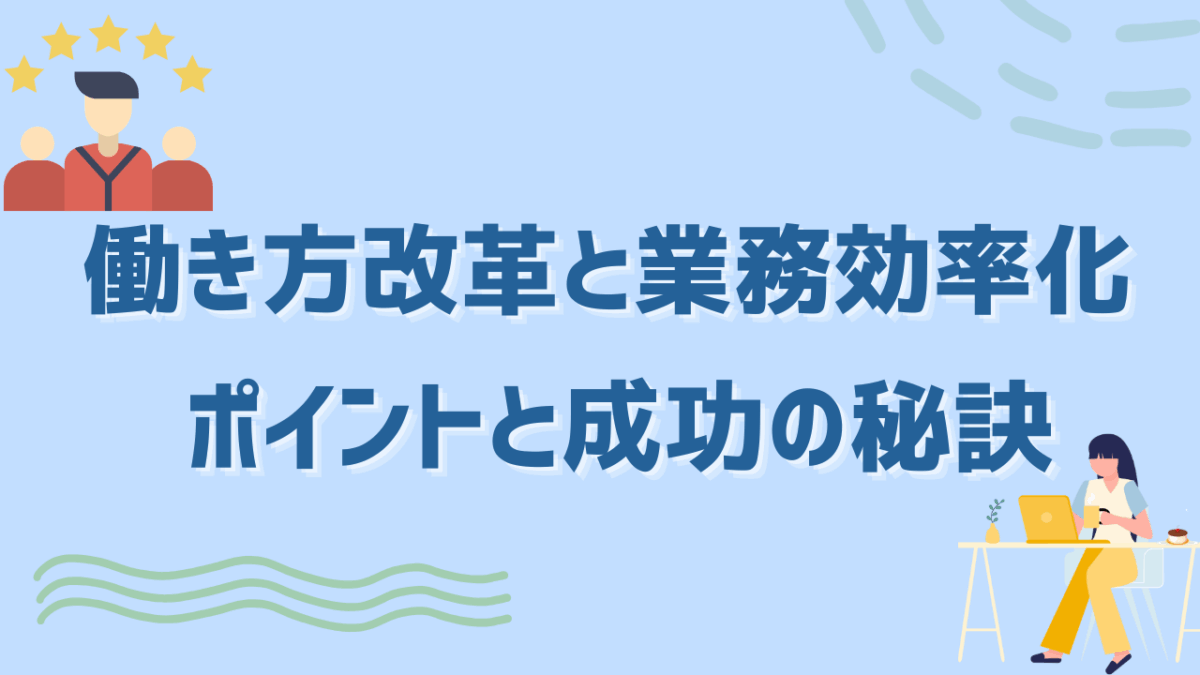日本企業にとって「働き方改革」はもはや避けて通れない課題となりました。少子高齢化による労働人口の減少や長時間労働による健康リスク、多様な働き方への対応など、企業はこれまで以上に柔軟かつ効率的な働き方を求められています。
しかし、働き方改革を実現するためには、単なる制度変更や残業削減だけでは不十分です。根本的な業務の見直し、つまり業務効率化がセットで求められています。業務のムダを取り除き、生産性を高めることが、誰もが働きやすい職場づくりにつながります。
本記事では、「働き方改革の成功は業務効率化によってどう実現されるか」という視点を軸に、背景や課題、具体的施策、ツール紹介、そして成功のポイントまでを体系的に紹介します。
この記事は、働き方改革を進めたい 経営層・管理職・業務改善担当者 に向けて、「制度導入だけでは成果が出ない理由」と「業務効率化とセットで進める重要性」を解説する実践ガイドです。トップのリーダーシップと現場の巻き込み、業務の可視化、部門特性に合わせた改善設計、継続的な振り返りなど、改革を成功させる具体策をわかりやすく整理しています。
なぜ今、働き方改革と業務効率化が同時に求められるのか?
少子高齢化や人手不足が深刻化するなかで、企業は限られた人材で成果を上げることが求められています。そのためには、働き方改革と業務効率化を連動させて進めることが不可欠です。
働き方改革の目的と企業に求められる背景
働き方改革は単なるブームではなく、政府主導で進められている政策課題です。労働力不足を背景に限られた人材資源を有効活用し、生産性を高めることが求められています。
企業側にも、長時間労働の是正やワークライフバランスの向上、多様な人材の活躍支援などの取り組みが求められており、競争力維持のための必須条件とも言えます。
さらに、働き手からも柔軟な働き方や働きがいのある職場を求める声が高まっており、企業はその期待にも応えなければなりません。
業務効率化が働き方改革を支える理由
制度や意識改革だけで労働時間を減らしても、仕事量やフローがそのままでは現場の負担が増す一方です。そこで必要なのが、業務効率化です。
無駄な作業を省き、手作業を自動化し、情報共有をスムーズにすることで同じ仕事をより短時間・少人数で行えるようになります。
業務効率化によって空いた時間は社員の成長や新たな価値創出に使うことができ、企業全体の競争力にも貢献します。
時間削減だけじゃない!業務効率化がもたらす多角的な効果
業務効率化は単に時間を減らすための手段ではありません。属人化の解消や業務の標準化、品質の向上、社員のストレス軽減など、組織全体に多方面のメリットがあるのです。
特に属人化を解消することで、誰でも同じ水準で業務を遂行できる体制が整い、急な人員変動にも対応しやすくなります。また、業務の見直しにより仕事の無駄が減り、社員が本来の業務に集中できる環境が整備されます。結果として社員の満足度や定着率が向上し、ひいては企業の競争力強化にもつながるでしょう。
働き方改革がうまく進まない理由は“業務のムダ”にある?

働き方改革を進めようとしても、「残業が減らない」「生産性が上がらない」という声は多いものです。背景には、業務のムダが温存されているケースが少なくありません。
無意味な報告書作成や重複業務、属人化したタスクなどを放置していては、いくら制度を整えても現場は疲弊するばかりです。ムダな業務は社員のモチベーションを下げ、改革の足かせになります。まずは足元の業務を見直し、ムダを「見える化」しましょう。
業務フローの見直しによる業務効率化の基本
業務効率化の第一歩は、現状の業務フローを「見える化」し、ムダ・ムラ・ムリを洗い出すことです。その上で、不要な工程の削減や役割の明確化、業務の標準化などを行います。
特に現場社員の声を聞きながら改善を進めることで、現実的かつ実行力のある施策になります。フローを改善する際は、最終的な業務の目的や成果を明確にし、そこから逆算して必要な工程を組み立てることが効果的です。
ITツールで“改革×効率化”を同時に実現する方法
クラウド型のプロジェクト管理ツールや勤怠管理システムなどのITツールは、業務効率化を推進するうえで効果的です。導入によって情報共有がスムーズになり、リモートワークをはじめとする柔軟な働き方にも対応しやすくなります。
さらに、業務データの「見える化」が進むことで、管理職の意思決定の精度も高まります。大切なのは、現場の実態に合ったツールを見極め、スムーズに定着させる仕組みを整えることです。
マニュアル整備と属人化の解消が働き方改革に与える効果
業務が特定の個人に依存していると、担当者が不在の際に作業が滞ったり、新人の教育に余計な時間がかかったりすることがあります。こうした属人化は、業務の継続性や品質を脅かす大きなリスク要因です。
リスクを回避するためには、誰が担当しても一定の水準で業務を遂行できる体制づくりが不可欠です。マニュアルを整備し、業務内容を標準化することは、働き方改革を実現するうえでの基本とも言えるでしょう。
特に、バックオフィス業務のように属人化しやすい分野では、優先的な取り組みが求められます。近年では、動画や図解を用いたマニュアルの電子化も実用性の高い手法として注目されています。
参考:無料で始める電子マニュアルの作成方法|メリットからツール選定・導入ステップまで徹底解説
働き方改革と業務効率化に役立つツール6選
働き方改革と業務効率化を同時に進めるには、現場に即したツール選びが不可欠です。
ここでは、目的別に導入しやすく効果の高いツールを6つ紹介します。
プロジェクト管理ツールで業務効率化
プロジェクト管理ツールは、チーム内のタスクを「見える化」し、スケジュールや進捗の共有をスムーズに行うために効果的です。AsanaやNotionといったツールを活用することで、作業の重複や抜け漏れを防ぎ、業務全体の効率を高めることができます。
こうしたツールの導入により、属人化を防ぎつつ、誰でも業務の状況を把握・引き継ぎやすくなります。リモート環境下でもリアルタイムで進捗を共有できる点は、柔軟な働き方を支えるうえで大きなメリットと言えるでしょう。
勤怠・労務管理ツールで働き方改革を促進
正確な労働時間の記録や残業状況の把握は、働き方改革を進めるうえでの基本です。ジョブカンやKING OF TIMEといった勤怠管理ツールを導入すれば、労務管理の透明性が向上し、労働時間の適正化が促進されます。
加えて、フレックスタイム制やテレワーク制度など、多様な働き方にも柔軟に対応できるため、社員の働きやすさと法令遵守の両立が可能になります。これは従業員の満足度向上と企業リスクの軽減にもつながります。
経費・会計システムでバックオフィスの業務効率化
経費精算や会計処理の自動化は、バックオフィス業務の生産性を大きく高めるために必要です。たとえば、領収書の読み取りや申請の一括処理など、煩雑で手間のかかる作業を効率化することで、従業員の負担を大幅に軽減できます。
その結果、経理担当者が本来の分析業務や経営サポートに注力できるようになります。
情報共有ツールでチームの働き方改革をサポート
Google Workspaceのような情報共有ツールを活用すれば、ドキュメントの同時編集やリアルタイムでのファイル共有が可能となり、業務のスピードや正確性が飛躍的に向上します。
さらに、時間や場所に縛られずアクセスできる柔軟な環境は、ハイブリッドワークや海外拠点との連携にも適しており、現代の多様な働き方に対応可能です。これにより組織の知識やノウハウを一元管理し、企業の「知的資産」として有効活用する体制が整います。
マニュアル管理ツールで業務効率化&教育工数削減
業務マニュアルを一元管理し、誰もがスムーズにアクセスできる環境を整えることで、新人教育が効率化され、同時に属人化のリスクも軽減されます。業務の標準化が進み、ナレッジが蓄積されていくと組織全体の対応力も向上するでしょう。
さらに、更新履歴や閲覧状況を記録できるツールを活用すれば、マニュアルの内容が陳腐化するのを防ぎ、常に最新かつ現場に即した情報を提供し続けることが可能です。
コミュニケーションツールでリモート時代の働き方改革
SlackやMicrosoft Teamsなどのチャットツールは、時間や場所に縛られない柔軟な働き方を実現するために、今や多くの企業で欠かせない存在です。チャンネルごとに情報を整理できるほか、ビデオ会議やファイル共有などの機能も充実しており、対面に近いスムーズなコミュニケーションを実現します。
また、業務連絡だけでなく、雑談やアイデア交換の場を意識的に設けることで、チーム内の心理的な距離が縮まり、一体感や信頼関係の醸成にもつながります。リモートワークの環境下でも、社員同士が「つながっている」と感じられる風土づくりが働き方改革の鍵となるでしょう。
働き方改革×業務効率化を社内で成功させる4つの実践ポイント
取り組みを形だけで終わらせないためには、現場の納得と継続的な改善が欠かせません。社内で確実に浸透させるための具体的な工夫を4つ紹介します。
トップダウンとボトムアップの両立で進める働き方改革
働き方改革は経営層の強いリーダーシップがなければ社内に定着しませんが、現場の協力なくして成功もありません。上層部が方向性を示しつつ、現場の声を吸い上げて改善を繰り返すことで、全社一丸の取り組みになります。
日々のコミュニケーションや会議を通じて、経営層が改革の意義を語り続ける姿勢を保ちましょう。
業務効率化の効果を「見える化」して社内浸透を促す
業務改善の成果が見えにくいと、従業員のやる気や理解が薄れてしまいます。そのため、KPIの設定や数値による効果測定、ビフォーアフターの共有を通じて、業務効率化の価値を実感できる仕組みを整えることが求められます。
ポスター掲示や社内ニュースを活用し、取り組みの成果を全社員に向けて分かりやすく伝えることも効果的です。
部門ごとに合った働き方改革・業務効率化戦略を設計する
営業、バックオフィス、製造など、部門によって課題や文化は大きく異なります。画一的な施策ではなく、それぞれの現場に即した改革プランを策定することで、実効性の高い改善が可能になります。
部門リーダーを巻き込み、各チームで独自の取り組みを考える機会をつくると、現場の主体性も高まるでしょう。
定期的な振り返りと改善で継続的な業務効率化を実現
一度導入した施策であっても、時間が経つにつれて形だけのものになってしまうリスクがあります。定期的なアンケートや業務レビューを通じて現場の実態を把握し、必要に応じて業務フローや使用ツールの見直しを行うことが大切です。
こうした継続的な見直しを「当たり前」とする文化を根付かせることで、改善が一過性に終わらず、組織としての成長と成果につながります。
働き方改革を成功させるには業務効率化が不可欠
本記事では、働き方改革と業務効率化の関係性から始まり、背景や課題、解決策としての業務フロー見直しやITツールの活用、そして実行段階での成功ポイントまでを幅広く紹介しました。
働き方改革を形だけの取り組みで終わらせないためには、業務の見直しと効率化が欠かせません。ツールや制度だけでなく、現場の課題に目を向け、組織全体で取り組む姿勢が求められます。
まずは業務のムダを洗い出し、できるところから改善を始めましょう。
外部支援の活用も選択肢に
業務効率化を図るには、現状分析やフロー改善、ツール選定などに専門的な視点が求められる場面もあります。そのようなときは、外部の知見を取り入れることで、よりスムーズに効果的な施策を進めることができます。特に、全体像の見える化や改善方針の策定が課題となっている場合は、業務分解図のような手法と外部支援の組み合わせが有効です。
業務効率化を考えている担当者の方は、ぜひmayclassのサービスページをご覧ください。
※業務分解図メール受け取りご希望の際は、お問合せ内容に「業務分解図希望」と記載してください。
▼こちらの記事もおすすめ▼
マニュアル・手順書・仕様書・説明書の違いとは?正しく使い分けるポイントを徹底解説!
【図解でわかる】生産性向上と業務効率化の違いとは?意味・目的・施策を徹底比較!
【完全ガイド】Wordでマニュアル作成する方法!デザイン・レイアウトの工夫もご紹介
ーーー
Work Style Reform and Efficiency Go Hand in Hand: Key Points for Corporate Success