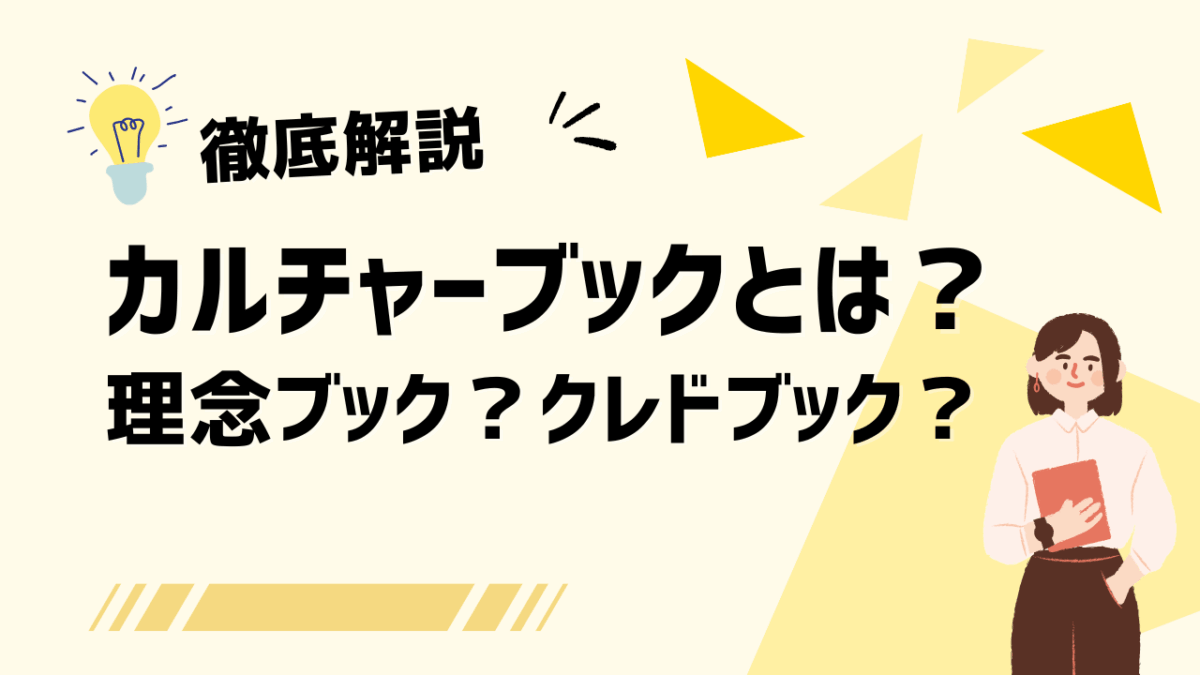近年、企業文化や価値観を社内外に発信する手段として「カルチャーブック」が注目されています。「自社らしさを採用活動で伝えたい」「理念や行動指針をもっと浸透させたい」そんな課題を抱える企業にとって、カルチャーブックは強力なツールになります。一方で、「理念ブックやクレドブックと何が違うの?」「どれを作ればいいかわからない」と感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、カルチャーブックの意味や目的はもちろん、理念ブック・クレドブックとの違い、作り方や活用事例まで詳しく解説します。
自社に合ったブック作成を検討されている方は、ぜひ最後までご覧ください。
企業文化や価値観を言語化し社内外に伝える「カルチャーブック」の意義を、理念ブック・クレドブックとの違い、作り方、活用事例を交えて解説します。
採用・社員教育・ブランド発信を目的とする企業に最適なガイドです。
カルチャーブックとは?意味や目的をわかりやすく解説
カルチャーブックとは、企業の文化や価値観、社風を言語化・可視化し、社内外に伝えるための冊子や資料のことを指します。カルチャーブックは、会社の「らしさ」を社員や求職者、取引先などにわかりやすく伝えるツールとして、近年多くの企業に取り入れられています。
理念やビジョンなど、経営層が語る「ありたい姿」だけでなく、実際に働く社員の声や日常のエピソード、働き方の工夫など、リアルな企業文化が伝わる内容で構成されるのが特徴です。特に、写真やイラストなどのビジュアル要素を活用し、読み手がイメージしやすいよう工夫されているものが多く見られます。
カルチャーブックを作成する目的
カルチャーブックを作成する目的は、主に三つあります。一つ目は、採用活動において会社の魅力を伝えることです。企業理念や制度だけでは伝わりにくい「働く雰囲気」「どんな人が活躍しているのか」といった情報を、カルチャーブックを通じて求職者に届けることができます。
二つ目は、既存社員への文化浸透やエンゲージメント向上です。特に、組織拡大や多拠点展開が進む企業にとって、共通の価値観を再確認し、一体感を高めるためのツールとして活用されています。
三つ目は、社外に対するブランディングや共感づくりです。取引先やパートナー企業に対して、自社の文化や考え方を共有し、より良い関係構築につなげる企業も増えています。
このように、カルチャーブックは単なる会社紹介ではなく、文化を言語化し、共感を生み出すコミュニケーションツールとして重要な役割を果たしています。理念や行動指針とセットで運用することで、より強い組織づくりに貢献できるでしょう。
カルチャーブックと理念ブック・クレドブックの違いとは
理念ブックとは何か
理念ブックとは、企業のミッション・ビジョン・バリューをまとめた資料のことです。会社の存在意義や目指す未来像、経営方針などを言語化し、社員や関係者に伝える役割を担います。経営者や役員のメッセージが中心となり、会社の方向性や意思決定の基準を共有するために活用されます。
クレドブックとは何か
クレドブックとは、日々の業務や社員の行動指針を具体的にまとめた資料です。クレドとは信条や信念を意味し、社員が大切にすべき考え方や行動を簡潔なフレーズで示すことが特徴です。例えば「お客様第一主義」や「笑顔を忘れない」といった内容が記載され、朝礼や会議で読み上げる運用を取り入れている企業もあります。
カルチャーブックとは何か
カルチャーブックは、会社の文化や価値観、働き方をわかりやすく伝えるための資料です。理念や行動指針だけでなく、実際に働く社員の声やエピソード、社内の雰囲気をリアルに伝えることを目的としています。写真やイラストなどを使い、読み手がその会社で働くイメージを具体的に持てるように工夫されているのが特徴です。
それぞれの違いと使い分けのポイント
理念ブックは「目指す方向性」を、クレドブックは「日々の行動指針」を、カルチャーブックは「会社の文化や雰囲気」を伝える役割を担っています。いずれか一つを作成する企業もありますが、目的に応じて複数を使い分けることで、企業文化の浸透効果を高めることができます。
どれを作ればいいか迷った場合は、まず自社が解決したい課題を明確にすることが大切です。採用活動で自社の魅力を伝えたいならカルチャーブック、経営方針を全社員に共有したいなら理念ブック、日常の行動基準を明確にしたいならクレドブックを選ぶと良いでしょう。
カルチャーブックが注目される理由とは
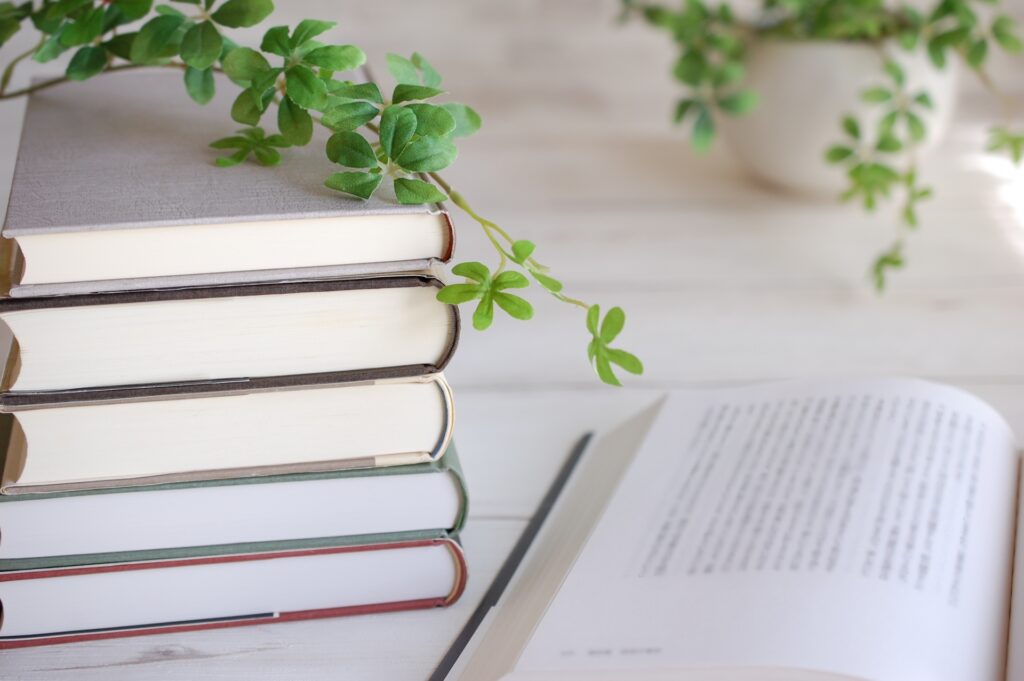
採用活動で企業の魅力を伝える武器になるカルチャーブック
カルチャーブックが注目される大きな理由の一つは、採用活動において企業の魅力を伝えるための有効なツールになることです。求人票や会社説明会だけでは伝わりにくい「実際の雰囲気」や「働く人のリアルな声」を可視化できるため、求職者に具体的なイメージを持ってもらいやすくなります。特に若い世代ほど「どんな人と働くのか」「どんな価値観を大切にしている会社なのか」を重視する傾向が強く、カルチャーブックを活用することでミスマッチを防ぐ効果も期待できます。
社員のエンゲージメント向上に役立つカルチャーブック
カルチャーブックは、既存社員のエンゲージメントを高める効果もあります。事業拡大や拠点増加などにより組織が大きくなると、社員一人ひとりが自社の文化や価値観を共有し続けることが難しくなります。そんな時、カルチャーブックを通じて改めて自社の「らしさ」や「大切にしていること」を確認し合うことで、組織としての一体感や誇りを育むことができます。定期的に内容を見直し、社員の声を反映し続けることで、より強い文化づくりにつながるでしょう。
企業ブランディングにもつながるカルチャーブック
カルチャーブックは、社外へのブランディングにも効果を発揮します。取引先やパートナー企業に対して、自社がどんな文化を大切にし、どんな価値観で事業を展開しているかを伝えることで、共感や信頼を得やすくなります。近年は、自社サイトやSNSでカルチャーブックを公開し、社会に向けて発信する企業も増えています。単なる採用ツールにとどまらず、企業価値を高めるブランディング戦略の一環としても注目されています。
カルチャーブックの作り方とは?作成ステップをわかりやすく解説
カルチャーブックの作り方①:目的とターゲット設定が重要
カルチャーブックの作り方で最初に重要なのは、誰に何を伝えたいのかを明確にすることです。採用活動で学生や求職者に向けて自社の雰囲気を伝えたいのか、既存社員に向けて価値観を再確認させたいのか、ターゲットによって内容や表現方法が大きく変わります。目的とターゲットが決まれば、どんな情報を集めるべきかも自然と見えてきます。
カルチャーブックの作り方②:社員の声やリアルな情報収集から始める
次に行うのが情報収集です。経営理念や方針だけでなく、実際に働く社員のエピソードや社内で大切にされている習慣など、リアルな情報を集めることがポイントになります。座談会やアンケート、インタビューなどを通じて、社員が普段大事にしている価値観や社風を言語化していく作業が大切です。経営層だけで作るのではなく、社員を巻き込むことで共感されやすいカルチャーブックになります。
カルチャーブックの作り方③:デザインや表現にもこだわる
カルチャーブックの作り方では、デザインや表現方法にも工夫が必要です。文字だけでなく写真やイラストを使って視覚的に伝えることで、読み手の理解や共感を得やすくなります。特に、実際に働く社員の写真やインタビューを掲載することで、よりリアリティが増します。冊子として印刷するだけでなく、デジタルブックや動画コンテンツとして展開する企業も増えており、届け方にも工夫することが求められます。
カルチャーブックの作り方④:更新し続ける
最後に、カルチャーブックは一度作って終わりではなく、定期的に見直しや更新を行うことが大切です。会社の成長や変化に合わせて内容をアップデートし続けることで、常に「今の自社らしさ」を正しく伝えることができます。社員の声を反映し続けることで、社員にとっても「自分たちのカルチャーブック」と感じられるツールになるでしょう。
カルチャーブックを作る際のポイントとは
社員のリアルな声やエピソードを盛り込む
カルチャーブックを作る際に最も大切なのは、社員のリアルな声やエピソードを必ず盛り込むことです。経営層だけが語る理想や制度説明だけでは、「本当にそうなのか」と読み手に距離を感じさせてしまうことがあります。実際に働く社員が、どのような想いを持ち、どんなエピソードを経験しているのかを集めて反映させることで、「自社らしさ」がリアルに伝わる一冊になります。
例えば、社員一人ひとりから未来の仲間への手紙を書くような形式や、実際の言葉をそのまま掲載するスタイルなど、読み手の心に響くような表現を工夫することも効果的です。ただの説明文ではなく、まるでその人から直接メッセージを受け取ったかのような臨場感や温度感を大切にすることで、読む人の共感を引き出しやすくなります。座談会やインタビューを実施し、社員の生の声をそのまま届けるような工夫を取り入れてみることをおすすめします。
写真やデザインで視覚的に伝える工夫をする
カルチャーブックは、どうしても文字ばかりが続いてしまい、読みにくくなるケースがあります。そのため、写真やイラスト、レイアウトの工夫を取り入れ、読みやすさや親しみやすさを高めることが大切です。特に、社員の写真や職場の風景などを掲載すると、ページ全体にメリハリが生まれ、視覚的にも読みやすくなります。また、読み手が「ここで働く自分」をイメージしやすくなり、共感や好感を得やすくなる効果も期待できます。文字情報だけに頼らず、視覚的な工夫を取り入れることが、伝わるカルチャーブック作りのポイントです。
目的とターゲットを明確にして作る
カルチャーブックは誰に向けて、何を伝えたいのかを最初に明確にしておくことも大切です。採用活動で学生や求職者に伝えたいのか、既存社員に向けて文化浸透を図りたいのか、社外へのブランド発信を強化したいのかによって、内容や構成は変わります。目的とターゲットを定めてから作成を始めることで、効果的な一冊に仕上がります。
定期的な更新で「今の自社」を伝え続ける
カルチャーブックは一度作って終わりではなく、会社の変化や成長に合わせて定期的に見直し、更新していくことが求められます。新しいエピソードや取り組みを反映させることで、常に「今の自社らしさ」を正しく伝えることができ、社員にとっても自分たちが関わっているという実感を得られるツールになります。
カルチャーブック活用事例とは?具体的な使い方を紹介
採用活動でカルチャーブックを活用する事例
カルチャーブックの代表的な活用事例として、採用活動での利用があります。多くの企業が会社説明会やインターンシップ、選考時の資料としてカルチャーブックを配布し、学生や求職者に自社の文化や価値観を伝えています。求人票やホームページだけでは伝わりにくい「どんな人が働いているのか」「どんな空気感の会社なのか」といった情報をカルチャーブックで伝えることで、応募者に具体的なイメージを持ってもらいやすくなります。これにより、入社後のギャップやミスマッチを防ぎ、採用の質向上にもつながっています。
新入社員研修でカルチャーブックを活用する事例
新入社員研修でカルチャーブックを活用する企業も増えています。入社直後の社員に対して、自社の文化や価値観を伝えることで、早い段階から会社への理解や共感を深めてもらうことができます。理念や方針だけでなく、実際に活躍している先輩社員のエピソードや働き方を紹介することで、自分自身がどのように活躍できるかをイメージしやすくなります。カルチャーブックを繰り返し読み返すことで、日々の業務や行動にも自社らしさを意識しやすくなる効果が期待できます。
社外へのブランド発信にカルチャーブックを活用する事例
カルチャーブックは、社外へのブランド発信ツールとして活用する事例もあります。取引先やパートナー企業に対して、自社の文化や考え方を伝えることで、共感や信頼を得やすくなるからです。最近では、自社のホームページやSNSでカルチャーブックを公開し、広く社会に向けて発信する企業も増えています。企業理念や事業内容だけでなく、カルチャーや社風まで積極的に発信することで、企業ブランドの強化やファンづくりに役立てることができます。
成功企業のカルチャーブック活用事例
実際にカルチャーブックを活用している成功企業の事例として、スタートアップ企業や大手IT企業などが挙げられます。スタートアップ企業では、急速な組織拡大に伴う文化の分断を防ぐため、全社員参加型でカルチャーブックを作成し、文化浸透に成功したケースがあります。また、大手IT企業では、グローバル展開を見据えて多言語対応のカルチャーブックを作成し、世界中の社員に共通の価値観を届ける取り組みを行っています。このように、企業規模や業種を問わず、カルチャーブックを上手に活用している事例は年々増えています。
カルチャーブックとは何かを正しく理解し、自社に合った活用を
ここまで、カルチャーブックとは何か、理念ブックやクレドブックとの違い、そして作り方や活用事例について解説してきました。カルチャーブックは、単なる会社紹介ではなく、自社の文化や価値観を言語化し、社内外に伝えるための重要なツールです。
理念ブックは経営の方向性を示す資料、クレドブックは日々の行動指針をまとめた資料であるのに対し、カルチャーブックは会社の空気感や社員のリアルな声を伝えることに重きを置いています。それぞれの役割を理解し、自社の課題や目的に合わせて取り入れることが大切です。
採用活動や社員教育、企業ブランディングなど、さまざまな場面で活用できるカルチャーブックは、会社の魅力や「らしさ」を伝える強力なツールになります。まずは小さく作ってみることから始め、自社らしい一冊を作り上げてみてはいかがでしょうか。
ーーー
What Is a Culture Book? Differences from Mission or Credo Books and How to Create One
カルチャーブックの制作はmayclassへ
企業が大切にしている「想い」や「文化」を、社員一人ひとりが自分ごととして行動に移すためには、 心に響く言葉 で伝えることが何より重要です。
mayclassでは、言葉をカタチにするプロが、貴社の価値観・文化・未来像を深く掘り下げ、 共感と行動を生み出すカルチャーブック を制作します。
「つくること」がゴールではなく、「浸透し、育つこと」を目指して。貴社らしいカルチャーブックづくりは、mayclassにお任せください。

▼下記記事もおすすめ▼