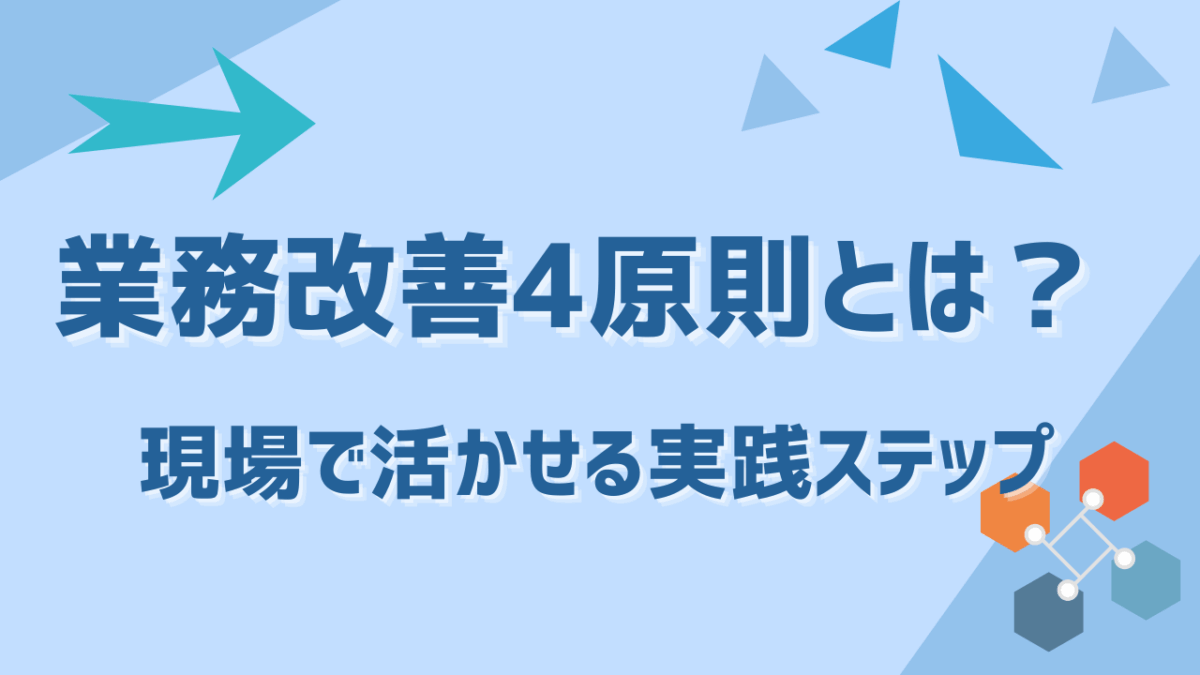業務改善を進める際に、「どこから手をつければいいのか分からない」と感じたことはありませんか?
現場では日々の業務が複雑化し、ムダな手順や属人化した作業が積み重なりやすくなっています。その結果、効率が落ちたり、品質が不安定になったりと、さまざまな問題を引き起こします。
こうした課題を解決するための代表的な考え方がECRSです。ECRSとは、Eliminate(排除)・Combine(結合)・Rearrange(入替)・Simplify(簡素化) の4つの原則を指し、業務を改善する際の基本フレームワークとして広く活用されています。トヨタ生産方式やリーン生産方式と同じく、シンプルで実践的な手法であるため、多くの企業が現場改善に導入しています。
本記事では、全体像をまとめた「業務改善・業務効率化の原則と目標を徹底解説!4原則・3要素・8原則を一挙紹介」の詳細解説編として、この業務改善4原則を掘り下げます。
具体例やマニュアル管理との関係、活用のポイントについて紹介します。業務改善を継続的に進めたい方にとって、実務に直結するヒントを得られる内容になっていますのでぜひ最後までご覧ください。
現場のムダや属人化を見直したいが、「どこから改善すべきか分からない」。そんな担当者・管理職に向けて、業務改善の基本フレームワーク「ECRS(排除・結合・入替・簡素化)」を分かりやすく解説します。具体例や実務での進め方、マニュアル管理との連動、失敗しないための注意点、改善を定着させる方法まで体系的に整理。現場で使える実践的な改善手法を知りたい方に役立つ内容です。
ECRSとは?業務改善に欠かせない思考法
ECRSとは、業務を効率化・最適化するための代表的なフレームワークで、Eliminate(排除)・Combine(結合)・Rearrange(入替)・Simplify(簡素化) の4つの視点から業務を見直す方法を指します。製造業を中心に広まった考え方ですが、近年ではバックオフィスや営業活動、さらにはマニュアル管理に至るまで、あらゆる業務改善に応用されています。
ECRSが重視される理由
業務改善を進める際、多くの現場では「人の努力や残業に頼る」アプローチになりがちです。しかし、それでは一時的な解決にしかならず、根本的な改善にはつながりません。ECRSは業務の仕組みそのものを見直す考え方であり、次のような効果を生み出します。
- ムダな作業を徹底的に削減できる
- 作業の流れを整理し、属人化を防げる
- マニュアルをシンプルに標準化できる
- 継続的に改善サイクルを回しやすくなる
このように、ECRSは「人の頑張り」に依存せず、業務フローを根本から効率化する仕組みを作る点に大きな特徴があります。
他の改善手法との違い
業務改善の代表的な手法には、5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾) や カイゼン(継続的改善) があります。これらが「職場環境」や「改善文化」の形成に重点を置いているのに対し、ECRSは業務プロセスそのものを具体的に見直すための思考法である点が大きな違いです。
また、ECRSの考え方はマニュアル管理とも親和性が高いです。マニュアルをECRSの視点で作り直せば、不要な手順を削り、複数の作業を統合し、流れを整理し、誰でも理解できるように簡素化することができます。これにより、現場に浸透しやすい「活きたマニュアル」に生まれ変わります。
ECRSの4原則と具体例
ECRSは、業務改善を行う際に 「排除・結合・入替・簡素化」 の4つの視点で業務を見直すフレームワークです。ここでは、それぞれの原則を具体例とともに解説します。
業務改善4原則①:Eliminate(排除)― 不要な業務をなくす
最も重要かつ効果が大きいのが Eliminate(排除) です。
「本当に必要な業務か?」という視点で見直し、価値を生まない作業や二重作業を削除します。
- 例1:同じデータを複数のシステムに入力している → API連携で一度の入力に統合
- 例2:承認フローが多段階になっている → 承認権限を整理し、段階を削減
- 例3:マニュアル内の不要な説明や重複した手順を削除
排除は「やらなくてもよい仕事」を見つけることがポイントで、これにより大幅な効率化が可能になります。
業務改善4原則②:Combine(結合)― 作業をまとめて効率化する
次に、複数の作業を Combine(結合) し、一度で処理できる形にまとめることです。
- 例1:複数部署が個別に作成していた報告書を共通フォーマットに統合
- 例2:会議での進捗報告と週次レポート提出を一体化
- 例3:マニュアルとチェックリストを一つにまとめ、現場ですぐ使える形にする
結合の目的は「作業の重複や手戻りを減らす」ことです。複数の業務をまとめることで、情報の一元管理やマニュアルの簡略化につながります。
業務改善4原則③:Rearrange(入替)― 流れや順序を見直す
Rearrange(入替) は、業務の手順や順番を変えることで効率を高める考え方です。
- 例1:資料作成を会議の後に行っていた → 会議前にテンプレートを準備して効率化
- 例2:顧客対応のフローを見直し、初期段階でFAQやマニュアルを案内 → 問い合わせ件数を削減
- 例3:倉庫でのピッキング作業の順番を変え、動線を短縮
業務の順序や配置を最適化することで、時間のロスを防ぎ、全体のスピードを上げることができます。
業務改善4原則④:Simplify(簡素化)― 誰でもできる仕組みにする
最後に、業務をSimplify(簡素化) します。作業手順をできるだけシンプルにして、誰でもすぐ理解できる状態にすることが目的です。
- 例1:文章だけのマニュアルを図解やフローチャートに置き換える
- 例2:複雑な操作を自動化ツールに置き換える
- 例3:社内申請フォームを一画面で入力できるように設計
簡素化によって属人化を防ぎ、新人でもスムーズに業務を習得できるようになります。特にマニュアル管理においては「短く・わかりやすく・見やすい」構成が重要です。
ECRSを活用した業務改善の進め方
ECRSは単なる理論ではなく、実際の業務改善を進めるための実践的なフレームワークです。ここでは、ECRSを日常業務に取り入れる際の具体的な進め方を紹介します。
現状分析と課題の洗い出し
業務改善4原則を効果的に活用するためには、まず現状を正確に把握することが出発点となります。感覚や推測ではなく、実際の業務データや現場の声をもとに分析を行い、問題の所在を明確化します。
具体的には、業務フローを可視化し、各工程ごとにかかっている時間や担当者、使用しているツールなどを整理します。これにより、どこにムダな工程があるのか、どの作業が属人化しているのかが見えてきます。例えば、同じ情報を複数のシステムに二重入力している、承認フローが複雑でボトルネックになっている、といった課題が浮かび上がります。
また、この段階で現場スタッフへのヒアリングやアンケートを行うと、日常業務の中で感じている非効率や改善ニーズを直接把握できます。数値データと現場の感覚を組み合わせることで、より精度の高い課題分析が可能になります。
ECRSの視点で見直す
業務の全体像が把握できたら、ECRSの4つの原則に当てはめて改善点を探す段階に入ります。
- Eliminate(排除):不要な作業はないか?
- Combine(結合):まとめられる業務はないか?
- Rearrange(入替):順序や担当を変えると効率的にならないか?
- Simplify(簡素化):もっとシンプルにできないか?
このプロセスは「業務診断」とも言え、改善案を具体化する重要なステップです。
改善活動のPDCAサイクル
改善は一度実行して終わりではなく、定期的な見直しと修正を繰り返すことで効果が持続します。そのために活用するのがPDCAサイクル(Plan=計画、Do=実行、Check=評価、Act=改善)です。
まず改善計画を立て(Plan)、現場で実行します(Do)。次に、その成果を数値や定性的評価で検証し(Check)、必要に応じて改善や修正を行います(Act)。この流れを定期的に繰り返すことで、新しい課題や環境変化にも柔軟に対応できます。
例えば、承認フローの簡略化を行った場合、初期段階では承認スピードが上がっても、別の工程で不具合が生じることがあります。その際は現場の声を聞き、承認ルールの見直しやシステム設定の変更などを行うことで、改善効果を最大化できます。
継続的なPDCAは、業務改善4原則を一過性の施策ではなく、企業文化として根付かせるための最大の要因となります。
マニュアル管理と連動させる
ECRSで見直した内容は、必ずマニュアル管理の仕組みに反映させましょう。
- 更新した手順をマニュアルに記録
- 社員に周知し、全員が同じ手順で業務を行えるようにする
- バージョン管理やアクセス権限を設定して正確性を担保
ECRSとマニュアル管理を連動させることで、「改善した業務が現場に根付く」サイクルが作られます。
業務改善4原則を定着させるポイントと注意点
ECRSはシンプルで強力な業務改善のフレームワークですが、誤った使い方をすると効果が出なかったり、逆に混乱を招いたりすることもあります。ここでは、ECRSを効果的に活用するために意識すべきポイントと注意点を解説します。
効率化だけに偏らない
ECRSを適用すると、ムダの排除や作業時間の短縮に注目しがちです。しかし、「効率化」だけを追求すると、品質や顧客満足度が犠牲になる可能性があります。
- Eliminateで業務を削りすぎると必要なチェック工程まで消してしまう
- Simplifyで簡素化しすぎて情報不足になる
効率化と同時に、品質・安全性・利便性のバランスを取ることが重要です。
部分最適ではなく全体最適を意識する
ECRSを特定の部署や作業にだけ適用すると、全体として逆に非効率になるケースがあります。
- 部署ごとに改善した結果、部門間の連携が遅くなる
- 結合(Combine)で便利になったが、他部門との情報共有が複雑化した
ECRSはあくまで業務全体を俯瞰して適用するフレームワークであり、全体最適を意識することが欠かせません。
現場の声を反映する
業務改善は現場で実際に働く人の協力なしには成り立ちません。
- 管理者だけでECRSを適用すると「机上の空論」になりやすい
- 改善案を実行しても、現場で定着しないケースが多い
改善の検討段階から現場メンバーを巻き込み、「誰が・いつ・どう使うのか」 を意識した仕組みを整えることが重要です。
マニュアル管理と必ず連動させる
ECRSの改善内容を反映したマニュアルが更新されなければ、せっかくの改善も時間が経つと形骸化してしまいます。
- 改善した業務フローをマニュアルに書き換える
- 更新履歴を残して、誰が修正したか明確にする
- 社員へ周知し、研修や日常業務で活用できる状態を維持する
ECRSを単発の改善で終わらせず、マニュアル管理を通じて組織全体に浸透させることが成果を持続させるポイントです。
改善文化を根付かせる
ECRSは「一度導入して終わり」ではなく、継続的に使い続けることで効果を発揮します。そのためには、改善提案を歓迎する文化や、定期的な見直しの仕組みが必要です。
- 月次の業務レビューで「ECRSの視点」を取り入れる
- 改善提案を評価・表彰する仕組みを作る
- マニュアル更新を「現場全員の責任」として定着させる
改善が「一部の人の仕事」ではなく「みんなで育てる活動」となれば、ECRSは組織文化として定着します。
業務改善4原則(ECRS)を取り入れよう
ECRSは、Eliminate(排除)・Combine(結合)・Rearrange(入替)・Simplify(簡素化) の4つの視点で業務を見直す、シンプルで実践的な改善フレームワークです。
「ムダを減らし、流れを整え、作業をシンプルにする」という考え方は、製造業だけでなく、オフィス業務・バックオフィス・営業活動など、あらゆる場面で効果を発揮します。
特に、マニュアル管理とECRSは相性が非常に良い組み合わせです。
- 改善内容をマニュアルに反映することで、業務改善を形骸化させず定着できる
- バージョン管理や更新ルールを徹底することで、常に最新の業務フローを維持できる
- 属人化を防ぎ、誰もが同じ基準で業務を行えるようになる
ECRSを使えば、単なる「効率化の一手段」ではなく、継続的に改善を回す仕組みを組織に根付かせることができます。
業務改善を進めるうえで、「人の頑張り」に頼るのではなく、仕組みとして改善を続けられる環境づくりが重要です。そのために、ECRSの4原則とマニュアル管理を組み合わせて、現場に浸透する改善サイクルを構築していきましょう。
業務改善4原則を現場で確実に活かすには、現状の業務フローを可視化することが欠かせません。
「業務分解図」なら、ムダの発見や標準化の設計までワンストップでサポート可能です。改善の第一歩を踏み出すために、ぜひご相談ください。

ーーー
What Are the 4 Principles of Business Improvement? Practical Steps for On-Site Application
▼こちらの記事もおすすめ▼
業務効率化は“数値化”から始まる!成果を見える化する方法と実践ステップ
【図解でわかる】生産性向上と業務効率化の違いとは?意味・目的・施策を徹底比較!
【保存版】営業資料の作り方を徹底解説!成果につながる構成・デザイン・伝え方のコツとは?